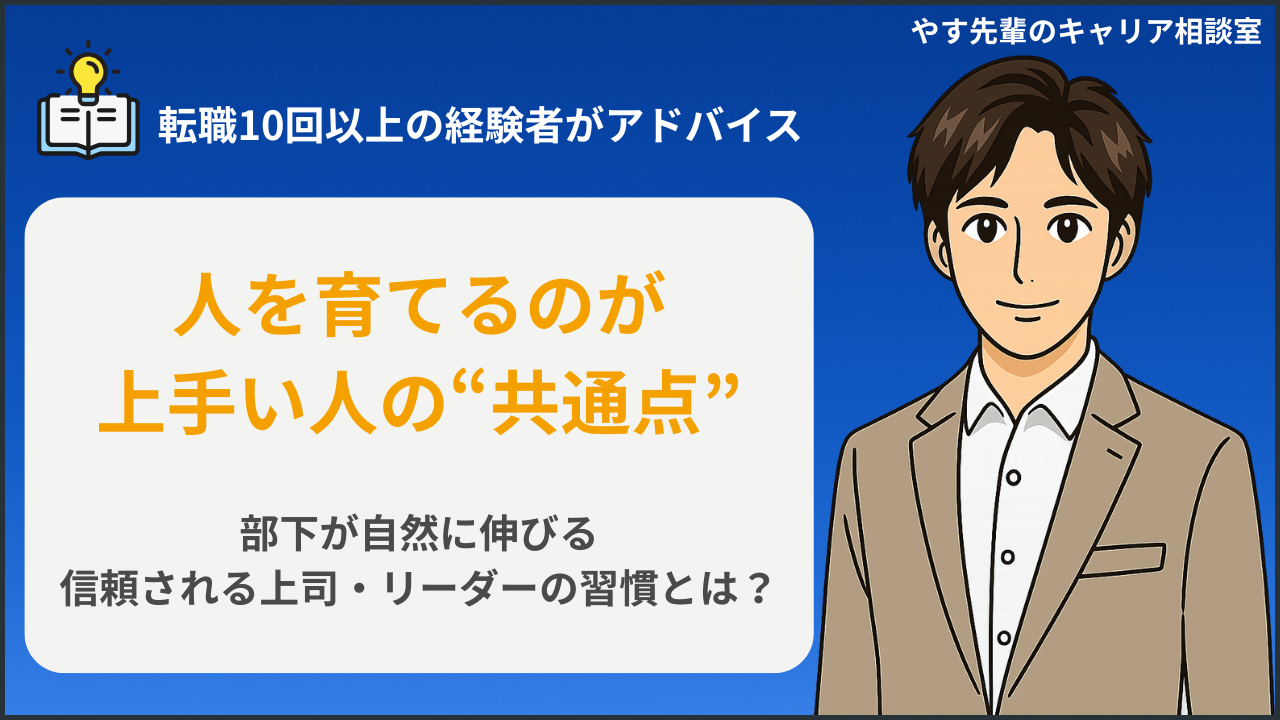やす先輩
やす先輩40代半ば、転職10回の管理職。上場もベンチャーもブラックも経験してきました。失敗も学びも交えながら、キャリアや働き方に悩むあなたへ“現実的な解決策”を届けます。
⇒詳しいプロフィール
「何度教えても、なかなか成長しない」
「自分の関わり方が悪いのだろうか」
「どうして、あの人の部下は自然と育つんだろう?」
そんな悩みを抱えながら、上司・リーダーとしての役割に向き合っていませんか?
実は、人を育てるのが上手い人には、はっきりした共通点があります。
それは、教え方のテクニックだけではありません。
・相手の状態をどう見ているか
・どんな言葉を選んでいるか
・どのタイミングで任せ、どこで支えるか
こうした関わり方の“前提”そのものが違うのです。
僕自身も、
「教えているのに育たない」
「自分はマネジメントに向いていないのかもしれない」
と悩んだ時期がありました。
でも振り返ると、それは能力不足ではなく、自分の特性と環境が噛み合っていなかっただけでした。
この記事では、
・人を育てるのが上手い人に共通する特徴と行動習慣
・育て下手になりやすい人との決定的な違い
・新人・部下が伸びやすくなる関わり方のコツ
・やす先輩自身の育成経験から学んだこと
を、具体例ベースで整理します。
もし今、
「自分は育成に向いているタイプなのか」
「どんな環境なら、もっと良いリーダーになれるのか」
と感じているなら、まずは自分の強みを客観的に把握してみてください。
ミイダスを使えば、あなたの経験や特性がどんな場面で活きやすいのかが見えてきます。
「人を育てる力」は、才能ではなく活かしどころで決まることも多いのです。
この記事を通して、“人が自然と育つ関わり方”と、自分らしいリーダー像を一緒に整理していきましょう。
人を育てるのが上手い人とは?意味と特徴を整理しよう
「人を育てるのが上手い人」とは、知識や技術を“教える人”ではなく、相手の中にある力を引き出せる人のことです。
相手をコントロールするのではなく、「自分で考え、成長できる状態」に導くことを大切にします。
たとえば、優秀なリーダーは「できない理由」を責めるより、「どうしたらできるか」を一緒に考えます。
人を育てるのが上手い人は、部下の失敗すらも“学びの素材”として活かし、信頼と挑戦のバランスを取れる人なのです。



“人を育てる”って、上から教えることじゃないんですよね。
相手の中にある“成長したい気持ち”を引き出す。
そのサポートができる人こそ、本当に育てるのが上手い人だと思います。
「教える」より「育てる」に重きを置く人
教えるのが上手い人は「正解を伝える人」。
育てるのが上手い人は「考える力を引き出す人」です。
前者は一時的に成長を促せますが、後者は“自走できる人材”を育てます。
だからこそ、育て上手なリーダーは「答えを与えない勇気」を持っています。
たとえば部下がミスをしたとき、
- ❌「どうしてこんなこともできないの?」
- ⭕「次はどうすればうまくいくと思う?」
この問いかけの違いが、相手の成長スピードを変えます。
また、育てる人は「結果」よりも「変化」に注目します。
- 前よりも早くできた
- 考え方が変わった
- 挑戦しようとする姿勢が出てきた
そうした“小さな成長”を見逃さず、認め、褒める。
この積み重ねが、部下の自信を育てていくのです。



“教える”のは上司の自己満足で終わることがあるけど、
“育てる”って、相手の未来を信じる行為なんですよ。
ちょっとした変化に気づいて声をかけるだけで、人は本当に伸びます。
人を動かすより“人の成長を支える”思考
人を育てるのが上手い人は、「どう動かすか」より「どう支えるか」を考えています。
命令で動かすのではなく、信頼で動く関係を築くのが特徴です。
こうした人は、部下のモチベーションを「外から刺激する」のではなく、
内側から引き出すことを意識しています。
たとえば:
- 自分の言葉で考えさせる
- 成長に必要な挑戦の機会を与える
- 適度に任せて、失敗も経験させる
支える姿勢を見せることで、「この人の期待に応えたい」と思わせる。
これが“人を動かす”よりもはるかに強いモチベーションを生み出します。



育て上手な人って、“相手の中にある答え”を信じてるんですよね。
コントロールしないからこそ、相手も自分を信じられるようになる。
信頼が循環するチームって、自然と強くなるんです。
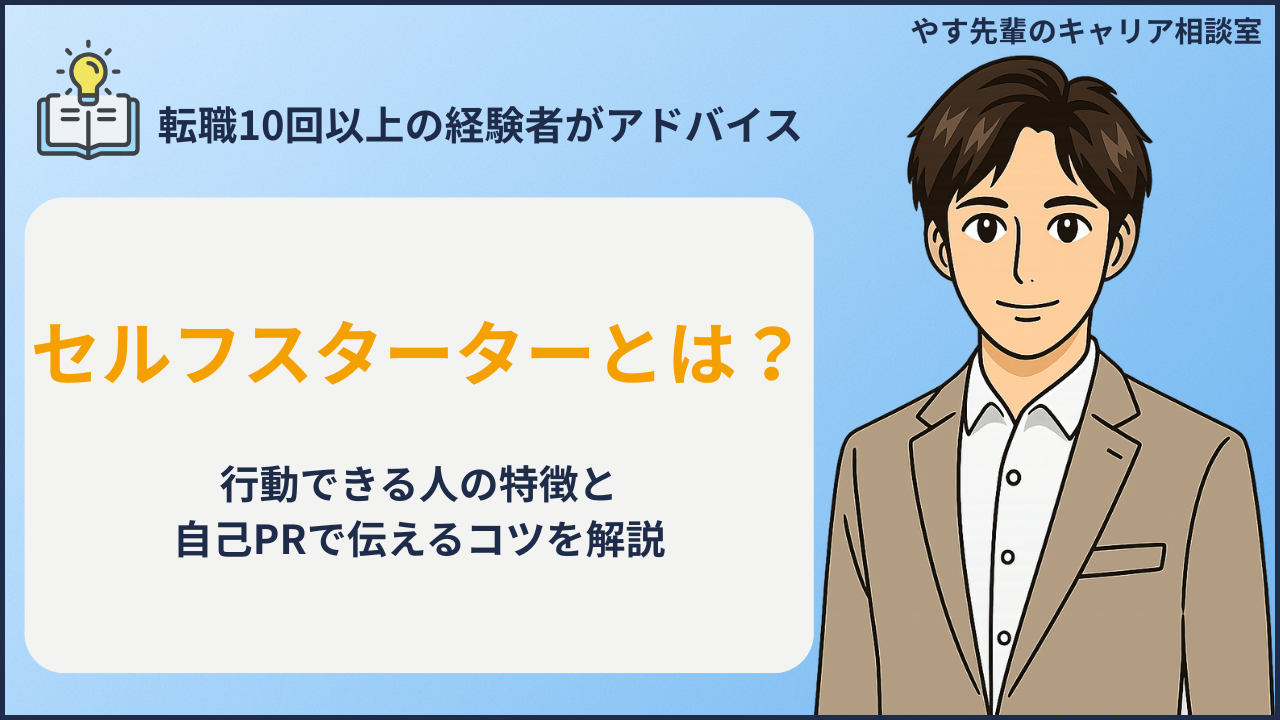
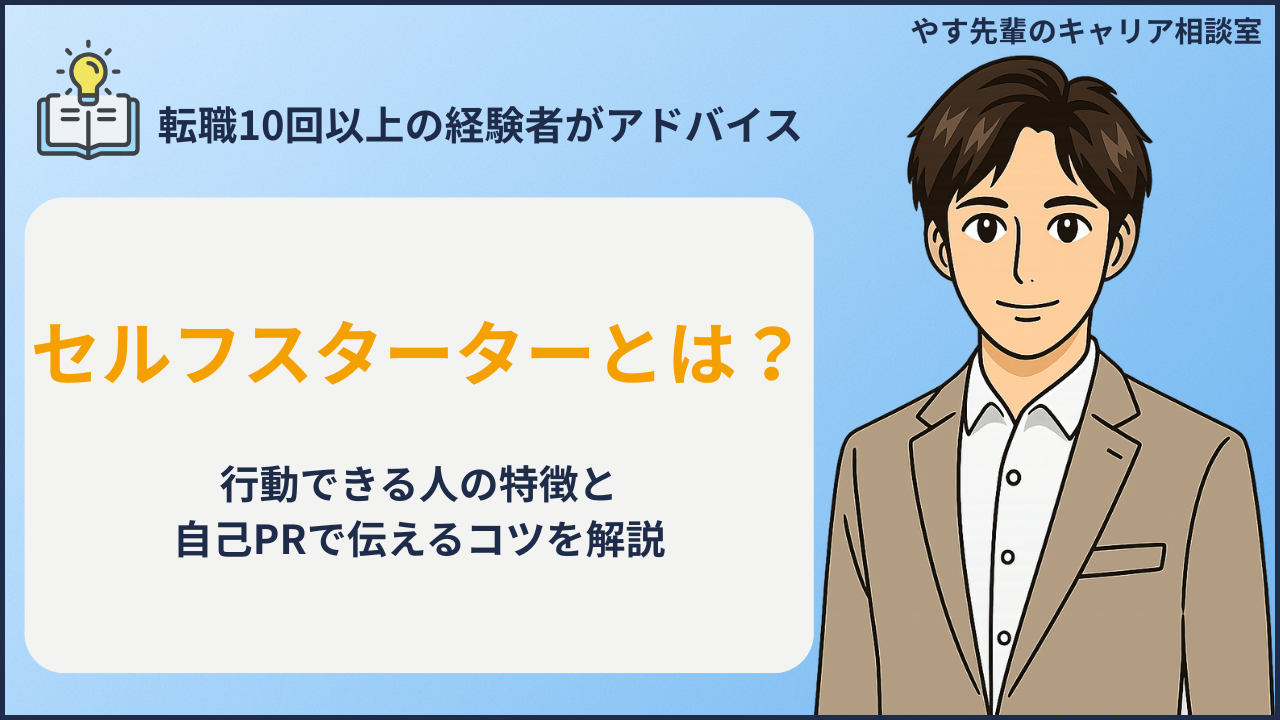
「人を育てる才能」は“信頼を築く力”にある
「人を育てる才能」って、特別なスキルではありません。
本質は、“信頼を積み上げられる人間性”にあります。
信頼は一瞬では生まれません。
日々の地道な行動の積み重ねでしか築けません。
信頼される人の共通点は、次の3つです。
- 約束を守る
- 感情的にならない
- 相手の努力をきちんと認める
この3つを徹底できる人は、どんな職場でも“安心して成長できる環境”を作れます。
そして、人を育てる上で欠かせないのが「一貫性」。
態度や言葉が日によって変わらない上司ほど、部下は心を開きます。



信頼って、特別な才能じゃないんですよ。
“約束を守る”“話を聞く”“感情的にならない”
当たり前を続けることが一番むずかしくて、一番強いんです。
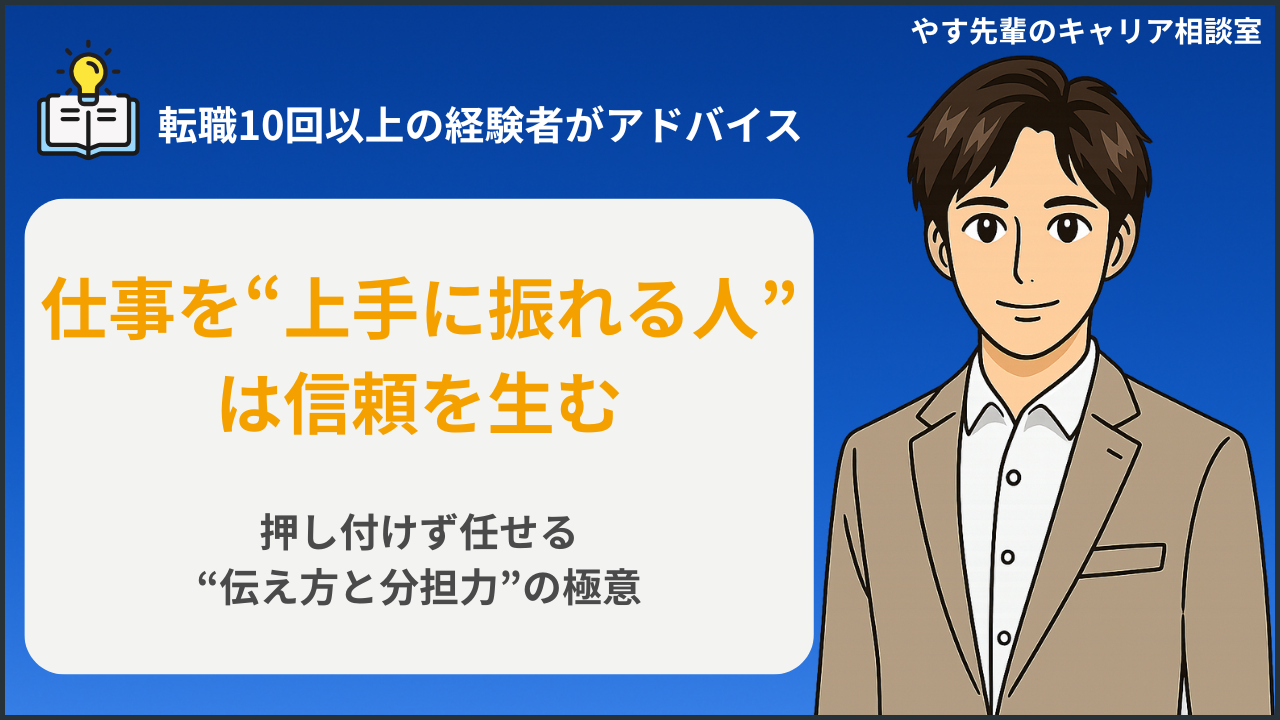
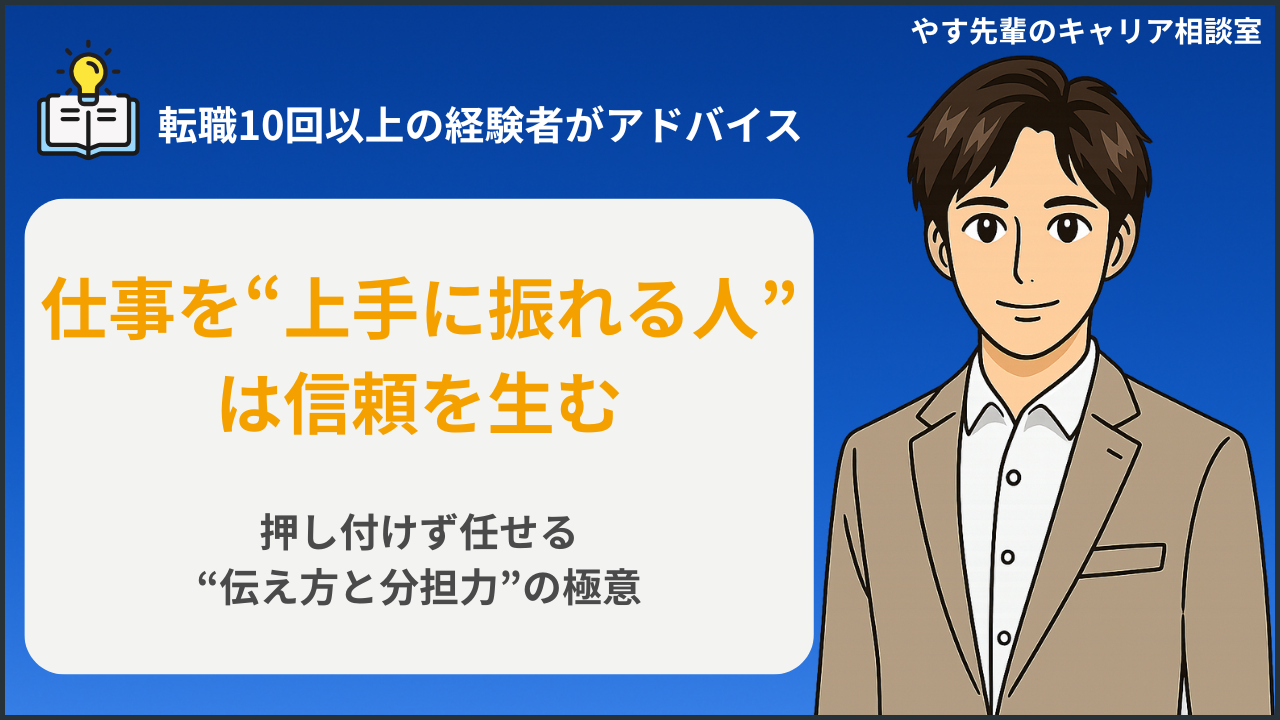
人を育てるのが上手い人の特徴7選【部下を育てる上司の共通点】
人を育てるのが上手い人には、共通する「7つの行動パターン」があります。
これらは才能ではなく、意識と習慣で誰でも身につけられるスキルです。
一つひとつの特徴を丁寧に見ていきましょう。
① 相手のレベルに合わせて教え方を変えられる
人を育てる上手い人ほど、「誰にでも同じ教え方」はしません。
相手の理解度や経験値を瞬時に見極め、“今の相手に最も届く言葉”を選べる人です。
たとえば、新人には具体的に、経験者にはヒントだけ伝える。
「伝える量」を調整することで、相手が考える余地を残し、成長を促すことができます。



“一番わかりやすく教える”より、“相手に合わせて教える”ほうがむずかしい。
でも、そこを意識できる上司ほど、信頼されるんですよね。
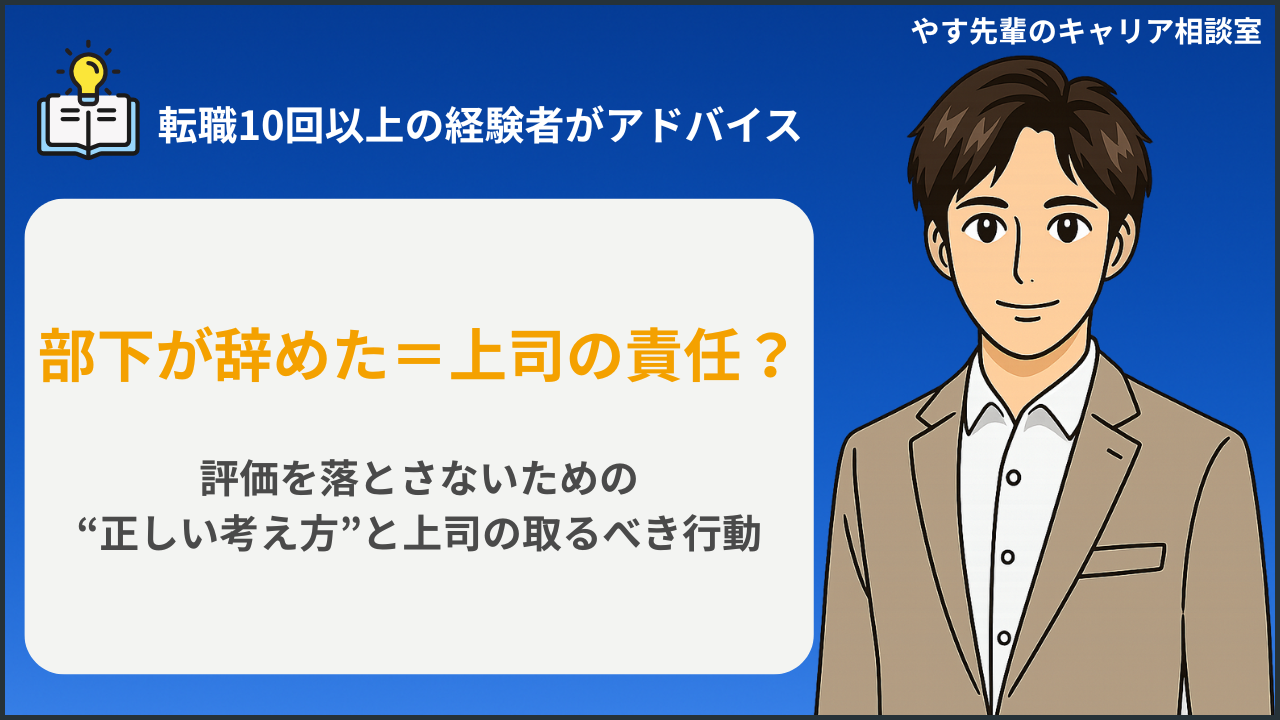
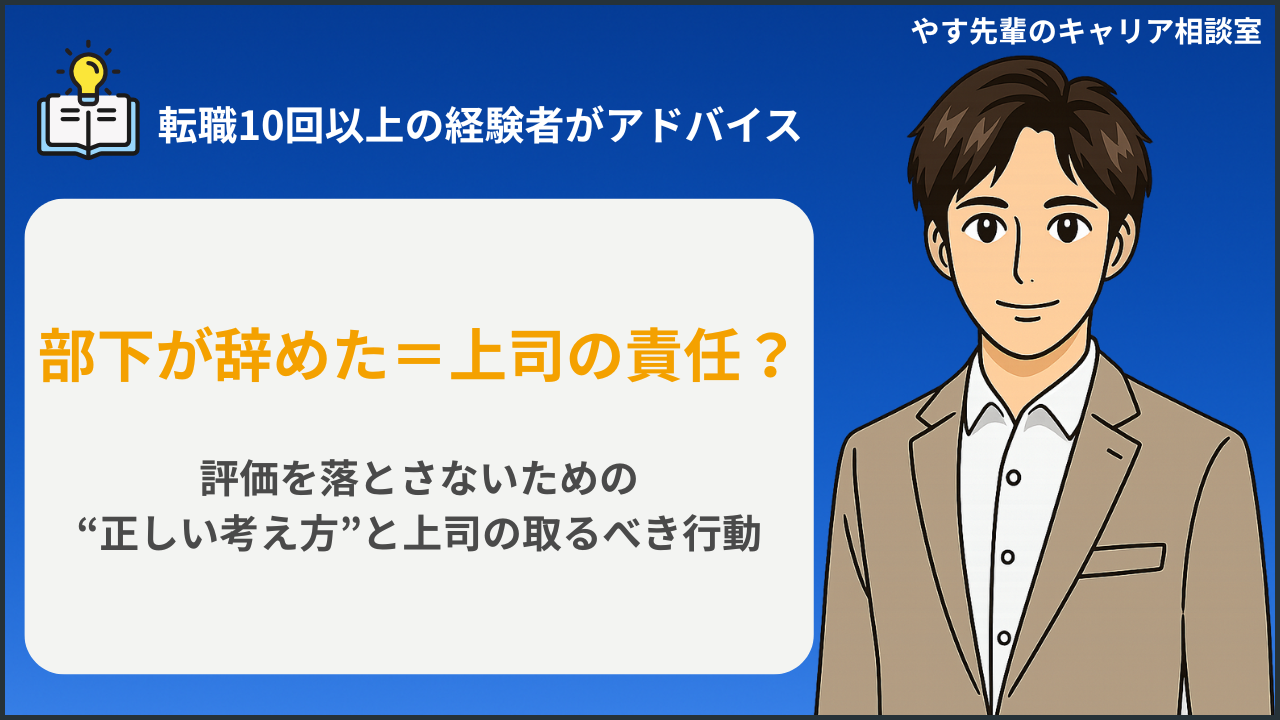
② 否定せず、できる部分を伸ばす視点を持つ
部下のミスや未熟さよりも、「できている部分」にまず目を向ける。
これが人を育てる上司の共通点です。
「まだまだだな」ではなく、「ここまでは良かったね」と伝えるだけで、
相手のモチベーションは大きく変わります。
否定は人を縮こまらせますが、肯定は挑戦を引き出します。
「失敗の指摘」よりも「成長の種探し」ができる人こそ、育て上手です。



僕も昔、“できてないところ”ばかり見てたけど、
それだと部下が“怒られないために働く”ようになる。
今は“できたこと”を伝えるようにしたら、全員が動き出しました。
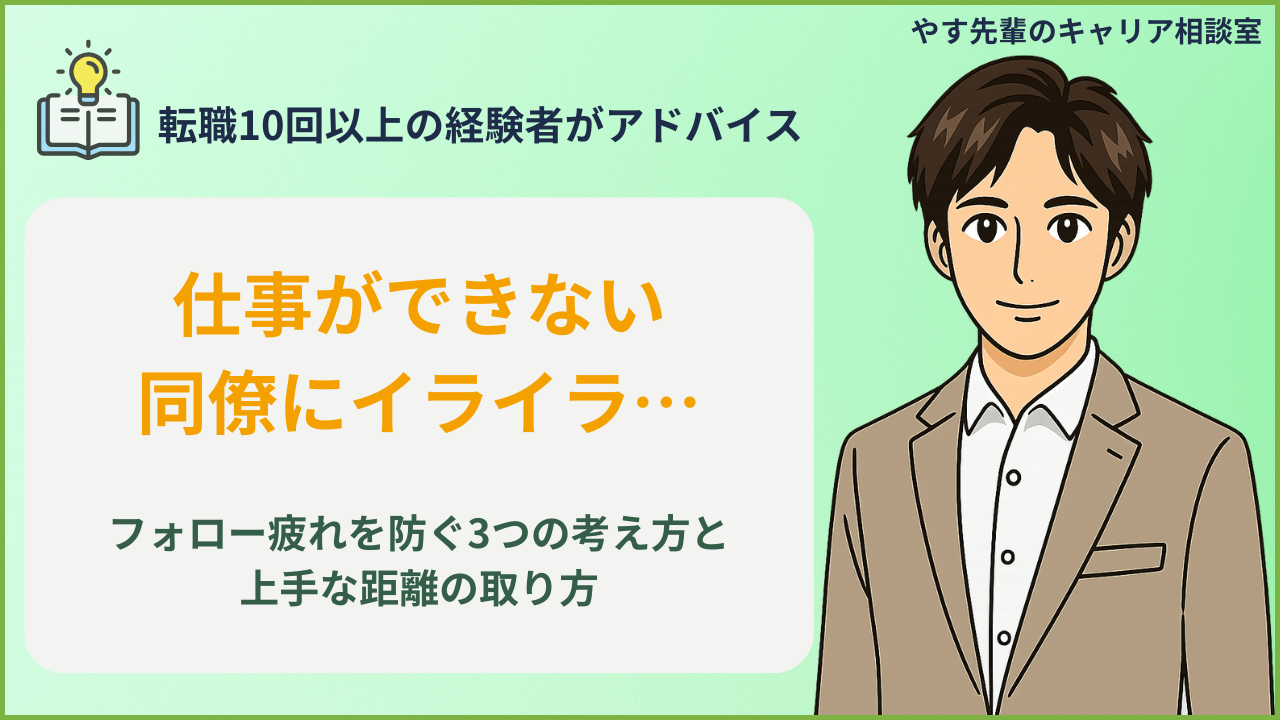
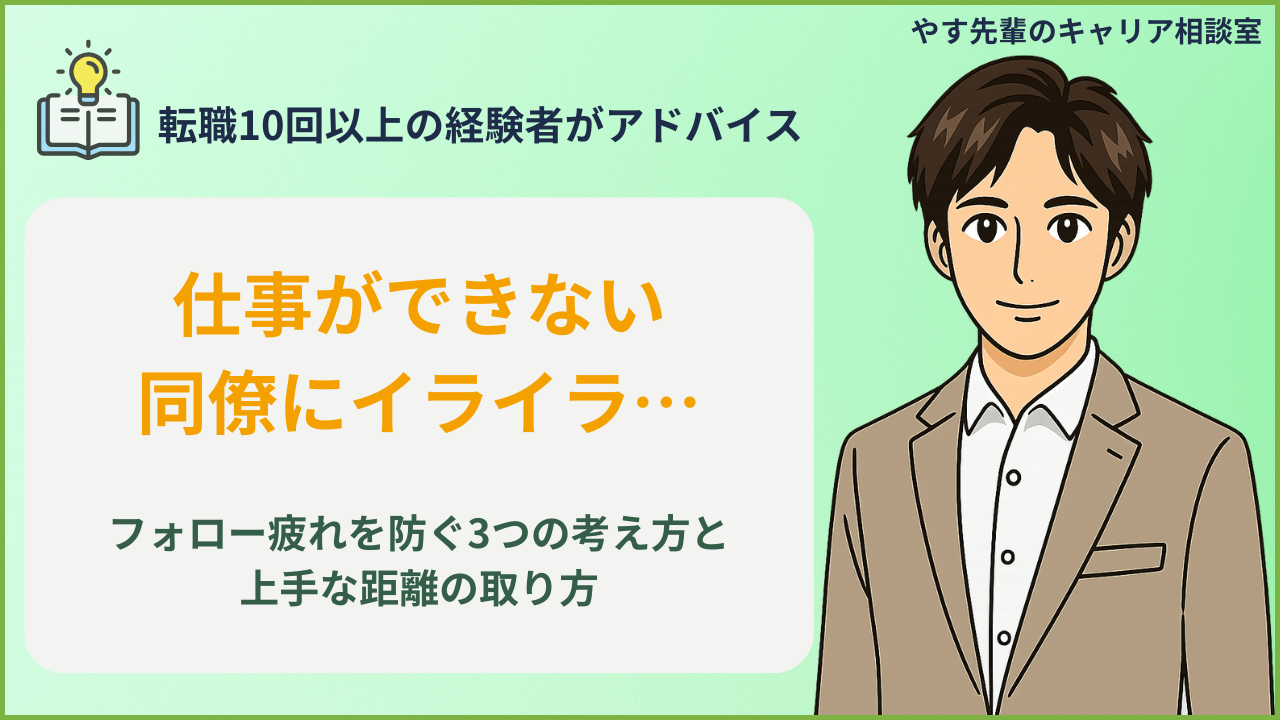
③ フィードバックが具体的で短く伝わる
人を育てるのが上手い人は、伝え方がシンプルです。
「何をどうすればいいか」が一瞬でわかるフィードバックを心がけています。
たとえば、
- ❌「もっと考えて」→ 抽象的で伝わらない
- ⭕「次は〇〇を3行でまとめてみよう」→ 具体的で実行しやすい
ポイントは、「長い説教」よりも「短い行動提案」。
短くても、的確な一言が相手の行動を変えるきっかけになります。



人は“正しい指摘”より、“すぐ動けるアドバイス”を求めてます。
フィードバックは“短くて伝わる”が一番です。
④ 教えるより“考えさせる”質問がうまい
育て上手な人ほど、“質問力”が高いです。
すぐに答えを与えるのではなく、相手が自分で答えを導けるよう導く質問をします。
たとえば、
- 「どう思う?」
- 「なぜそう考えたの?」
- 「他に方法があるとしたら?」
このように問いを重ねることで、相手が自分の考えを言語化し、思考が整理されていきます。
結果として、「自分で考える力」が身につくのです。



“答えを教えない勇気”って大事です。
少しもどかしくても、“考える余白”を与えた方が、後の成長が全然違うんですよ。
⑤ 感情で叱らず、冷静に信頼関係を守る
感情的な叱責は、どんなに正しい意見でも届きません。
人を育てるのが上手い人は、感情を抑えて“伝える目的”を明確にしているのが特徴です。
- 怒るのではなく、「伝える」
- 否定ではなく、「期待」
- 一方的ではなく、「対話」
叱るタイミングも冷静に選び、相手が受け止めやすい形で伝えます。
「叱る=成長のチャンス」に変えられる上司は、本当に信頼されます。



怒るときは、“相手の未来”のためになってるかを自分に問います。
その確認ができないときは、叱らない。これが僕のルールです。
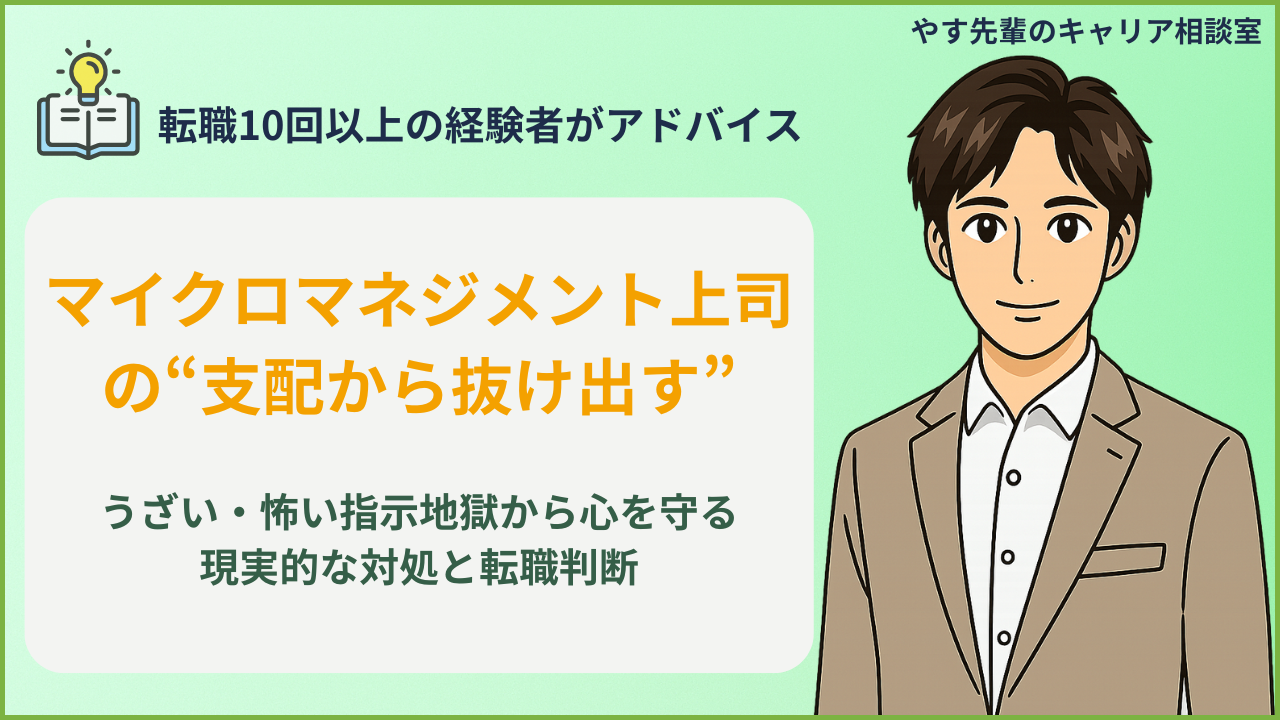
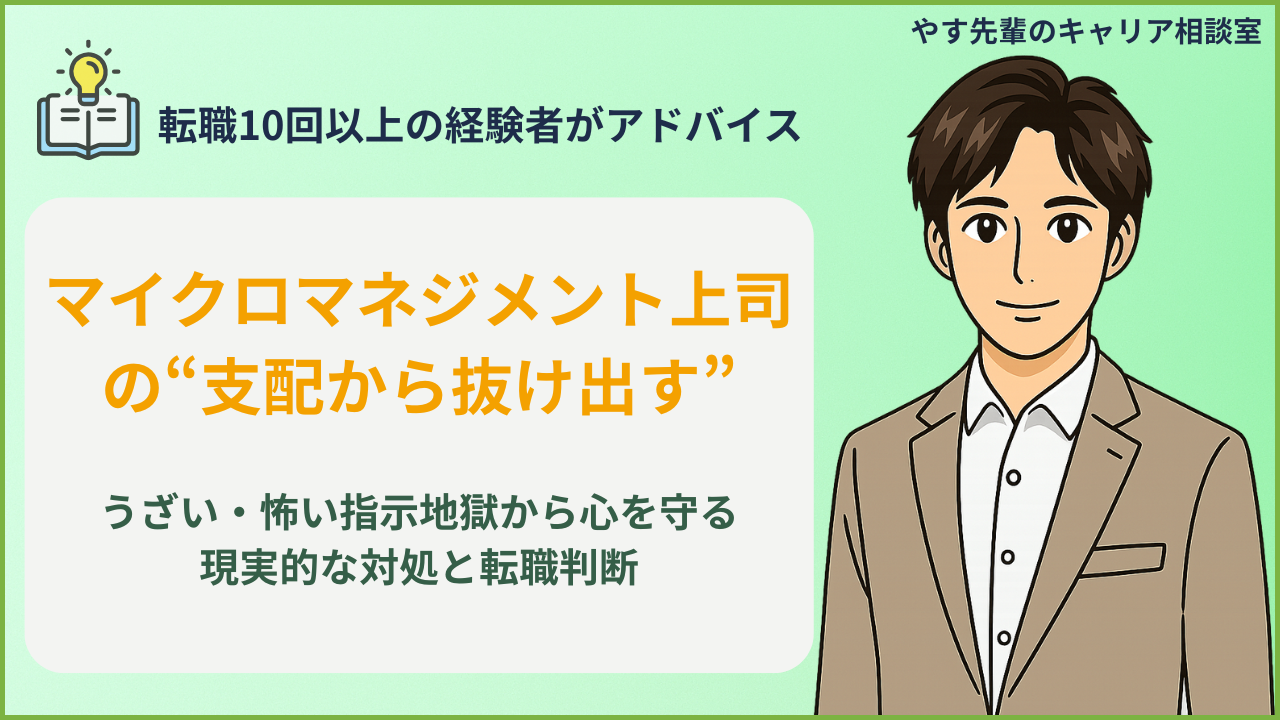
⑥ チーム全体で育てる文化を作る
育て上手な上司は、「一人で教える」ことに固執しません。
“チーム全体で育てる”文化を作るのがうまい人です。
具体的には、
- 教える役割を分担する
- 成長をチームで共有する
- 互いに学び合う仕組みをつくる
これにより、上司1人の負担が減るだけでなく、
チーム全体に「学び合う空気」が広がります。



本当に人を育てるのが上手い人は、“一人で抱えない”。
チームで支え合う文化をつくる力こそ、リーダーシップだと思います。
⑦ 育てながら自分も学び続けている
最後に、人を育てるのが上手い人は、自分の成長を止めない人です。
「教える立場=学びの終わり」ではなく、
「教える立場=学びの始まり」と考えています。
育成の過程で気づいた課題や改善点を、
自分のスキルやマネジメントに還元していく。
その姿勢こそが、部下にとっての最高の“背中”になります。



教えるたびに、自分の理解も深まるんですよね。
育てるって、相手の成長だけじゃなく、自分の成長でもあるんです。
「人を育てるのが下手な人」との違いはここにある
「人を育てるのが上手い人」がいる一方で、残念ながら“育てるのが下手な人”もいます。
その違いは能力ではなく、“関わり方の姿勢”と“感情の使い方”にあります。
どれだけ知識があっても、信頼がなければ人は育ちません。
逆に、多少指導が未熟でも、「この人は自分を見てくれている」と感じれば、人は伸びていきます。
ここでは、育て下手な上司にありがちな3つの特徴と、育て上手な人との決定的な違いを見ていきましょう。
感情的に叱る・押し付ける指導スタイル
人を育てるのが下手な人ほど、「感情」で指導してしまう傾向があります。
怒りや焦りのまま叱ってしまうことで、部下の行動を“止めて”しまうのです。
たとえば、ミスをした新人に対して
- 「なんでこんなこともできないんだ!」
- 「前も言ったよね?」
こうした言葉は、指導ではなく“威圧”になってしまいます。
本人の意欲を削ぐだけでなく、上司への不信感も生み出してしまう結果に。
逆に育て上手な人は、「叱る目的」を常に意識しています。
相手を傷つけるためでなく、「次にどうすればいいか」を冷静に伝える。
叱るという行為の“出口”が違うのです。



感情的な叱責って、その場ではスッキリしても、何も残らないんですよね。
大事なのは、“どうすれば次に進めるか”を一緒に考えること。
叱るより“導く”が上手い人が、本当の意味で人を育てられます。


「自分のやり方」を押しつけてしまう
育て下手な人ほど、“自分の成功体験”を部下にも当てはめようとする傾向があります。
「自分はこうやってきた」「これが正解だ」という思考が強すぎると、
部下の多様な考え方や成長の余地を奪ってしまいます。
人にはそれぞれ、得意・不得意、考え方の癖があります。
だからこそ、指導で求められるのは「合わせる力」。
育て上手な人は、「自分の型」に合わせるのではなく、
“相手の個性をどう活かすか”を考えながら教えていきます。



“俺のやり方が正しい”って言いたくなる気持ち、よくわかります(笑)
でも、それを押しつけた瞬間に部下は受け身になります。
僕も、“どう教えるか”より“どう引き出すか”に変えたら、みんな動き出しました。
失敗を許さず、挑戦の機会を奪っている
人を育てるのが下手な人ほど、“失敗を恐れる環境”を作ってしまいます。
「失敗=評価が下がる」と感じた部下は、
安全な選択しかしなくなり、結果として成長スピードが止まるのです。
逆に、人を育てる上手い人は“失敗を許す文化”を作ります。
- 失敗しても責めず、学びを一緒に整理する
- 「やってみよう」と言える空気を作る
- 成功よりも「挑戦した過程」を評価する
この「安心して失敗できる環境」こそが、成長を加速させる最大のポイントです。



“失敗しないチーム”って、一見良さそうだけど、実は危険なんです。
みんな守りに入って、何も変わらない。
だから僕は、“小さく失敗できるチーム”を作るようにしています。
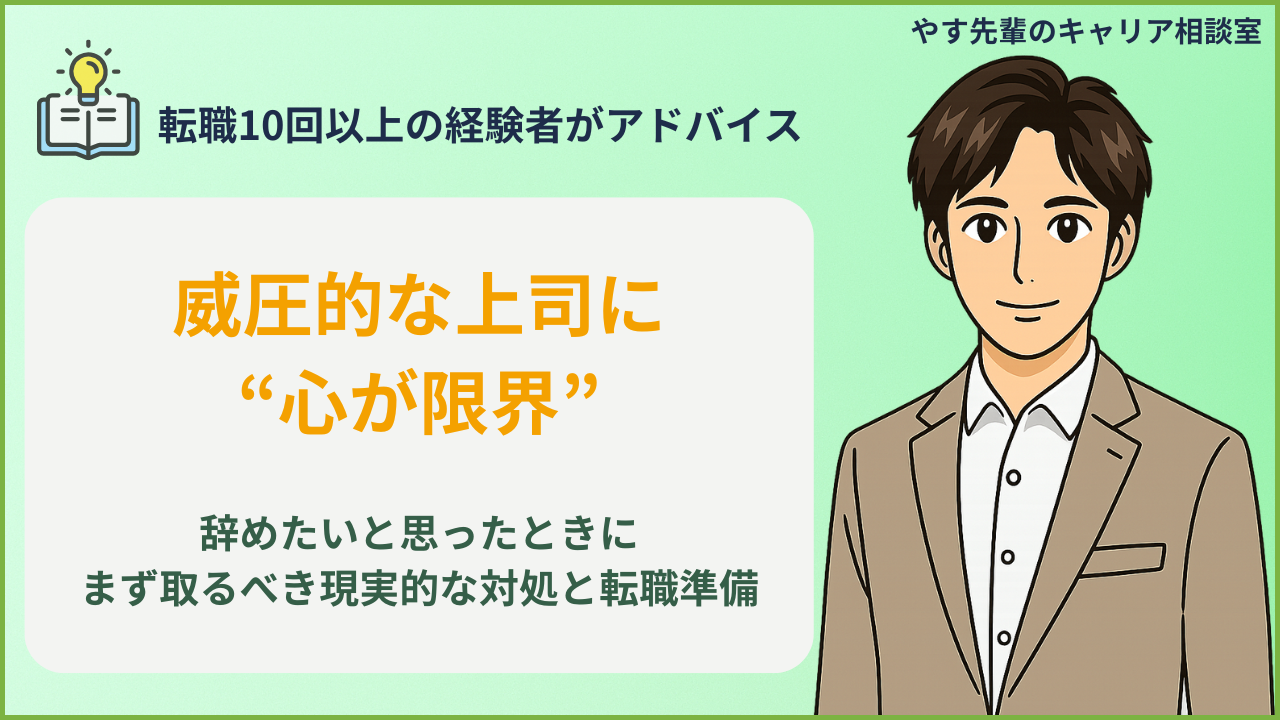
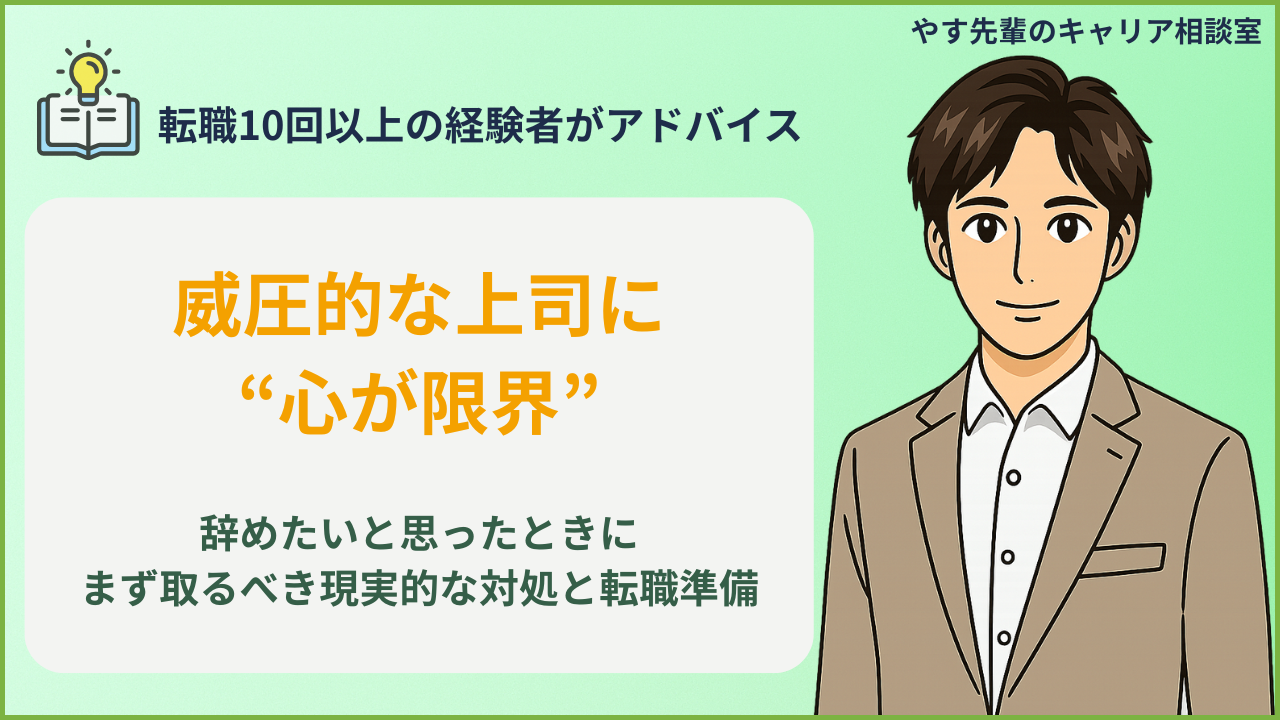
人を育てるのが下手な人は、
- 感情的に叱る
- 自分のやり方を押しつける
- 失敗を許さない
この3つの特徴を持っています。
一方で、育て上手な人は、
- 冷静に伝える
- 相手に合わせる
- 失敗を受け入れる
という真逆の姿勢を取ります。
つまり、育てる力とは「教える技術」ではなく、
“相手を信じて待つ力”と“環境を整える力”なのです。
新人を育てるのが上手い人の関わり方とは?
新人を育てるのが上手い人には、共通した“関わり方の設計力”があります。
それは「たくさん教えること」ではなく、“新人が自分で成長できる環境を整えること”です。
多くの職場では、新人教育が“詰め込み型”になりがちです。
けれど、覚える前に「なぜそれをやるのか」「どう役立つのか」を理解させないと、
新人は“作業としての学習”に留まってしまい、成長スピードが鈍ります。
ここでは、新人育成の上手い人が実践している3つの関わり方を紹介します。
教える前に“目的と全体像”を伝える
育て上手な人は、最初に「全体像」と「目的」を丁寧に伝えます。
人は“意味がわからない作業”にモチベーションを持てません。
たとえば、
「この作業は○○の工程の中で□□の役割を果たしている」
「最初はスピードより正確さを意識してね」
こうして目的を明確にすることで、
新人は「何を意識すればいいか」がわかり、学びが“自分事”になります。
逆に、目的を伝えずに「とにかくやってみて」と任せると、
新人は“何が正しいのか”がわからず、次第に萎縮してしまうのです。



“何をやるか”より、“なぜやるか”を最初に伝えるのが大事。
理解してから動く新人は、吸収スピードも段違いに早いですよ。
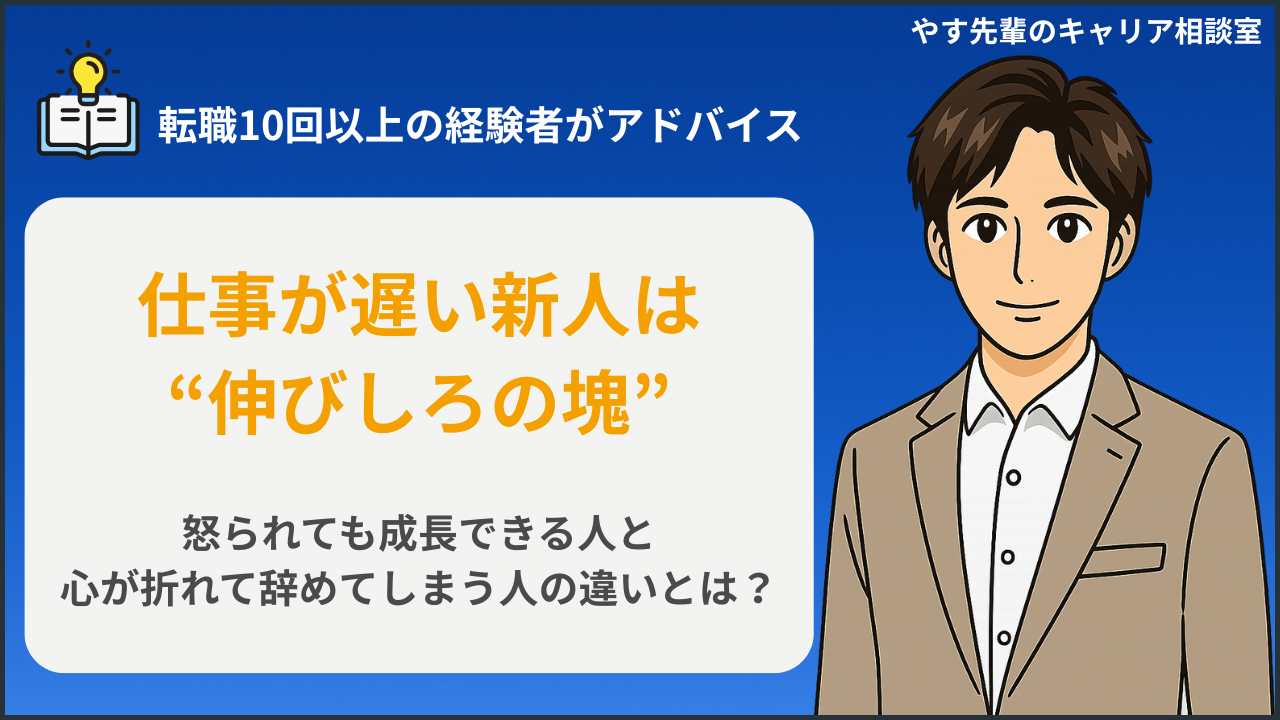
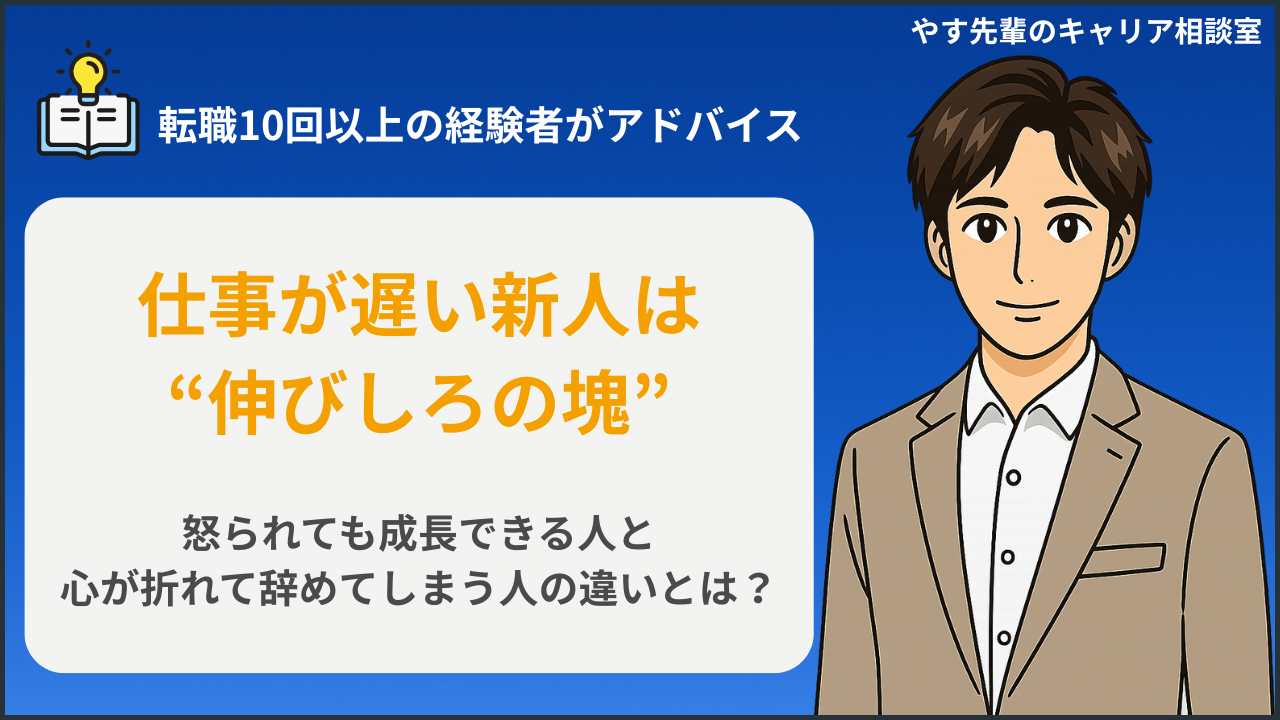
「質問しやすい雰囲気」を意図的につくる
新人教育で最も大切なのは、“質問のハードル”を下げること。
「聞きづらい」「間違ったら怒られそう」と感じた瞬間、
新人は自分から学ぶ姿勢を失ってしまいます。
育て上手な人は、あえて柔らかい雰囲気を意図的に作ります。
- 「質問してくれて助かるよ」
- 「一回で覚えなくて大丈夫」
- 「悩んだら、5分でいいから話そう」
こうした一言で、新人が安心して助けを求められる空気を作るのです。
「報連相ができる新人」に育つのは、指導スキルより“心理的安全性”の設計力にあります。



“わからないです”って言わせてあげられる上司が、育て上手なんですよね。
質問できる雰囲気って、スキルよりも大事な“信頼の証”です。


最初の成功体験を演出して“自信”をつけさせる
新人が伸びる最大のきっかけは、“小さな成功体験”です。
最初に「やればできた」という感覚を持てると、その後の吸収力が一気に上がります。
たとえば、
- 簡単な仕事を任せて「助かったよ」と伝える
- プレゼンの一部を担当させて「いい視点だった」と褒める
- 小さなミスもフォローしながら「挑戦してくれてありがとう」と言う
このように、“成果より行動”を認めることで、
新人は「ここで頑張っていいんだ」と前向きな気持ちを持ちます。
一方で、「最初から完璧を求める上司」は、成長の芽を摘み取ってしまいます。
育て上手な人ほど、“成功を演出する力”を持っているのです。



新人のときって、ほとんどの人が“自信ゼロ”です。
だからこそ、“最初の1勝”を作ってあげるのが上司の役目。
人って、“できた”を積み重ねるほど伸びていきます。


部下を育てるのが上手い上司のマネジメント術
部下を育てるのが上手い上司に共通するのは、「支配ではなく支援のマネジメント」です。
つまり、コントロールするよりも、信頼して任せ、挑戦を支えることを重視します。
優れた上司ほど、「部下を育てる=自分の手を離していくこと」と理解しています。
今回は、そんな“育て上手なリーダー”が実践している3つのマネジメント術を紹介します。
信頼と任せる勇気で人は育つ
人が育つ最大の要素は、「任されている」と感じることです。
上司がすべて指示を出してしまうと、部下は“考える力”を失ってしまいます。
育て上手な上司は、部下の現状を見極めながら、「少し背伸びが必要な仕事」を任せます。
- 完璧じゃなくても挑戦させる
- 結果より“過程”を評価する
- 口を出しすぎず、失敗を見守る
この「任せる勇気」が、部下の責任感と主体性を育てるのです。
また、信頼を伝える言葉を意識して使うのもポイント。
「この仕事、君にお願いしたい」
「君ならできると思ってる」
こうした言葉は、プレッシャーではなく“期待のエネルギー”として伝わります。



“任せる”って、実はすごく怖いんですよね。
でも、そこで我慢して見守れた上司ほど、信頼を勝ち取ってます。
信頼されたいなら、まず“信じる”ことから始めるんです。
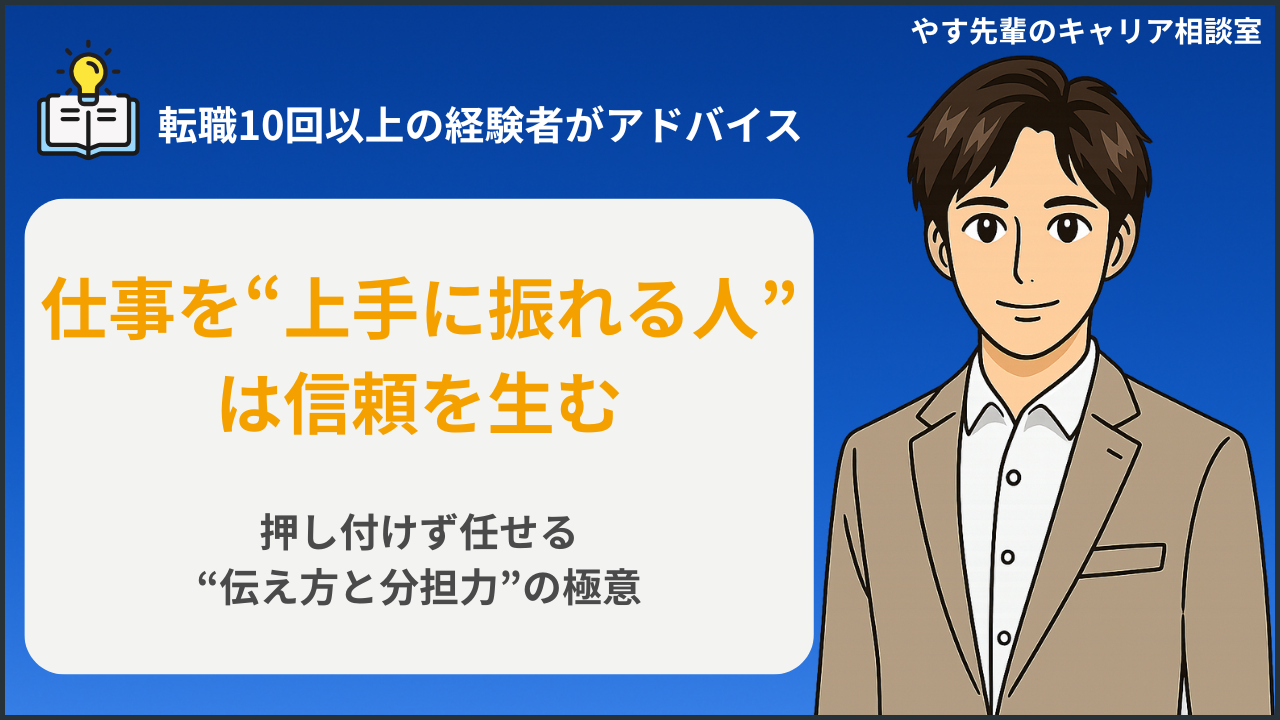
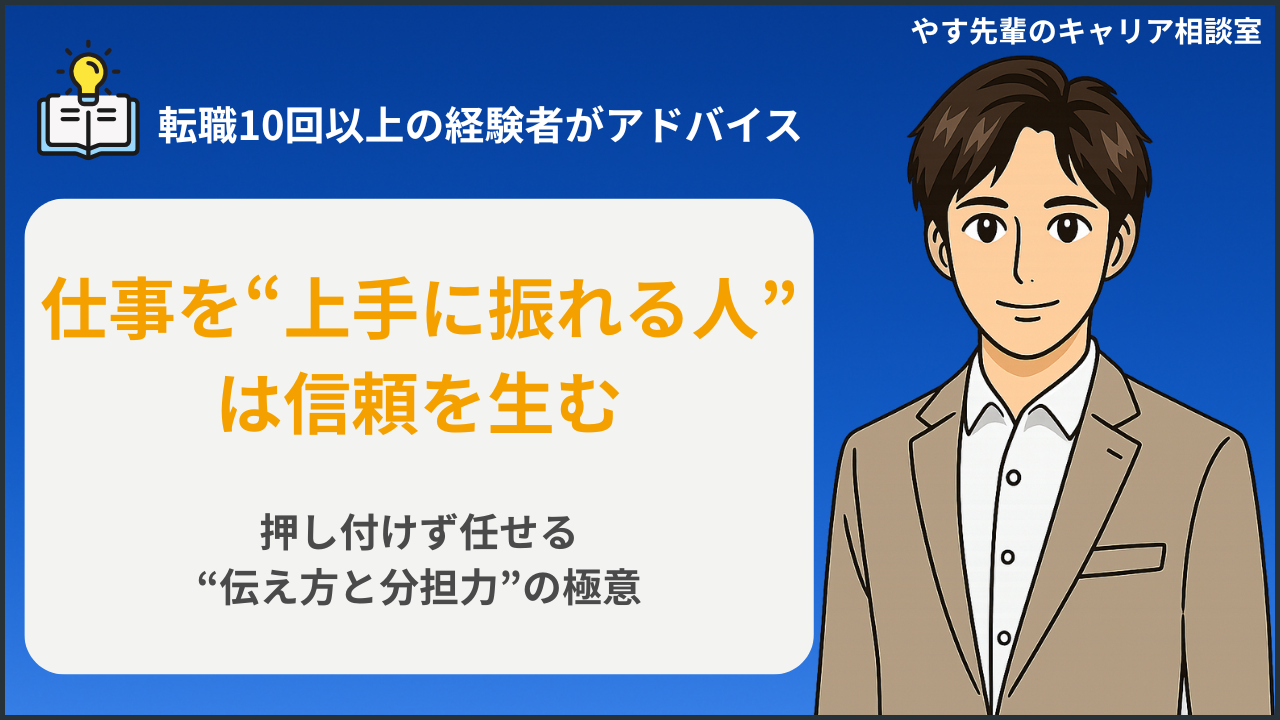
叱るより“問いかける”で気づかせる
育て上手な上司は、「叱る」よりも「問いかける」ことで人を育てます。
感情的に注意するのではなく、自分で考えさせる質問で気づきを促すのです。
たとえば、
- ❌「なぜこんなミスをした?」
- ⭕「どうすれば次は防げると思う?」
- ⭕「この経験から何が学べた?」
このような対話によって、部下は“自分の中で答えを出す力”を身につけます。
叱られて動く人より、気づいて動ける人のほうが強い。それを知っているのが、育て上手なリーダーです。



僕も昔、何度も“叱って反省させよう”として失敗しました。
人は、怒られても変わらない。
でも、自分で“気づけた瞬間”に、ちゃんと変わるんですよ。
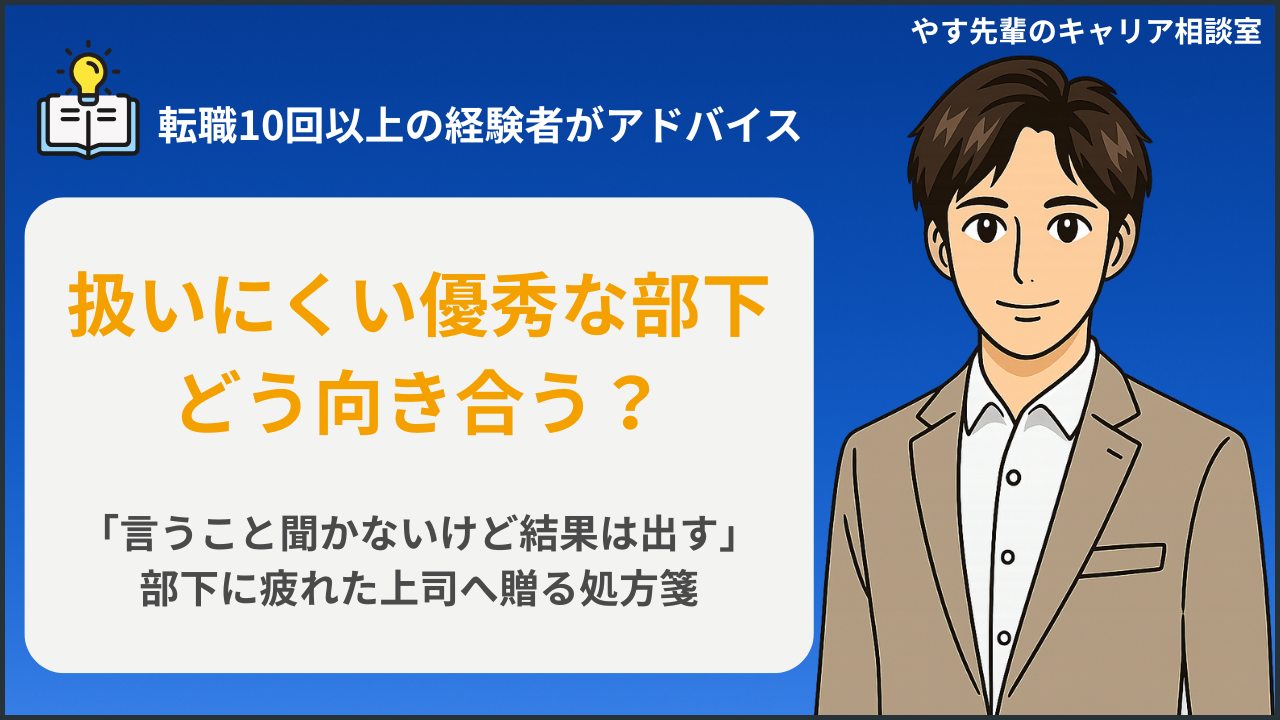
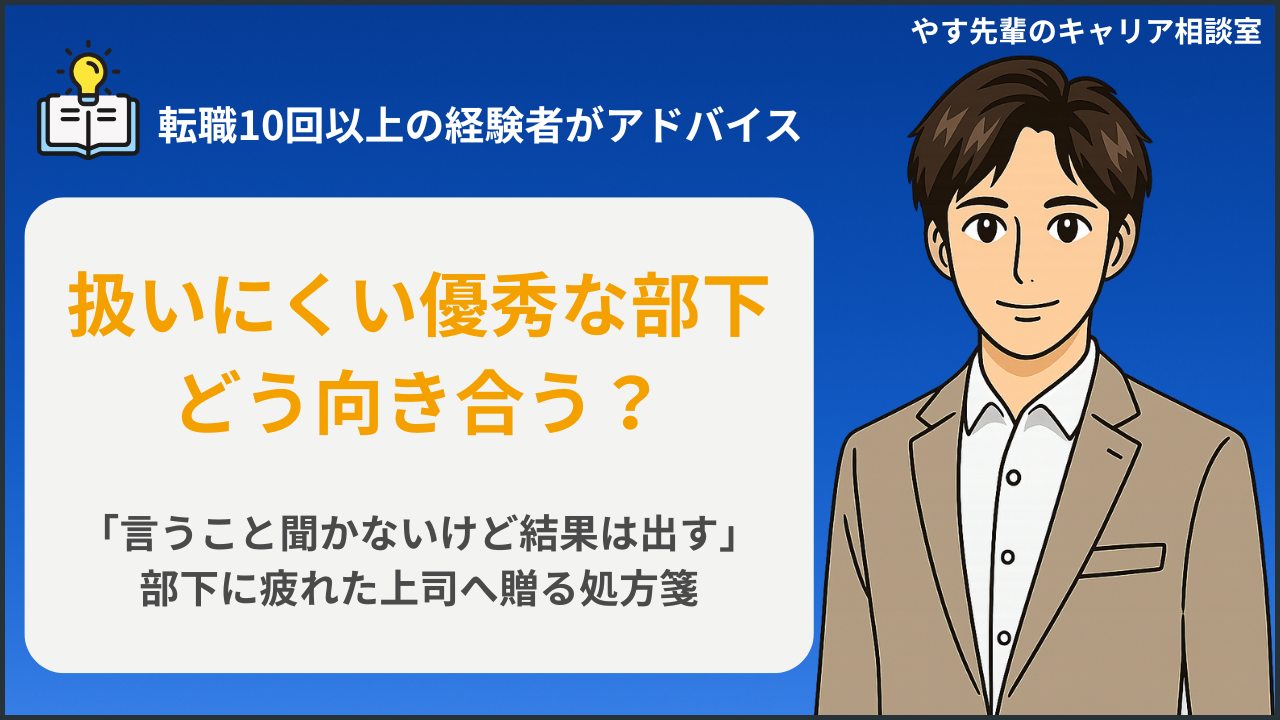
人を動かす力より「人を支える力」を磨く
マネジメントというと、“人を動かす力”が注目されがちですが、
本当に人を育てる上司は、「支える力」の方を磨いています。
- 部下の強みを理解し、活かす場を作る
- 成果よりも努力のプロセスを認める
- 誰よりも部下の「安心感」を優先する
こうした“支える姿勢”が、チームの信頼関係を強くします。
支える上司のもとでは、部下が自ら動き、成長の連鎖が生まれます。
また、部下を育てることは「次のリーダーを育てる」ことでもあります。
「自分がいなくても回るチーム」をつくるのが、本当のマネジメントです。



“動かす”マネジメントは短期的。
“支える”マネジメントは長期的。
結局、後者がチームを強くするんですよね。
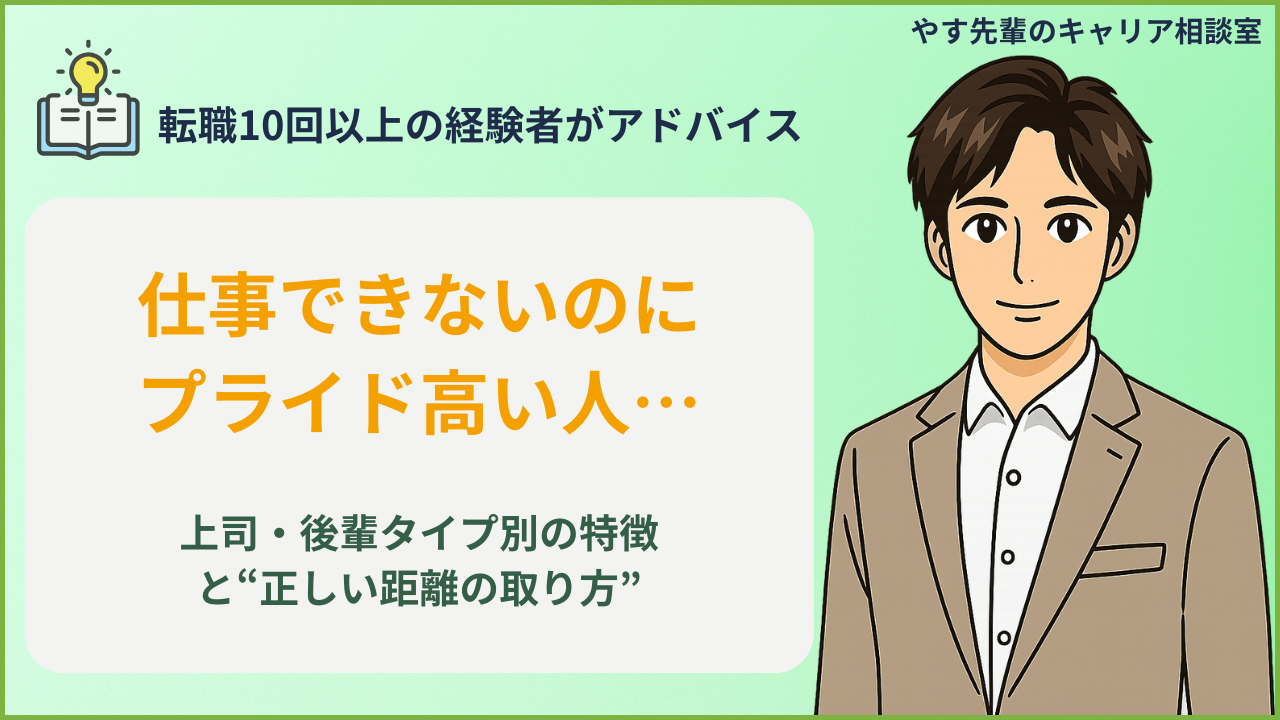
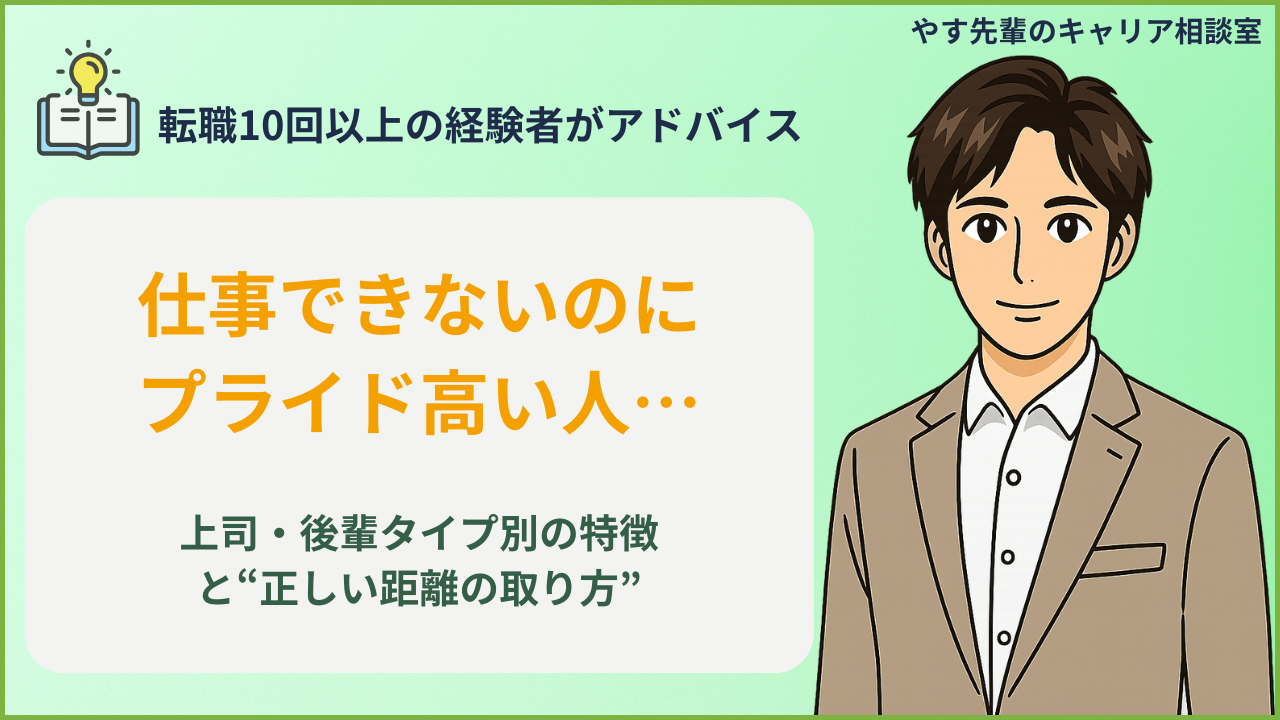
教えるのが上手い人の性格と共通する思考法
「教えるのが上手い人」とは、単に説明が上手い人ではありません。
相手の立場に立ち、理解の段階を読み取りながら、“相手が自分で気づけるよう導ける人”です。
優しさと厳しさのバランスを取りながら、相手のモチベーションを保つ。
その裏には共通する「思考のクセ」や「人との向き合い方」があります。
ここでは、教えるのが上手い人に共通する3つの性格的特徴と考え方を紹介します。
「優しい」より「寄り添う」姿勢を大切にしている
教えるのが上手い人は、単に“優しい人”ではなく、“相手に寄り添える人”です。
優しいだけでは、相手が間違っていても指摘できず、成長の機会を奪ってしまいます。
寄り添うとは、
- 相手の立場や感情を理解した上で、必要なことはしっかり伝える
- 相手の「いまの限界」を見極め、少し背伸びできる課題を与える
- 結果よりも「プロセス」を認める
つまり、「共感」と「導き」を両立できる人です。



“優しい人”は安心感をくれますが、“寄り添える人”は成長のきっかけをくれます。
僕が信頼してきた上司も、優しいだけじゃなく“厳しさに温度”がある人でしたね。
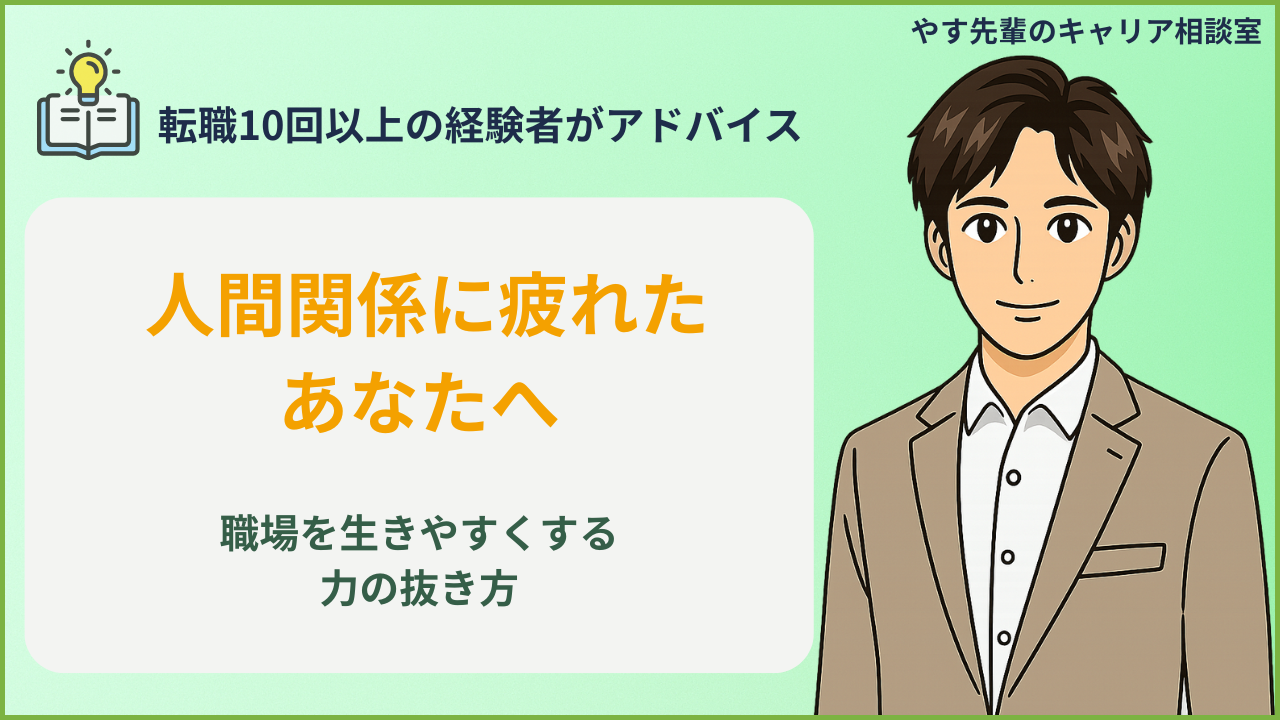
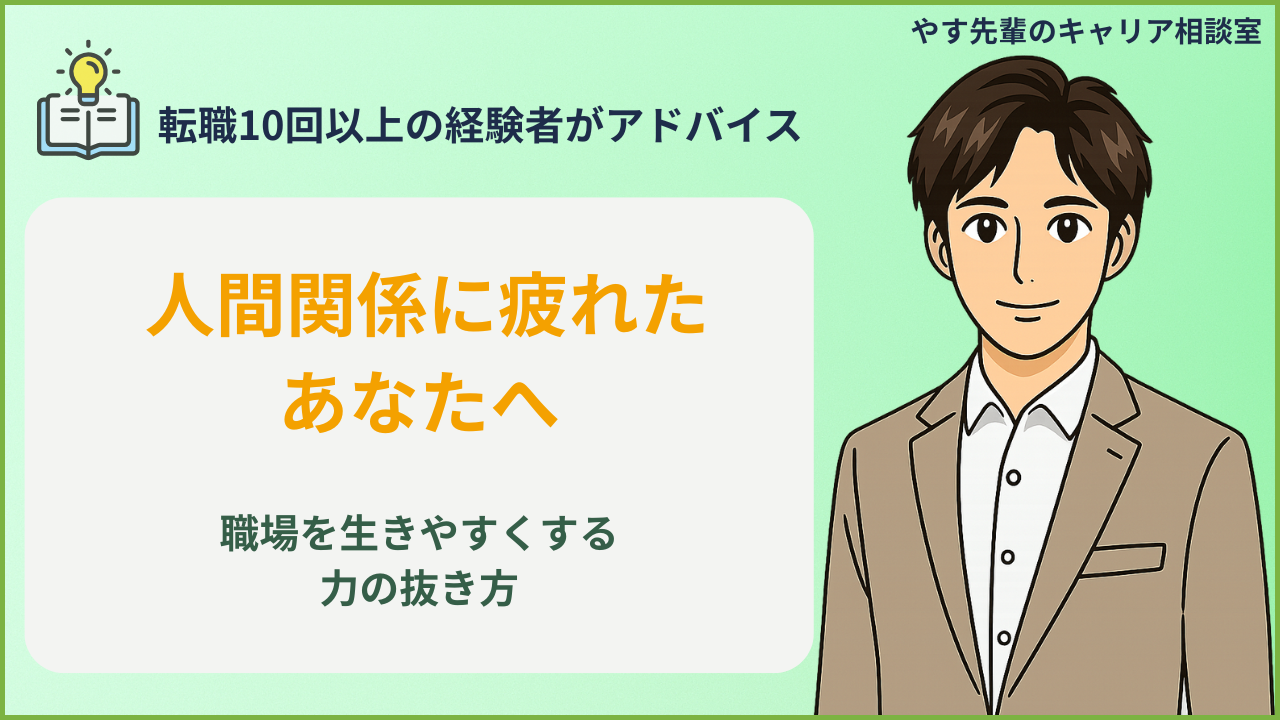
相手の理解スピードに合わせる柔軟性がある
教えるのが上手い人は、“相手の理解ペース”を観察しながら教え方を変える柔軟性を持っています。
同じ説明をしても、すぐ理解できる人もいれば、何度も繰り返さないと定着しない人もいます。
そんな中で、焦らず、相手の反応を見ながら調整できる人が「教え上手」。
- 「この人は図で説明した方が早いな」
- 「まず体験させて、あとで理論を教えよう」
- 「いまは詰め込まず、できた部分を褒めよう」
このように“伝え方を変える努力”を惜しまない人は、自然と信頼される存在になります。
逆に、理解が遅い相手にイライラしてしまう人は、「教えるより先に自分をコントロールする力」を鍛える必要があります。



相手の理解度を測るって、スキルじゃなく観察力なんですよね。
教える人が焦ると、相手はますます萎縮します。
だから僕は“伝えた”じゃなく、“伝わったか”を意識しています。
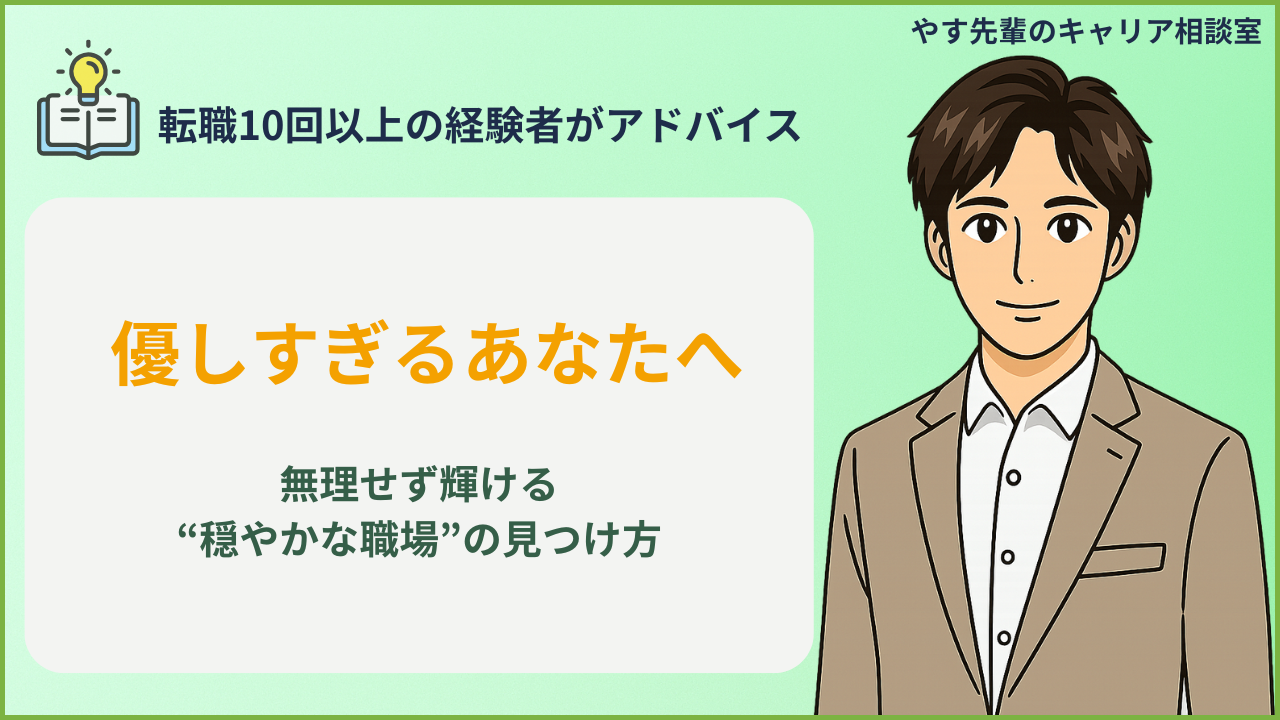
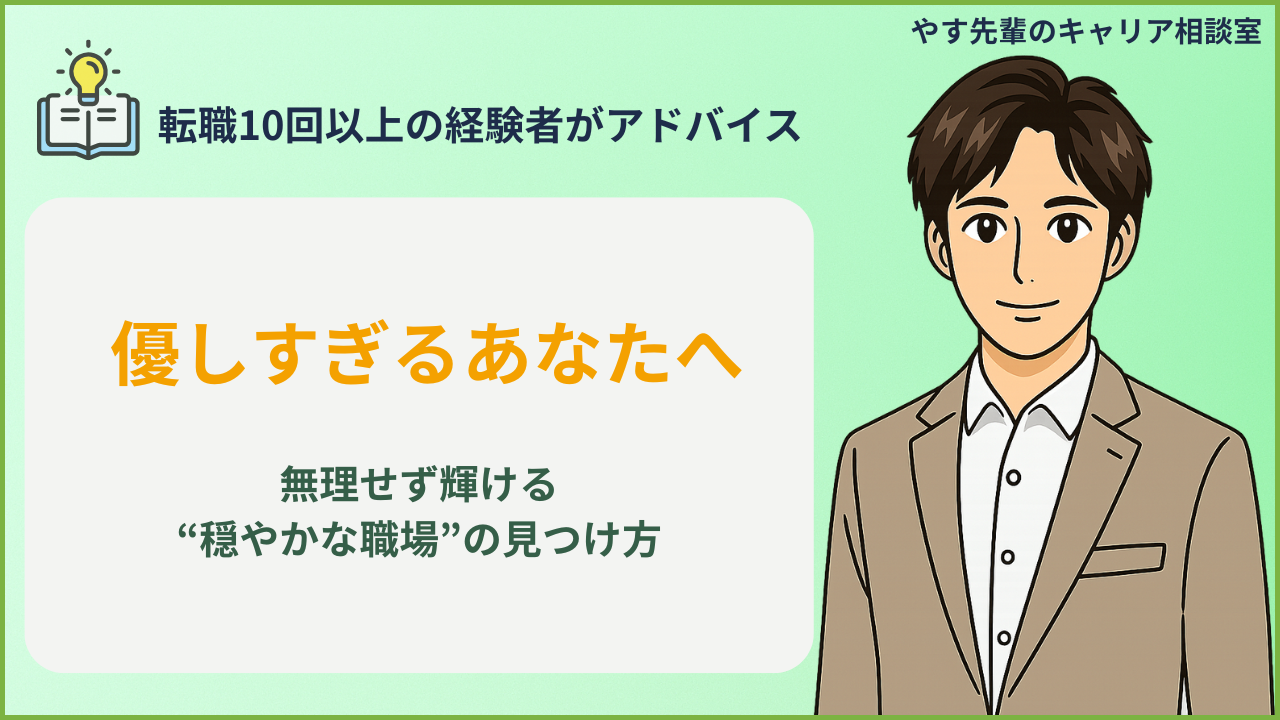
失敗しても“育つ過程”として受け入れられる器の大きさ
教えるのが上手い人ほど、「失敗=成長の材料」と捉えます。
人が学ぶ過程では、ミスやつまずきは避けられない。
それを「できない」と評価するのではなく、「伸びしろ」と見る余裕を持っているのです。
たとえば、
- 失敗したときに「次にどうするか」を一緒に考える
- 結果より「挑戦したこと」を評価する
- 間違いを責めず、改善のヒントを与える
こうした上司・先輩の姿勢が、新人や後輩に“安心して挑戦できる空気”をつくります。



教える側が“失敗を怖がる”と、教えられる側も挑戦しなくなります。
僕は“失敗したらラッキー、学べるじゃん”って空気を意識的に作ってます。
そうすると、自然とチームが前向きになるんですよ。


やす先輩の体験談|「育て下手」から「育て上手」に変わった瞬間
当時の状況:部下に教えても伸びず、空回りの日々
正直、最初は「自分が教えれば部下は伸びる」と思っていました。
でも現実はまったく違いました。
どれだけ丁寧に説明しても、部下は指示待ちのまま。
僕が先回りして動くたびに、部下は自信を失っていき、
気づけばチーム全体が“やらされ感”で動かなくなっていました。
「なんで伝わらないんだ」「もっと努力してくれ」と思っていたけれど、
いま思えば、“育てる”つもりが、“支配していた”のかもしれません。
出会い:育て上手な上司の“待つ姿勢”に学ぶ
そんなとき、部署異動で出会った上司が、まさに「育て上手な人」でした。
その人は、部下の報告にすぐ口を出さず、じっと聞くタイプ。
アドバイスを求められても、すぐに答えを言わずにこう言うんです。
「どう思う?」「自分ならどう動く?」
最初は正直、もどかしかった。
でも、自分の意見を聞いてもらえるうちに、
“自分で考える責任感”が芽生えていったのを覚えています。
そして、僕はその姿勢にハッとしました。
「教えること」より、「考えさせる環境」を作ることが大切なんだと。
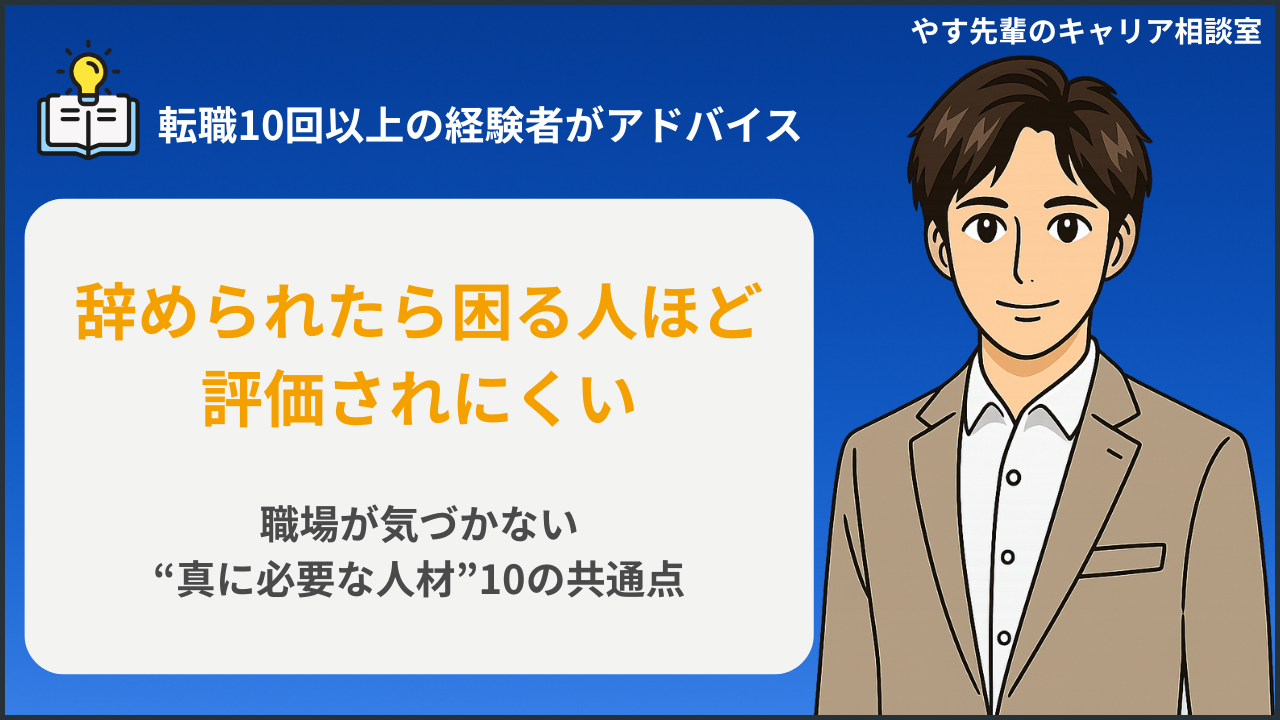
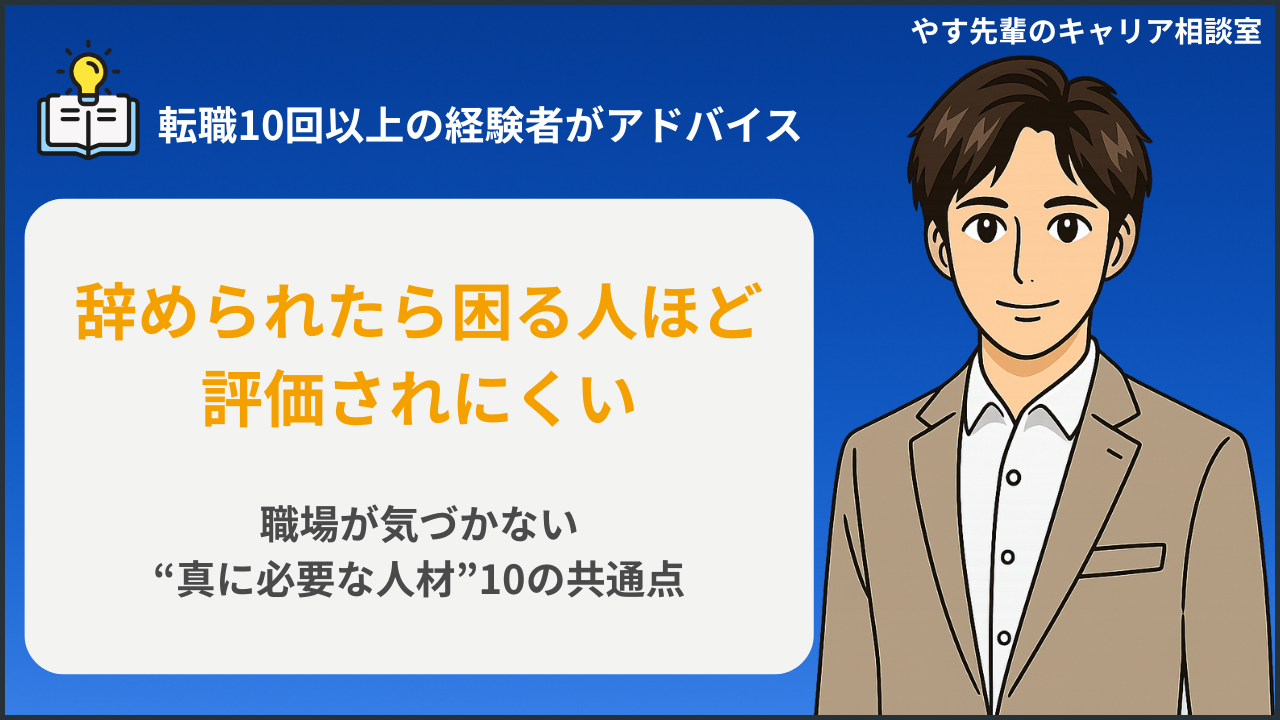
行動:教えるより「任せて見守る」へシフト
それから僕は、「教える量を減らし、任せる量を増やす」ことにしました。
部下が迷っていても、すぐに答えを出さず、
「どうしたらいいと思う?」と問い返すようにしたんです。
最初は不安でした。
でも、少しずつ部下が自分の考えを口にするようになり、
ミスをしても「次はこうしてみます」と自ら改善策を言うようになった。
僕が驚いたのは、
「自分が口を出さない方が、チームがうまく回る」こと。
まさに、“任せることが最強のマネジメント”
でした。
結果:部下が自走し、チーム全体の成果が向上
任せて見守るスタイルに変えてから、
部下の報連相の質が上がり、提案が増えました。
チームの雰囲気も前向きに変わり、
数字だけでなく「チームとしての信頼関係」も格段に良くなったんです。
何より、僕自身が“気持ちに余裕”を持てるようになった。
部下を育てようとしていたつもりが、
実は自分も育てられていたのかもしれません。
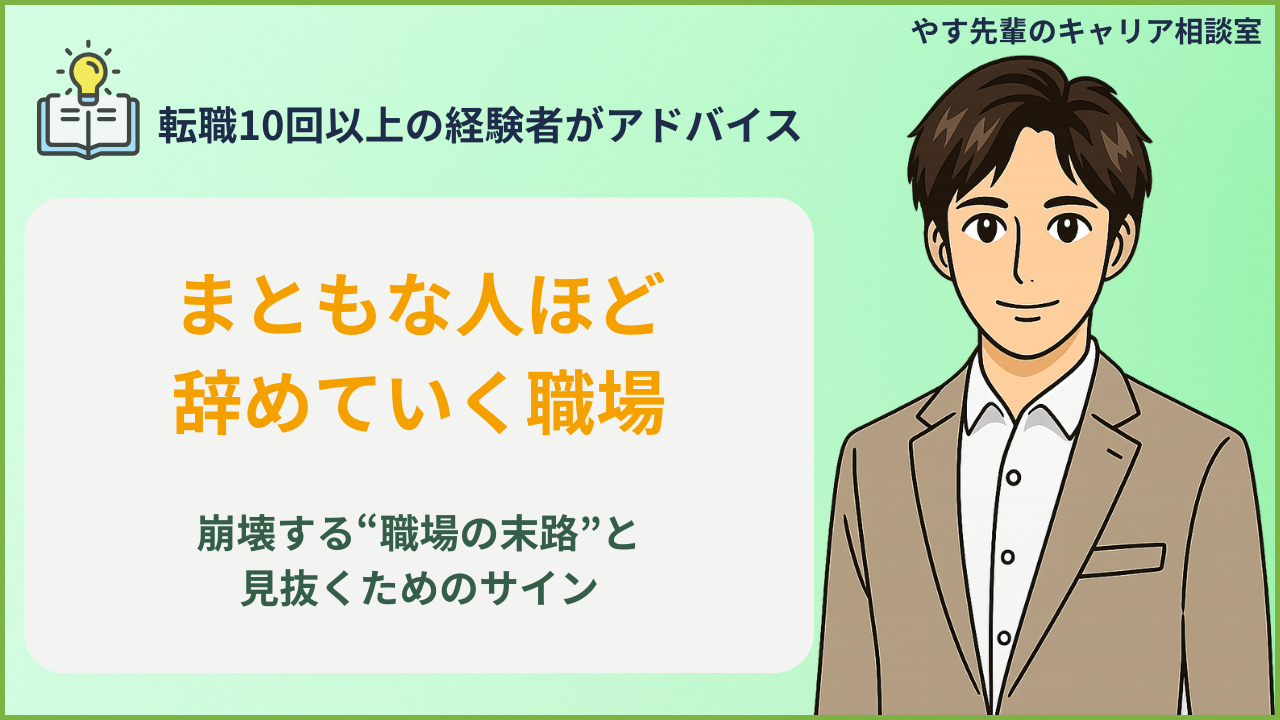
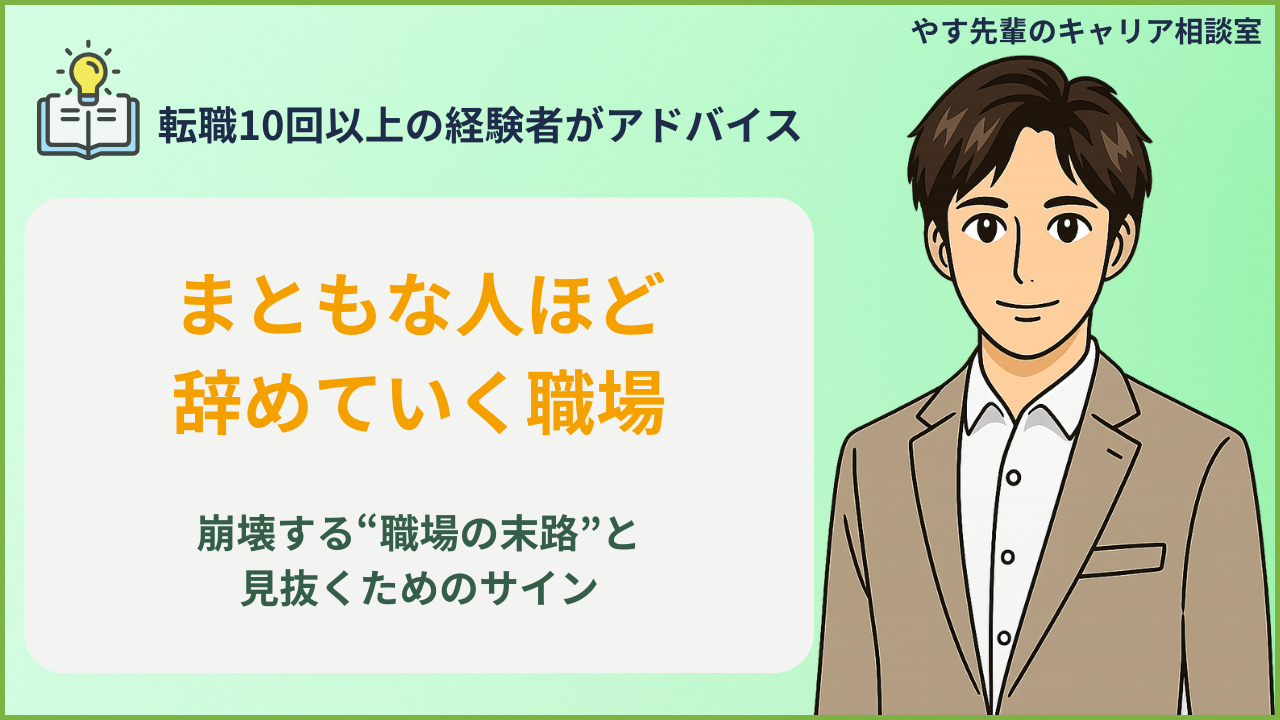
学び:「信じて任せること」が最強の育成法
この経験を通して強く感じたのは、
「人は教えられて動くより、信じられて伸びる」ということ。
どんなにロジックを駆使しても、信頼がなければ人はついてきません。
逆に、信頼をベースにした関係では、失敗すら学びに変わる。



“任せる勇気”って、育てる覚悟でもあると思うんです。
上司が信じきった瞬間、部下は本当に変わる。
育成の本質は、相手を動かすことじゃなく、“信じて待つ力”なんですよ。
いまでは、「育てるのが上手い人」と言われることもあります。
でもその裏には、たくさんの失敗と学びがありました。
そして結論はひとつ、
「信じて任せる上司」こそ、最強の育て手です。
人を育てるのが上手い人になる3つの習慣
人を育てるのが上手い人には、「偶然」ではなく「習慣」があります。
それは、特別なスキルではなく、日々の小さな関わり方の積み重ね。
- 感情ではなく“行動”に目を向ける
- 相手の意見を引き出す余白をつくる
- 成長を見逃さず、すぐに認める
この3つを実践できる人が、結果として「人を動かす力」や「巻き込む力」を持つようになります。
ここでは、育て上手な人が自然に行っている3つの習慣を紹介します。
フィードバックを“行動ベース”で伝える
育て上手な人ほど、「人格」ではなく「行動」に焦点を当ててフィードバックします。
たとえば、
- ❌「やる気がないね」
- ⭕「報告が昨日より早くて助かったよ」
同じ伝え方でも、相手の受け取り方は大きく変わります。
行動ベースの指摘は、相手に「何を変えればいいか」が明確に伝わるため、次の行動につながるのです。
また、小さな進歩をその場で認めることも大切です。
「昨日よりスムーズでしたね」
「さっきの説明、わかりやすかったよ」
その一言が、本人のやる気を大きく引き上げます。



僕も昔、“できない理由”ばかり伝えてたんです。
でも“できた部分”を伝えるようにしたら、部下の表情が変わった。
行動を認めるって、信頼を積み上げることなんですよね。
相手の考えを引き出す質問を心がける
「人を動かす力のある人」は、命令ではなく質問で相手を動かすことができます。
問いかけによって、相手の思考を促し、主体性を引き出すんです。
たとえば、
- 「どう感じた?」
- 「次にやるとしたら、どんなやり方が良さそう?」
- 「もし自分がリーダーなら、どう判断する?」
このような質問は、“考える責任”を相手に渡します。
それによって、指示待ちではなく、自走できる人材が育ちます。
また、質問のトーンも重要です。
詰問ではなく、「興味を持って聞く」姿勢が信頼関係を作ります。



問いかけるって、相手を信じてる証拠なんですよね。
“考えられる人だ”と認めることで、自然と成長していく。
指示より“問い”の方が、よっぽど強いマネジメントです。
成長の瞬間を逃さず「言葉で承認」する
育て上手な人は、部下や後輩の“変化の瞬間”を見逃さない。
そして、その場で“言葉で伝える”ことを習慣にしています。
「前より落ち着いて話せてたね」
「その提案、いい視点だったよ」
こうした一言は、本人にとって“自分が成長している実感”になります。
人は、「見られている」「認められている」と感じたときに最も伸びるもの。
一方で、無反応や無関心は、どんな努力も無力化してしまいます。
言葉にしなければ、信頼も成果も伝わらないのです。



人は“できた”瞬間に褒められると、次も頑張れる。
でも褒めるタイミングが遅いと、効果は半減します。
“気づいたときにすぐ伝える”これだけで育成の質は劇的に変わります。
育て上手な人の3つの習慣は、どれも特別なことではありません。
- 行動を見て伝える
- 問いで引き出す
- 成長をすぐ認める
この3つを繰り返すだけで、相手の成長速度も信頼関係の深さも変わります。
“人を動かす”のではなく、“人が動きたくなる環境”を作れる人こそ、
本当の意味で人を育てるのが上手い人です。
まとめ|「人を育てる上手さ」は才能ではなく姿勢
人を育てるのが上手い人。それは、特別な才能を持つ人ではありません。
どんな上司・先輩でも、「信頼する姿勢」と「待つ勇気」があれば、誰でも育て上手になれます。
「教えるのが上手い人」とは、実は“人を信じて任せられる人”のこと。
焦って口を出さず、相手の成長を信じて見守る。
そして、小さな行動の変化を見逃さず、「ちゃんと見ているよ」と伝える。
それこそが、
- 部下を育てる上司に共通する「観察力」
- 人を動かすリーダーに欠かせない「承認力」
- チームを成長させる「信頼の姿勢」
です。



「昔の僕は“教える=指導すること”だと思ってました。
でも本当に人が伸びる瞬間って、“信じてもらえたとき”なんですよね。
育てるって、教えることじゃなく、“相手の可能性を信じること”なんです。」
明日からできる“育て上手”の第一歩は、「待つ勇気」を持つこと。
相手の成長を信じて、一歩引いて見守る。
その姿勢こそが、人を育て、チームを強くしていく最大の武器になります。
よくある質問
- 教えるのが苦手でも部下を育てられる?
-
はい、育てられます。大切なのは「教える技術」ではなく「相手を理解しようとする姿勢」です。
完璧な説明よりも、「どこでつまずいてる?」と聞ける上司の方が部下は安心します。
“寄り添って一緒に考える”だけで、信頼と成長の循環が生まれます。 - 新人が思うように育たないのは上司の責任?
-
一概には言えません。新人の性格・環境・経験値によって成長スピードは違います。
ただし、上司の「関わり方次第」で成長を後押しすることはできます。
焦らず、“短所を叱るより長所を伸ばす”ことを意識しましょう。 - 育て上手な上司の言葉がけにはどんな特徴がある?
-
共通点は、「評価」よりも「承認」が多いことです。
たとえば「助かった」「ありがとう」「よく気づいたね」など、
“行動を見ている”言葉が信頼を生みます。
承認は、部下のやる気を最大化する最もシンプルなマネジメントです。 - 優しいだけの上司ではダメ?
-
優しさは大切ですが、“甘さ”とは違います。
本当に育て上手な上司は、「相手の成長のために厳しく言える人」です。
優しさと厳しさのバランスがあるからこそ、部下は安心して挑戦できます。 - 自分より優秀な部下をどう育てればいい?
-
恐れず、「任せる勇気」を持ちましょう。
自分より優秀な部下は、上司の管理よりも“信頼”と“機会”を求めています。
方向性だけを示し、口出しは最小限に。
部下の成功をチームの成果として喜べる上司が、本物のリーダーです。