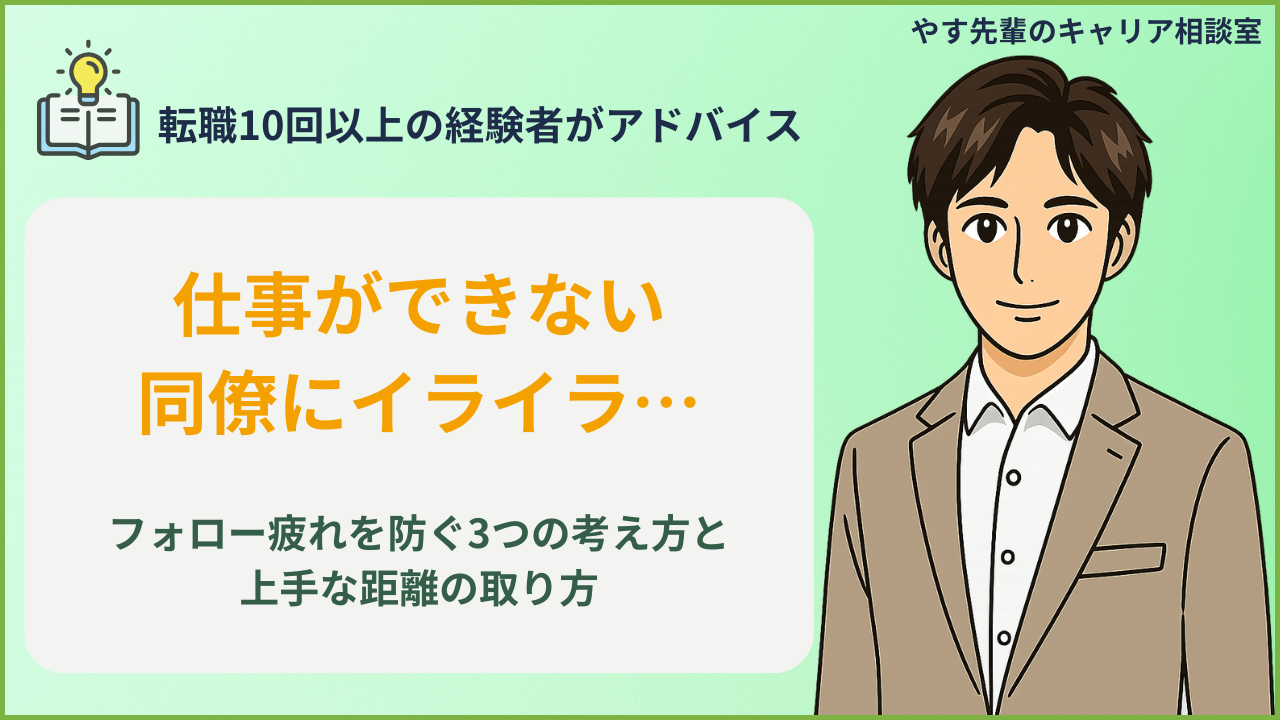やす先輩
やす先輩40代半ば、転職10回の管理職。上場もベンチャーもブラックも経験してきました。失敗も学びも交えながら、キャリアや働き方に悩むあなたへ“現実的な解決策”を届けます。
⇒詳しいプロフィール
「どうしてあの人は、何度言ってもできないんだろう…」
そう思いながら、今日も同僚のフォローに追われていませんか?
ミスの尻拭いで自分の仕事は後回し。
なのに上司は注意せず、気づけば“できない同僚を支える役”が固定化されている。
僕自身も、まさに同じ状況を経験しました。
フォローすればするほど負担が増え、それでも断れず、「イライラする自分の心が狭いのかもしれない」と、自分を責めるようになっていったんです。
でも、先に伝えます。
あなたが悪いわけではありません。
フォロー疲れは、優しさや責任感がある人ほど陥りやすい“構造的な消耗”です。
この記事では、
・仕事ができない同僚にイライラしてしまう本当の理由
・フォローしすぎないための正しい距離感
・自分だけが損をしない考え方と行動
を、やす先輩の実体験をもとに具体的に解説します。
もし今、
「このままここで頑張り続けて意味があるのか?」
「評価されない役回りに固定されていないか?」
と感じているなら、一度ミイダスで自分の市場価値を確認してみてください。
今の職場で“便利な人”になっているだけで、あなたの価値が低いわけではありません。
「逃げ道がある」と分かるだけで、同僚との距離感や、心の余裕は大きく変わります。
この記事で、フォロー疲れを溜め込まないための判断軸を一緒に整理していきましょう。
仕事ができない同僚にイライラするのは普通のこと
「なんであの人、何度言ってもできないんだろう」
「結局いつも自分がフォローしてるじゃないか」
そんなふうに感じて、ついイライラしてしまう。
でも大丈夫。それはあなただけではありません。
僕も何度も同じような気持ちを経験しました。
仕事ができない同僚にストレスを感じるのは、あなたが責任感のある証拠です。
ここでは、そのイライラの正体を少し整理してみましょう。
なぜ「できない人」にほど腹が立つのか
不思議なことに、本当に何もできない新人よりも、
「ある程度できるのに詰めが甘い同僚」の方が腹が立つことがありますよね。
その理由は、人は「自分と同じ基準で動く」と無意識に期待してしまうからです。
あなたが丁寧に仕事を進めるタイプなら、
ミスを繰り返す同僚を見て「どうして改善しないんだ」と感じてしまう。
つまり、怒りの正体は“裏切られた期待”なんです。
もう一つの理由は、あなたが「自分の仕事に誇りを持っている」から。
だからこそ、同僚のミスで自分の努力が無駄になると感じると、強く反応してしまう。
責任感がある人ほど、他人の怠慢に耐えられないんです。



僕もかつて「なんでこんな簡単なこともできないんだ」とイライラしてました。でも、それは自分が“ちゃんとやってきた”からこそ感じる怒りなんですよね。頑張り屋ほど、人の手抜きに敏感になるものです。
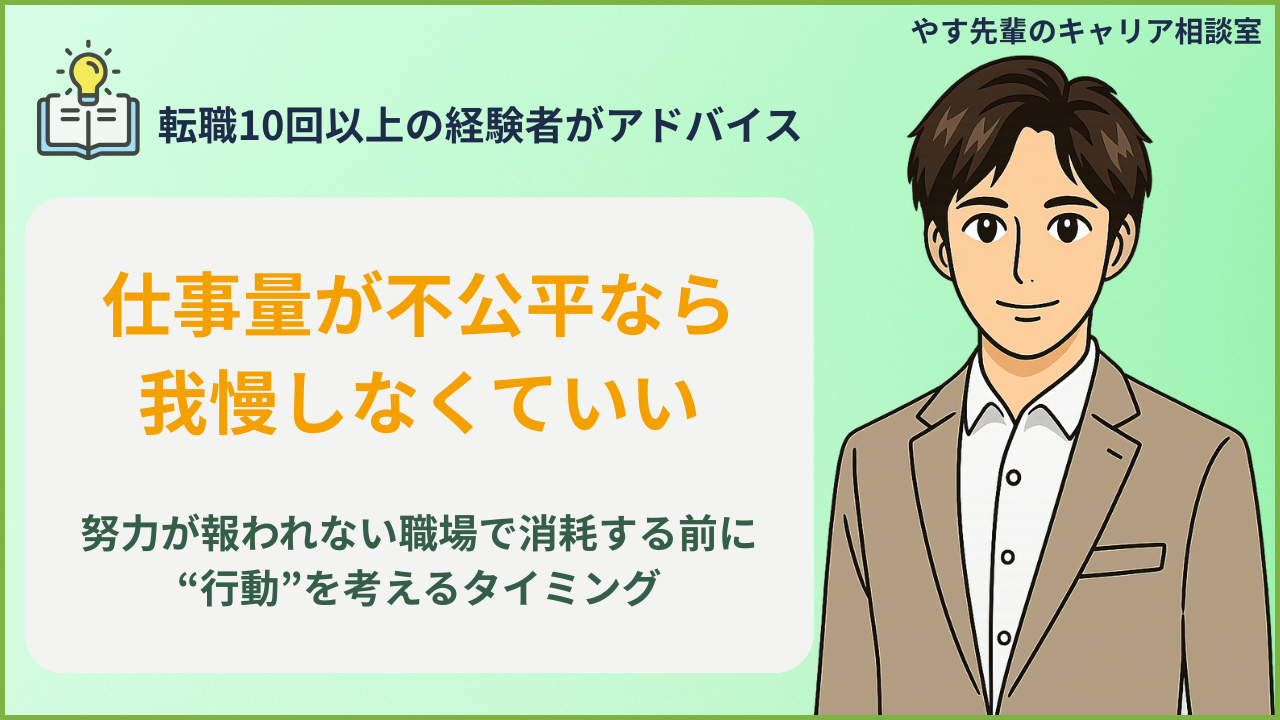
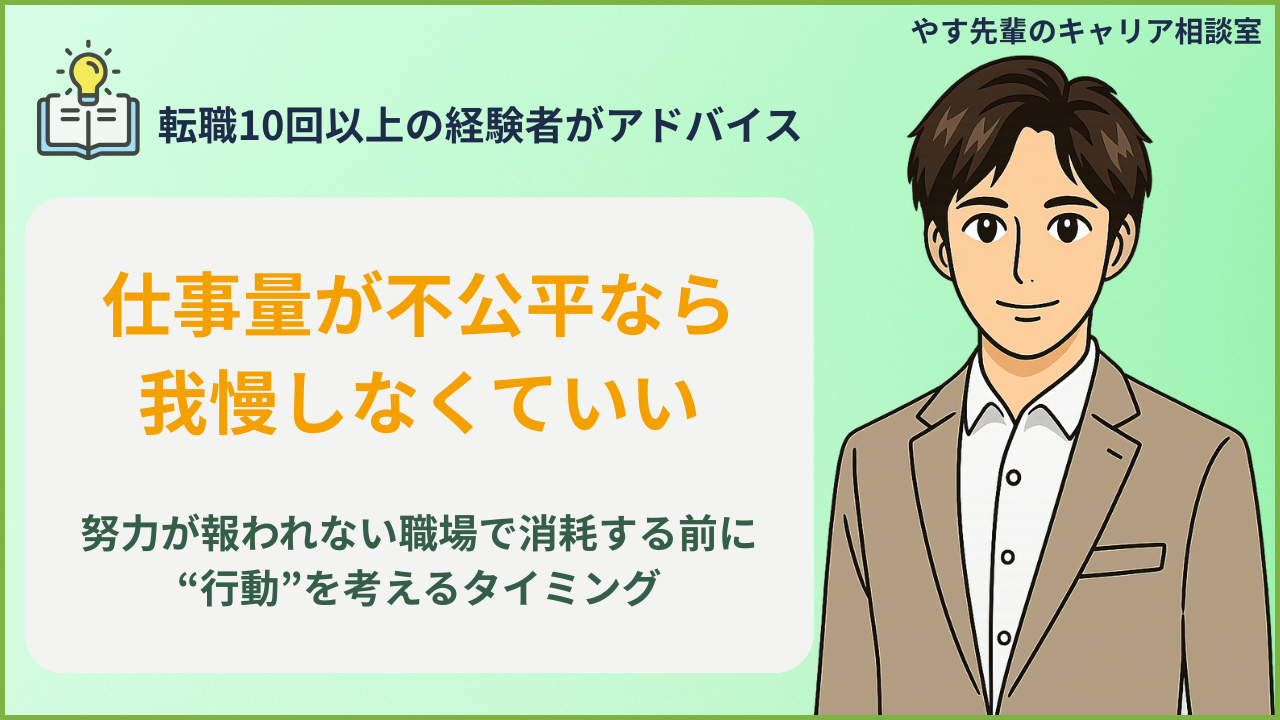
「優しくできない自分」を責める必要はない
同僚にきつく当たってしまったあと、「自分は心が狭いのか」と落ち込む人も多いでしょう。
でも、それも自然な反応です。
「できない人に優しくするべき」と頭ではわかっていても、
現場で自分の仕事が止まっているときに冷静でいられる人なんてほとんどいません。
むしろ、その状況で無理に笑顔を作る方が危険です。
人はストレスが一定を超えると、脳が“防衛モード”に入ります。
これは悪意ではなく、自分を守る自然な反応なんです。
だから、「優しくできなかった自分」を責めるより、
「今、自分は疲れてるんだ」と気づくことの方が大切です。



僕も昔、フォローばかりで心がすり減った時期がありました。
そのとき医師に言われたのは、「優しくなれないのは、もう限界が近いサイン」です。
人を変えるより、まずは自分を守ること。これが本当の優しさなんです。
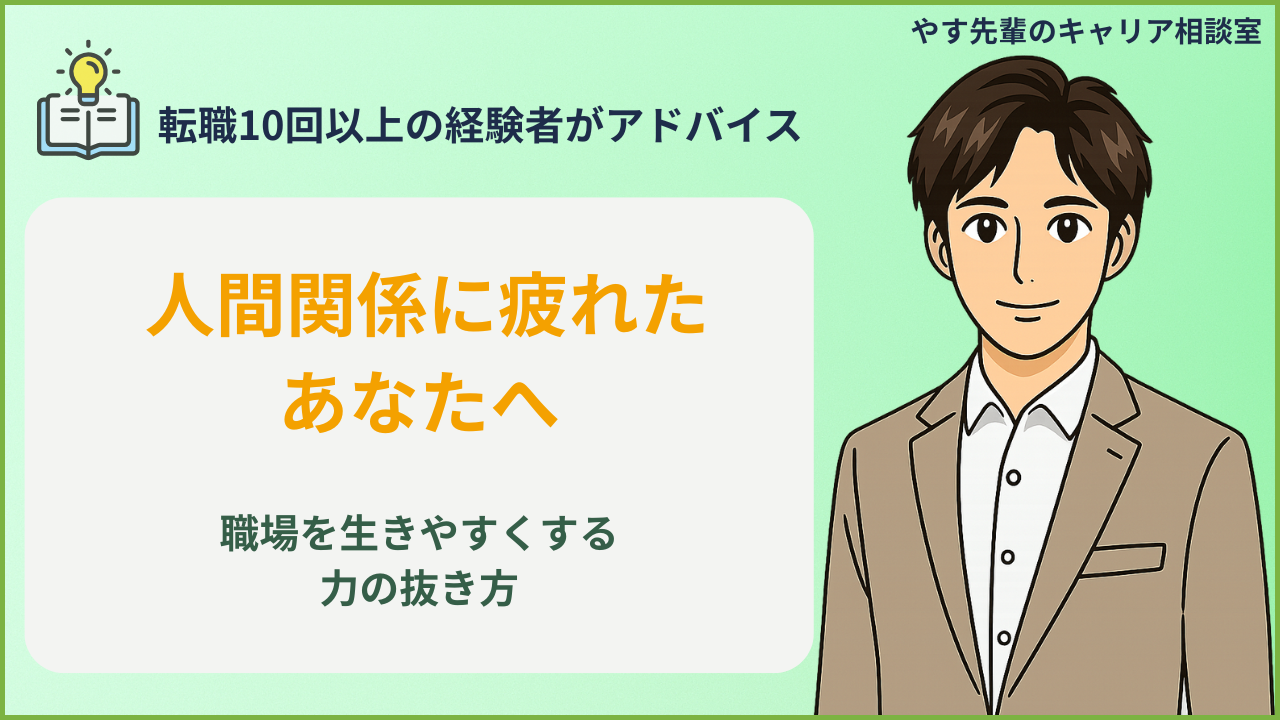
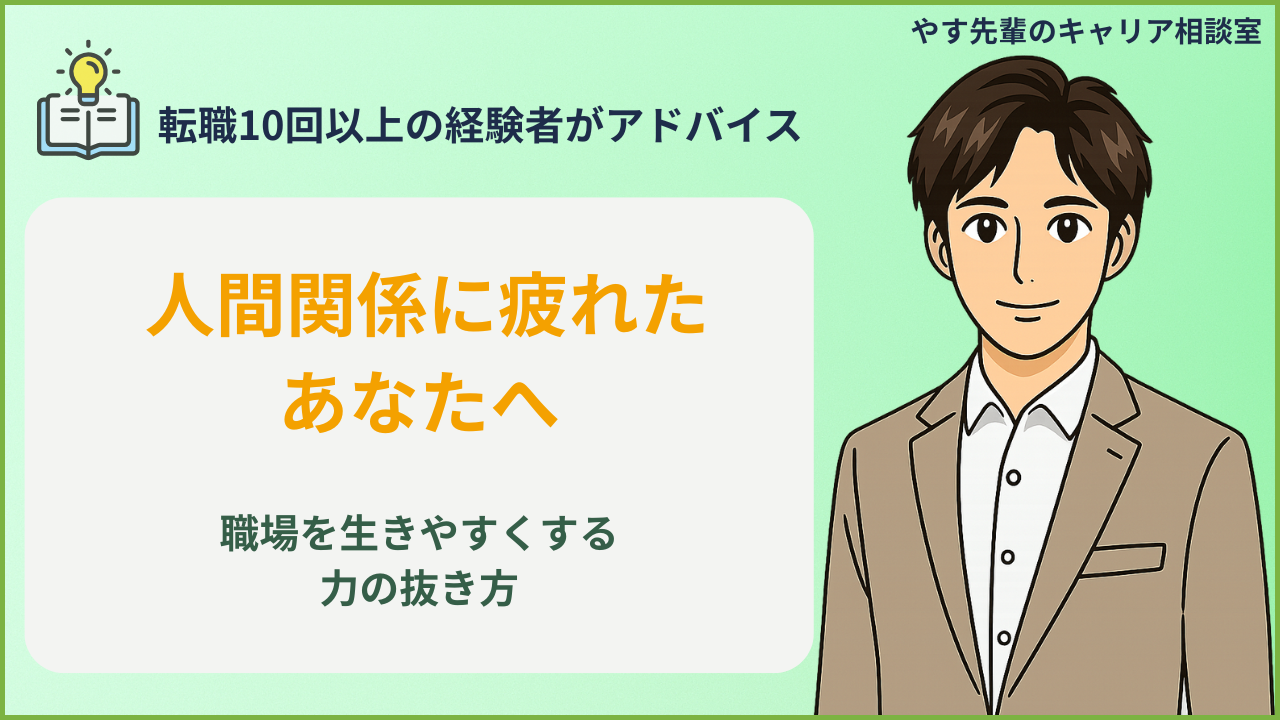
ストレスの根本は「評価と責任の不均衡」にある
仕事ができない同僚に対するストレスの多くは、
実は“自分ばかり損している”という感覚から来ています。
- 自分がフォローしても、評価は変わらない
- 同僚は怒られず、なぜか守られている
- 責任の重さだけが自分にのしかかる
この「評価と責任の不均衡」が続くと、
真面目な人ほど「なんのために頑張ってるんだろう」と心が折れてしまうんです。
ここで大切なのは、評価されない環境に居続けないこと。
努力を正しく見てもらえる環境に身を置くのも、立派な自己防衛です。
もし「頑張っても報われない」と感じるなら、
一度ミイダス市場価値診断で自分の市場価値を確認してみてください。
「自分の努力がどのくらい評価されるのか」を客観的に知るだけでも、
気持ちが整理され、冷静に次の一歩を考えられるようになります。



僕はミイダスで自分の市場価値を初めて見たとき、
「ここまで頑張ってきたんだから、自分を安く扱う必要はない」と思えました。
ストレスの根本は、環境があなたを正しく評価していないことかもしれません。
仕事ができない同僚に共通する特徴と関わり方
「なんであの人、ずっと成長しないんだろう」
「教えてもまた同じミスを繰り返す」
そんな同僚に、心の中でため息をついたことはありませんか?
仕事ができない人には、実は明確な“共通点”があります。
そして、そのタイプごとに関わり方を変えることで、
あなたのストレスを大幅に減らすことができます。
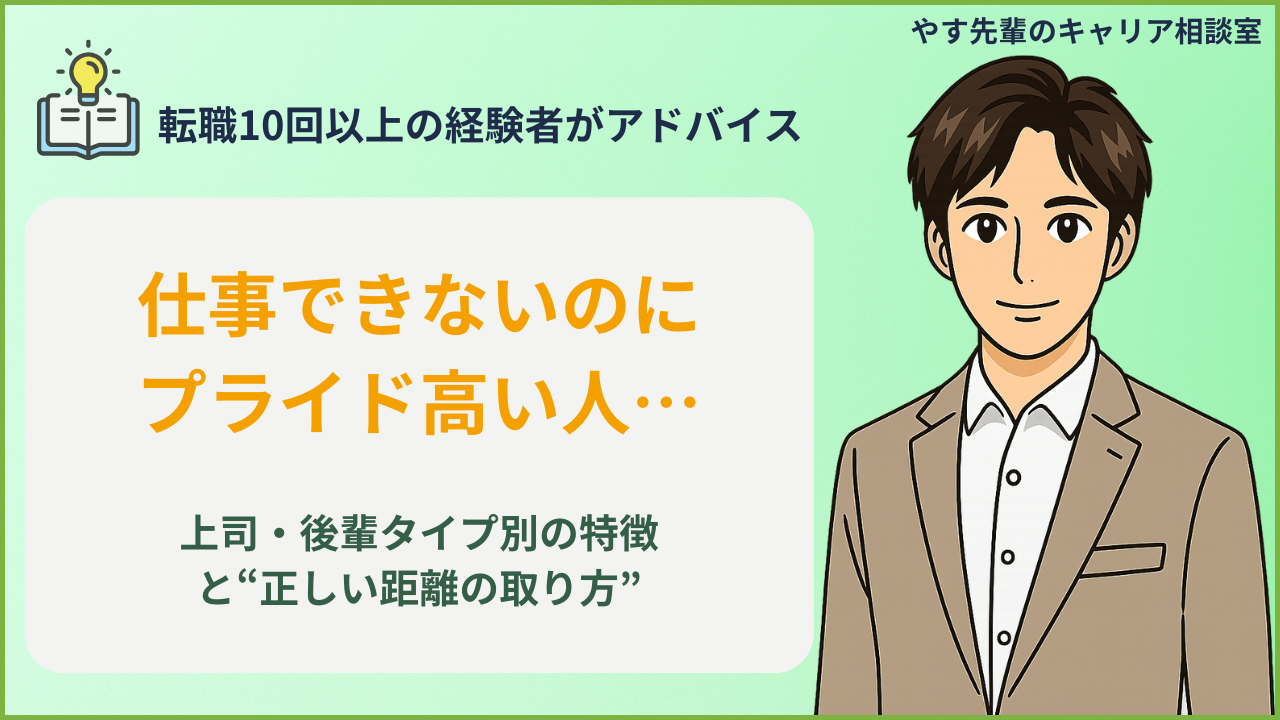
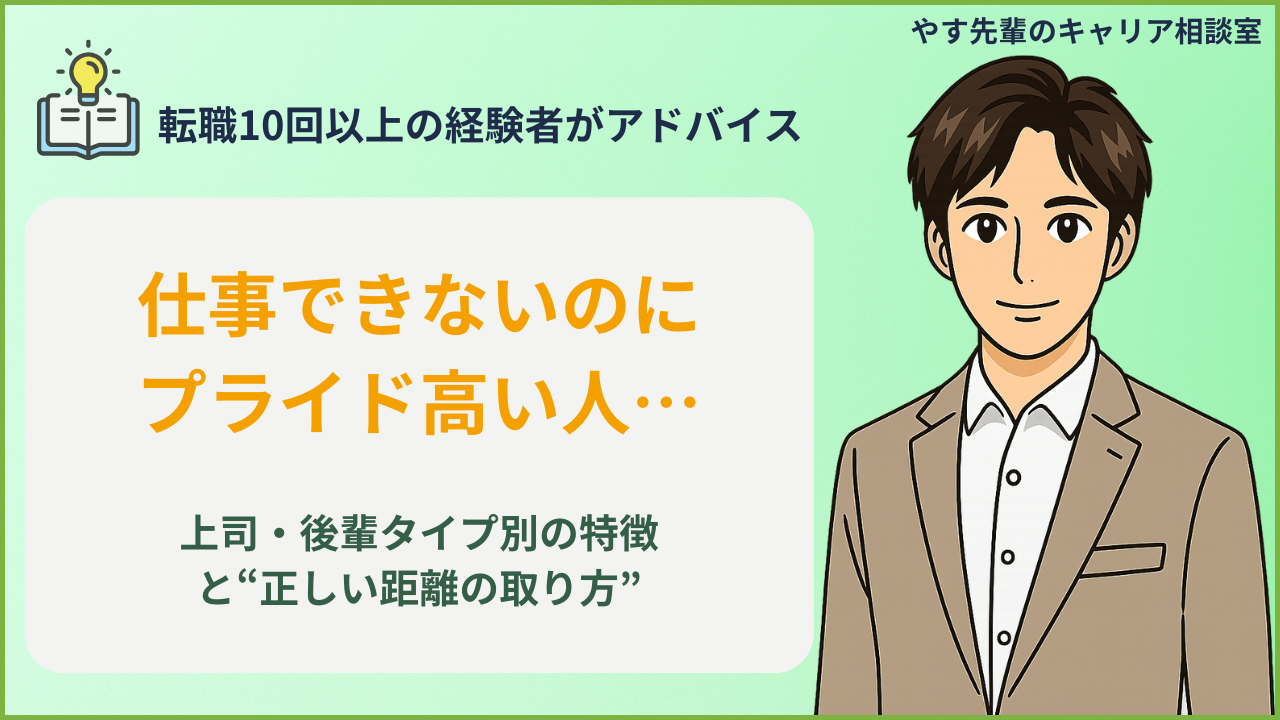
指示待ち・責任回避・成長意欲の欠如タイプ
仕事ができない同僚の多くは、以下のような特徴を持っています。
- 指示待ちタイプ:自分で判断せず、指示がないと動けない
- 責任回避タイプ:失敗を恐れて他人に決定を委ねる
- 成長意欲欠如タイプ:学ぼうとせず、現状維持を好む
こうしたタイプの共通点は、「自分の成長よりも失敗しないことを優先する」姿勢です。
だから、いくら正論で指摘しても、響かない。
むしろ「また怒られた」と防御的になって、改善が止まります。
つまり、彼らは“努力しない人”ではなく、変化を怖がっている人なんです。
そんな相手に必要なのは、期待ではなく線引きです。
「どこまで関わるか」「どこからは本人に任せるか」を決めるだけで、
あなたの心はぐっと軽くなります。



僕も以前、責任を取らない同僚に毎日イライラしていました。
でもある日、「もう助けない」と決めたら、不思議と気持ちが楽になったんです。
他人を変えるより、距離を変えるほうが現実的です。
「関わりすぎない」「頼られすぎない」関係をつくる
できない同僚と上手くやるコツは、「関わりすぎない」関係を意識的に作ることです。
真面目な人ほど、つい「自分がやらなきゃ」とフォローしてしまいがち。
でも、それが続くと、相手は“やってもらえるのが当たり前”になります。
結果、あなたの仕事量だけが増え、相手の成長は止まる、最悪のパターンです。
具体的には、次のようなスタンスを意識しましょう。
- 相手の仕事を“手伝う”ではなく“任せる”
- ミスをフォローする前に、「次はどうする?」と聞く
- 責任を明確に分ける(誰が、どこまでやるか)
こうすることで、相手にも“自分でやる責任”を感じさせることができます。
そして、頼られすぎたときは「今は自分の業務が立て込んでるから」と
やんわり距離を取ることも必要です。
やさしさを優先して自分が壊れてしまっては本末転倒です。



昔の僕は「助けることが正義」だと思ってました。
でも、本当の優しさって、“相手が自立できる距離”を保つことなんですよね。
相手のためにも、自分のためにも、境界線は必要です。
「無視」ではなく“距離を置く”のが正解
「もう無視したい」「関わりたくない」と感じるほど、
心が疲れている人も多いでしょう。
ただ、完全な無視は職場の人間関係を悪化させるリスクがあります。
“無視”ではなく、“距離を置く”が正解です。
距離を置くとは、感情的に反応せず、
「必要な会話だけ」「業務上の報連相だけ」に絞るということ。
たとえば、雑談や感情的な話題には踏み込まず、
業務のやり取りもチャットやメールなど記録が残る形で行う。
そうすれば、関係は冷えすぎず、あなたの心も守られます。
相手に「冷たい」と思われるかもしれませんが、
自分を壊すよりずっと健全な選択です。



僕も一時期、職場で“無視してる人”と噂されたことがあります。
でも実際は「必要以上に関わらないようにした」だけ。
仕事に支障がないなら、それは立派なセルフケアです。
上司が注意しない・放置する場合の対処法
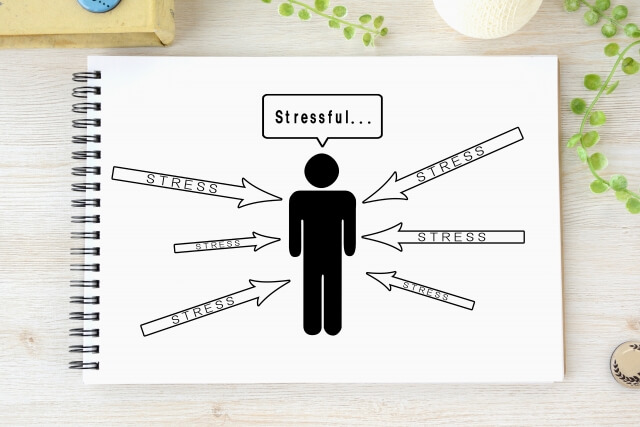
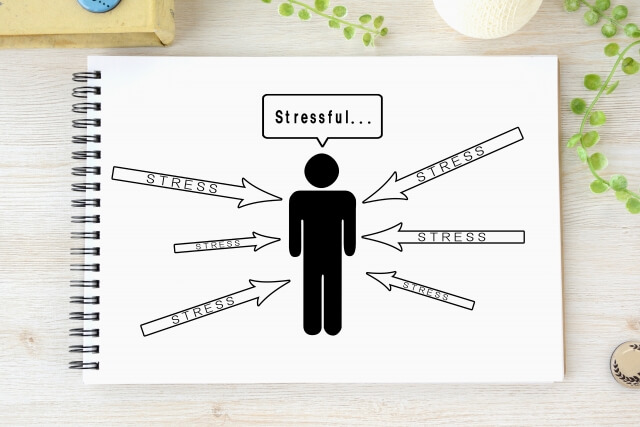
「なんで上司は何も言わないの?」
「こっちばかり負担が増えてるのに、見て見ぬふり?」
仕事ができない同僚がいても、上司が直接注意しない・放置することはよくあります。
正直、理不尽ですよね。僕も何度も経験しました。
でも、そこで感情的にぶつかると、あなたが“トラブルメーカー扱い”されてしまうことも。
まずは冷静に「なぜ上司が動かないのか」を理解するところから始めましょう。


上司が動かない理由を理解する
上司が部下に注意しない背景には、いくつかの理由があります。
- あえて注意しない方針:本人の自覚を待っている
- 人間関係の悪化を避けたい:波風を立てたくない
- 上層部への報告を恐れている:問題を表に出したくない
- 単純に忙しくて見ていない:現場の実情を把握できていない
つまり、「放置している」というよりも、
“リスク回避型の上司”が多いのが現実です。
上司も上司で板挟みになっており、
人に注意することを“エネルギーを使う仕事”と感じていることが多い。
ただ、それを理解したうえで「黙って従う」のも違います。
あなたが消耗しているなら、上司に“見える形で現状”を伝えることが大切です。



僕も昔、「なぜ注意しないんですか?」と直球で聞いて失敗しました。
上司は“放置してる”つもりじゃないんです。
背景を理解したうえで伝えるだけで、会話の温度が変わります。
「自分が損してる」と感じたときの伝え方
同僚のフォローが増えて「自分ばかり損してる」と感じるときは、
感情的に訴えるのではなく、“事実ベース”で伝えるのがポイントです。
たとえばこんな言い方をしてみましょう。
「〇〇さんの作業が止まると、私の業務が一部滞ってしまいます」
「進行をスムーズにするために、チーム全体でタスク分担を見直したいです」
こうした“提案型の伝え方”をすると、
上司も「クレーム」ではなく「改善提案」として受け取ってくれます。
また、上司の性格によっては「自分の責任になる話」を避けたがる場合もあります。
そのときは、「私の方でできる範囲を整理したいのですが」と
主体的な姿勢を見せながら引き出すのが効果的です。



上司への相談って、“伝え方次第”なんですよね。
「困ってます」ではなく「どうしたら改善できそうですか?」と聞くと、
相手のスイッチが入るんです。これは僕も上司になって痛感しました。


上司に伝えるときの言葉選びとタイミング
上司に話をする際は、「いつ」「どんなテンションで伝えるか」が非常に重要です。
忙しい時間帯や会議の直後など、
上司が余裕のないタイミングで話すと、
どんな正論でも“文句”に聞こえてしまいます。
おすすめのタイミングは、
- 朝イチの出勤直後(比較的冷静な時間)
- 定例1on1や週次ミーティングの終盤
- 雑談中など、空気が柔らかいとき
言葉選びは「責める」より「共有する」意識を持ちましょう。
「少し相談したいことがあるのですが」
「私の業務を円滑に進めるために、〇〇さんとの連携について見直したくて」
このように目的を“仕事改善”に置くことで、建設的に受け取ってもらえます。
また、もし上司が全く動かない場合は、
自分の環境を冷静に見直すサインでもあります。
一度ミイダス市場価値診断で自分の市場価値を確認してみてください。
「今の職場にしがみつく必要はあるのか?」を
データで客観的に見られると、気持ちが整理できます。
僕自身も過去にミイダスで市場価値を見て、
「もっと評価される場所がある」と確信して転職を決めました。



上司に期待しすぎて疲れるくらいなら、
「自分が変えられる範囲」にエネルギーを使ったほうが健全です。
上司も同僚も変えられませんが、“自分の立場”はいつでも変えられます。
フォロー疲れを防ぐ3つの考え方
「また自分がフォローか…」
「冷たくしたくないけど、もう限界…」
仕事ができない人の尻拭いが続くと、
優しい人ほど“フォロー疲れ”を起こします。
僕も何度も経験しました。
でも、疲れの根本は“人を助けること”ではなく、
自分の中で責任を抱え込みすぎることにあります。
ここでは、心をすり減らさずに働くための3つの考え方を紹介します。
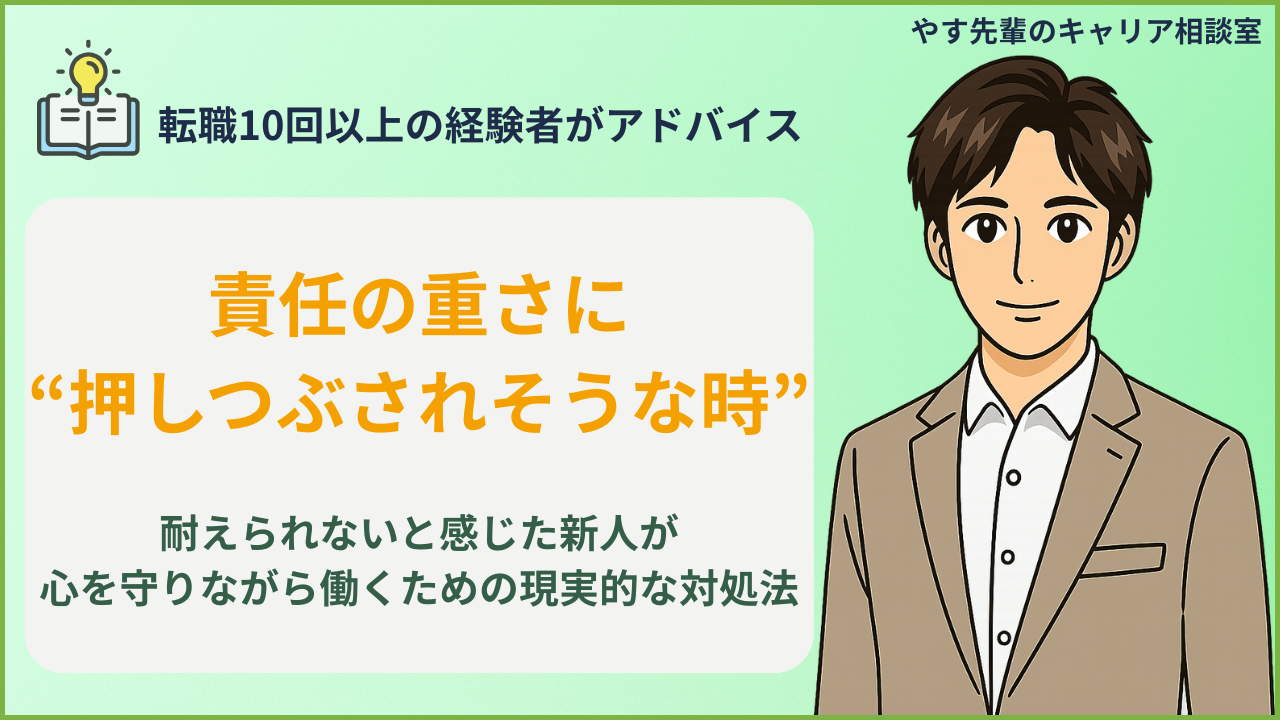
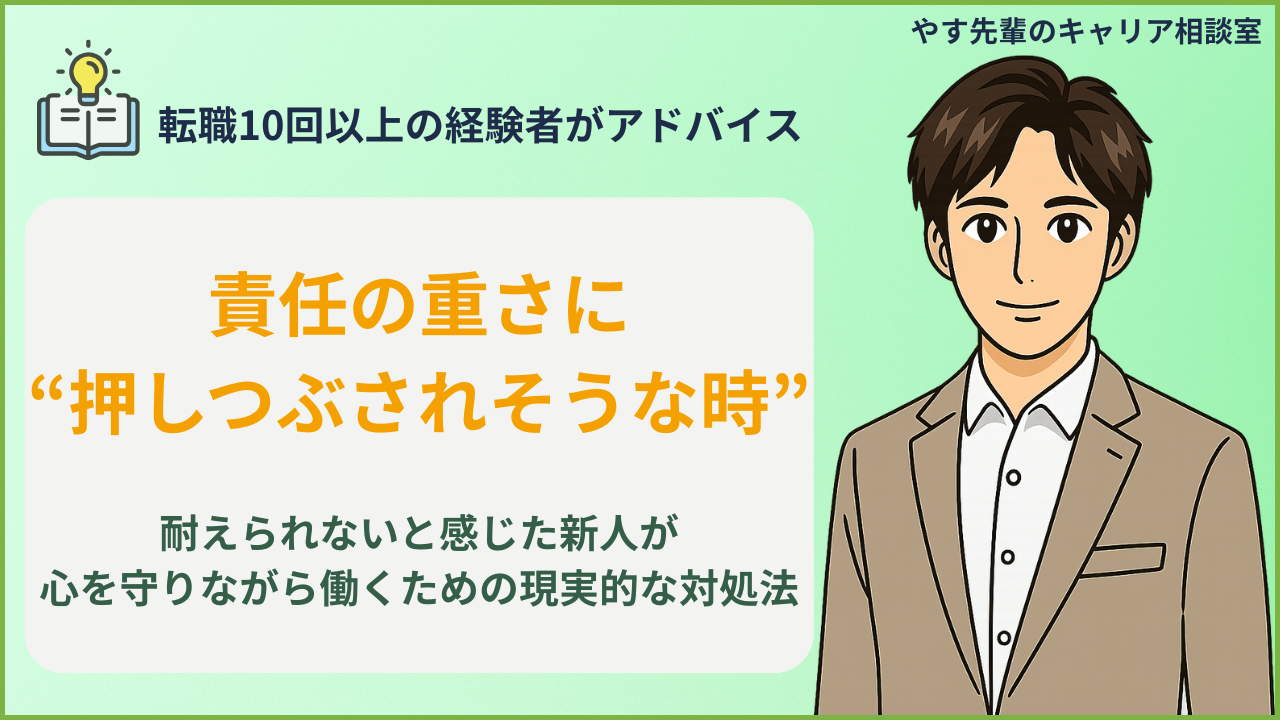
相手の欠点を「自分の責任」と思わない
フォロー疲れの最大の原因は、
「自分がしっかりしなきゃ」「自分の指導が悪いのかも」と、
相手の問題まで背負ってしまうことです。
でも、それはあなたの責任ではありません。
仕事ができない人の中には、
- 失敗を恐れて挑戦しないタイプ
- 注意されても反省しないタイプ
- 成長より“現状維持”を優先するタイプ
など、本人の意識の問題で止まっている人もいます。
あなたがどれだけ努力しても、
本人が変わる意志を持たない限り、状況は変わりません。
相手の課題を“自分の成績”のように感じてしまうと、
終わりのないストレスに飲み込まれてしまいます。



僕も昔、「自分が教育できないから悪い」と思い込んでました。
でも、人にはそれぞれのペースがある。
「自分が悪い」と思うのをやめた瞬間、心がすごく軽くなりました。
フォローの“限度ライン”を決める
どこまでフォローすべきか悩む人も多いですが、
「限度ライン」を決めることが自己防衛になります。
目安としては次のような考え方がおすすめです。
- 相手が努力しているなら、一度はフォローする
- 同じミスが3回続いたら、本人に修正を任せる
- 業務に支障が出る場合は、上司へ報告する
つまり、「助けない」のではなく、
“手放すタイミングを決めておく”ことです。
人は「自分が責任を持つ」と決めた瞬間に、
心の負担が一気に増えます。
逆に、「ここまでやったら十分」と線を引くと、
不思議と心の余裕が戻ってきます。



僕は昔、限度を決めずに全部背負ってました。
でも、あるとき「ここまでやったら終わり」と決めたら、
仕事がシンプルになって、相手も自立するようになったんです。
自分を守る仕組み(タスク共有・上司報告)を作る
フォローを減らすには、“仕組み”を作るのが一番効果的です。
- 業務をチームで共有し、特定の人に依存しない
- 進捗を可視化して、ミスを早期に発見できる状態にする
- トラブルが起きたら、必ず上司に報告して記録を残す
こうして仕組み化することで、
「また自分だけが損してる」という感覚がなくなります。
自分の心と時間を守るための“防御壁”を作る意識が大切です。
もし、今の職場がこうした体制を整える気配がないなら、
環境を変える選択も検討していい時期です。
若手のうちに身を置く環境を変えることで、
キャリアの方向性も大きく変わります。
僕の知人は、フォロー疲れで限界を感じて転職を決意し、
マイナビジョブ20’sで相談して、
「ちゃんと努力が報われる会社」に出会いました。
環境が変われば、人間関係も心の余裕も大きく変わります。



僕は今なら「仕組みがない職場で消耗するくらいなら、変えた方が早い」と断言します。
“頑張る力”は有限。自分を守る仕組みを持って働くのが、長く続けるコツです。
やす先輩の体験談|フォローに疲れ、ついに限界を迎えた日
当時の状況:できない同僚の尻拭いで自分の仕事が止まる
数年前、僕がマネージャーをしていた頃の話です。
チームに一人、どうしても仕事が追いつかない同僚がいました。
期限を守れない、指示を忘れる、ミスの修正もしない。
結局、彼の尻拭いをするのはいつも僕。
納期に間に合わせるために、夜遅くまで残業するのが当たり前になっていました。
「なんで自分ばかり…」という気持ちを押し殺しながら、
「チームのためだから」と自分に言い聞かせていたんです。
でも気づけば、自分の本来の仕事は後回し。
社内でも「やすさんは面倒見がいい」と言われながら、
心の中では限界に近づいていました。
感じたこと:イライラと自己嫌悪のループ
最初のうちは「仕方ないな」と思えていました。
でも、何度フォローしても状況は変わらない。
むしろ、同僚は「どうせやすさんがやってくれる」と言わんばかりの態度に。
そんな様子を見るたびに、イライラが募っていきました。
「なんであいつは成長しないんだ」「自分ばかり損してる」と怒りがわく。
でも同時に、「怒る自分が器の小さい人間なんじゃないか」と自己嫌悪に陥る。
仕事ができない人に関わりたくないのに、関わらざるを得ない。
まさに、イライラと自己嫌悪のループでした。
行動:距離を取り、上司に正直に相談
そんな状態が数ヶ月続いたある日、
出社する足取りが重くて仕方なくなりました。
「これはまずい」と思い、勇気を出して上司に相談したんです。
最初は「自分が弱いだけかもしれません」と前置きしながら、
「業務のバランスが崩れていて、自分の仕事に支障が出ています」と正直に伝えました。
すると上司は意外にも理解を示し、
「やすさんが背負いすぎてる」と言ってくれたんです。
そこから一緒に業務を整理し、
「このタスクは本人に任せる」「サポートはここまで」という線を引くことに。
同僚との関わり方も、意識的に距離を取るようにしました。
必要な報連相だけに絞り、雑談や個人的な相談は避ける。
最初は冷たいと思われてもいいと割り切りました。
結果:チームで分担を見直し、負担が軽減
行動を変えたことで、少しずつ流れが変わりました。
僕が全部抱え込まなくなった分、
他のメンバーも自然と「自分の範囲を考える」ようになったんです。
上司もチーム全体の仕事配分を見直してくれて、
同僚には別の教育担当がつくことになりました。
僕の負担は確実に減り、
「もう無理かもしれない」と思っていた心がようやく落ち着きました。
正直、あのとき行動しなければ、
僕は今もストレスで仕事を嫌いになっていたかもしれません。
学び:「我慢」ではなく「仕組み」で解決するのが正解
この経験で痛感したのは、
「我慢」では何も解決しないということです。
僕がやるべきだったのは、
同僚を責めることでも、無理に助け続けることでもなく、
“チームの仕組みを見直すこと”でした。
フォローに疲れたときこそ、
「もう少し自分を大事にしてもいい」と思ってほしい。
もし今、同じように「限界だ」と感じているなら、
まずは上司に相談する勇気を持ってください。
それでも改善が難しいなら、
自分を守るために環境を変える選択もアリです。
僕の知り合いの若手社員も、
フォロー疲れで心が折れる前にマイナビジョブ20’sで転職相談を受け、
今は「自分のペースで働ける職場」にいます。
「逃げた」ではなく「守った」と言える選択です。



あのときの僕は、誰かに助けてほしかった。
でも、助けを求める勇気が出なかったんです。
今の僕なら言います。「我慢より仕組み」「孤独より相談」。
それが、仕事を続けるための一番のコツです。
まとめ|「できない同僚」に疲れたら、まず自分を守ろう
仕事ができない同僚にイライラしたり、疲れてしまうのは、
あなたに責任感がある証拠です。
「チームを支えたい」「迷惑をかけたくない」と思う気持ちは素晴らしいこと。
でも、その優しさを続けすぎると、いずれ自分が壊れてしまいます。
だからこそ、まず大事なのは「守る意識」。
感情で反応するのではなく、
“線引き”と“仕組み”で自分を守ることが、長く働くためのコツです。
- フォローの限界を決める
- 記録を残して上司に共有する
- 関わる範囲を明確にする
それだけでも、心の負担は確実に減ります。



僕も昔は「頑張ればなんとかなる」と信じてました。
でも、どんなに頑張っても“環境”が変わらないと限界がくる。
自分を守るための線を引けるようになって、ようやく楽になりました。
もし我慢が続くようなら、
「環境を変える」という選択も立派な行動です。
たとえば、
- もっと評価される職場を探したいなら、ビズリーチ
→ スカウト型なので、今のあなたの市場価値を見た企業から直接声がかかります。 - 20代・若手で「このまま今の職場にいていいのかな」と迷っているなら、マイナビジョブ20’s
→ 20代専門のキャリアアドバイザーが、相性の合う企業を一緒に探してくれます。 - 「もう限界」「精神的にきつい」という状態なら、退職代行サービス「トリケシ」
→ 退職の手続きをすべて代行してくれるので、上司に直接話す必要はありません。
どれを選ぶにしても共通しているのは、
「逃げる」ではなく「自分を守る」という前向きな行動だということです。
仕事はチームで進めるものですが、
自分の心の健康を守れるのは自分だけです。
無理を続けるより、冷静に環境を選び直す。
それが、これからの働き方ではいちばん賢い選択です。
よくある質問
- 仕事できない同僚を注意しても変わらないときは?
-
何度伝えても変わらない人は、あなたの責任ではありません。感情的に言っても逆効果なので、指導内容を記録に残し、上司に共有するのが安全です。上司が動かない場合は、改善提案という形で冷静に伝えましょう。
- 無視すると職場の雰囲気が悪くならない?
-
「無視」は避けるべきですが、“距離を置く”のは問題ありません。必要な会話だけを丁寧にこなし、私情を挟まないようにするのがコツです。感情的に関わるよりも、業務上の最低限の関係を維持した方が健全です。
- 上司が注意しないとき、どうすればいい?
-
上司もあえて注意しないケースがあります。まずは「自分の業務に影響が出ている」ことを事実ベースで伝えてください。感情ではなく改善提案として話すことで、協力を得やすくなります。言葉選びがカギです。
- フォローに疲れて優しくできない自分が嫌です…
-
優しくできないのは、あなたが冷たいからではなく“限界のサイン”です。まず休息を取り、誰かに相談してください。職場環境に問題がある場合は転職も選択肢です。自分を責めず、“守る行動”を優先しましょう。
- もう限界。辞めたいと思うのは甘えですか?
-
いいえ、甘えではありません。限界を感じるのは、真面目に頑張ってきた証拠です。どうしても状況が変わらないなら、ビズリーチやマイナビジョブ20’sで新しい職場を探すのも一つの道。心が壊れる前に行動を。