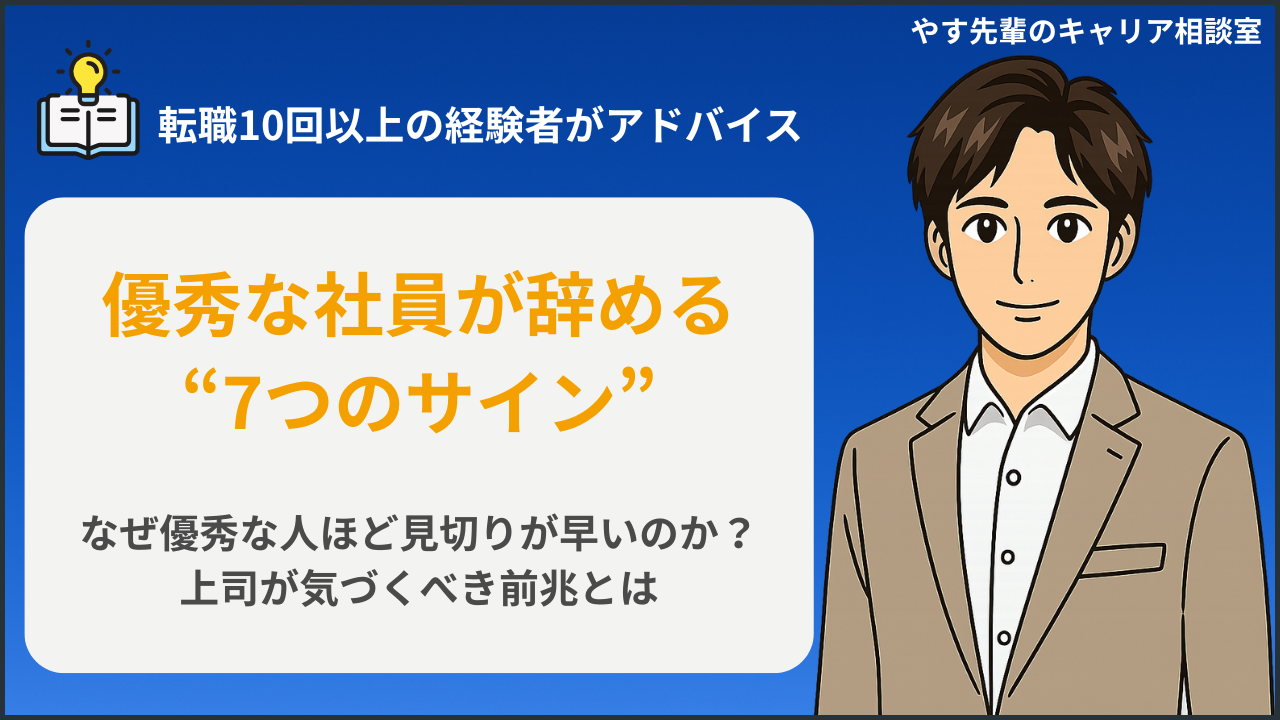やす先輩
やす先輩40代半ば、転職10回の管理職。上場もベンチャーもブラックも経験してきました。失敗も学びも交えながら、キャリアや働き方に悩むあなたへ“現実的な解決策”を届けます。
⇒詳しいプロフィール
「まさか、あの人が辞めるなんて…」
そう思ったときには、すでに次の転職先が決まっていた。
職場でこんな経験はありませんか?
実は、優秀な社員ほど辞める決断が早く、しかも静かです。
不満を声高に訴えることもなく、限界まで我慢することもなく、“見切り”をつけた瞬間に、淡々と次へ進みます。
その前兆は、派手ではありません。
・急に意見を言わなくなる
・期待されなくても感情が動かない
・仕事はきっちりこなすが、熱量が下がる
こうした小さなサインを見逃すと、気づいたときにはもう引き止められない状態になっています。
この記事では、
・優秀な社員が辞める前に見せる7つの兆候
・なぜ優秀な人ほど「早く見切る」のか
・上司・本人が気づくべき危険な前兆
を、やす先輩の実体験を交えて整理します。
そしてもし今、あなた自身が
「最近、評価されていない気がする」
「この職場で成長できているのか分からない」
と感じているなら、一度“社外からの評価”も確認してみてください。
ミイダスを使えば、あなたの経験が今の会社だけの評価なのか、市場全体で通用するのかが分かります。
残るか、動くか。
感情ではなく、データで判断できる状態をつくることが、優秀な人ほど後悔しない選択につながります。
優秀な社員が辞める兆候7つのサイン
優秀な人は感情的に爆発して辞めるより、静かに合理的に「見切りが早い」のが特徴です。
以下の“微細な変化”が同時多発的に起きたら、退職の意思決定プロセスがもう走っている可能性があります。
会議での発言が減る(意見があっても言わなくなる)
以前は論点を整理してくれていた人が、会議で黙る。これは典型的な「優秀な人 辞める兆候」。
発言が減るのは「考えがないから」ではなく、「言っても変わらない」確信からです。
現場で起きるサイン
- 論点メモは用意しているが、あえて口にしない
- 反論すべき箇所で目線を落とす/視線を外す
- 会議後に個別チャットでだけ建設的提案を送る
上司が取る行動
- 決定前に小さなレビュー会を設置し、下書き段階で意見を募る
- 「反対OK、代替案歓迎」と心理的安全性を宣言
- 発言の内容を採用→クレジットを明確化(貢献が可視化されると戻る)



“沈黙=無関心”じゃない。優秀な人ほど、成果につながらない議論から先に撤退します。
雑談や飲み会など、非公式な場に顔を出さなくなる
“非公式の場”は温度を可視化します。ここからフェードアウトするのは、
組織への関心や愛着の希薄化、情的コストの削減のサイン。
現場で起きるサイン
- ランチの誘いへの既読スルーが増える
- オフラインイベントに直前キャンセルが続く
- 業務終了後は5分以内にログアウト
上司が取る行動
- 飲み会ではなく短時間の1on1雑談を定常化
- 「雑談=評価対象外」を明言(参加圧を消す)
- オフサイトは目的提示(学び・交流)+自由参加に設計



“距離”は静かに取られます。情のつながりが切れたとき、退職の意思は固まるんですよね。
上司への報告が“最低限”になる
「了解です」「対応します」短文・無機質が続くのは、信頼残高の枯渇。
優秀な人が辞める会社の特徴として、報告が儀礼化します。
現場で起きるサイン
- 週報が箇条書きの事実羅列のみ
- Slack返信がスタンプ中心(言外の解釈を避ける)
- 相談が期限直前の通知型になる
上司が取る行動
- 週報に3問テンプレ:「困りごと1つ/学び1つ/次週の仮説」
- 指示はWHY→WHAT→DONE基準まで明示
- 結果に対し即フィードバック+称賛の具体化(誰に何が価値だったか)



報告が“用件だけ”になったら危険。情の断捨離が始まっているサインです。
他部署との接点が急に増える
横連携は良いことですが、社内外ネットワークを静かに広げる動きは、
次のキャリアを見据えた情報収集・比較の可能性が高い。
現場で起きるサイン
- 他部署と勉強会/輪読を頻繁に実施
- 外部コミュニティでの登壇・LTが増える
- 社内異動の空きポジション情報を自然に把握
上司が取る行動
- 他部署コラボを本人の成長計画に正式に組み込む
- 目標管理(OKR/KPI)に越境成果を反映
- 気軽に社内シャドーイングを制度化(外に出る前に内で動ける)



外側の酸素を吸い始めたら要注意。比較対象が増えるほど、見切りは早くなります。
業務引き継ぎをさりげなく始める
優秀な人ほど、いきなりは辞めません。
属人化の解除/ドキュメント化が前倒しで進みます。これは静かな退職準備。
現場で起きるサイン
- 手順書・図解・テンプレを自発的に整備
- 定例を“仕組み”で回る設計に刷新
- 権限・鍵情報の棚卸しを提案
上司が取る行動
- 引き継ぎ対象を称賛+評価指標に入れる(損をさせない)
- バディ運用で属人解消を仕組みに昇華
- 「ここからはあなたの挑戦領域」と新しい余白を提示



引き継ぎの上手い人は、去り方も美しい。だからこそ、止めにくいんです。


目の奥の“熱”が消える(燃え尽き・諦めのサイン)
パフォーマンスは維持しているのに、喜怒哀楽の振れ幅が消える。
燃え尽き→諦め→見切りのフェーズ移行です。
現場で起きるサイン
- 成果を出しても表情変化が薄い
- 評価や昇給の話題に無反応
- 新規プロジェクトに自薦しない
上司が取る行動
- 1on1で「最近、楽しかった瞬間」だけを聞く(快の再起動)
- ミッション再定義:役割を“指示”から“任務”へ
- 裁量×挑戦×学習の3要素を次四半期OKRに反映



スキルより熱量。熱が戻らないなら、環境を変える提案まで視野に入れます。
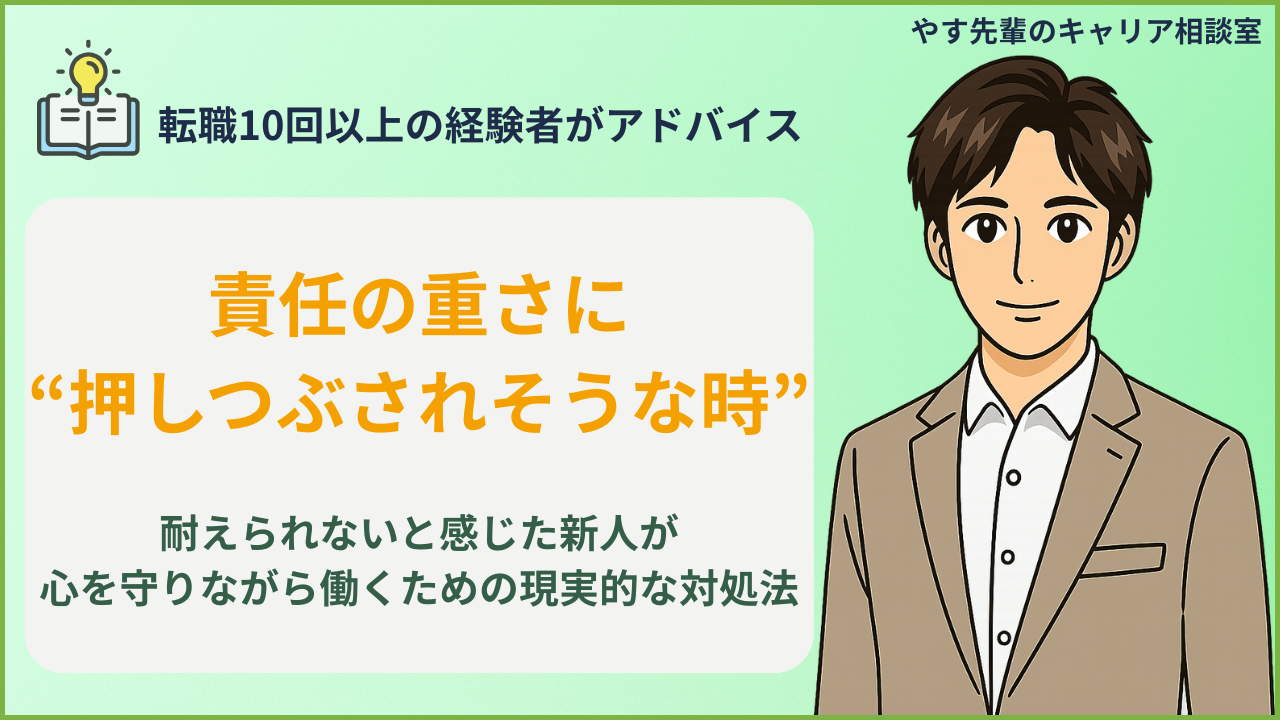
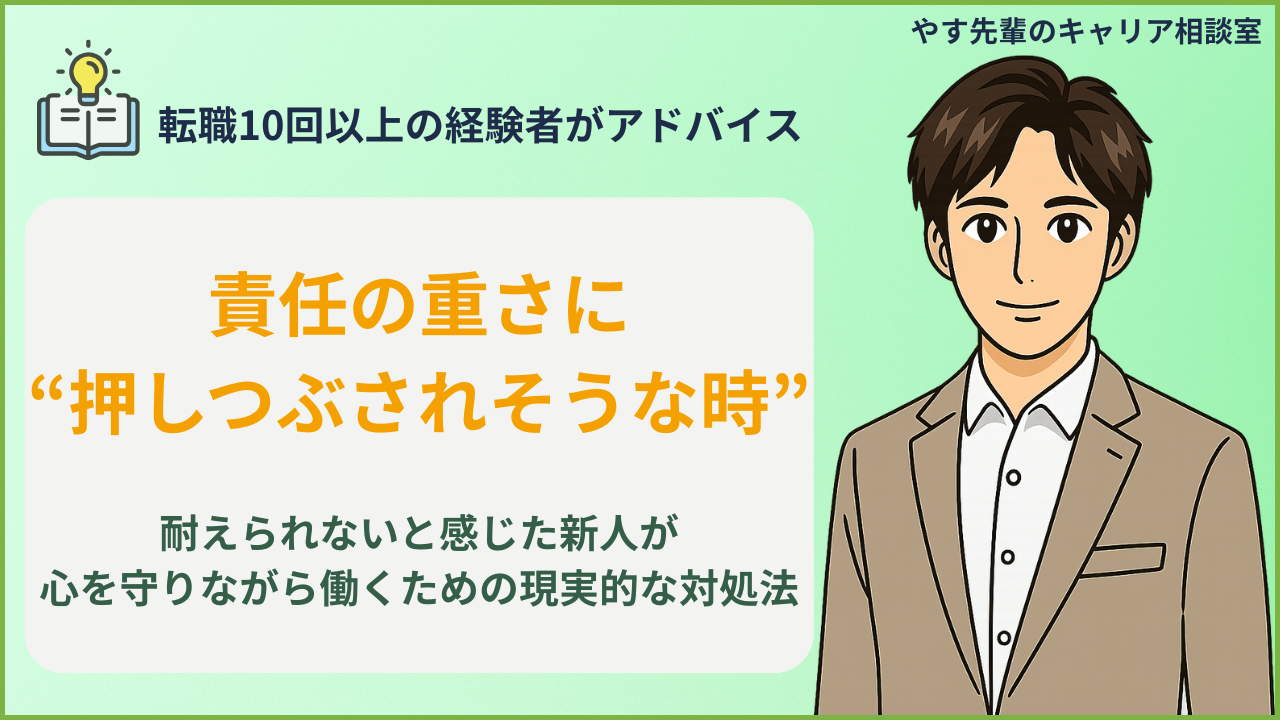
有給の取り方が計画的になる(次の準備段階)
点ではなく線で有給を配置し始めたら、転職活動の面接調整や私用の重要面談の可能性が高い。
現場で起きるサイン
- 平日午後のピンポイント有給が増加
- 事前申請が常に早く、理由は一貫して「私用」
- カレンダーが“非公開ブロック”で埋まり始める
上司が取る行動
- 有給取得を歓迎の姿勢で扱い、監視に見える言動は厳禁
- 直近3ヶ月のキャリア希望と満たされ度を確認(数値化)
- 次期ポジションの仮オファー/ストレッチミッションを用意



予定が粒立って並び出したら、次の舞台の音合わせが始まってます。
なぜ優秀な人ほど見切りが早いのか
優秀な人が突然辞める時、上司や同僚は「まさか、あの人が」と驚きます。
しかし、当人からすれば“突然”ではありません。
彼らは、誰よりも早く「この組織はもう伸びない」と冷静に判断しているだけです。
優秀な人ほど、感情ではなく合理的な見切りを行います。
ここでは、その思考のメカニズムと、見切りを早くする環境要因を解説します。
「変わらない組織」に時間を使うことを無駄だと感じる
優秀な人ほど、時間の価値を知っています。
「変化のない組織」に自分の時間を投じることは、
彼らにとって“機会損失”であり、キャリアの停滞に直結します。
優秀な人が離れる職場の特徴
- 意見を出しても「前例がない」と却下される
- 新しい提案が「リスク」として処理される
- 成果を出しても、次のステップが用意されていない
つまり、成長曲線が止まった組織は、優秀な人にとって“成長を奪う場所”になります。
彼らは未来志向であり、「守り」ではなく「進化」を選ぶ。
だからこそ、静かに見切りをつけるのです。



優秀な人って、“今の居心地”より“未来の伸びしろ”で判断するんですよね。
成長が止まった瞬間、その場所に“いる理由”がなくなるんです。
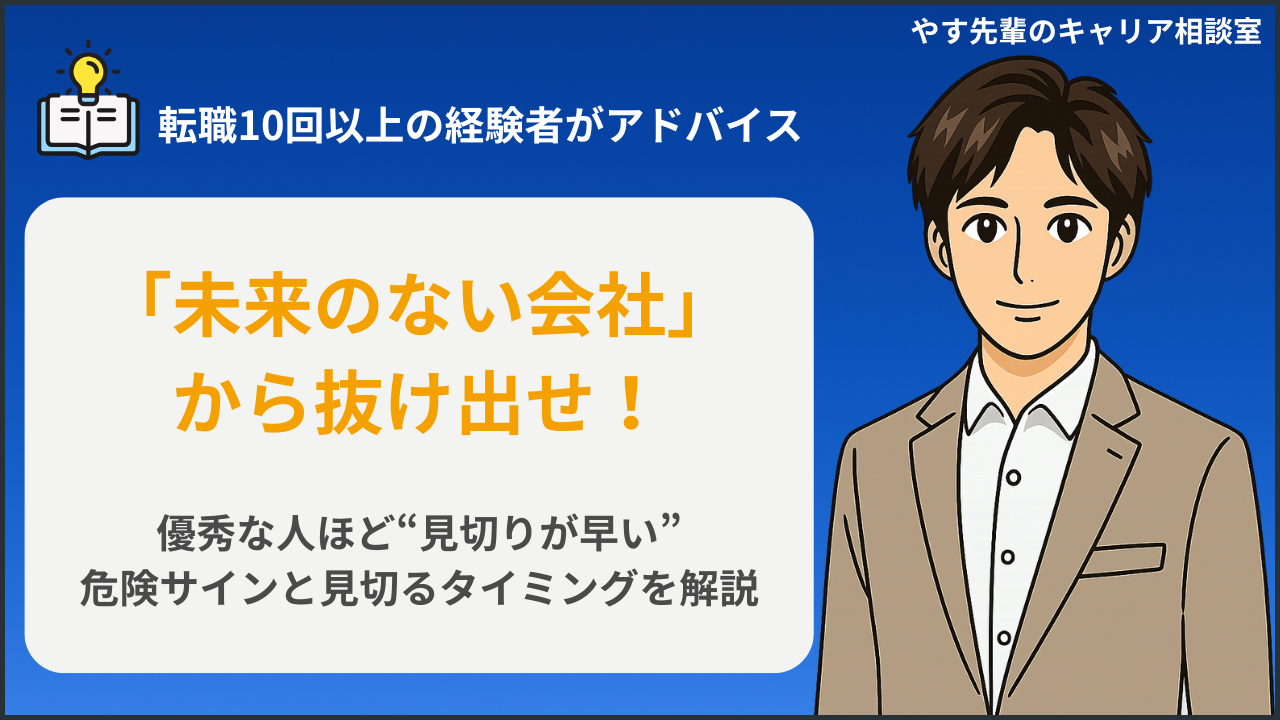
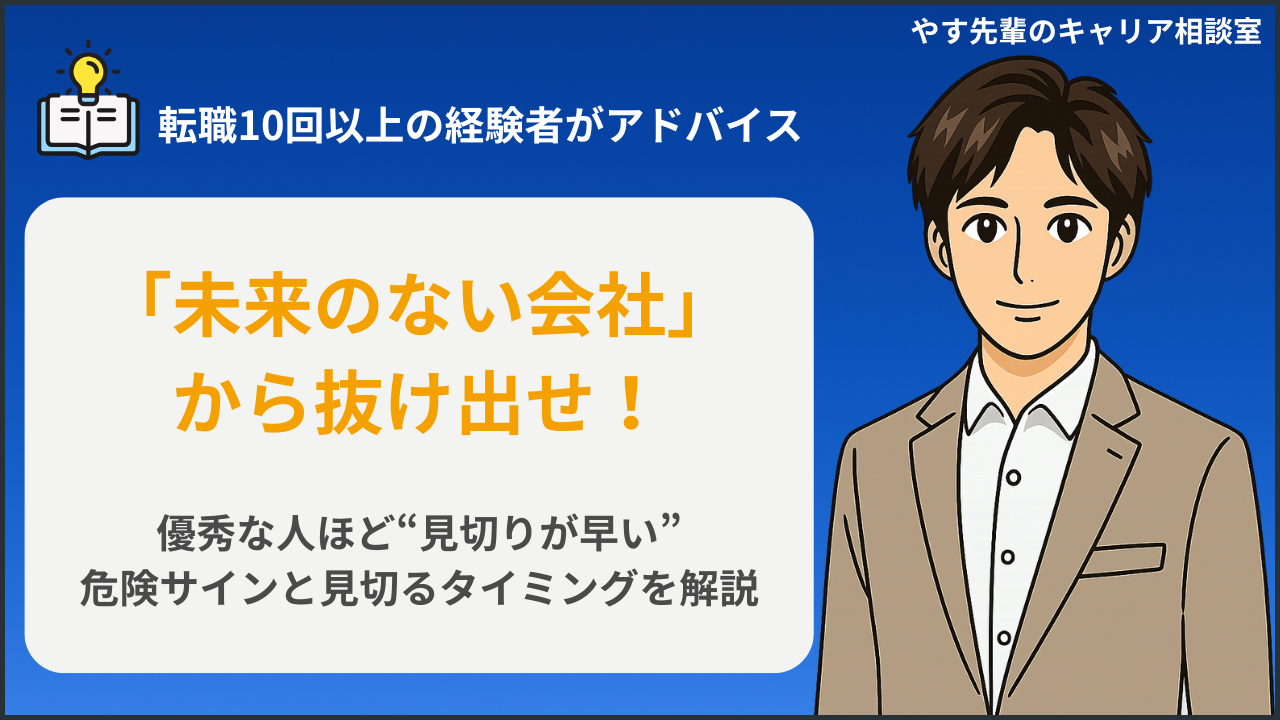
「感情」より「合理性」で動く
多くの人は、上司や同僚への“情”で仕事を続けます。
しかし、優秀な人ほど感情に縛られず、合理的に環境を見極める力を持っています。
彼らは次のように考えます:
- 「上司が好きでも、学びが止まるなら離れる」
- 「チームが仲良くても、挑戦がないなら意味がない」
- 「今の会社で得られる“経験値”が頭打ちなら、次へ行こう」
この“冷静な計算”は決して冷たいわけではありません。
むしろ、自分と組織の相互最適を見極める思考です。
だからこそ、優秀な人は「逃げる」のではなく、「戦う場所を変える」決断が早いのです。



感情的に爆発して辞める人は止められるけど、
合理的に判断して辞める人はもう決めてる。
だから“なぜ?”と聞く頃には、もう次の会社が決まってるんです。
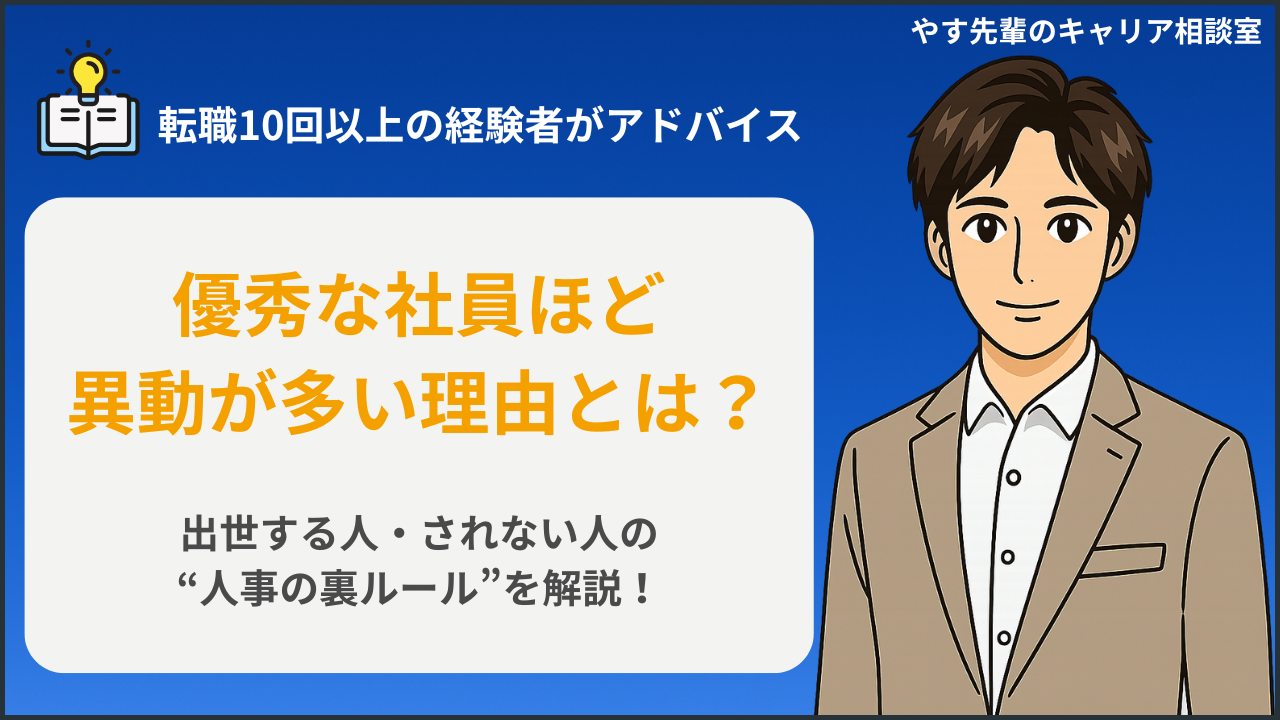
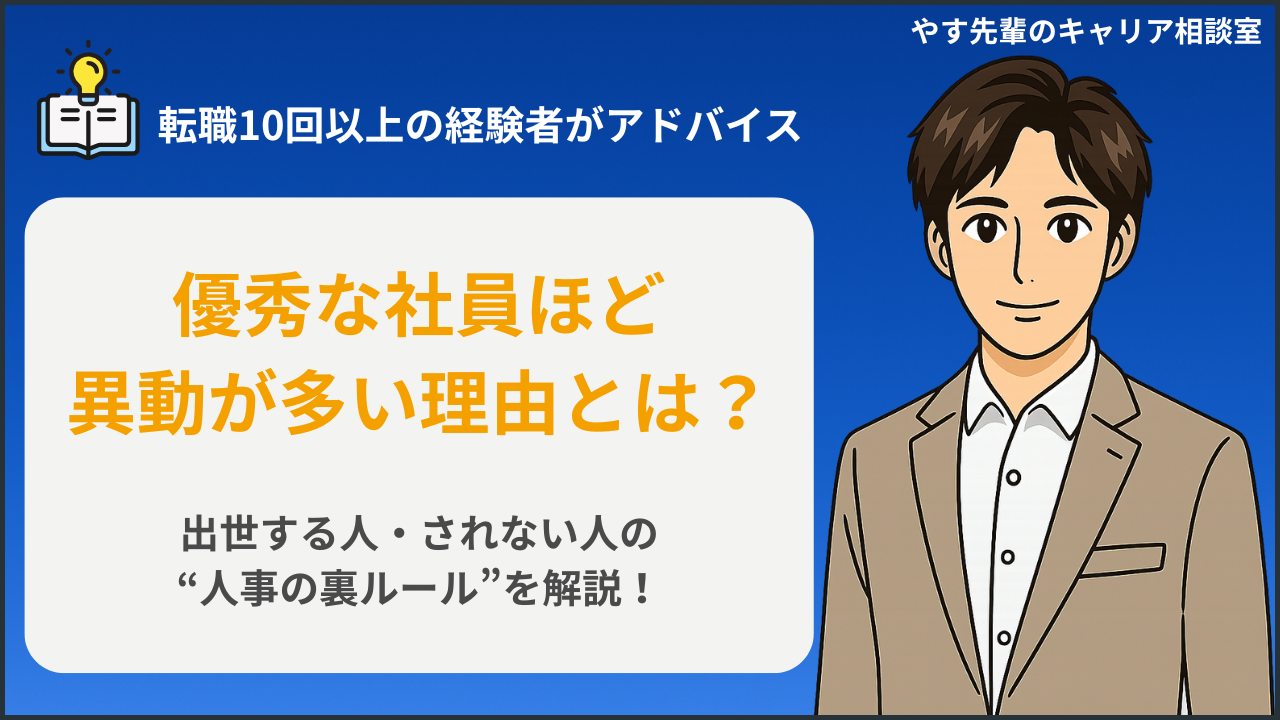
「我慢」より「次の挑戦」を選べるメンタル構造
優秀な人の特徴の一つは、“自己効力感(自分ならできるという確信)”の高さです。
彼らは、「今の環境がダメなら、他でもやれる」と本気で思っている。
一方で、組織に残る人の多くは「我慢=忠誠」と捉えがちです。
しかし、優秀な人は我慢を美徳とは考えません。
むしろ、“我慢を続けることこそ成長の停滞”だと理解しています。
優秀な人の思考回路
- 「努力が報われない場所で努力しても意味がない」
- 「変わらない上司に時間を使うより、新しい挑戦に使おう」
- 「ここで戦うより、次で勝つ方が合理的」
この“挑戦志向のメンタル構造”が、彼らを早期行動型の転職へ導きます。
優秀な人ほど、“リスクを取る勇気”よりも、“停滞を恐れる本能”で動いているのです。



優秀な人って、“耐える力”より“変える力”が強い。
だから、我慢の限界じゃなくて、“飽きた瞬間”に動くんです。
優秀な人が辞める会社の共通点
優秀な人が辞める理由の多くは、「組織の限界」×「上司の鈍感」です。
いくら人材が優秀でも、仕組みが古く、上司が耳を塞いでいれば、
いずれ“抜け出す人”から去っていきます。
優秀な人が辞める会社の共通点
- 挑戦が評価されない
→ 失敗より「前例踏襲」が好まれる。
→ 新しい試みより「手順通り」を褒める文化。 - 管理が重い
→ 上司が“監視”と“報告”を混同している。
→ 裁量がない、意思決定が遅い。 - 上司が聞かない
→ 1on1が形骸化しており、「何かあれば言って」止まり。
→ 話しても変わらない経験が積み重なり、沈黙を選ぶ。
優秀な人ほど、こうした構造の「詰まり」を敏感に察知します。
「挑戦できない」「成長が止まる」と判断した瞬間、
見切りスイッチが静かに入るのです。



優秀な人が辞めるのは、“不満”じゃなく“見極め”。
“この会社じゃもう伸びない”と悟った瞬間、
彼らは次の場所で、もう勝負を始めてるんです。
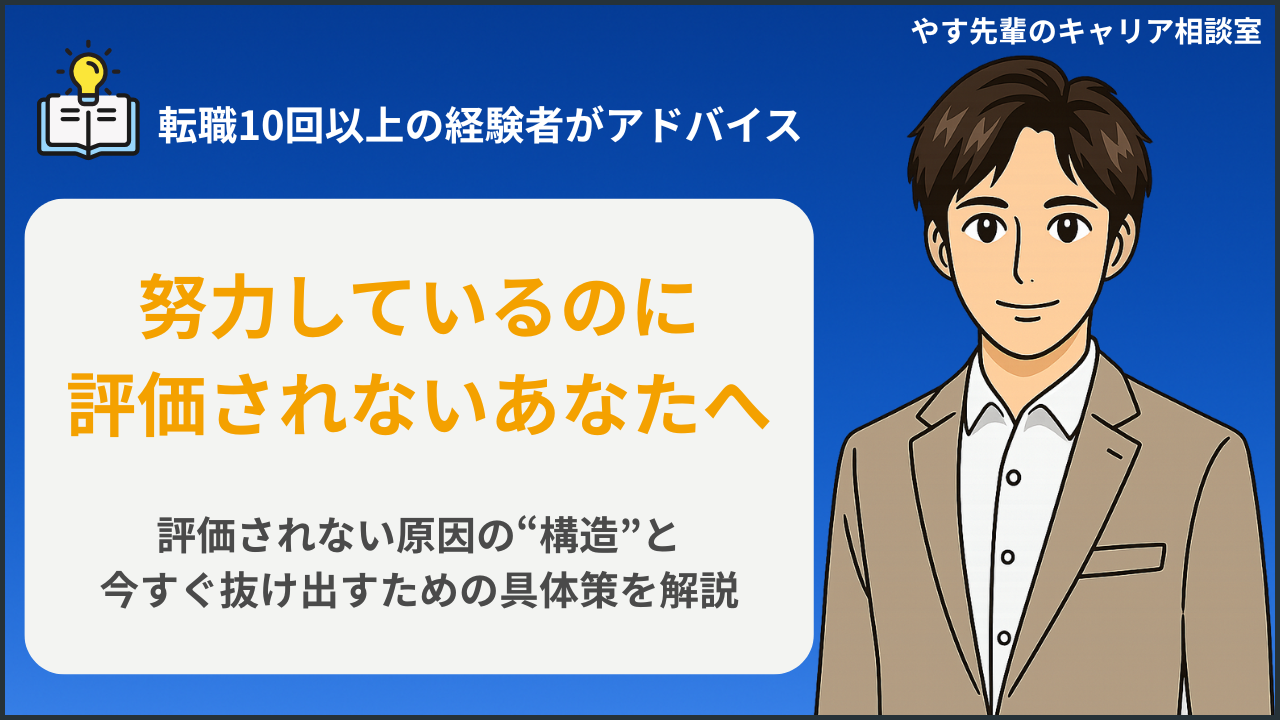
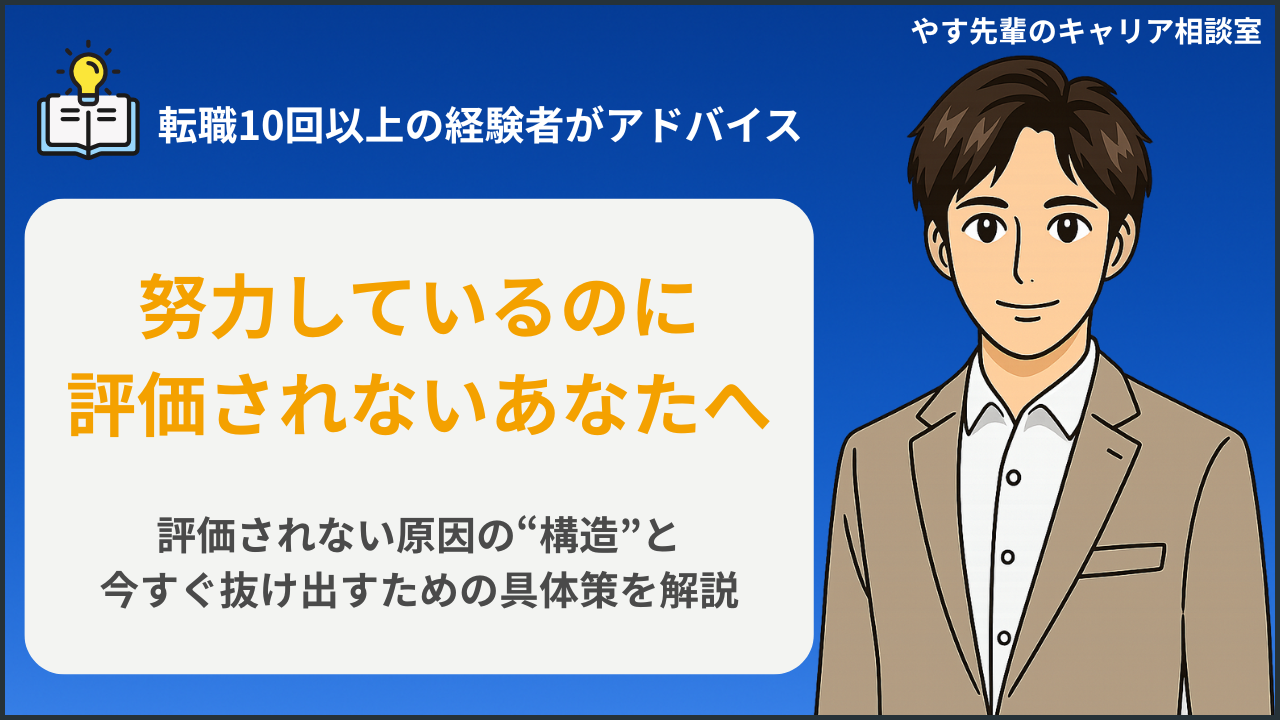
優秀な人が辞める会社の特徴と上司の落とし穴
優秀な人が辞めていく会社には、個人ではなく仕組みに問題があることが多いです。
ここでは、離職を加速させる三つの構造的欠陥と、上司が陥りやすい「見えていない落とし穴」を整理します。
評価が曖昧で「結果よりプロセス」が重視される
優秀な部下が辞める上司のもとでは、評価の軸がぼやけがち。
プロセスの丁寧さは悪ではありませんが、結果が軽んじられる職場は、成果を出す人ほど疲弊します。
現場で起きるサイン
- 目標設定が「頑張る」「丁寧に」などの情緒語で記述されている
- 結果を出しても「手順を守らなかった」で減点される
- 評価会議で数値より「印象」や「声の大きさ」が影響する
- 昇給理由が説明できず、優秀な人が納得していない
是正アクション(上司が今日からできる)
- 目標を結果指標と行動指標に分け、重み付けを明示する
- レビューは「事実→解釈→学び→次の一手」で記録に残す
- 成果に対するクレジット付与を徹底(誰の貢献が何を動かしたか)
- 半期の評価基準を全員に公開し、事後説明ではなく事前合意にする



優秀な人は“正しい努力が報われるか”を見ています。
プロセス至上主義は、挑戦より安全運転を増やし、離職の火種になります。
“頑張る人ほど損をする”仕組みになっている
優秀な人が辞めていく会社の典型がこれ。
できる人に仕事が集中し、負荷は上がるのに裁量や報酬は据え置き。
やがて「ここに残るほど不利」と合理的に判断されます。
現場で起きるサイン
- “できる人”に火消しが常態化し、育成や改善の時間が奪われる
- 役割定義が曖昧で、成果を出すほど雑務も増える
- 昇給は年功ベース、抜擢は例外扱い
- 貢献の可視化がなく、静かな頑張りが埋もれている
是正アクション(仕組みで解消する)
- スループット指標でチーム稼働を可視化し、負荷平準化を習慣化
- 火消し件数ではなく「火事の未然防止」を評価項目に追加
- 役割をジョブ記述で再定義し、不要業務を定期的に断捨離
- 高難度案件には報酬・裁量・学習機会の三点セットを必ず紐づける



“任せやすい人に任せる”は短期効率、でも退職リスクは長期損失。
仕組みで報いる設計に変えない限り、優秀層から静かにいなくなります。
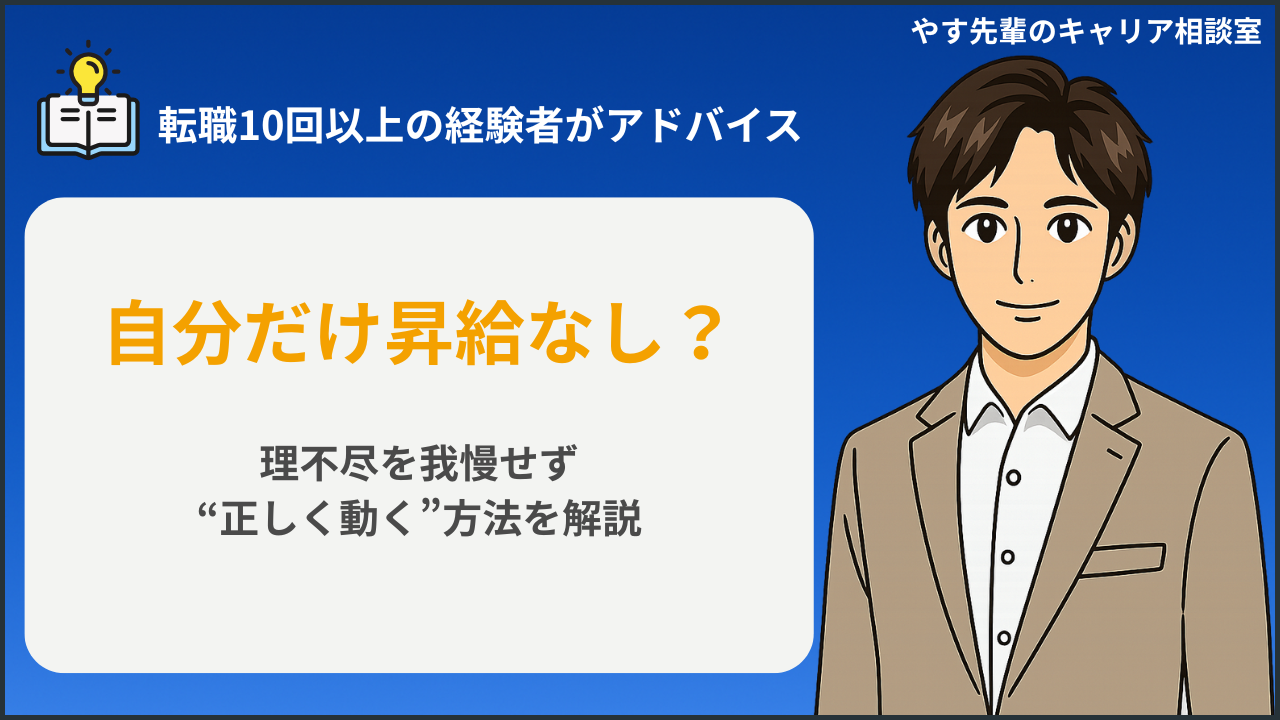
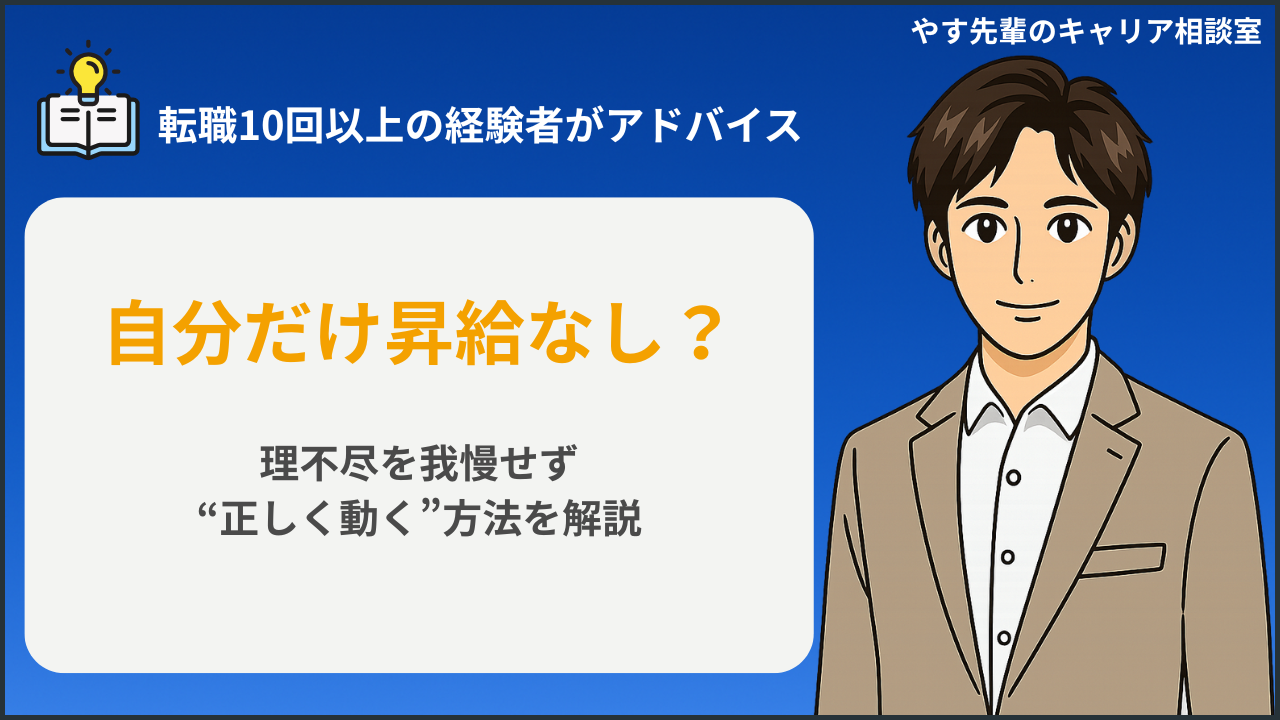
上司が「聞いてるふり」で終わっている
部下が辞める上司の気持ちは「裏切られた」になりがちですが、
現実は“聞いた後に何も変えていない”ことが原因のことが多い。
優秀な部下は、話を聞く姿勢より意思決定の質と速度を見ています。
現場で起きるサイン
- 1on1でボールは受けるが、アクションが翌週も「検討します」
- 決めたと伝えつつ運用が動かず、現場は元のまま
- 問題提起した本人が、次第に沈黙し始める
- 会議で「ご意見ありがとう」で終わる閉会癖
是正アクション(聞くを成果に変える)
- 1on1は「議題→決定→担当→期限→進捗」の五点を必ず文章化
- その場で二択を出し、ミニ意思決定を積み上げる習慣
- 変えられない時は理由と代替策を即共有し、未着手を放置しない
- 「やめる決定」を積極的に出す。撤退も意思決定



優秀な人は“話を聞く上司”より“変える上司”を選びます。
ふりではなく、一歩の改善が信頼を積みます。
やす先輩の体験談|エース社員が突然辞めた日
当時の状況:絶対に辞めないと思っていたエースが、突然の退職宣言
僕がマネージャーをしていた頃、チームに誰もが認めるエース社員がいました。
クライアントからの信頼も厚く、社内の調整力にも長け、まさに「右腕」と呼べる存在。
彼がいればチームは回る。そう信じて疑いませんでした。
ある月曜の朝、Slackに届いた短いメッセージ。
「今週いっぱいで退職させていただきます」
最初は目を疑いました。前週の金曜も一緒にミーティングをして、
「来期の方針どうしましょうか?」なんて前向きな話をしていたのに。
僕はパソコンの前で、数分間何も考えられませんでした。
後から振り返ると、小さな“違和感”はあったんです。
- 会議での発言が減っていた
- 雑談やランチの誘いを控えるようになっていた
- 報告が「最低限」になり始めていた
でも、その時の僕は「疲れてるのかな」「年度末で忙しいだけだろう」と軽く受け流してしまいました。
まさか、その静けさが「去る準備」だったなんて、思いもしませんでした。



“優秀な人ほど突然辞める”って、本当にあるんです。
感情で動かない人ほど、心の中ではもう何ヶ月も前に決断しているんですよね。
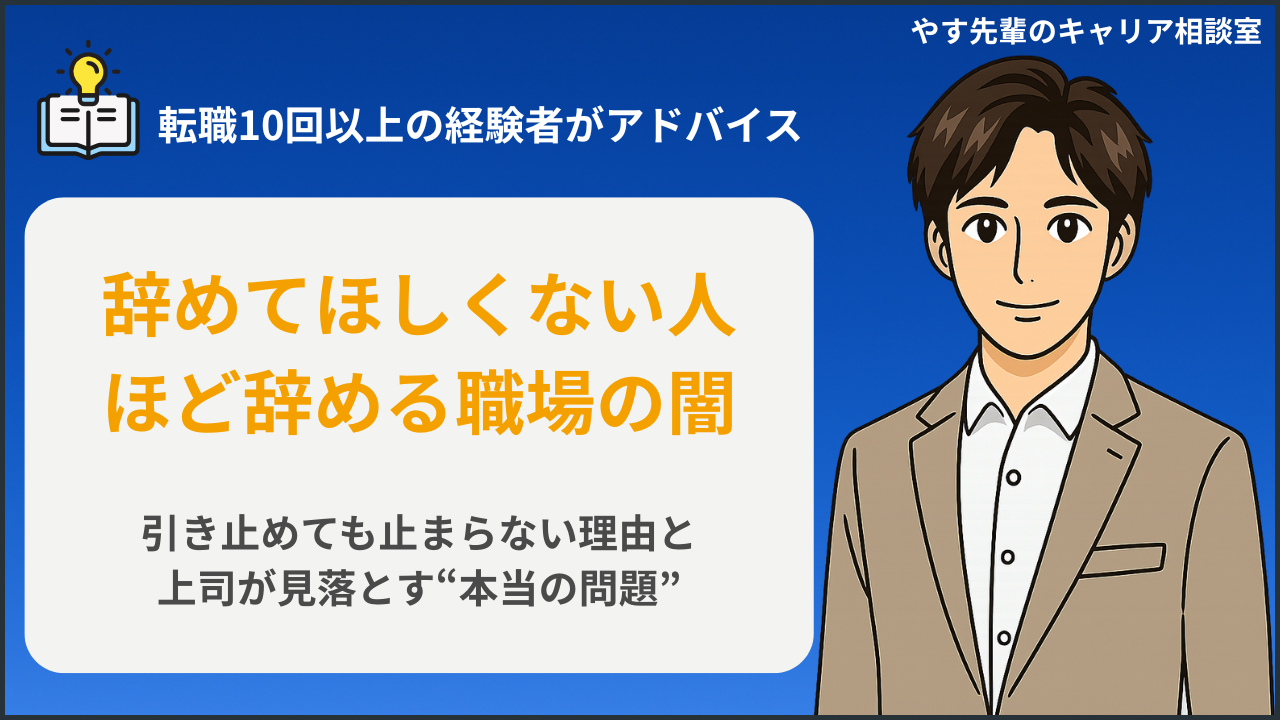
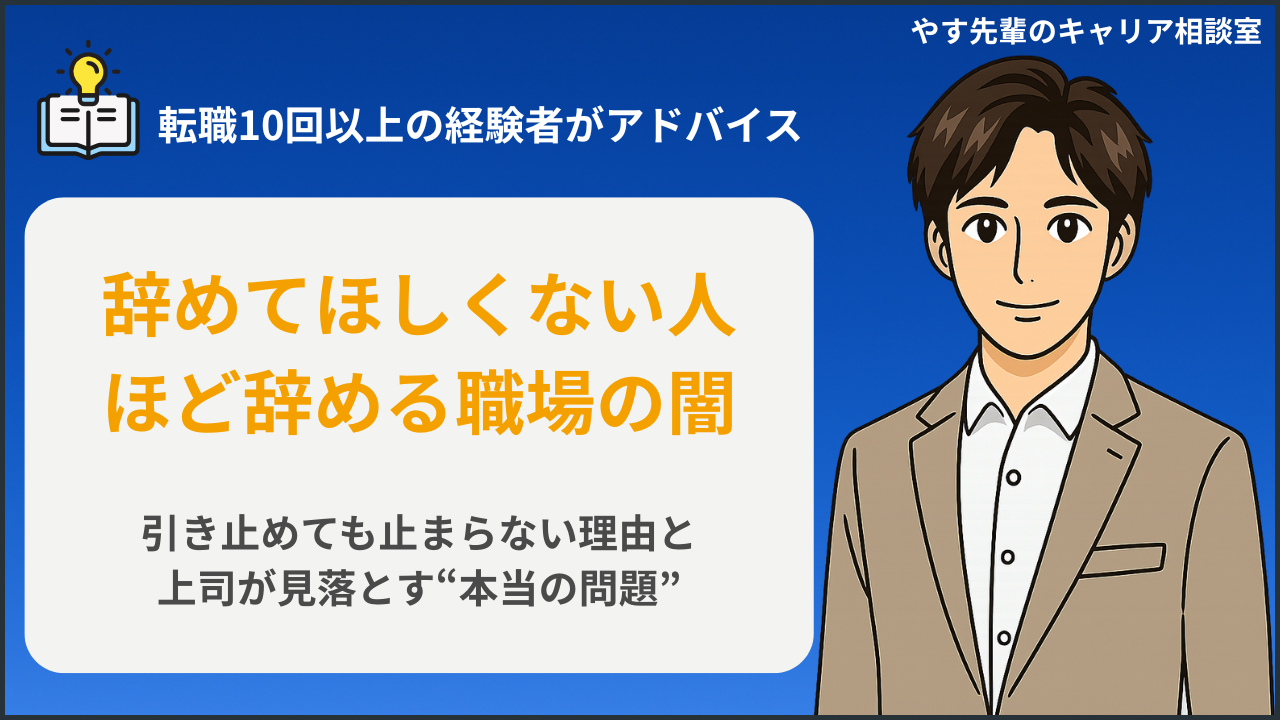
感じたこと:裏切られた気持ちと、自分への苛立ちが入り混じる
正直、そのとき僕はショックでいっぱいでした。
「なんで言ってくれなかったんだ」「何かできたはずなのに」
頭の中でその言葉がぐるぐる回っていました。
心の奥では、裏切られたような気持ちもありました。
あれほど信頼していたのに、何も相談されなかった。
でも同時に、「信頼されていなかったのは自分の方かもしれない」と気づきました。
思い返せば、彼が何か提案しても、僕はつい
「それはリスクがあるから」「今はまだ早い」と言っていた。
彼が未来を見ていたのに、僕は“守る側”でしかなかったんです。



その時、初めて気づきました。
部下の退職って、本人の決意じゃなく“上司の鈍感”の結果なんですよね。
行動:原因を“本人の問題”ではなく“自分のマネジメント”に見直した
落ち込んでいる時間はあっても、チームは待ってくれません。
僕は、残ったメンバーに同じことを起こさないために、
まず自分のマネジメントを根本から見直すことに決めました。
最初にやったのは、1on1の目的を変えること。
これまでは「業務報告」が中心だったのを、「心の温度」を聞く時間にしました。
たとえば、こんな質問をするようにしたんです。
- 「最近、仕事が楽しい瞬間ってどんなとき?」
- 「もし僕に言いづらいことがあるとしたら、どんなこと?」
- 「今後やってみたい仕事、1つだけ挙げるなら?」
最初はみんな警戒していました。
けれど、僕が自分の失敗談や本音を先に話すようにしてから、
少しずつメンバーも“安全に話せる空気”を感じ始めたようでした。



“辞める人を止める”ことより、“辞めたくなる空気を作らない”こと。
それが本当のマネジメントだって、痛いほど学びました。
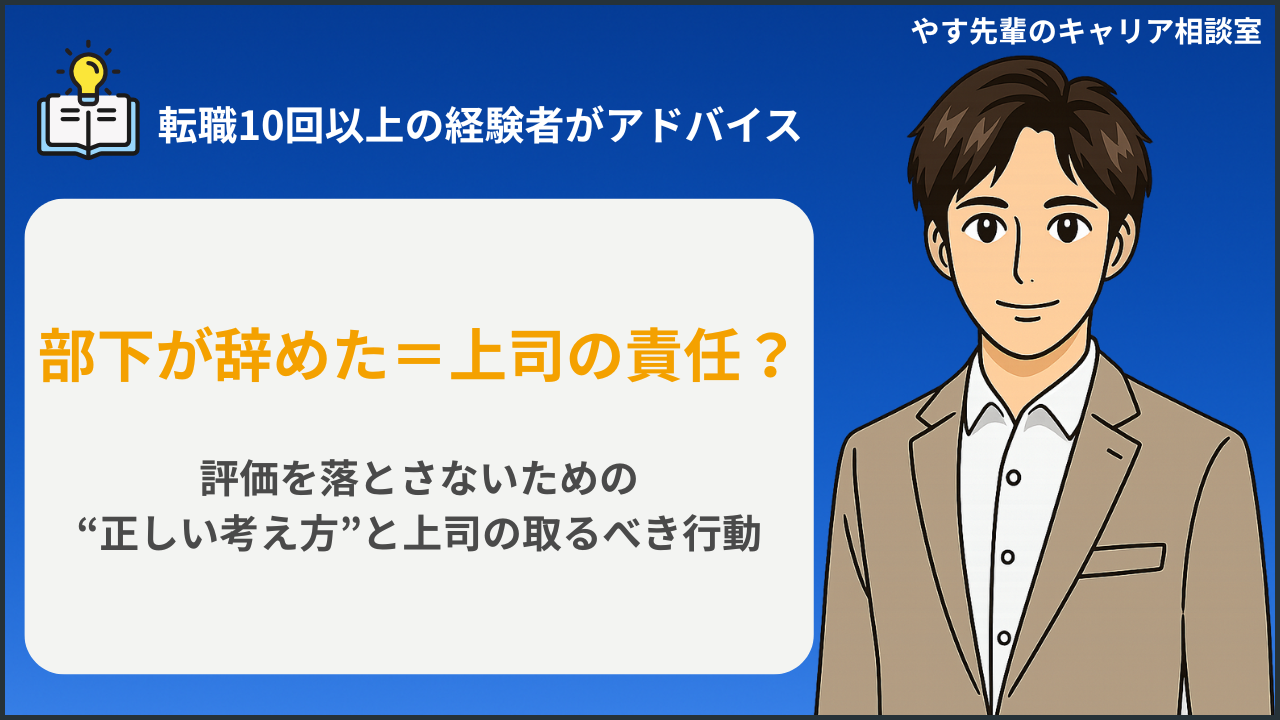
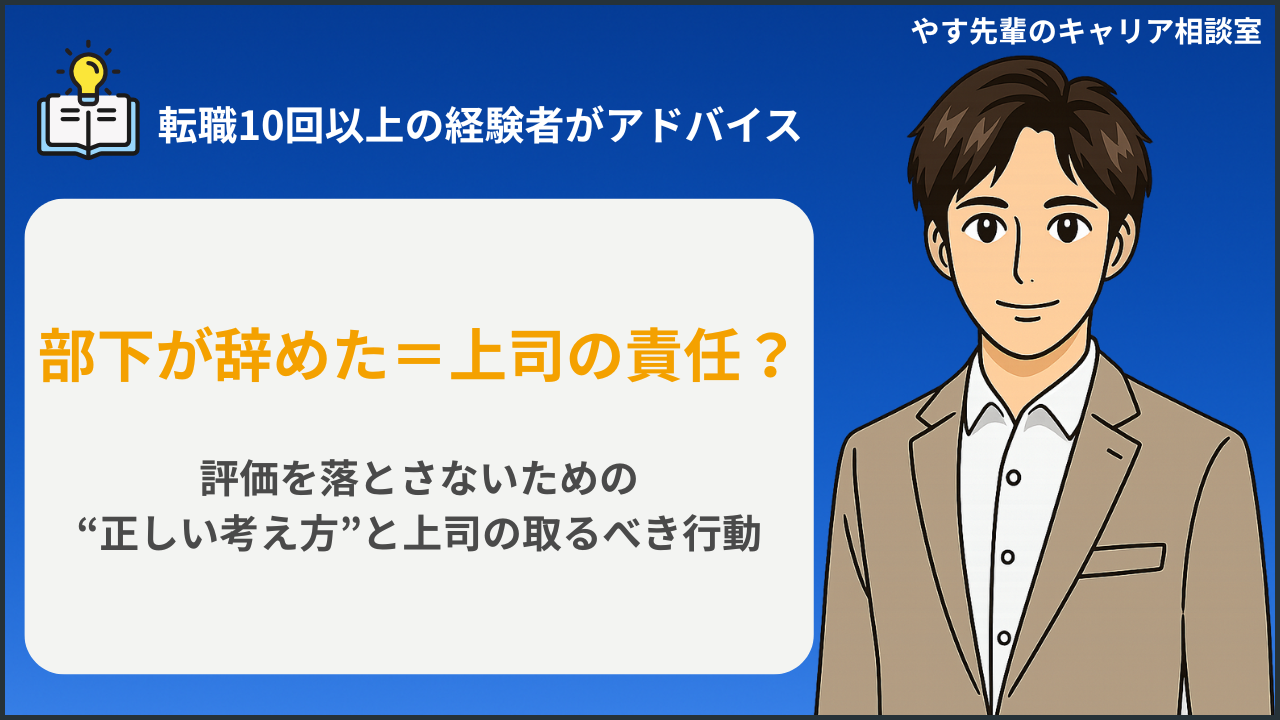
結果:残ったメンバーとの1on1で信頼関係を再構築
1on1を続けるうちに、チーム内で少しずつ変化が起こりました。
会議で意見を出す人が増え、Slackのやり取りにも前向きなトーンが戻ってきた。
「ここにいていい」と思ってくれるメンバーが増えたのを実感しました。
数ヶ月後、以前は黙っていたメンバーが僕にこう言ってくれました。
「実は、〇〇さん(辞めたエース)も同じことで悩んでたと思います。
でも、今のチームはちゃんと話せるようになった気がします。」
その言葉を聞いた瞬間、救われた気持ちになりました。
「エースを失った」という喪失感は大きかったけれど、
その経験がチームを再生させるきっかけになったのです。



人が辞める経験って、痛い。でも、
そこから“何を変えるか”でチームの未来は全然違ってくる。
退職は終わりじゃなく、“組織の鏡”なんですよ。
学び:「辞めない人を育てる」のではなく、「辞めたくないと思える関係」を築くことが本質
この経験から僕が学んだのは、
「辞めない人を作る」ことを目的にすると、関係は形骸化していくということです。
人は“辞めさせない仕組み”ではなく、“辞めたくない空気”の中で力を発揮する。
優秀な人が残る職場とは?
- 挑戦を“失敗”ではなく“経験”として扱う
- 上司が“守る”より“信じて任せる”
- 感謝や承認が、日常会話に溶け込んでいる
退職を「裏切り」と捉えるのではなく、
「信頼を取り戻すチャンス」として受け止めたとき、
チームの関係性はようやく本物になります。



辞めない人を育てるより、“この人と働きたい”と思ってもらえる上司を目指す。
それが僕のマネジメントの原点です。
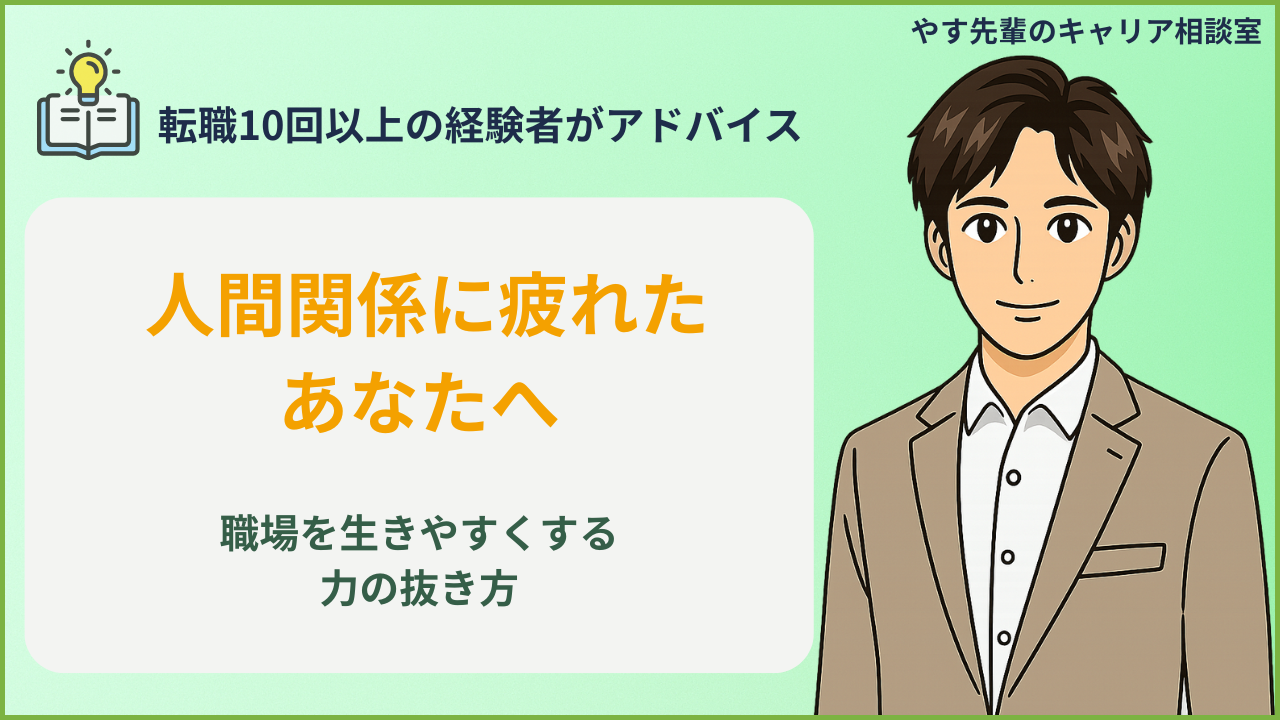
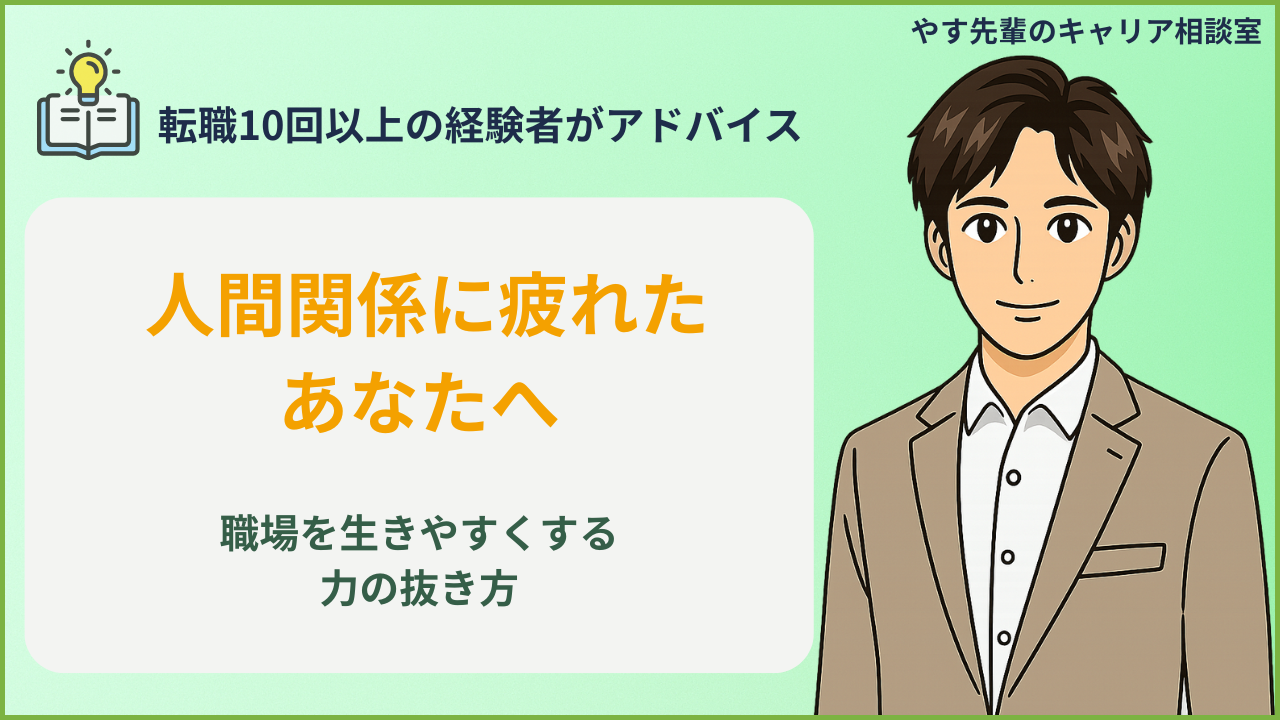
優秀な人が辞める“連鎖”を止めるには
優秀な人が去っていくと、残ったメンバーの士気が落ち、さらに優秀な人見限る流れが加速します。
ここでは、この“負のスパイラル”を断ち切るための三つの視点を具体策まで落とし込みます。
「辞める=裏切り」と思わない
退職を「裏切り」と捉えると、去る人=悪、残る人=正という分断が生まれ、
残った人の心理的安全性まで損なわれます。結果、優秀な人辞める連鎖が始まる。
やってはいけない反応
- 「せっかく育てたのに…」と感情をぶつける
- 送別会で“忠誠心”を暗に求めるメッセージ
- 「うちは合わなかっただけ」と片づけて内省を終わらせる
建設的な受け止め方(上司の一言テンプレ)
- 「あなたの決断を尊重する。ここまでの貢献に感謝している」
- 「最後に“ここを直せばもっと良くなる”点を教えてほしい」
- 「卒業後も相談できる関係でいよう」
組織としてのアクション
- 退職面談は感謝→学び→改善策の三段構成で議事録化
- 退職者の成果と知見をナレッジ化して称賛(損失感を“資産”化)



辞めるのは裏切りじゃない。キャリアの選択です。
ここで尊重できる上司だけが、次の離職を止められます。
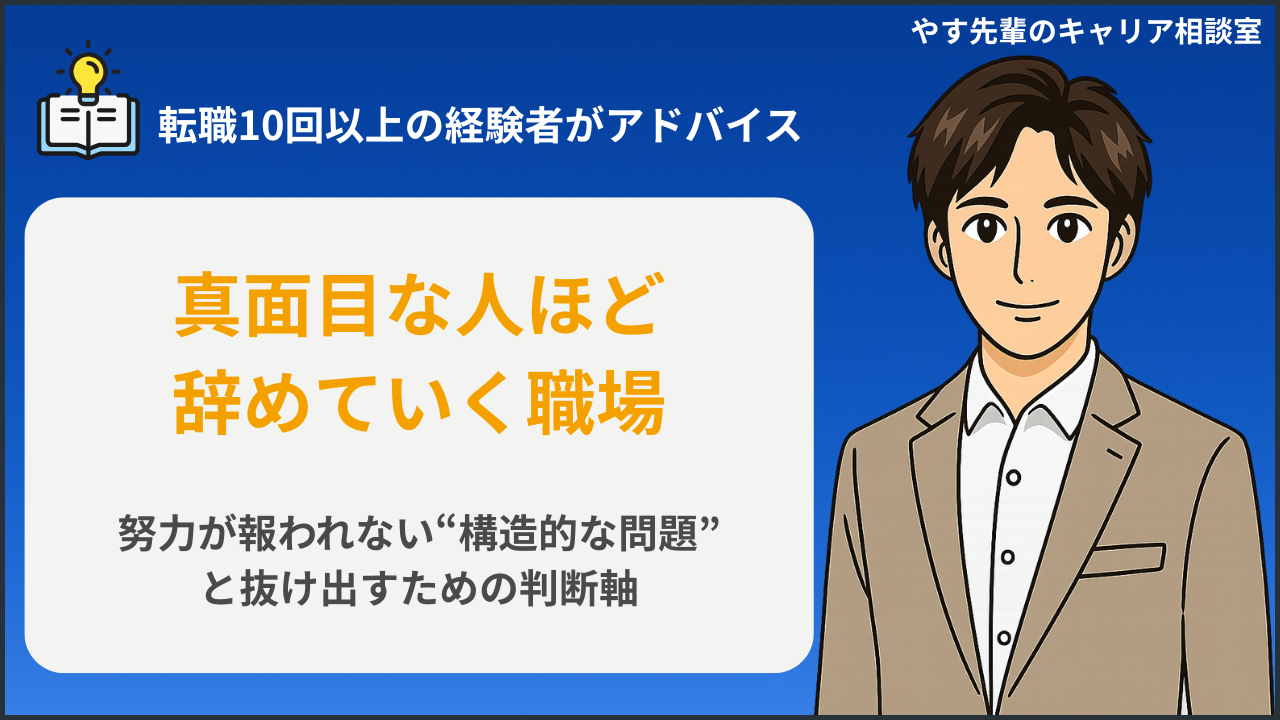
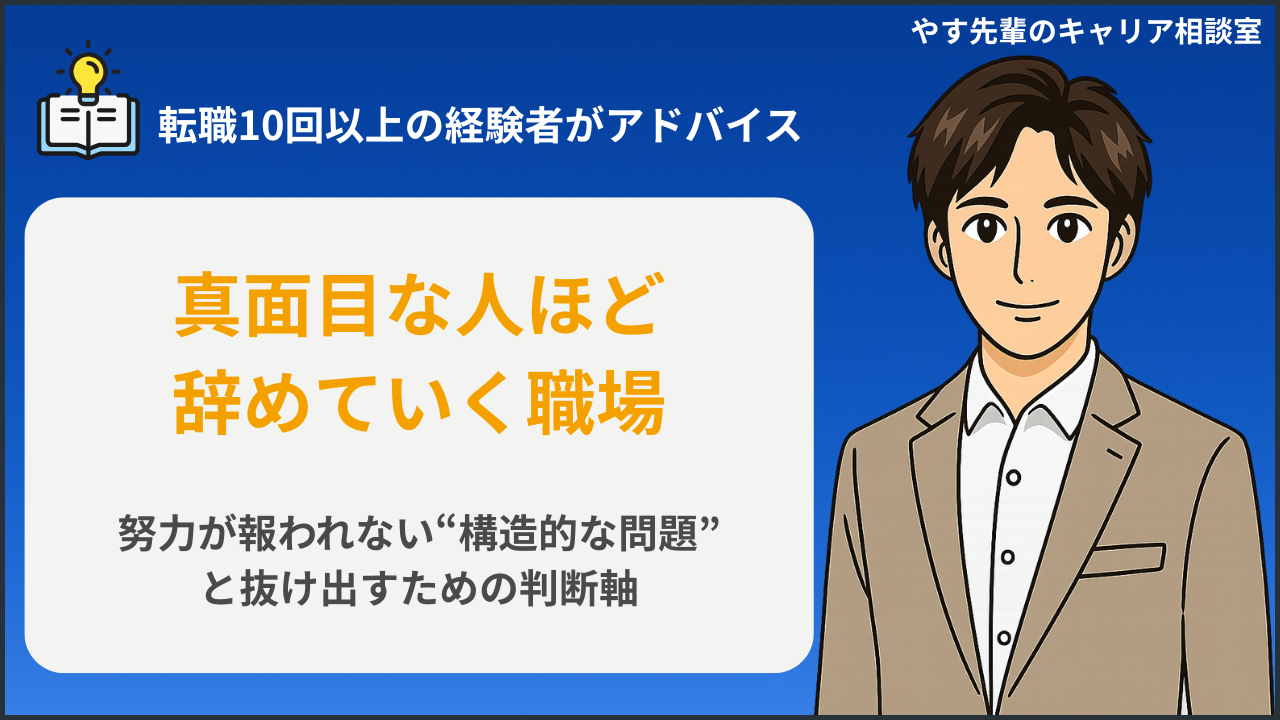
一人が去った理由を“個人の問題”で片づけない
「本人のワガママ」「家庭の事情」で終わらせると、構造の欠陥が温存されます。
優秀な人が見限る背景に共通点はないか、事実で検証しましょう。
原因の見える化(Factベース)
- 退職理由のカテゴリ化:評価/成長機会/裁量/人間関係/報酬/働き方
- 時系列の兆候を棚卸し:発言量・関与度・1on1ログ・有給の取り方
- 残存メンバーから“去らなかった理由”も回収(差分を見る)
変えるべきは仕組み
- 評価:成果×挑戦を事前合意の重み付けで運用(例:成果60/挑戦30/協働10)
- 裁量:意思決定権の範囲を職位別に明文化、実権の空洞化を防ぐ
- 成長:四半期ごとに“次の席(役割・技術・市場露出)”を提示
場づくり
- “退職理由共有会”は厳禁。代わりに“改善ロードマップ共有会”を実施
- 初動30日で改善1→停止1(始めるだけでなく、やめる決定も)



“個人の問題”にすり替えると、次の優秀層も静かに去る。
痛いけど、仕組みにメスを入れるのが最短の特効薬です。


チーム全体で「心理的安全性」を見直す
連鎖を止める最後の鍵は、心理的安全性の再設計。
“安全=甘さ”ではありません。率直さ×敬意×行動の設計です。
安全性の4指標(毎月サーベイ運用推奨・5段階)
- 発言安全:否定されずに異論を言える
- 挑戦安全:失敗が学びとして扱われる
- 承認安全:貢献がタイムリーに可視化される
- 関係安全:立場を越えた相談先が複数ある
即効性のあるルール(運用テンプレ)
- 会議は「仮説歓迎・前提疑いOK」を最初に宣言
- 反対意見には「感謝→要約→検討」の三段返し
- 1on1は議題→決定→担当→期限→進捗をドキュメントに残す
- 週次で称賛3つ(人×行為×結果を具体に)をSlackで可視化
“去っていく人”を見た後のケア
- 残ったメンバーに不安の棚卸し(匿名フォーム+公開回答)
- 当面3ヶ月の役割と期待を再合意(漂流を防ぐ)
- “穴埋め”ではなくストレッチ機会として再設計



安全って、“優しくする”ことじゃない。
率直に言い合っても関係が壊れない土台をつくること。
その土台があれば、優秀な人は残ります。
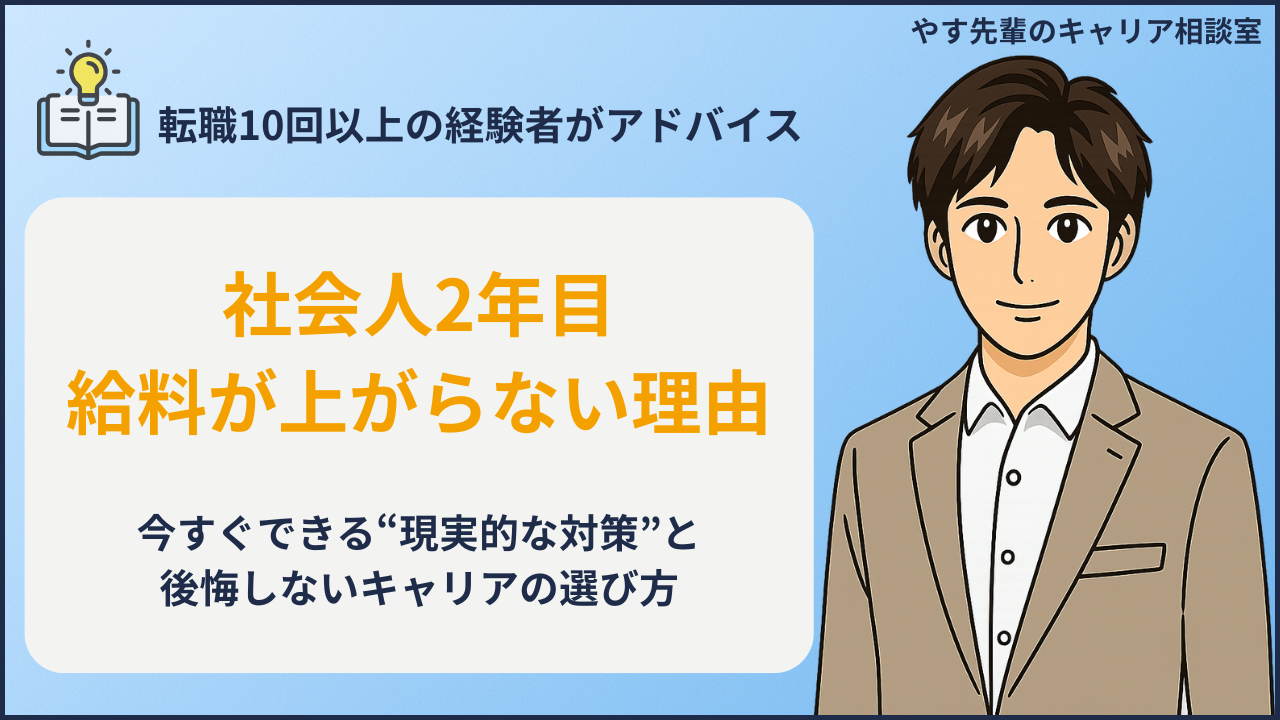
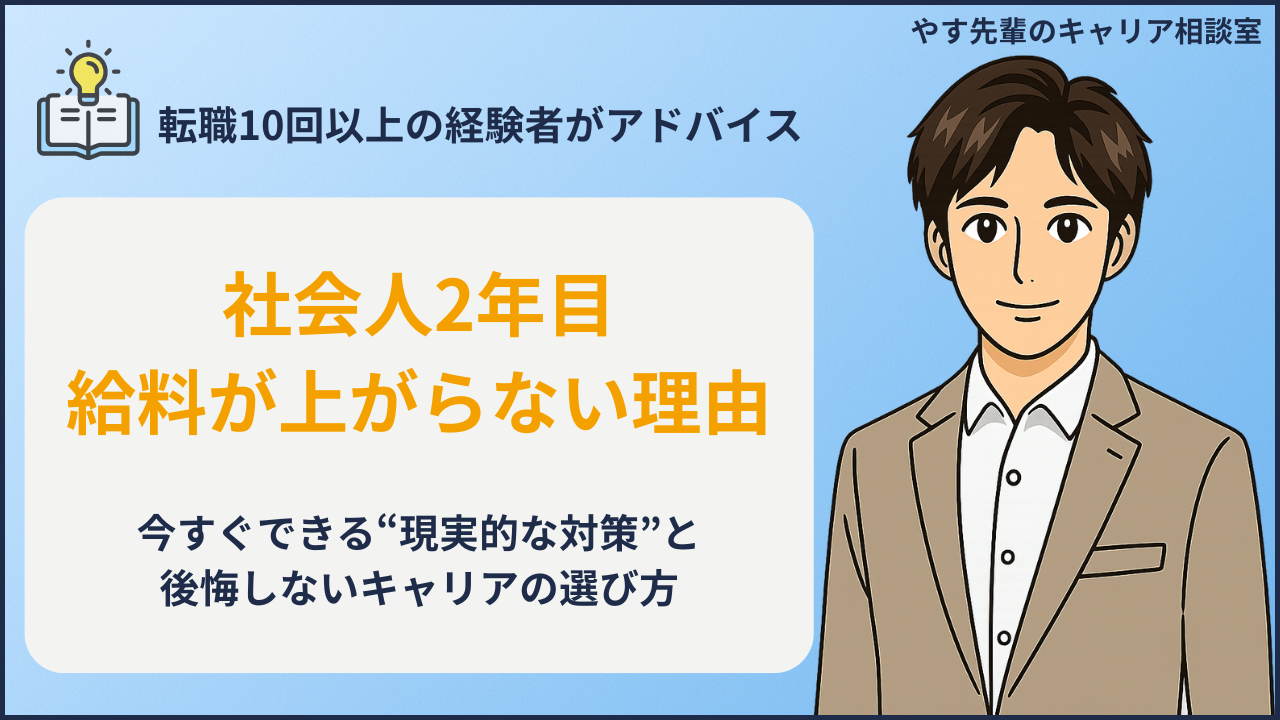
自分のチームが「辞めやすい職場」になっていないかチェック
人が辞める職場には、必ず「構造的な兆候」があります。
とくに真面目な人や優秀な人ほど、限界まで我慢してから突然辞める。
だからこそ、「問題が起きてから」ではなく「静かな異変」を早期に見抜くことが重要です。
ここでは、あなたのチームが“辞めやすい職場”になっていないかをチェックする3つの観点を紹介します。
感謝や評価の言葉が減っていないか
最初にチームが崩れ始めるサインは、「ありがとう」が減ることです。
日常の小さな承認がなくなると、心理的な報酬が枯渇し、メンバーは「何のために頑張っているのか」分からなくなります。
辞めやすい職場の兆候
- 定例MTGで成果の共有が「報告」止まり(称賛がない)
- 「ありがとう」がスタンプや定型文で済まされる
- 評価は期末だけ、日常では“無言の肯定”が続く
改善アクション
- Slackなどで「称賛チャンネル」を設け、行動×結果を言語化して褒める
- 上司が週に1回、1人へ15秒の感謝メッセージを送る
- 評価の面談では、“結果+貢献過程+期待”の三段構成で伝える
チェックポイント
- 最後に「ありがとう」と言ったのはいつか?
- その「ありがとう」は“行動”に対して言えたか?



感謝って、無料なのに最強の報酬なんですよ。
褒められなくても頑張る人ほど、褒められた瞬間に“もう少しやってみよう”って変わるんです。
余白のないスケジュール・慢性的な残業が常態化していないか
“真面目な人が急に辞める”理由の多くは、心と体のバッファが消えたときです。
優秀な人ほど責任感が強く、限界を超えても「自分さえ我慢すれば」と抱え込みます。
そして、突然限界を迎える。これが「まともな人 突然辞める」典型パターンです。
辞めやすい職場の兆候
- 会議・打ち合わせが詰まり、昼休みや帰宅時間が形骸化
- 突発タスクが「緊急」として常に優先される
- 残業が“黙認文化”になり、上司が先に帰れない空気
改善アクション
- チーム全員のカレンダーを可視化し、週5〜10%の余白を強制設定
- 「タスクの緊急度」をA:本日必須/B:今週中/C:要相談で整理
- 上司が自ら“定時で帰る姿”を見せる(文化は行動で変わる)
チェックポイント
- メンバーの予定表に「休む」「考える」時間が入っているか?
- 「急ぎ」タスクが週何件あるか? それは本当に急ぎか?



余白がないチームは、壊れ方も一瞬なんです。
仕事を詰めるのがマネジメントじゃなく、呼吸を作るのがマネジメントです。
フィードバックが「叱責」になっていないか
辞めやすい職場ほど、上司が「改善のため」と言いながら、
実際は“叱る”に寄っているケースが多い。
特に成果を出してほしい人ほど口調が強くなり、
それが「期待」ではなく「圧力」として伝わってしまいます。
辞めやすい職場の兆候
- “できなかった理由”を先に問う
- 成果よりもミスの報告を優先して求める
- 1on1が「ダメ出し反省会」になっている
- 上司の口ぐせ:「なんでできなかったの?」
改善アクション
- フィードバックを「事実→影響→期待」の順に伝える(例:「この対応で顧客満足度が下がった。次は〇〇で再挑戦しよう」)
- 叱る代わりに、「一緒に直そう」という伴走型コメントを増やす
- 1on1のうち3分の1は承認と雑談時間に充てる
チェックポイント
- 最近「褒める」より「直す」を多く言っていないか?
- フィードバック後、相手の表情が沈んでいないか?



“叱責”は一瞬の静けさを作るけど、信頼を削る。
フィードバックは“責める”じゃなく“支える”。
その違いをわかる上司に、人はついていくんです。
まとめ
優秀な社員は、感情で辞めるのではなく、合理的に「この場所ではもう成長できない」と判断して去る。
つまり、退職とは衝動ではなく、冷静な見切りです。
そのサインは、派手な不満ではなく、「発言が減る」「目の輝きが薄れる」といった“静かな違和感”として現れます。
上司がこの小さな変化に気づけるかどうかが、組織の分かれ道になります。
そして大切なのは、「辞めないように管理する」ことではなく、「辞めたくないと思える関係」を築くこと。
優秀な人は、強く引き止められても残りません。
でも、「この上司ともう少し一緒に働きたい」と思える環境があれば、自然と留まるのです。
信頼は、制度でも給料でもなく、日々の対話と理解の積み重ねから生まれます。
評価・感謝・挑戦のバランスを整え、
「ここならまだ成長できる」とメンバーが感じられるチームであれば、
優秀な人が辞める“連鎖”は起こりません。



人は辞めるけど、“関係”は残せる。
そして、その関係が次の成長を連れてくる。
だから僕は、辞めない人を育てるんじゃなく、“また一緒に働きたい”と思われる上司を目指しています。
よくある質問
- 優秀な人が辞める前兆を見抜く方法は?
-
会議での発言量が減る、雑談に加わらなくなる、Slackなどでの反応が淡白になるなど、
“日常の温度変化”が最初のサインです。
特に「目の奥の熱」が消えたときは要注意。静かな違和感こそ、最も確実な前兆です。 - 優秀な人が辞めるのを防ぐには?
-
「辞めない仕組み」を作るよりも、「辞めたくない関係性」を築く方が長期的に効果的です。
信頼は制度ではなく、上司の言葉・態度・聞く姿勢から生まれます。
1on1で「最近どう?」と心を聞く時間を定常化するだけでも、離職率は確実に下がります。 - 優秀な人が辞めた後のチーム立て直しは?
-
まずは「裏切られた」気持ちを整理することから。
感情を抑え込むより、メンバーと「何を学べたか」を共有し、失った意味をチームの財産に変えることが大切です。
“退職=失敗”ではなく、“改善の起点”にできる組織は強くなります。 - 優秀な人はなぜ見切りが早いの?
-
彼らは「時間=最大の資産」と理解しています。
変わらない組織に居続けることを機会損失と捉え、次の挑戦へ動く決断が早いのです。
我慢ではなく、進化を選ぶ合理性が、見切りの早さの正体です。 - 優秀な人が辞めた後、自分も転職したくなったら?
-
感情のままに動く前に、ミイダスで自分の市場価値を数値で確認しましょう。
「今の自分が市場でどんな評価を受けるのか」を可視化することで、
現職に残るか、転職するかを冷静に判断できる軸ができます。
焦りではなく、データでキャリアを選ぶ姿勢が未来を変えます。