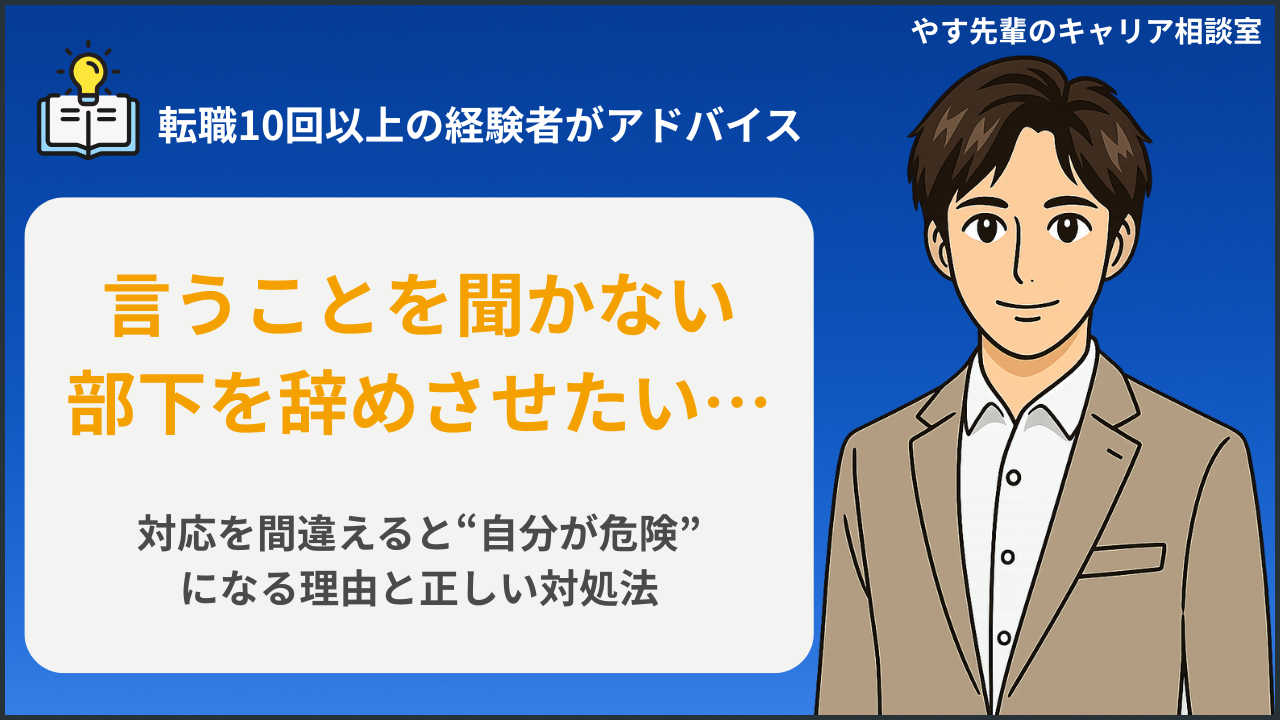やす先輩
やす先輩40代半ば、転職10回の管理職。上場もベンチャーもブラックも経験してきました。失敗も学びも交えながら、キャリアや働き方に悩むあなたへ“現実的な解決策”を届けます。
⇒詳しいプロフィール
「何を言っても動かない」
「指示を無視する」
「報告もなく、チームの空気が悪くなる」
言うことを聞かない部下に悩み、「正直、辞めさせたい…」そう思ってしまう上司は、決して少なくありません。
僕自身もマネージャー時代、注意しても響かず、周囲に悪影響を与える部下に振り回され、精神的にかなり追い込まれた経験があります。
だからこそ断言できます。
感情のまま動くと、一番危険なのは“上司側”です。
対応を間違えれば、パワハラ・不当解雇・評価トラブルといった形で、立場やキャリアを一気に失いかねません。
大切なのは、
・辞めさせたいと思う前に整理すべき判断軸
・安全に取るべきステップ
・「切る/切らない」以外の現実的な選択肢
を、感情ではなく構造で理解することです。
この記事では、
・言うことを聞かない部下が生まれる背景
・辞めさせたいと感じるのが自然な理由
・やってはいけないNG対応
・自分を守りながら取れる正しい対処法
を、やす先輩の実体験と、法律・人事の観点を交えて解説します。
もし今、
「このマネジメント、本当に自分だけの問題なのか?」
「自分の評価やキャリアまで危なくなっていないか?」
と少しでも不安を感じているなら、一度、自分の市場価値や立ち位置を客観的に確認してみてください。
管理職の悩みは、今の職場だけが基準ではありません。
「逃げ道がある」と分かるだけで、部下への向き合い方は驚くほど冷静になります。
この記事で、感情ではなく“安全な判断軸”を一緒に整理していきましょう。
言うことを聞かない部下に共通する特徴とは?
「何度言っても変わらない」「指示を無視して独断で動く」
言うことを聞かない部下に頭を抱える上司は本当に多いです。
でも、こうした部下を単に“無能”や“反抗的”と決めつけてしまうのは危険です。
多くの場合、そこには共通する行動パターンや心理的な背景があります。
まずは、その特徴を冷静に見極めることが、対応の第一歩になります。
注意しても改善しない「受け身型・反発型」の2タイプ
言うことを聞かない部下には、大きく分けて2つのタイプがあります。
- 受け身型タイプ
「指示されないと動けない」「やる気が見えない」タイプです。
本人に悪気はないものの、常に“責任を取りたくない”姿勢で行動します。
このタイプは、仕事の優先順位を自分で決めるのが苦手で、
結局「上司の言うことを聞かない」ように見えてしまいます。 - 反発型タイプ
「自分の考えが正しい」と思い込むタイプ。
指摘されると反論し、改善指示を“攻撃”と受け取ります。
上司に対して反発的な態度を取るのは、自己防衛の一種ですが、
周囲から見るとチームの和を乱す厄介な存在に見えます。
この2タイプを混同すると、対処を間違えやすくなります。
重要なのは、「性格の問題」ではなく「思考のクセ」として捉えることです。



僕も昔、反発型の部下を相手に何度も衝突しました。
でも、あるとき「反発の裏には不安がある」と気づいてから、関係が改善しました。
人は“守りたいもの”があるときほど、素直になれないものなんです。
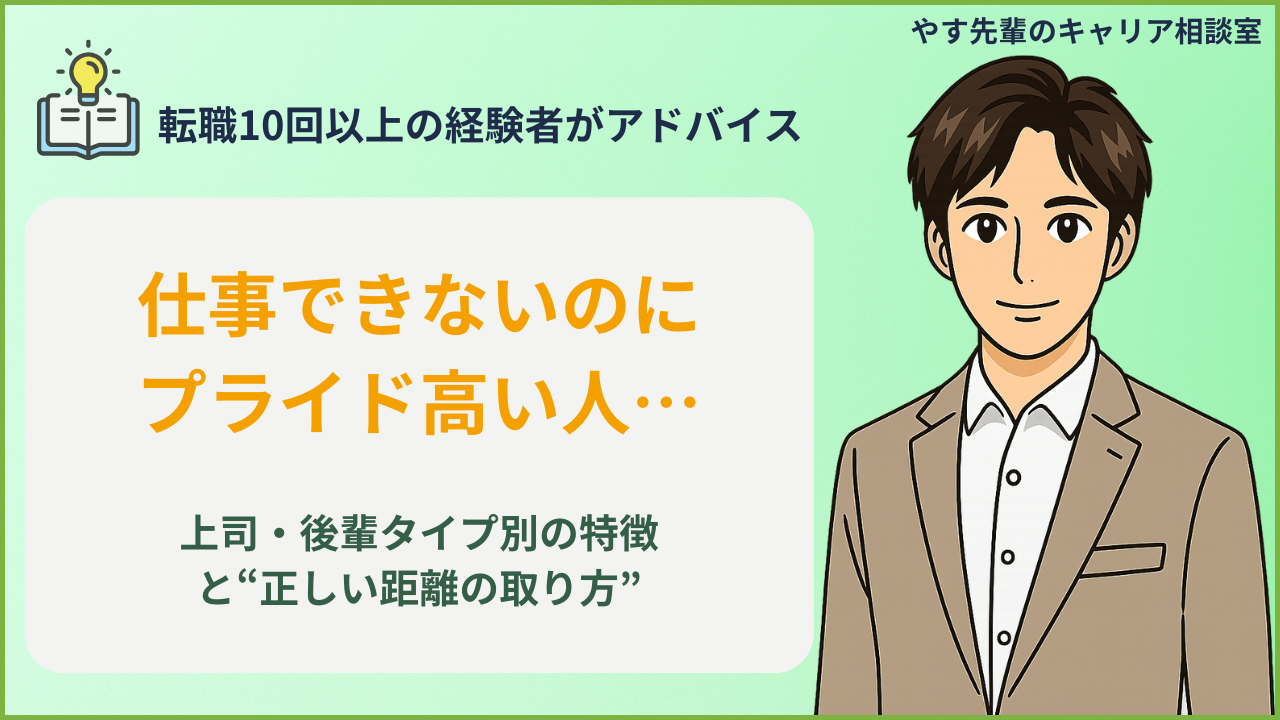
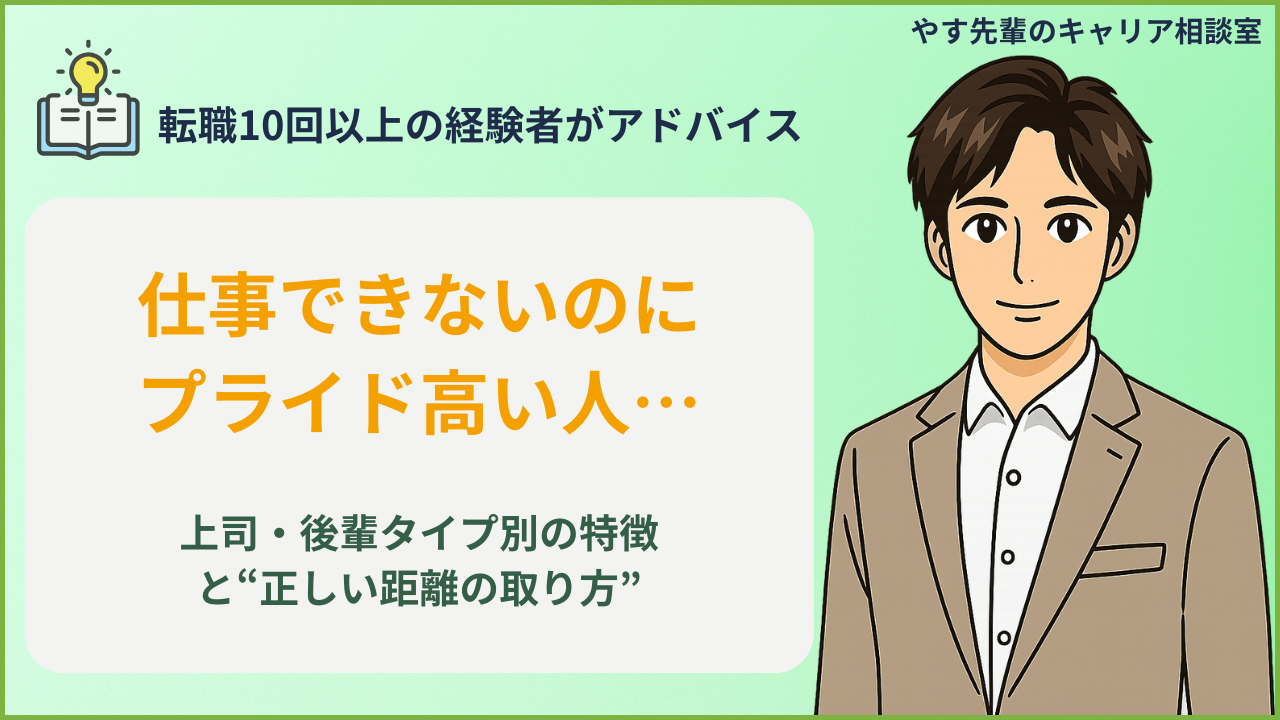
自己中心的・責任転嫁・学習意欲の低さに共通点がある
もう一つの共通点は、「自分の立場を理解していない」こと。
仕事ができない人ほど、他責思考(人のせい)になりがちです。
たとえば、
- ミスをしても「自分は悪くない」と言い訳をする
- 評価されない理由を「上司が嫌いだから」と決めつける
- 改善のために学ぼうとしない
このような行動は、本人が悪いというよりも「自分の価値を見失っている」サインです。
自己肯定感が低いと、注意を“攻撃”と受け取って防御的になってしまう。
そんなとき、上司がいくら正論をぶつけても逆効果です。
まずは“相手の現状を可視化”するところから始めましょう。
たとえば、ミイダス市場価値診断を使って、
「今の自分の立ち位置」や「評価されているスキル」を数値で見せると、
部下本人が「思っていたより評価されていない」と気づくケースもあります。
感情論ではなく“データ”を使うことで、指導の説得力が格段に上がります。



僕の部下にもいました。何度言っても響かないタイプ。
でも、一緒にミイダスを見せたら、自分の市場価値を知って少しずつ前向きになったんです。
数字で現実を見ることは、どんな説教よりも効果があります。
実は「上司との関係悪化」が原因になっていることも
「言うことを聞かない部下=性格の問題」と思いがちですが、
実は“関係性のこじれ”が原因であることも少なくありません。
過去の注意が厳しすぎた、または上司が忙しくて話を聞かなかった。
そんな小さなすれ違いが積み重なり、「この人には何を言われても聞かない」という
心理的な壁を作ってしまうケースもあります。
この場合、叱るよりも信頼の再構築を優先すべきです。
たとえば、1on1で「最近どう思ってる?」と雑談ベースで聞くだけでも、
「この人は話を聞いてくれる」と感じて関係が和らぐことがあります。
関係を立て直さないまま指導を繰り返すと、
どんなに正しいことを言っても“反発”しか生まれません。



僕が一番後悔してるのは、「伝え方を変えなかった」こと。
言葉は同じでも、信頼があるかないかで伝わり方がまったく違う。
“指導”はコミュニケーションなんですよね。


なぜ「辞めさせたい」と感じてしまうのか?上司側の心理を整理する
言うことを聞かない部下を前にすると、
「もう辞めてほしい」と思ってしまうのは、決して珍しいことではありません。
僕も管理職時代、同じ気持ちを抱いたことが何度もあります。
指導しても改善せず、チームの足を引っ張られると、
「このままだと自分の評価まで下がる」と焦ってしまうんですよね。
でも、その感情を“悪いこと”と責める必要はありません。
むしろ、どの上司も一度は通る道です。
ここでは、そんな心理の正体を整理してみましょう。
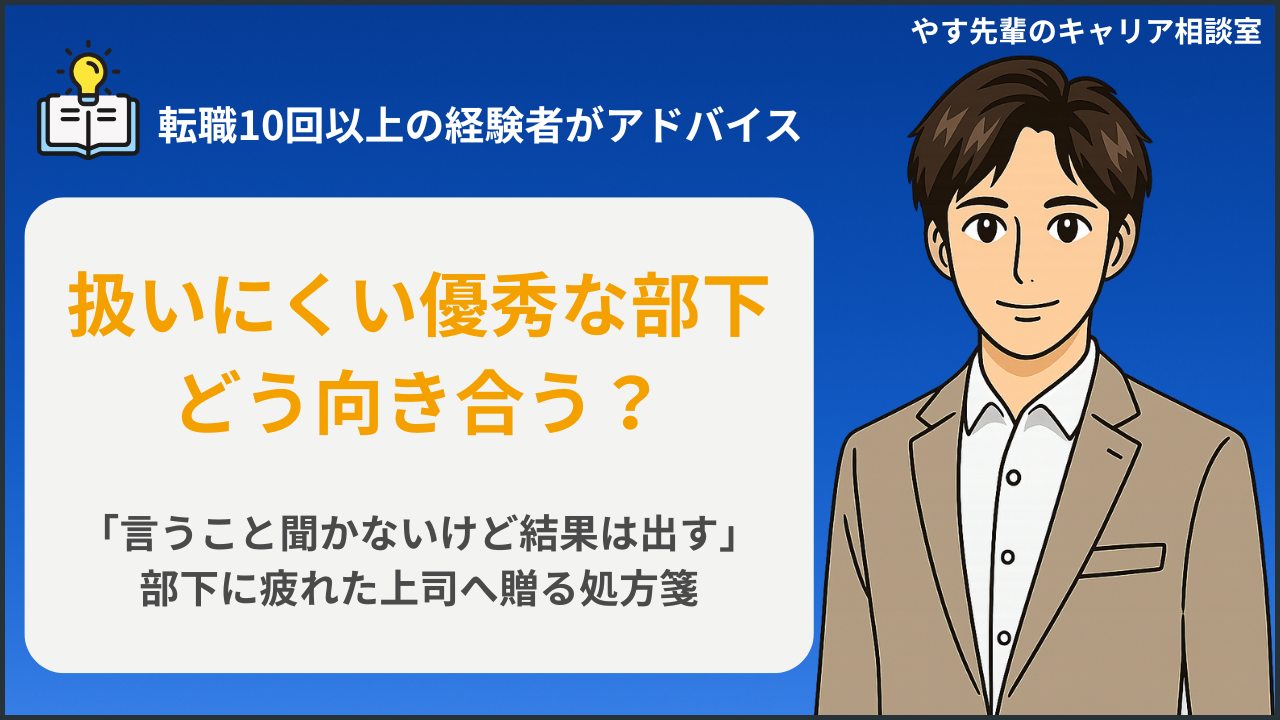
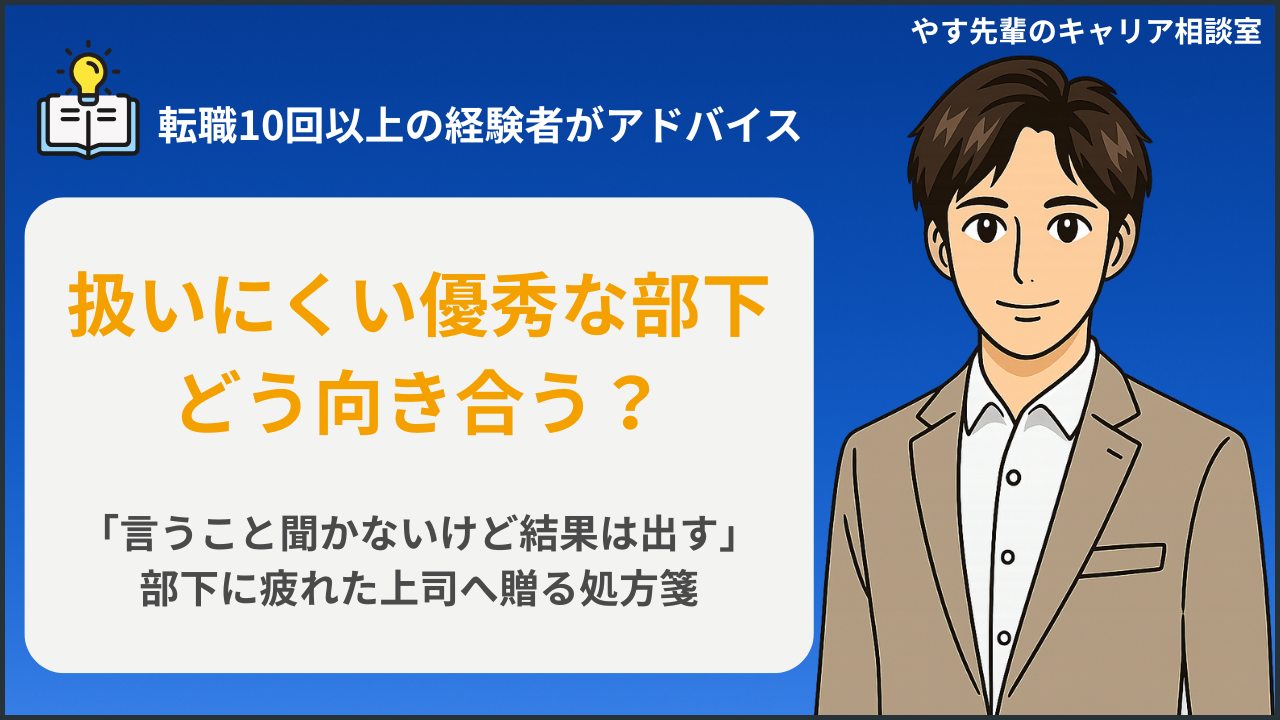
成果主義の中で「足を引っ張られる」焦り
今の職場はどこも成果主義が強く、
上司自身が数字で評価される時代です。
そんな中で、言うことを聞かない部下がいると、
「自分がフォローしないと目標に届かない」と感じ、
余計な仕事が増えてストレスが溜まります。
しかも、評価シートには「チーム全体の成果」も反映される。
だからこそ、部下のパフォーマンスが低いと、
上司が“自分の将来”まで脅かされているように感じてしまうんです。
この焦りが続くと、
「もう辞めてほしい」「いない方が楽だ」と思ってしまうのも無理はありません。



僕も数字に追われていた時期、部下の行動にイライラしてばかりでした。
でも冷静に考えると、焦りの原因は“自分の評価への不安”だったんですよね。
一度その気持ちを整理すると、少しだけ楽になります。
他の部下との公平性が崩れるストレス
もう一つの大きな要因は、「チーム内の公平性」です。
真面目に努力するメンバーがいる中で、
言うことを聞かない部下がいると、当然バランスが崩れます。
- 指示を守らないのに同じ給与をもらっている
- 反抗的なのに注意されない
- 手を抜いても誰も責任を問わない
こうした状況が続くと、他のメンバーのモチベーションまで下がってしまいます。
上司としても、「優遇している」と思われるのが怖い。
だからこそ、「辞めてもらった方がチームがまとまるのでは」と考えてしまうのです。
ただし、ここで重要なのは“公平に扱う姿勢”を見せることです。
注意の記録を残し、面談の場を設けて、
「きちんとプロセスを踏んでいる」とチーム全体に伝えることで、信頼を守れます。



僕もかつて、問題のある部下を放置してチームの士気を下げた経験があります。
結局、“公平に接している姿勢”がないと、信頼は失われる。
対応のスピードより、丁寧さの方が大事なんです。
「人を辞めさせたい」と思うこと自体を責めなくていい理由
「人を辞めさせたいなんて、冷たいのでは」と罪悪感を抱く人も多いでしょう。
でも、部下を辞めさせたいと感じるのは“責任感がある人ほど”陥りやすい感情です。
なぜなら、
- チームを守りたい
- 周囲に迷惑をかけたくない
- 自分の役割を果たしたい
という意識があるからこそ、問題行動に強く反応してしまうのです。
つまり、「辞めさせたい」と思うこと自体が悪いのではなく、
その感情をどう扱うかが上司の力量なんです。
冷静に自分の感情を可視化し、
「これは怒りではなく、焦りなんだ」と気づけるだけで、行動は変わります。
もし感情を整理できないほど疲れているなら、
ミイダス市場価値診断で一度“自分自身の今の立場”を見直すのもおすすめです。
数字で自分の強みを確認すると、「まだ自分には選択肢がある」と前向きになれます。



僕も一時期、「辞めさせたい」と思う自分を責めていました。
でも、感情を抑え込むより“見える化”した方がずっと健全でした。
上司だって人間です。感情を整える力も立派なマネジメント力ですよ。
感情で辞めさせるのは危険!違法・不当と判断されるケース


「もう限界。辞めさせたい」と思ったとき、
感情のままに動いてしまうのはとても危険です。
僕も管理職時代に、一歩間違えば「パワハラ」と取られかねない指導をしてしまい、
人事から呼び出されたことがあります。
その経験を通じて感じたのは、「悪気がなくても不当な扱いに見られることがある」という現実です。
ここでは、特に注意すべき「違法・不当」と判断されるケースを解説します。


指導記録なしでの退職勧奨は「パワハラ」扱いのリスク
部下に「もう辞めた方がいいんじゃない?」と口にしてしまう上司は少なくありません。
しかし、指導記録や改善の経過が残っていない状態での退職勧奨は、ほぼ確実に“パワハラ扱い”になります。
会社が社員を辞めさせるには、
- 明確な業務上の問題がある
- 改善指導を複数回行った
- それでも改善が見られなかった
この3ステップが証拠として残っていることが前提です。
つまり、感情的に「もう無理」と判断して退職を促すと、
「不当解雇」「不当な圧力」として逆に訴えられるリスクがある。



僕も当時は「ここまで注意しても変わらないなら仕方ない」と思っていました。
でも、上司の主観だけではダメなんですよね。
“記録に残す”ことが、あなた自身を守る最大の防衛策です。
圧力・孤立・業務外しはすべて「いじめ」「モラハラ」に該当
問題社員をなんとかしたい一心で、
つい「関わらないようにしよう」「仕事を減らして様子を見よう」としてしまう。
実はこれも危険です。
- 仕事を与えない
- 会議や情報共有から外す
- 周囲に「関わるな」と伝える
これらはすべて“業務上のいじめ・モラハラ行為”と見なされる可能性があります。
辞めさせる意図があると判断された瞬間、
“被害者と加害者”の立場が逆転することも珍しくありません。
最悪のケースでは、上司自身が懲戒処分や降格になることもあります。
いわゆる「人を辞めさせる人の末路」がここです。
相手を排除しようとするほど、自分が追い込まれる構造になっているんです。



僕も一度、部下をチームから外したことで人事に注意されたことがあります。
意図は「様子を見るため」でも、やっていることは“孤立”なんですよね。
感情より“仕組み”で動く大切さを痛感しました。
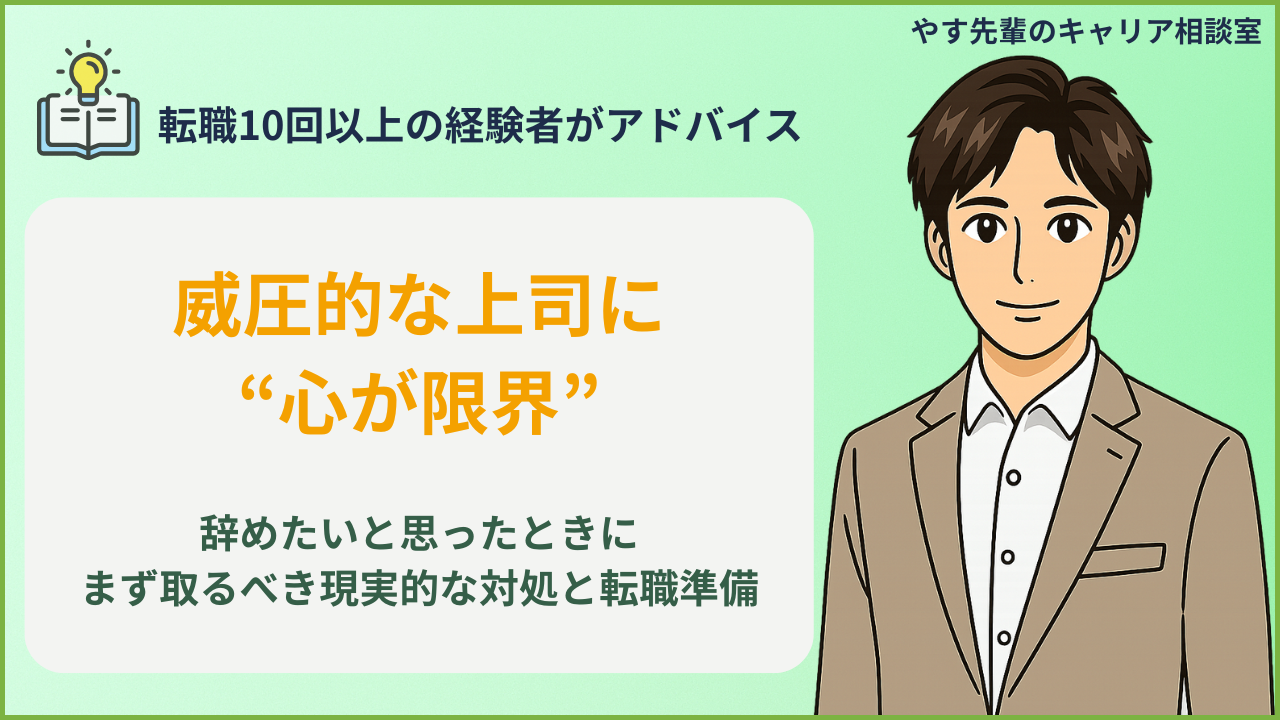
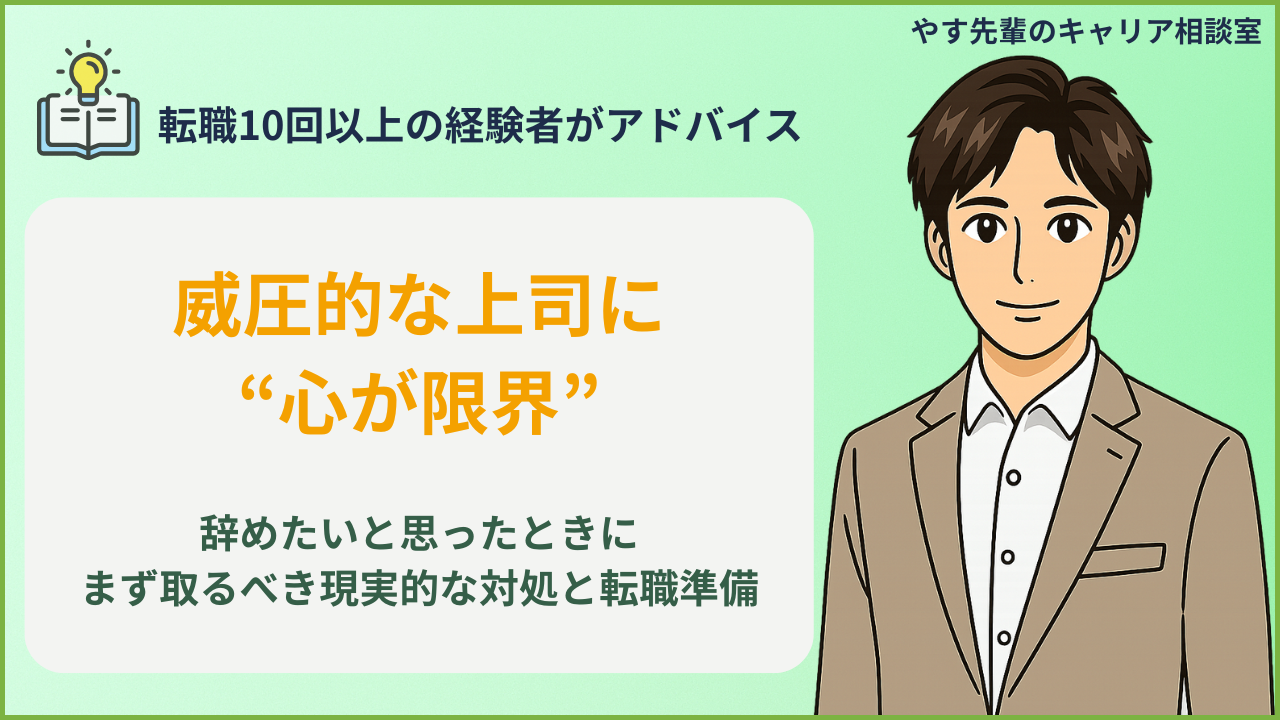
「辞めさせる側」がトラブルに発展しやすい3パターン
感情的に動いた結果、「辞めさせる側」がトラブルに巻き込まれるケースは多いです。
特に以下の3パターンには注意が必要です。
- 証拠がなく、口頭だけのやり取りで注意していた
→「そんなこと言われていない」と反論され、記録が証拠にならない。 - 感情的な発言をしてしまった
→「人格否定された」と捉えられ、パワハラ申告の原因になる。 - 本人の意思確認をせずに人事へ報告した
→「辞めさせようとしている」と誤解され、職場全体の信頼を失う。
こうしたミスは、上司本人に悪意がなくても起きます。
だからこそ、冷静に、客観的な手順を踏むことが重要なんです。
もし今、「この部下とはもう限界」と感じているなら、
一度、ビズリーチで他社の管理職求人を覗いてみるのもいいかもしれません。
僕自身、過去に転職サイトで“外の世界”を見たことで、
「いまの職場だけが全てじゃない」と心が軽くなりました。
環境を変える選択肢を知るだけでも、余裕が戻ります。



本気で限界を感じているなら、まず“自分を守る”視点を持ってください。
部下に責任を押し付ける前に、自分のキャリアを守るのも立派な判断です。
冷静な行動こそが、一番のリスクヘッジです。
正しいステップで「辞めさせる」ための現実的対応策
「もう辞めてもらうしかない」と感じても、
感情的に動くとトラブルになるのは前章でお伝えした通りです。
では、実際に法的・人事的に問題のない形で辞めさせるには、どんな手順を踏めばいいのでしょうか。
ポイントは、「感情ではなく証拠と手順」。
正しい流れで進めれば、上司としての信頼も守れます。
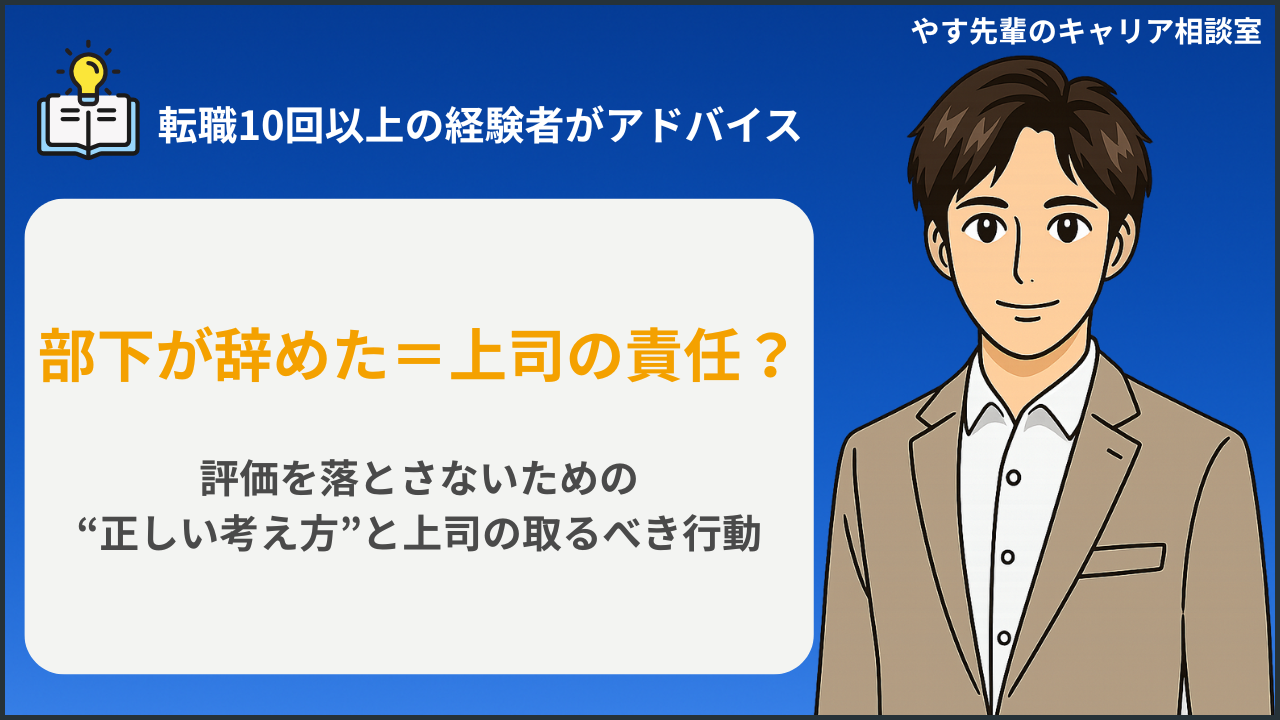
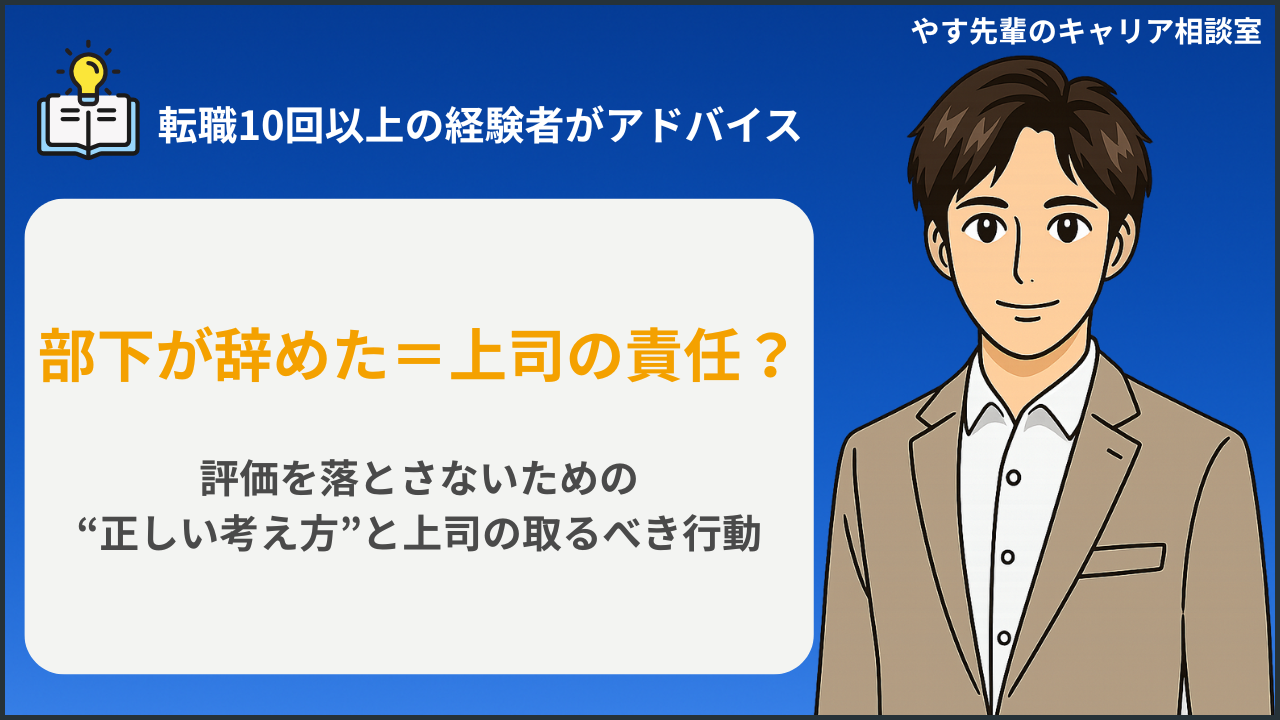
まずは「指導・注意・改善指示」を3回以上、記録に残す
どんなに能力不足の社員でも、会社は“改善の機会”を与えなければなりません。
つまり、「注意→指導→再指導」の流れを少なくとも3回以上行い、
その内容を日報・面談記録・メールなどで残すことが重要です。
記録には、次のようなポイントを押さえましょう。
- いつ、どんな問題が起きたのか
- どんな指導を行ったのか
- 本人の反応や改善意欲の有無
これを残しておくだけで、後に「不当な扱い」と主張されても防御できます。
口頭でのやり取りだけでは「言った・言わない」になってしまうため、証拠化は必須です。



僕も最初の頃は、注意した内容を覚えておく程度でした。
でも、トラブルを経験してから“記録を残す”ようにしたんです。
それ以来、何があっても冷静に対応できるようになりました。
改善が見られなければ「面談」で本人の意思を確認
指導を続けても改善が見られない場合は、
本人と1対1の面談を行い、意識や方向性を確認します。
このときの目的は「辞めさせる」ではなく、
「本人が現状をどう捉えているか」を把握することです。
質問例としては、
- 今の仕事で何が一番難しいと感じているか
- 自分の成長や貢献をどう考えているか
- 会社に残って改善する意思があるか
こうした問いかけを通じて、“自らの意思”で今後を考えるきっかけを与えます。
上司が結論を押し付けるのではなく、相手に気づかせるスタンスが大切です。
もし20代の若手社員で、「自分の将来を見失っている」と感じる場合は、
マイナビジョブ20’sなどのキャリア相談サービスを案内するのも一つの方法です。
実際、僕の部下の一人もここで相談を受けたことで、
「今の職場ではなく、自分が成長できる場所へ行く」という前向きな決断ができました。



無理に引き止めるより、“相手が納得して動ける状態”をつくること。
これが、上司として一番誠実な対応だと僕は思っています。
「退職勧奨」を行う場合は人事・法務と連携して進める
最終手段として「退職勧奨」を行う場合は、
必ず人事部・法務担当と連携して進めることが大前提です。
退職勧奨とは、会社が社員に「自主的な退職を促す」行為。
解雇とは違い、本人の同意が必要です。
そのため、圧力をかける言い方や強制的な表現は厳禁です。
手順としては、
- 問題点と改善経過を客観的に説明する
- 「今後どんな道を選びたいか」を本人に確認する
- 退職を希望した場合、正式な意思確認書を残す
この流れを守れば、不当解雇のリスクを避けられます。
また、上司自身も「適正に対応した」として会社からの信頼を得られるでしょう。
もしあなたが管理職として「これ以上は難しい」と感じているなら、
ビズリーチでキャリアを広げてみるのも一つの選択肢です。
僕も当時、他社のマネージャー求人を見たことで、
「自分が評価される環境を選ぶのも勇気だ」と気づきました。



部下を辞めさせるよりも、自分の働く環境を変える方が早いこともあります。
“守るべき立場”だからこそ、自分のキャリアも守ってくださいね。
どうしても改善しない場合の最終手段
指導や面談を重ねてもまったく改善が見られない。そんなとき、上司として「最終手段」を考えるのは自然な流れです。
ただし、最終手段は会社と本人の双方に大きな影響を与えるため、慎重に進める必要があります。
ここでは、懲戒や配置転換などの制度的手段を検討する前に確認すべきこと、第三者を交えた安全な進め方、そして最終的に本人に退職の判断を促す現実的な方向性を紹介します。
懲戒や配置転換を検討する前に社内ルールを確認
懲戒処分や配置転換は会社の正当な手段ですが、まずは就業規則・懲戒規程・人事制度を確認することが絶対条件です。
特に懲戒は、行為の重大性、過去の処置、改善機会の提供が適正に行われているかが問われます。就業規則に基づかない一方的な処分は「不当」とみなされるリスクが高く、労働審判や訴訟に発展する可能性があります。
配置転換についても、業務内容や労働条件が大きく変わる場合は本人の同意や適性確認が必要になる場合があります。まずは人事と就業規則を読み込み、どの手続きが社内ルールに沿っているかを明確にしてから動きましょう。感情的に「関係を切る」ような対応を取ると、上司が逆に責任を問われることがあります。
また、懲戒や配置転換を検討する際は、過去の同種事案で会社がどのように対応してきたか(前例)も確認してください。一貫性がないと不公平だと指摘されやすくなります。
第三者(人事・弁護士)を交えて進めるのが安全
問題が深刻で最終手段を検討する段階になったら、人事部門はもちろん、必要に応じて法務や外部の労働弁護士を巻き込みましょう。第三者を入れることで、手続きの正当性が担保されやすくなり、感情論で物事が進むリスクを減らせます。
具体的には、人事と共に事実関係を整理し、記録を提示して客観的に評価を行います。弁護士が介入すれば、就業規則・労働基準法・判例に照らしてリスクを検討してくれます。必要に応じて、社内での聴取方法や面談での言い回し、証拠の保存方法などを指示してもらうと安全です。
第三者を交えることは決して「相手を追い詰める」ためではなく、会社と個人双方を守るための手続きです。上司としては感情的にならず、事実と記録を基に冷静に進める姿勢を保ちましょう。
最終的には「本人に辞める判断をさせる」方向へ誘導する
法的リスクや会社側の負担を最小化する現実的な最終方針は、本人の意思で退職に至る道筋を作ることです。これが「退職勧奨」の基本的考え方ですが、強制にならないよう慎重に進める必要があります。ポイントは、圧力をかけず選択肢を提示し、必要があれば再就職支援や転職サービスを案内することです。
面談では、問題点と改善経過を冷静に説明し、本人の今後の希望やキャリア観を確認します。そのうえで、会社としての立場(配置転換の可能性や改善の最終期限など)を提示し、本人が「別の道を選ぶ」ことを検討できる状況をつくります。ここで第三者(人事・弁護士)が同席すると、公平性が保たれます。
もし本人が精神的に限界を迎えている、あるいは即時の離職が望ましい状況であれば、退職代行サービスのような選択肢も紹介できます。退職代行を使うかどうかは本人の判断ですが、急を要する場合に備え、選択肢として示しておくことは上司としての配慮です。



最終局面で大切なのは「自分の感情で決めない」ことです。僕も一度、感情的に突っ走りかけて人事からストップが入った経験があります。結局、手順を守って第三者を交えたら、双方にとって最もダメージが少ない解決策が見つかりました。追い込む方法ではなく、選択肢を示して本人に決めてもらう――これが長くマネジメントを続けるコツです。
やす先輩の体験談|部下トラブルで心が折れかけた日
当時の状況:反抗的な部下に注意しても無視される毎日
数年前、僕がマネージャーをしていたときの話です。
チームの中に、一人だけどうしても言うことを聞かない部下がいました。
指示を出しても「わかりました」と言いながら動かない。
報告を求めても返ってこない。会議ではスマホをいじり、
他のメンバーの前で僕の指示を否定することもありました。
何度も注意しましたが、態度は変わらず。
他のメンバーの士気まで下がっていくのを見て、
「もうこのままではチームが壊れる」と強く感じていました。
感じたこと:ストレス・焦り・無力感
正直、心が折れかけていました。
朝出社するたびに、「今日はまた何を言われるだろう」と憂うつになる。
注意することにも疲れて、だんだん顔を合わせるのが怖くなっていきました。
仕事のことを考えると眠れず、休日も気が休まらない。
このままでは自分まで壊れてしまう――そう感じた頃には、
軽い不眠と頭痛が続き、病院で「ストレス性の不調」と診断されました。
モンスター社員という言葉がありますが、
実際にその相手を前にしたとき、怖いのは“怒り”よりも“無力感”です。
「自分が悪いのかもしれない」と思ってしまうんですよね。
行動:冷静に記録を取り、人事と相談
このまま感情的に接しても逆効果だと感じ、
僕は一度、冷静に「記録を取る」ことにしました。
・いつ、どんな発言や態度があったか
・どう注意したか
・相手がどう反応したか
これをすべてメモに残し、人事部へ相談しました。
結果、人事担当から「記録をもとに対応すれば問題にならない」とアドバイスをもらい、
次の面談からは人事にも同席してもらうようにしました。
その後の話し合いでは、上司一人では出せなかった“客観的な意見”が入り、
部下も少し冷静になって話を聞くようになりました。
結果:会社主導で配置転換、チームの雰囲気が回復
数週間後、会社が正式に判断を下し、
その部下は別部署への配置転換となりました。
正直、ホッとしました。
チームの空気はすぐに明るくなり、
「前より仕事がやりやすくなった」とメンバーから言われたとき、
やっと肩の力が抜けました。
僕自身も、無理に“我慢して解決しよう”としていたことに気づきました。
上司が一人で抱え込むのは、誰にとってもプラスにならない。
学び:「我慢」ではなく「仕組みで解決する」ことの大切さ
この経験を通じて学んだのは、
「感情で動く」よりも「仕組みで解決する」方が早くて確実だということです。
人を辞めさせるかどうかの判断は、上司の仕事ではなく会社の仕組みの範囲。
上司の役割は、“冷静に記録を残し、正しい手順を踏む”ことです。
もし今、あなたが同じように心が限界に近いと感じているなら、
無理に抱え込まないでください。
一度、退職代行サービス「トリケシ」などの専門機関を調べておくのもいい。
それを使うかどうかは別として、
「逃げ道がある」と知るだけで、心が少し軽くなります。



僕はこの経験で「我慢しない勇気」の大切さを知りました。
人を変えることより、自分が動くことの方が早い。
そして、“仕組みを味方につける”ことで、上司も部下も救われるんです。
まとめ|「辞めさせる」より「守る対応」が上司を救う
言うことを聞かない部下に悩むと、「もう辞めてほしい」と感じてしまうのは自然なことです。
でも、こうした問題の多くは個人の性格ではなく“構造的な問題”です。
業務の仕組み、評価体制、コミュニケーションの断絶。その背景に原因があります。
だからこそ、感情で動いてはいけません。
怒りや焦りのままに辞めさせようとすると、最終的に不当な扱いをしたと見なされ、
自分が不利な立場になることもあります。
上司として最も大切なのは、「正しいプロセスを踏んで、自分を守ること」。
記録を残し、人事や法務に相談し、会社のルールに沿って対応する。
それが、結果的に自分の立場もチームの信頼も守る一番の方法です。



僕も昔は「どうにかして辞めさせたい」と思っていました。
でも、冷静に手順を踏んだことで、トラブルにならずチームも守れたんです。
“守る対応”は、逃げではなくマネージャーとしての成熟なんですよね。
もし、どうしても心が限界だと感じるなら、
一度ミイダス市場価値診断で自分の市場価値を確認してみてください。
客観的な数字で自分の立場を知ると、「転職」という選択肢が現実的に見えてきます。
さらに、若手ならマイナビジョブ20’s、管理職層ならビズリーチで
より自分らしく働ける環境を探すのも良い判断です。
そして、「もう本当に無理」「明日が怖い」と思うほど追い詰められているなら、
退職代行サービス「トリケシ」を使って環境をリセットするのも立派な選択。
逃げることは負けではなく、自分を守る行動です。
冷静に記録を残し、正しく相談し、そして必要なら環境を変える。
それが、あなた自身を救う一番の方法です。
よくある質問
- 言うことを聞かない部下をすぐ辞めさせることはできますか?
-
基本的にはできません。指導・改善の機会を与えたうえで、記録を残すことが必要です。感情的に退職を促すと不当解雇扱いになるリスクがあるため、必ず人事・法務を交えて対応してください。
- 改善しない部下を放置したら、上司の評価は下がりますか?
-
長期的にはチーム全体の成果に影響するため、評価が下がる可能性はあります。ただし、焦って独断で動くのは危険です。人事に相談し、記録を残したうえで「適正な対応」を取ることが最も安全です。
- 注意しても反抗的な態度を取られる場合、どうすればいいですか?
-
感情でぶつからず、客観的な証拠を残すことが大切です。必要に応じて第三者(人事や弁護士)を交えるとトラブルを防げます。本人の意見を聞く姿勢を示すことで、関係改善につながるケースもあります。
- 上司が疲弊して精神的に限界を感じるときはどうすれば?
-
まずは自分を責めず、医療機関や信頼できる人に相談しましょう。限界を超えてまで我慢する必要はありません。退職を視野に入れる場合は、トリケシなどの退職代行サービスを使うことで安全に離脱できます。
- 問題社員を辞めさせた後、チームの再建はどう進めるべき?
-
まず「公平で冷静な判断をした」という信頼を示すことです。メンバーに対しては、今後の方針や評価基準を明確に伝えましょう。信頼を取り戻すには時間がかかりますが、透明性が最大の武器になります。