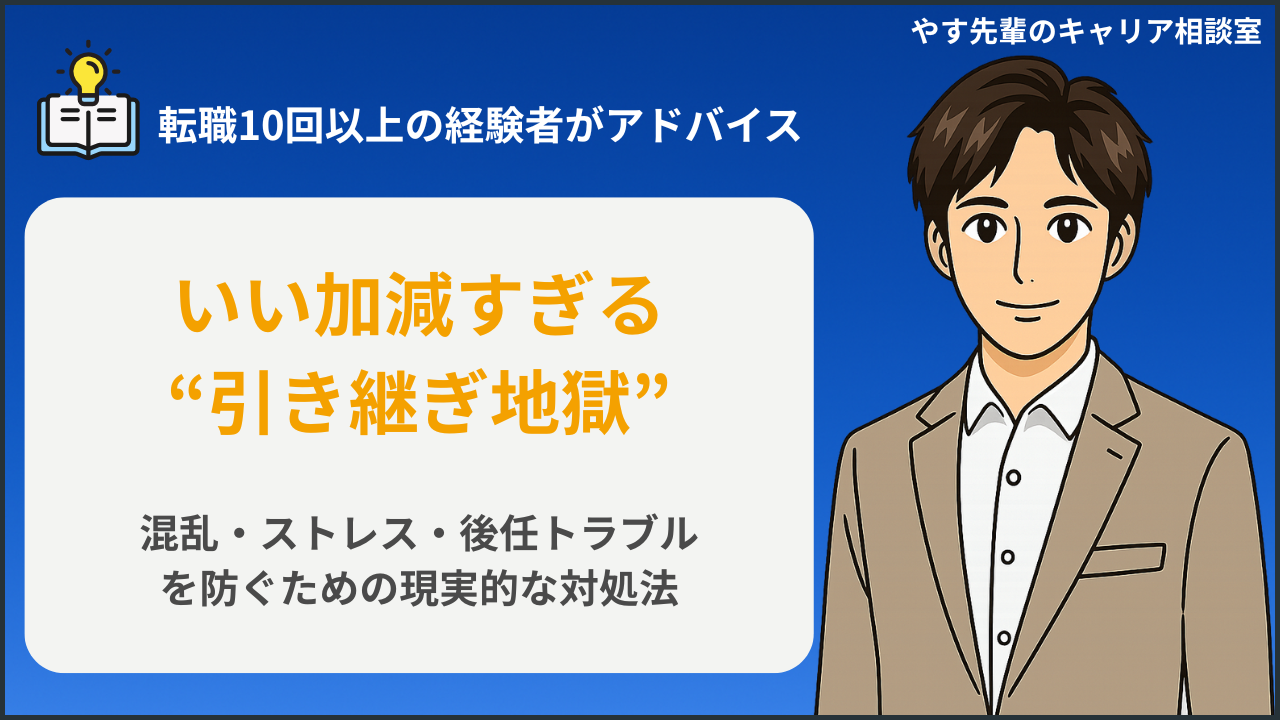やす先輩
やす先輩40代半ば、転職10回の管理職。上場もベンチャーもブラックも経験してきました。失敗も学びも交えながら、キャリアや働き方に悩むあなたへ“現実的な解決策”を届けます。
⇒詳しいプロフィール
「引き継ぎ資料が適当すぎて、何がどこにあるのか分からない…」
「“とりあえず大丈夫”って言われたのに、全然大丈夫じゃなかった!」
そんないい加減な引き継ぎに振り回され、毎日余計な混乱とストレスを抱えていませんか?
引き継ぎが雑だと、後任は混乱し、ミスの責任を背負わされ、前任は去ったあとで不満を持たれる。
結果として、職場全体の信頼関係まで壊れていくことも珍しくありません。
僕自身も、「これで全部」と渡された引き継ぎがスカスカで、一から手探りで立て直す羽目になった経験があります。
あのとき一番つらかったのは、自分の努力不足のように扱われる理不尽さでした。
はっきり言います。
完璧な引き継ぎは、現実にはほとんど存在しません。
大切なのは、足りない情報をどう補うかと、自分だけが消耗しない立ち回り方を知ることです。
この記事では、
・いい加減な引き継ぎが起きやすい職場の特徴
・混乱を最小限に抑える現実的な対処法
・後任/前任それぞれが取るべき正しい立ち回り
・責任を一人で背負わないための考え方
を、やす先輩の実体験を交えて分かりやすく解説します。
もし今、
「この職場では、いつも自分ばかり負担が大きい」
「頑張っても報われない構造かもしれない」
と感じているなら、一度“職場の外の評価”も確認しておくことをおすすめします。
ミイダスなら、職務経歴やスキル、性格特性をもとに、想定年収・強み・向いている働き方が数分で見えてきます。
転職する・しないに関係なく、「この環境に耐え続けるべきか」を冷静に判断する材料として、一度チェックしておく価値はあります。
仕事の引き継ぎがいい加減になる原因とは?
引き継ぎが「雑」「適当」「ぐちゃぐちゃ」と感じる背景には、
単なる“個人の怠慢”だけでなく、職場全体の構造的な問題が潜んでいます。
ここでは、なぜ引き継ぎがずさんになるのか、その代表的な3つの原因を整理します。



“いい加減な人”より、“いい加減でも回ってしまう職場”のほうが問題。
引き継ぎトラブルは、仕組みの欠陥が積み重なった結果なんです。
前任者の“引き継ぎ意識の低さ”が最大の原因
最も多いのが、前任者の「引き継ぎは形式的でいい」という思い込みです。
退職や異動が決まると、本人のモチベーションが下がり、
「どうせもう辞めるし」「後任が何とかするだろう」となりがち。
具体的には以下のような行動がよく見られます。
- 手順書や資料を作らず、口頭でざっくり説明して終わる
- 業務の背景や判断基準を伝えず、“作業”だけ引き渡す
- 「分からなかったら聞いて」で責任を放棄する
結果、後任者は表面的な情報だけを頼りに手探り状態に。
これが“引き継ぎ地獄”の始まりです。



引き継ぎって“やる気がない人”ほど丁寧にすべきなんですよ。
でも実際は逆。だからこそ、受ける側が仕組みでカバーするのが大事。


引き継ぎマニュアルが存在しない・更新されていない職場
次に多いのが、会社として引き継ぎの仕組みが整っていないケースです。
特に中小企業やベンチャーでは、業務が属人化しやすく、
「前任者の頭の中にしかない情報」が大量に存在します。
- 過去の担当者の資料が見つからない
- 手順書が古く、現在の運用に合っていない
- 更新ルールがなく、“作りっぱなし”で放置
こうした環境では、どんなに優秀な人でも正確な引き継ぎは不可能です。
つまり「いい加減な引き継ぎ」は、個人ではなく組織の未整備が原因で起きているのです。



僕がいた会社でも“引き継ぎシート”が3年前のまま使われてました。
引き継ぎを“文化”として回す仕組みがないと、誰がやってもぐちゃぐちゃになります。
引き継ぎ期間が短すぎる・人員計画の問題
最後に、人員計画の甘さも大きな原因です。
理想的には「1〜2週間以上の引き継ぎ期間」が必要ですが、
実際は「最終週に数日だけ」「半日でまとめて説明」といったケースが多いのが現実。
- 後任が決まるのが遅く、引き継ぎが一瞬で終わる
- 前任者の退職スケジュールを会社が把握していない
- 業務量が多すぎて、引き継ぎ準備の時間が取れない
これでは、どれだけ優秀な人でも完璧な引き継ぎはできません。
つまり、「時間が足りない構造」こそが、雑な引き継ぎを生む温床なのです。



“時間がない”って、実は最も危険な言い訳。
引き継ぎは“急ぐほどミスが増える仕事”なんです。
いい加減な引き継ぎが引き起こす職場トラブル


「ちょっと聞いてないんですけど…」「そのデータどこにあります?」
いい加減な引き継ぎが行われた職場では、こんな混乱が日常茶飯事になります。
その影響は後任だけでなく、チーム全体・会社全体にまで波及するのです。



“いい加減な引き継ぎ”は一人の問題じゃなく、職場の空気を壊すウイルス。
放置すると、信頼も生産性も一気に崩れていきます。


ミスや二重作業が頻発する
引き継ぎが曖昧なままだと、情報の欠落や誤解が連鎖的にトラブルを生みます。
よくあるのは、こんなパターンです。
- 重要なファイルの保存場所が分からず、再作成して二重工数になる
- 顧客対応の履歴が共有されておらず、同じ説明を繰り返す
- 契約・請求関連の引き継ぎ漏れで、取引先との信頼を損なう
これらは単なる“うっかり”ではなく、引き継ぎ設計の不備による構造的ミス。
特に顧客対応や請求業務のように、後工程が社外とつながる領域では、
一度のミスが信用問題やクレームにつながるリスクが高まります。



僕が前職で見た“引き継ぎ事故”の8割は、
“聞いてなかった”“どこにあるか分からなかった”という情報欠落が原因でした。
紙一枚のメモ不足が、10時間の手戻りを生むこともあるんです。
前任・後任の間に不信感が生まれる
「前任者の説明が雑すぎて、こっちは困ってる」
「後任が自分で調べようとしない」
このように、お互いが“相手が悪い”と思い込み、関係が悪化するのも典型的です。
引き継ぎトラブルの厄介な点は、「悪意がなくても摩擦が生まれる」こと。
どちらも“自分なりに頑張っている”のに、認識のズレが信頼を崩していきます。
不信感が広がると、こんな負のループが起こります:
- 後任が前任を「いい加減」と感じる
- 前任が「後任が理解力ない」と反発
- 周囲の同僚まで「どっちも面倒」と距離を取る
最終的には、チーム全体の協力関係が崩壊してしまうことも。
“仕事の引き継ぎ”が、いつの間にか“人間関係の引き裂き”に変わってしまうのです。



本来、“引き継ぎ”は信頼をつなぐバトン。
それが“責任の押しつけ合い”になると、一気にチームがギスギスします。
チーム全体の生産性とモチベーションが下がる
引き継ぎがぐちゃぐちゃだと、後任者だけでなく周囲のメンバーも巻き込まれます。
- 新人のフォローに時間を取られ、他メンバーの業務が圧迫される
- 手戻り・再確認・修正対応が増えて、全員の残業時間が増える
- 「どうせまた引き継ぎで揉める」と組織にあきらめムードが広がる
このようにして、職場全体のパフォーマンスと士気がじわじわ下がっていくのです。
さらに恐ろしいのは、“優秀な人ほど離れていく”こと。
真面目にカバーしている人ほど負担が集中し、燃え尽きてしまう構造になっています。



“引き継ぎが雑な会社”って、実は離職率が高いんですよ。
優秀な人ほど“また同じ思いはしたくない”と去っていくんです。
いい加減な引き継ぎに遭遇したときの対処法
引き継ぎが雑で、「これ本当に終わってるの?」と感じたとき、
感情的に不安や怒りが込み上げても、まず冷静に“守りの姿勢”を取ることが大切です。
なぜなら、「情報が抜けている」「資料が不十分」といった問題は、
後から“あなたのミス”として扱われるリスクがあるからです。
ここでは、現場で実際に役立つ3つの具体策を紹介します。



“前任が悪い”と嘆くより、“自分の手で整える”。
それが一番早くて、自分を守る一番の方法なんです。


引き継ぎ内容を“自分用マニュアル”として整理する
まずやるべきは、「もらった情報を自分の言葉で再構築する」こと。
どんなに雑な引き継ぎでも、メモやメール、口頭説明の断片から全体像を見える化すれば、
それだけで理解が一段階深まります。
おすすめは以下のような整理法です。
- 業務一覧を作る(担当タスクをすべて書き出す)
- 手順・関係者・期限・参照ファイルをセットでまとめる
- 「不明点」「確認済み」「完了」を色分けして管理する
ExcelやNotion、Googleスプレッドシートなどを使えば、
「自分だけの引き継ぎマニュアル」として再利用もできます。
特に後任がいない場合でも、この作業をしておけば
「どこまで理解していて、どこが不明か」を明確に伝えられ、
上司やチームへの説明責任を果たせます。



僕も引き継ぎ資料が“箇条書き5行だけ”だったことがあります。
でも、それを自分で体系化したら、次の新人にも感謝される“資産”になりました。
不明点は「後で聞ける人」をリスト化しておく
雑な引き継ぎで一番怖いのは、「分からないことがあっても、誰に聞けばいいか分からない」状態。
だからこそ、“質問できるルート”を明確にすることが重要です。
次のように、質問リストと相談先を紐づけておくと混乱を防げます。
| 不明点の内容 | 質問すべき人 | 備考 |
|---|---|---|
| A社の見積書の承認フロー | 元担当の佐藤さん | Slackで連絡OK |
| 月次レポートのテンプレート | 経理の山田さん | Google Driveにあるか要確認 |
| システム操作マニュアル | 情シス担当 | 操作動画があるか確認 |
このように整理しておくことで、
後から「誰も聞いてない」「引き継ぎ済みです」と責められるリスクを回避できます。
また、引き継ぎが終わったあとでも、
“フォロー可能な関係”を残しておくことが重要です。
メール一本で質問できる関係性を築いておくだけで、心理的にも安心感が生まれます。



引き継ぎで一番大事なのは“情報”より“人脈”。
誰に聞けるかを押さえておくだけで、トラブルの9割は回避できますよ。
上司へ「引き継ぎ状況」を共有してリスクを明確化
そして最後に忘れてはいけないのが、上司への報告です。
雑な引き継ぎのまま放置すると、後でミスが起きたときに
「確認しなかったあなたの責任」と扱われるリスクがあります。
そのため、以下のように事実ベースで共有することが大切です。
📩 報告メールの例文
件名:引き継ぎ内容の確認について(進捗共有)
○○課長
お疲れさまです。
○○業務の引き継ぎについて、現時点での確認状況を共有いたします。
- 引き継ぎ資料は一部未整備(特にA・B業務)
- 関係部署への確認が必要な点をリスト化済み
- 現在、担当者の○○さんに追加で確認中
不明点については、来週までに整理して再共有予定です。
よろしくお願いいたします。
こうしたメールを残しておけば、
「引き継ぎが不十分な状態であった」ことを記録として残せるため、
トラブル発生時の防衛線になります。



“引き継ぎが適当でした”って、ちゃんと上司に伝えるのも責任。
黙って背負うより、“問題を共有する勇気”のほうが、評価されるんです。
前任者・後任者どちらが悪い?責任の線引きを考える
「引き継ぎがうまくいかないのは前任者のせい?それとも後任者?」
職場でよくあるこの議論。実は“どちらが悪い”ではなく、“どちらも責任がある”というのが正解です。
引き継ぎとは、単なる“情報の受け渡し”ではなく、“信頼のバトンリレー”。
一方が手を抜けば、どんなに優秀な人でもトラブルは避けられません。



“前任が悪い”って言いたくなる気持ちはわかる。でも、
プロとしては“引き継ぎを成功させる主体は自分”と考えたほうが、結果的に得なんです。
引き継ぎは「渡す側7割・受ける側3割」の共同責任
理想的な引き継ぎの責任割合は、前任者7割・後任者3割です。
理由は単純で、知識・経験・背景情報を持っているのは前任者側だからです。
ただし、後任者にも「聞く責任」があります。
前任者が忙しかったり、曖昧にしている部分を掘り下げるのは、後任者の積極性次第。
たとえば、
- 前任者が曖昧に説明しても、「つまりこの場合は○○ですか?」と確認する
- 期限やルールが不明な点は、その場でメモして後日再確認する
- 「この作業の目的」を聞き出し、背景を理解してから引き継ぐ
こうした
“能動的な聞き取り”があるだけで、引き継ぎの質は2倍以上変わります。



僕は“聞く力”も引き継ぎスキルの一部だと思ってます。
受け取る側が“質問上手”だと、前任者も自然と丁寧になるんですよ。
前任者の“説明不足”を責める前に、聞き方を工夫する
「説明が雑すぎる!」「マニュアルがない!」と感じたとき、
まずやるべきは“どう聞くか”の工夫です。
多くの人は「教えてください」と漠然と聞いてしまい、
前任者も“何をどこまで伝えるか”分からないまま会話が終わります。
おすすめは、“5W1H+目的”で質問すること:
- Who(誰):誰が関わっている仕事?
- What(何):具体的なタスク内容は?
- When(いつ):納期や頻度は?
- Where(どこ):データの保存場所・ツールは?
- How(どうやる):手順や注意点は?
- Why(なぜやる):目的・成果物の背景は?
これを意識すると、前任者も「そういえばこの資料も必要だね」と思い出してくれます。
つまり、質問の質が引き継ぎの深さを決めるのです。



僕も昔、“説明が雑な人”に当たって苦労しました。
でも、“質問リスト”を作って順番に聞くようにしたら、意外とスムーズに回り始めましたよ。
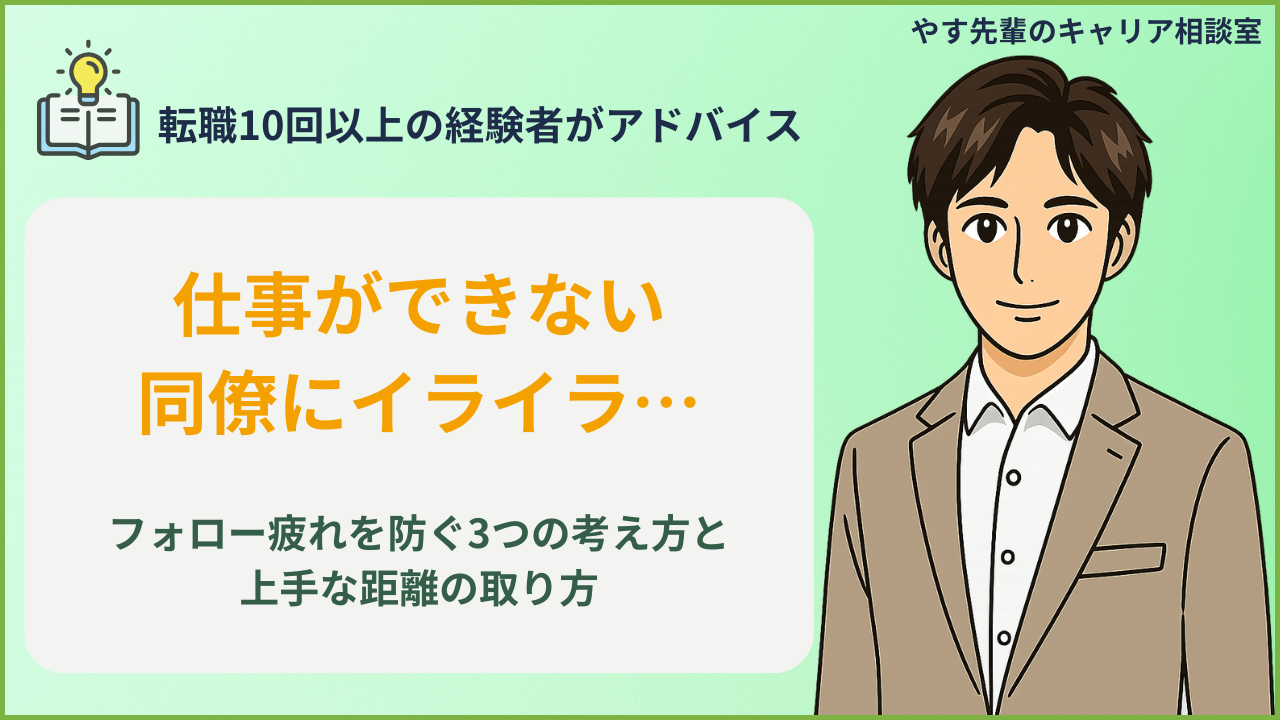
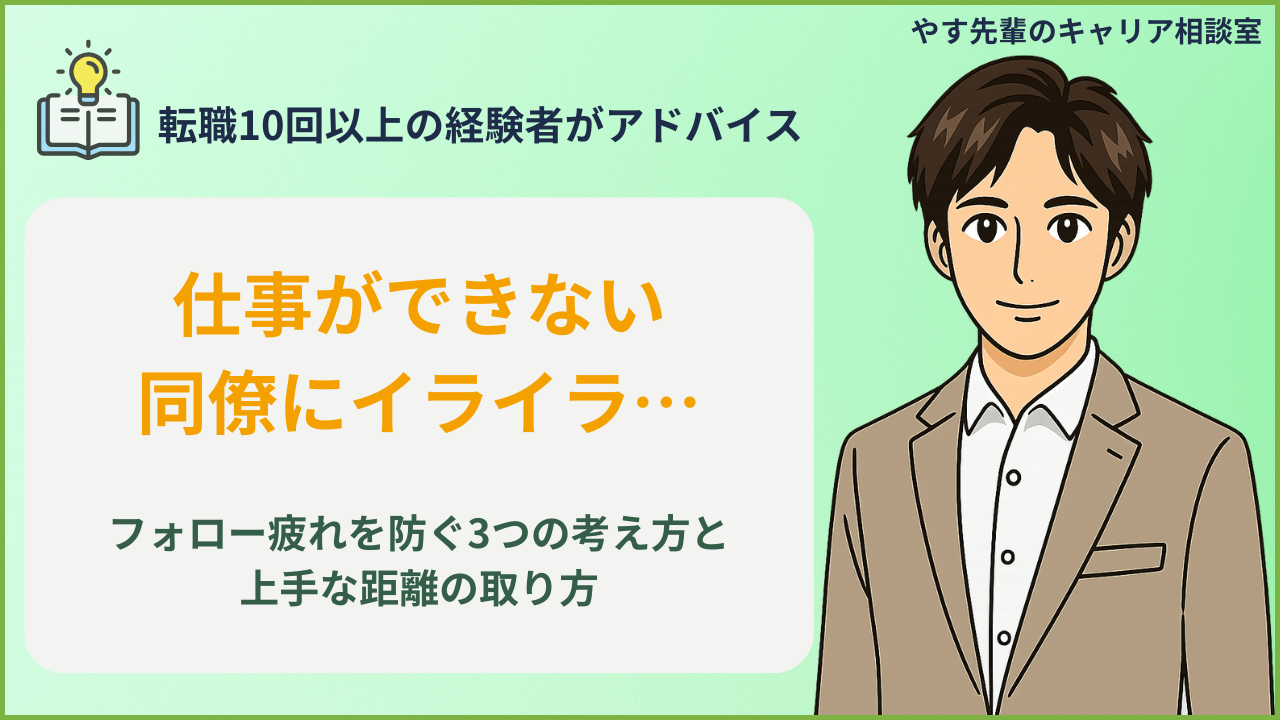
「引き継ぎ不備」を防ぐチェックリスト活用術
引き継ぎトラブルを防ぐ最も確実な方法は、チェックリストで“抜け”を可視化することです。
口頭や感覚的なやり取りでは、必ず漏れが発生します。
以下のようなチェックリストを使えば、どんな現場でも“最低限の品質”を保てます。
| チェック項目 | 状況 | 補足 |
|---|---|---|
| 業務マニュアルが最新版か | □済 / □未 | 日付を必ず記載 |
| 関係者・連絡先リストがあるか | □済 / □未 | Slack・社内電話など |
| データ保存場所が明確か | □済 / □未 | Google Driveなどに統一 |
| 定期業務のスケジュールを共有済みか | □済 / □未 | 月次・週次タスクを明記 |
| 取引先・顧客情報の引き継ぎ完了 | □済 / □未 | 担当・過去対応履歴含む |
| 不明点の問い合わせ先を明示 | □済 / □未 | 上司・前任・他部署など |
このチェックリストを印刷して前任者と一緒に確認すれば、
「聞いた/聞いてない」問題が激減します。
さらに、上司に提出しておけば“引き継ぎの透明性”が確保され、責任の所在も明確になります。



リスト化しておくと、“後で揉めない保険”になります。
会社って、証拠より“見える化”された努力を評価してくれるんですよ。
やす先輩の体験談|ぐちゃぐちゃな引き継ぎから立て直した話
当時の状況:退職者の引き継ぎがほぼ口頭。資料はバラバラ
前職でのことです。急な退職者が出て、僕がその業務を引き継ぐことになりました。
ところが、渡されたのは古いExcelファイルと、数回の口頭説明だけ。
フォルダ構成もぐちゃぐちゃで、どのデータが最新なのかも分からない。
しかも、前任者はすでに有給消化中。
誰に聞いても「○○さんしか分からない」と言われ、まさに情報の迷子状態でした。



“仕事を引き継ぐ”って言葉は聞こえがいいけど、
実際は“前任者の積み残しを整理する作業”なんですよね(笑)。
感じたこと:混乱・残業続き・「なんで自分ばかり」のストレス
最初の1か月は、本当に地獄のようでした。
前任者の意図を読み解くために夜遅くまで資料を漁り、
上司や他部署に確認しても「そこは○○さんの担当だったから…」の繰り返し。
毎晩のように残業が続き、
「なんで自分ばかり苦労しなきゃいけないんだ」とイライラする日々でした。
そんなとき、ふと気づいたんです。
“前任者を責めても、状況は変わらない”と。



ストレスの根本は“責任のなすりつけ合い”。
誰が悪いかより、“何を直せば回るか”を考えたほうが早いんですよ。
行動:タスクを一覧化し、属人業務を見える化
そこで僕は、徹底的に業務を分解・整理することにしました。
まず、「誰が・いつ・何を・どのツールで・何の目的でやっているのか」をすべてリスト化。
不明点は“仮説メモ”として残し、関係者に確認を取りました。
この作業をExcelで進めていくうちに、
- 無駄な二重処理
- 承認フローの重複
- 不要な報告資料
が次々と明らかになっていきました。
結果として、属人化していた仕事がチーム全員で共有できる形になり、
引き継ぎ資料そのものが再現性のある“業務マニュアル”へと進化したのです。



“資料をきれいに整える”って、地味だけど最強の自己防衛です。
誰が見ても分かる状態にしておけば、“自分のせい”にはされません。
結果:チーム全体の効率が改善、上司から信頼を得た
整理を始めてから1か月後、業務の遅延がほぼゼロに。
チーム全体のタスクフローが可視化されたことで、
「これ、次の人にも使えるね」と上司から感謝されました。
さらに、僕が作ったマニュアルが社内テンプレートとして採用され、
「引き継ぎ整備担当」として正式に評価されるようになりました。



“自分が困った経験”を“仕組み化”で解決できたとき、
一気に周囲からの信頼が変わるんですよ。
学び:「怒るより整える」ことが結果的に自分を守る
この経験で学んだのは、
“引き継ぎの雑さ”を嘆くより、“自分で整える力”を磨くほうが建設的ということ。
怒りや不満は一時的にスッキリしても、何も残りません。
でも、整えた仕組みは自分の評価・信頼・再現性として確実に積み上がります。



“怒るより整える”。
これは僕の社会人キャリアで、最も役立っている鉄則の一つです。
引き継ぎストレスで限界を感じたら環境を変える選択も
「引き継ぎ地獄」は努力では解決できない職場もある
どれだけ真面目に向き合っても、
「構造的に引き継ぎが回らない職場」というのは存在します。
たとえば、
- 常に人手不足で、前任者がギリギリまで働き続けている
- 業務マニュアルや共有ツールが一切整備されていない
- 「新人だから我慢して」と精神論で押し切られる
こうした環境では、努力や根性ではどうにもなりません。
むしろ、“頑張る人ほどキャパオーバーに陥る”悪循環に陥ります。
自分を責める前に、
「この職場で成長できるか?」「自分を大切にできるか?」を冷静に考えることが大切です。



“逃げたら負け”じゃなくて、“自分を守る勇気”こそ社会人の戦略。
無理な引き継ぎ体制を変えるより、自分の環境を変えたほうが早いですよ。
ミイダスで市場価値診断→“転職すべきか”の判断材料に
「辞めたいけど、本当に辞めていいのか?」
そう迷っている人には、ミイダス市場価値診断が最初の一歩になります。
ミイダスでは、あなたの職務経歴・スキル・強みを入力するだけで、
以下のような“可視化データ”が得られます。
- あなたの想定年収レンジ
- スキル偏差値・強み分析(コンピテンシー診断)
- 同じ経歴の人がどんな業界・職種で活躍しているか
これを見るだけで、
「自分の市場価値は思ったより高い」「転職しても通用するかも」
という判断の根拠が手に入ります。



僕も引き継ぎ地獄の時、ミイダスで“自分の価値”を数値で見て救われました。
まずは“冷静に比較する材料”を持つのが先です。
ビズリーチ/マイナビジョブ20’s/トリケシで次のステージへ
もし「もう限界」「この環境では成長できない」と感じたなら、
次の行動に移すタイミングです。
目的別に見ると、転職支援サービスはこう使い分けられます。
| サービス名 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| ビズリーチ | ハイクラス転職。年収アップ・マネジメント職も豊富 | キャリアアップを狙いたい中堅層 |
| マイナビジョブ20’s | 20代向けサポート型。未経験転職・第二新卒に強い | はじめての転職・若手社員 |
| 退職代行サービス「トリケシ」 | 弁護士監修の退職代行サービス。最短即日で退職可能 | 今すぐ職場を離れたい人 |
「体調が限界」「もう出社が怖い」という人は、
まずトリケシで安全に抜け出す。
そのあと、ビズリーチやマイナビジョブ20’sで
「次はどんな環境なら自分が輝けるか」を探していきましょう。



“逃げる”じゃなくて、“戦略的に離れる”。
自分の時間とメンタルを守ることが、次のキャリアの第一歩です。
まとめ|いい加減な引き継ぎに振り回されない働き方を
いい加減な引き継ぎに直面したとき、多くの人が「自分の理解力が足りないのでは?」と責めてしまいます。
でも実際は、それは“あなたの責任”ではなく、“仕組みの問題”です。
前任者がマニュアルを残さなかった、
上司が引き継ぎ期間を設けなかった、
チームで業務の可視化が進んでいなかった、
そのすべては組織としての課題です。
だからこそ、焦って完璧を目指す必要はありません。
あなたができるのは、「怒るより整える」姿勢を持ち続けること。
少しずつタスクを見える化し、
分からないことを整理し、
引き継ぎフローを“再現できる形”に整える。
この積み重ねが、上司や同僚からの信頼につながります。



僕も昔、“前任者がズボラだった”と嘆いてばかりでした。
でも、整える努力を見てくれる人は必ずいます。
“雑な環境で整えられる人”こそ、次の職場で一目置かれる存在になります。
そして、もし本当に限界を感じたら、
「環境を変える勇気」も大切です。
頑張る場所を間違えれば、どんなに努力しても報われません。
逆に、仕組みが整った環境に身を置けば、
あなたの“整える力”は大きな武器になります。
👉 次のキャリアを見据えるなら
- ミイダス市場価値診断で市場価値を客観的に確認
- ビズリーチで仕組みが整った職場へステップアップ
- マイナビジョブ20’sで丁寧にサポートしてくれる会社を探す
- 退職代行サービス「トリケシ」で“今すぐ抜け出す”選択もOK
「環境を変える=逃げる」ではなく、
“自分を守るための次の一手”です。
いい加減な引き継ぎに振り回されず、
“自分を主語にした働き方”を選びましょう。
よくある質問
- 前任者の引き継ぎがずさんすぎて困っています。どうすれば?
-
まずは「怒り」より「整理」を優先しましょう。
引き継ぎ内容をタスクごとに分解し、“自分用のマニュアル”としてまとめることで混乱を最小化できます。
不明点は「あとで誰に聞けるか」をリスト化しておくと、問い合わせの負担も減ります。 - 引き継ぎを受けたのに全然わからない…やめてもいい?
-
何も整っていない状態で丸投げされるのは、あなたの責任ではありません。
“放置型の引き継ぎ地獄”は努力でどうにもならないケースも多いです。
体調を崩すほど追い込まれる前に、上司や人事に報告+ミイダス市場価値診断をしてみましょう。
「今の職場にしがみつくべきか」の判断材料になります。 - 上司がフォローしてくれない場合は?
-
上司に「困ってます」と抽象的に伝えても動きません。
“具体的な課題+対応策案”をセットで報告すると、動いてもらいやすくなります。
(例:「A業務の手順が分からず滞留しているので、関係者と30分確認時間をもらえますか?」) - 後任が仕事を覚えられずストレスです。責任を感じます。
-
後任の成長スピードは人それぞれ。
あなたが丁寧に引き継いでも、相手の理解度や意欲に左右される部分があります。
責任を感じすぎず、「マニュアル化」「確認タイミングの設定」など、
再現性を重視した仕組みでサポートするのが最善策です。 - 引き継ぎトラブルを防ぐコツは?
-
ポイントは3つです。
- “口頭説明だけ”にしない(必ず資料・メモを残す)
- “いつ・誰が・どこまで完了したか”を明文化
- “次の担当者が見て分かる状態”で終える
これだけでトラブルの8割は防げます。