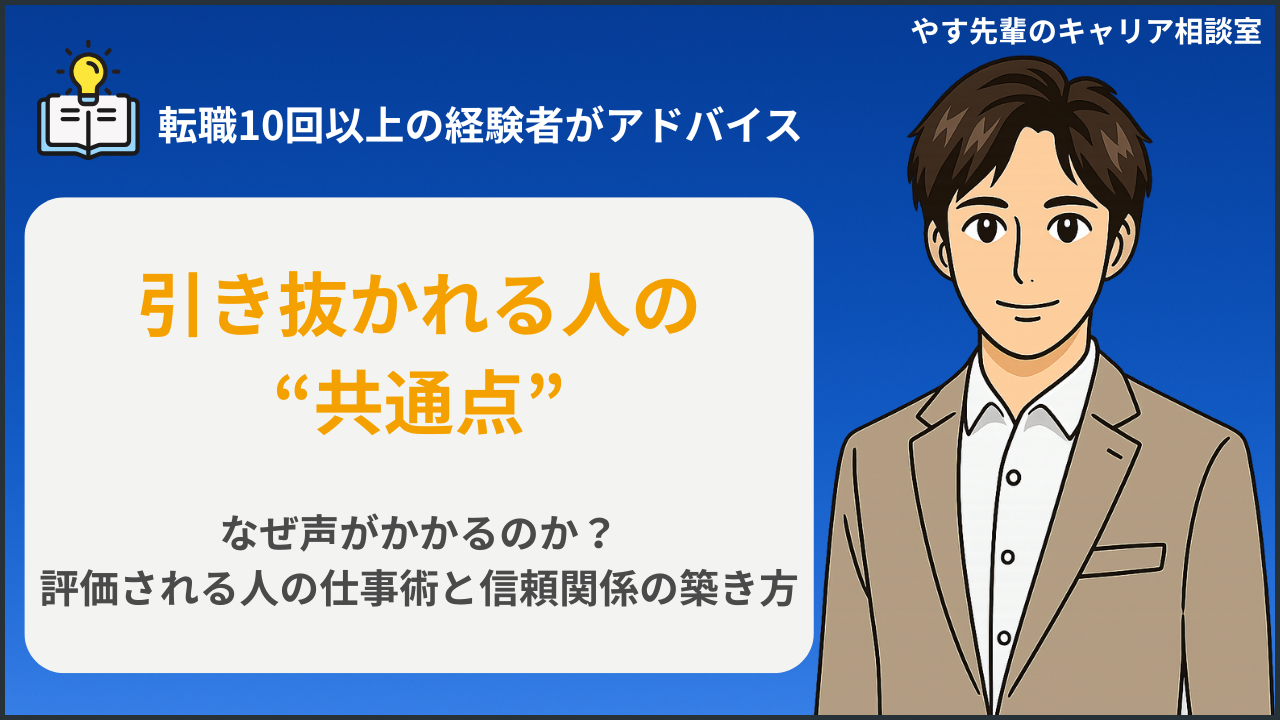やす先輩
やす先輩40代半ば、転職10回の管理職。上場もベンチャーもブラックも経験してきました。失敗も学びも交えながら、キャリアや働き方に悩むあなたへ“現実的な解決策”を届けます。
⇒詳しいプロフィール
「なぜ、あの人ばかり引き抜かれるんだろう?」
同じ職場で、同じように働いているはずなのに、なぜか“声がかかる人”と“かからない人”がいる。
その違いに、モヤっとしたことはありませんか?
実は、引き抜きたい人材にははっきりした共通点と行動パターンがあります。
それは単に「成果を出している人」ではありません。
・任せても再現性がある
・周囲から信頼されている
・一緒に働く姿がイメージできる
こうした“一緒に働きたい要素”を持っている人が、社内外から自然と声をかけられていくのです。
この記事では、
・引き抜きたい人材に共通する特徴と考え方
・社内スカウト・転職で声がかかる人の行動習慣
・「なぜ自分には声がかからないのか」の見極め方
を、現場視点でわかりやすく解説します。
もし今、
「自分の市場価値って、実際どれくらいなんだろう?」
と少しでも気になったなら、一度“外からの評価”を確認してみてください。
ミイダスを使えば、あなたのスキル・経験がどんな企業から、どんな条件で評価されるのかが見えてきます。
“引き抜かれる人”になる第一歩は、まず自分の立ち位置を知ることから始まります。
引き抜きたい人材の特徴とは?
「成果が出せる」だけでは、引き抜きスカウトの対象にはなりません。
“どこでも再現できるやり方”ד周囲からの信頼”ד合理的な判断”。この三拍子が揃った人が、社内引き抜き・ヘッドハンティングの両方で真っ先に声がかかります。
成果だけでなく“再現性”を持っている人
単発のヒットではなく、プロセスを言語化して誰にでも回せる仕組みにしている人。
引き抜きたい人材の特徴は、「やったらまた同じ結果が出せる」を周囲に確信させることです。
再現性を示す材料
- Before/AfterのKPIと、打ち手→因果→結果のひも付け
- 施策テンプレ(チェックリスト、手順書、FAQ)
- 失敗事例とリカバリーの型(リスク前提の設計)
今すぐできる行動
- 月1で「やり方のドキュメント」を10分だけ更新
- ダッシュボードに“見れば分かる”注釈(定義・更新頻度)を追記
- 成果報告は3行(課題/打ち手/結果)で統一



引き抜き スカウトは“再現できる仕組み”に寄ってきます。
天才より、仕組み化の職人が一番モテる。
信頼残高が高く、他部署からも頼られる
“信頼残高”とは、約束の履行×期待以上の返し×誠実な対応の積み上げ。
他部署が「あの人に聞けば早い」と感じている人は、社内引き抜き・他部署スカウトの第一候補です。
信頼残高が見える行動
- 依頼の期限・成果物・判断基準を一度で確認(往復を減らす)
- 断る時は代替案・紹介・再提案時期をセットで返す
- 会議後のフォロー要約(決定/担当/期日)を即送付
“頼られる人”になるミニ習慣
- 相談に15分の枠を置く(長引かせず、次の一歩を決める)
- 自分の専門外は最適な人へ橋渡し(信用のハブになる)



信頼って、“すぐ動く・はっきり決める・丁寧に返す”の3点セット。
これがある人は、部署を超えて引き抜かれる。
「報・連・相」の質が高く、上司から安心されている
引き抜きたい人材の共通点は、情報の粒度とタイミングが適切。
上司やステークホルダーが“この人なら任せて大丈夫”と確信できるレベルでコミュニケーションします。
質の高い報連相テンプレ
- 報告:事実→解釈→提案(3点セット/300字以内)
- 連絡:リスクは確率×影響×対策で即時共有
- 相談:選択肢A/B/C+推し案+必要資源
悪手になりがちな例
- 事実だけ羅列(解釈・提案がない)
- リスクの事後報告(“起きた後に”上げる)
- 相談の丸投げ(「どうしましょう?」で止まる)



上司が欲しいのは“情報”じゃなく判断の助け。
‘報・連・相’は意思決定の燃料にするのが正解。
他人の成功を喜べる「協働型リーダー」
ヘッドハンティングの現場では、自分が主役でなくても成果が出せる人が評価されます。
個の凄さより、チーム総量を底上げする力が重視されるからです。
協働型リーダーのふるまい
- 成果のクレジットをメンバー名で明記
- 仕組みやナレッジを他チームにも展開
- 会議で他者の発言機会を作る(指名・補助質問)
評価される“巻き込み”の型
- 「あなたの強み×この案件の要所」を具体に言語化
- 合意形成は小さなYesを積み上げる(段階的合意)



“自分の点”じゃなく“チームの面”で勝たせる人は、
どの組織でも不足してる。だから引き抜かれる。
感情で動かず、合理的に判断できる冷静さ
スカウト/ヘッドハンティングでは、難局での意思決定が問われます。
感情に飲まれず、目的→選択肢→条件→決定の順で動ける人は、引き抜きたい人材のど真ん中。
合理的判断のチェックリスト
- 目的(何を達成するか)を一文で言える
- 代替案を最低2つ並べ、トレードオフを明示
- 決めた後にやめるべきことを必ず決める
日常で鍛えるコツ
- 週1で「やらないリスト」を更新(負債を増やさない)
- 会議は“仮説歓迎・反対OK”を冒頭に宣言→決め切る



“熱量”は大事。でも、最後に組織が欲しいのは勝てる判断。
冷静さは、引き抜き スカウトの最大の評価軸です。
社内引き抜き・スカウトされる人の共通点
社内で「引き抜かれる人」には、明確な共通点があります。
それは“目立つ人”ではなく、“信頼されている人”。
実は、社内引き抜きや他部署スカウトは、成果よりも人間的な信頼と一緒に働きたい空気感で決まることが多いのです。
「自分の強み」を周囲に伝える力がある
どんなに能力が高くても、「何が得意なのか」が伝わっていなければ、声はかかりません。
社内スカウトされる人は、自分の強みをさりげなく可視化しています。
“強みを伝える人”がやっていること
- Slack・社内SNSで成果を共有する時、数字+自分の得意分野を一文添える
例:「今回の改善は、データ分析と設計調整を掛け合わせて実施しました」 - 社内MTGで「得意分野の質問」を歓迎する姿勢を見せる
- 周囲の相談に対して「それ、自分がやったことあるよ」と体験ベースで返す
一方で、謙遜が過ぎる人ほど、チャンスを逃します。
自己主張ではなく、“再現できる強み”を自然体で表現できる人が、社内で一目置かれます。



“黙ってても見てくれる”は幻想。
“自然に伝わる仕組み”を持ってる人が、引き抜かれる。
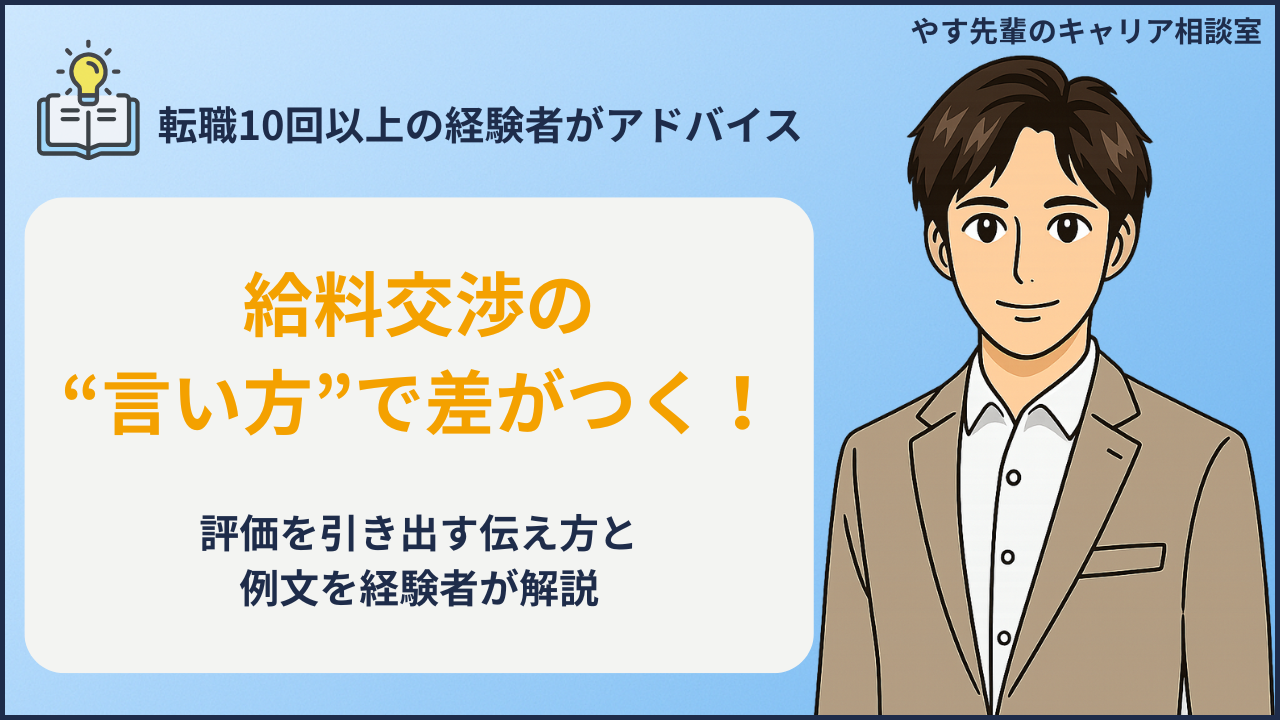
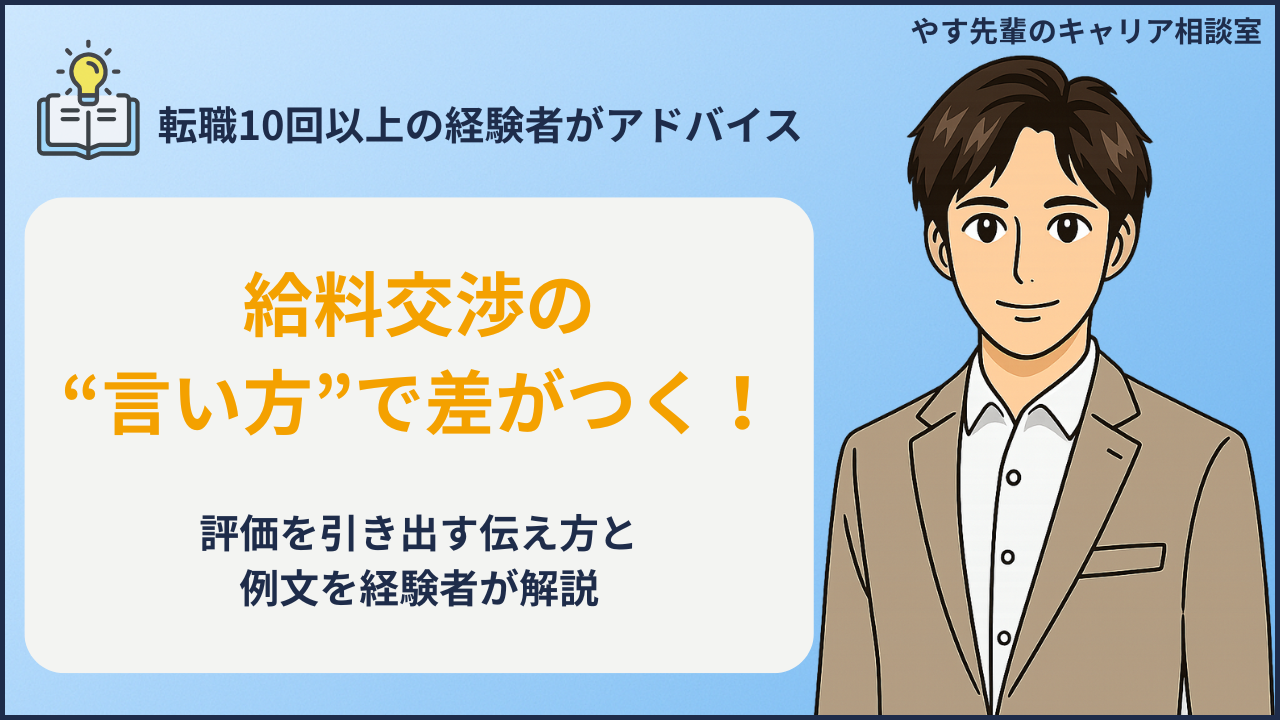
他部署との関係構築が早い(雑談・相談・連携が自然)
引き抜きが起きるのは、「この人と一緒に働きたい」という感情が先。
だからこそ、社内で“関係構築の早い人”は、最もスカウトされやすいです。
関係構築が早い人の特徴
- 会議やチャットで他部署の話題に共感・質問・感謝を自然に返す
- 雑談で相手の仕事領域に興味を持つ(「それ、どうやって進めてるんですか?」)
- 「困ったら○○さんに相談しよう」と相手の頭に残る接点をつくる
この「雑談力」と「共感力」は、“引き抜きの布石”です。
なぜなら、スカウトする側は「成果」よりも、空気感が合うかで判断しているからです。



“成果”でなく“印象”が先に残る。
だから、話しかけやすい人が最強の引き抜き候補になる。
どんな上司とも“うまく働ける人”
社内スカウトの際に意外と重視されるのが、上司適応力。
「この人ならどんな上司のもとでも成果を出せそう」と思われる人ほど、安心して声をかけられます。
上司との関係をうまく築ける人の行動
- 指示待ちせず、上司の“目的”を読んで先回り
- 意見が違っても、まず「理解→代案」の順で返す
- 感情的な対立を避け、合理的な会話で意見交換できる
一方で、「上司にだけ反抗的」「合う人としか仕事しない」というタイプは、
どれだけ有能でも他部署スカウトの対象から外れる。
スカウトする側が求めているのは、「スキルよりも扱いやすさ」「協調して動ける安心感」なのです。



上司を選ばない人は、どの組織でも引っ張られる。
スキルより、“やりやすい人”が最強なんですよ。
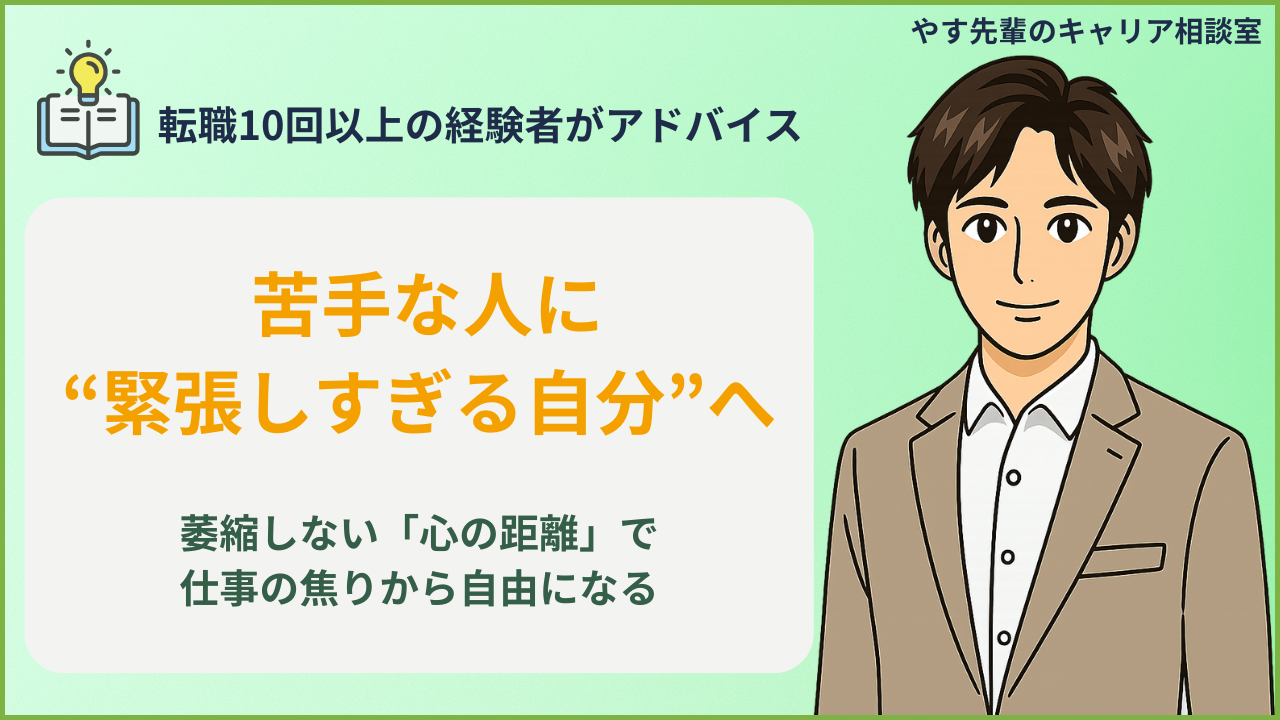
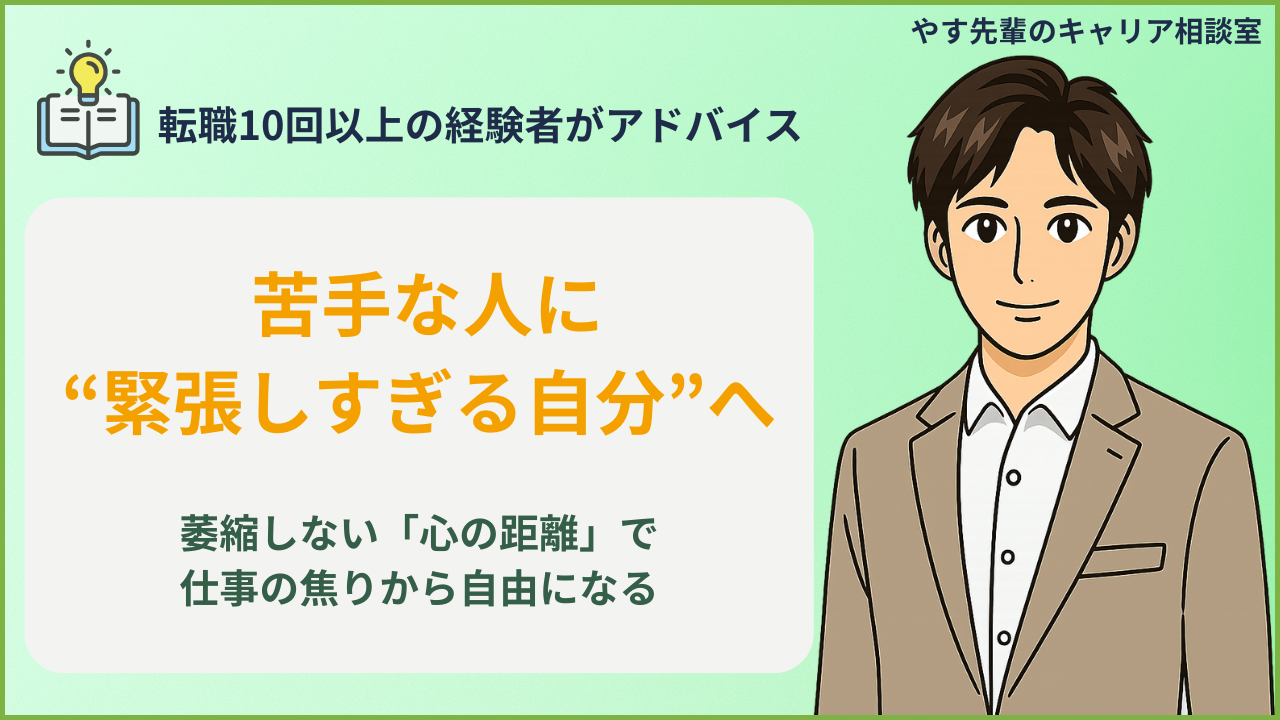
自分の役割を越えて、組織の成果を優先できる
スカウトされる人の最大の共通点は、“自分の仕事を超えて動く視点”を持っていること。
「自分のKPI」よりも「チームや部署全体の成果」を優先できる人にこそ、他部署は価値を感じます。
引き抜かれる人の行動例
- 他部署の課題を“自分ごと”として考え、アドバイスや支援を惜しまない
- トラブル時に「それ、うちでも手伝えます」と声をかける
- 成果報告に“チーム全体の成功”を含めて発信する
こうした人は、単なる優秀な社員ではなく、組織全体を動かす存在として認識されます。
結果的に「この人を自分の部署に迎えたい」という引き抜きが自然と起こるのです。



“うちの利益”より“会社全体の成果”を考えられる人。
そんな人がいれば、誰だって一緒に働きたくなる。
引き抜かれる人・される人の心理とリスク
“声がかかる”のは悪いことではありません。むしろ評価の証。
ただし、舞い上がり→即決→ミスマッチの流れで「引き抜き 後悔」に陥るケースも少なくありません。
ここでは「引き抜き される 人は どんな 特徴」かに触れつつ、心理の落とし穴と回避策を整理します。
引き抜き転職で“後悔”する人の共通点
よくある後悔のパターン
- 条件先行:年収や肩書に目がくらみ、役割の中身・上司の質・裁量を確認しない
- 期待ギャップ:オファー時の言葉と実務の乖離(権限が想定より狭い/評価基準が曖昧)
- 関係未設計:最初の90日で信頼を作れず、“外様扱い”のまま孤立
- 成果の再現性不足:前職の勝ちパターンが新環境で通じず、立ち上がりに失敗
回避チェック(面談前に3分)
- 役割の成功定義:30/60/90日で何を達成すれば合格か?
- 権限と境界:何が自分で決められて、どこから決裁が必要?
- 評価の設計:成果:挑戦:協働=何対何?(例:60:30:10)
- 成功に必要な仲間:初月から協力してくれる人の名前を聞く



“年収が上がる=幸せ”じゃない。
役割×上司×裁量が噛み合わないと、転職のコスパは一気に下がります。


社内引き抜きと転職スカウトの違い
社内引き抜き(他部署スカウト)のリアル
- メリット:文化ギャップが小さい/立ち上がりが速い/既存の信頼資産を活用できる
- リスク:前部署との温度差・嫉妬/「あの人は引き抜きで来た」のレッテル
転職スカウト(社外)のリアル
- メリット:年収・裁量の非連続ジャンプ/市場視点でスキルが磨かれる
- リスク:オンボーディング難度が高い/評価体系・意思決定速度の見極めコスト
判断軸(どちらも検討して良い)
- 成長総量:役割の広がり/上司の質/勝てる市場/学習投資
- 安全余白:立ち上がり90日の支援(リソース・メンター・権限移譲の計画)
- 文化適合:反対意見の扱い、失敗の学習化、会議の決め方



“社内異動 引き抜き”は低リスク高回転、“社外スカウト”は高リターン高難度。どちらも自分の勝ち筋で選ぶのがコツ。
引き抜かれた後のトラブル・人間関係リスク
起こりがちなトラブル
- 元部署との摩擦:引き継ぎの不満/“抜かれた側”のわだかまり
- 情報境界:機密・顧客情報の扱い(NDA・競業避止義務の誤解)
- 役割錯覚:期待値のズレ(「即戦力=全部できる」認知)
先回りの処方箋
- 引き継ぎ台帳を作る(案件・権限・期限・後任・リスク)
- 退職・異動時のコミュニケーションスクリプトを用意
- 感謝 → 学び → 残す資産(ドキュメント場所) → 今後の連絡窓口
- 機密ラインは就業規則・契約を再確認(不明点は人事・法務へ)※法的判断は専門家へ
人間関係のケア
- 元上司・同僚へワンクッションの1on1(5〜10分でOK)
- 新部署では“期待値の明文化”を主導(成功定義・期限・支援者)



“引き抜き トラブル”の多くは説明不足。
台帳と一言の感謝で、9割の摩擦は回避できます。
“声がかかった時こそ”冷静な判断を
引き抜き 転職 迷いは自然。舞い上がり→即断を避け、
事実・比較・時間の3点で冷静さを取り戻しましょう。
意思決定のフレーム
- 事実:現職とオファーを同じ軸で記述(役割・上司・裁量・評価・年収・働き方)
- 比較:3年スパンでの成長総量を見積もる(経験値・人脈・市場性)
- 時間:24〜48時間の“考えるバッファ”を取る(即答しない)
逆質問テンプレ
- 「最初の90日で合格とみなす成果は何ですか?」
- 「意思決定の最短経路を教えてください(誰がどこで決める?)」
- 「過去1年の失敗事例と、その扱いを教えてください」
決めた後にやること
- 30/60/90日プランの仮説資料を作る(初日から合意形成)
- 現職には感謝→学び→貢献の棚卸しを伝えて退路をきれいに



オファーは“褒め”じゃなく宿題。
冷静に解いて、自分の勝ち筋に合うなら初めて受けよう。
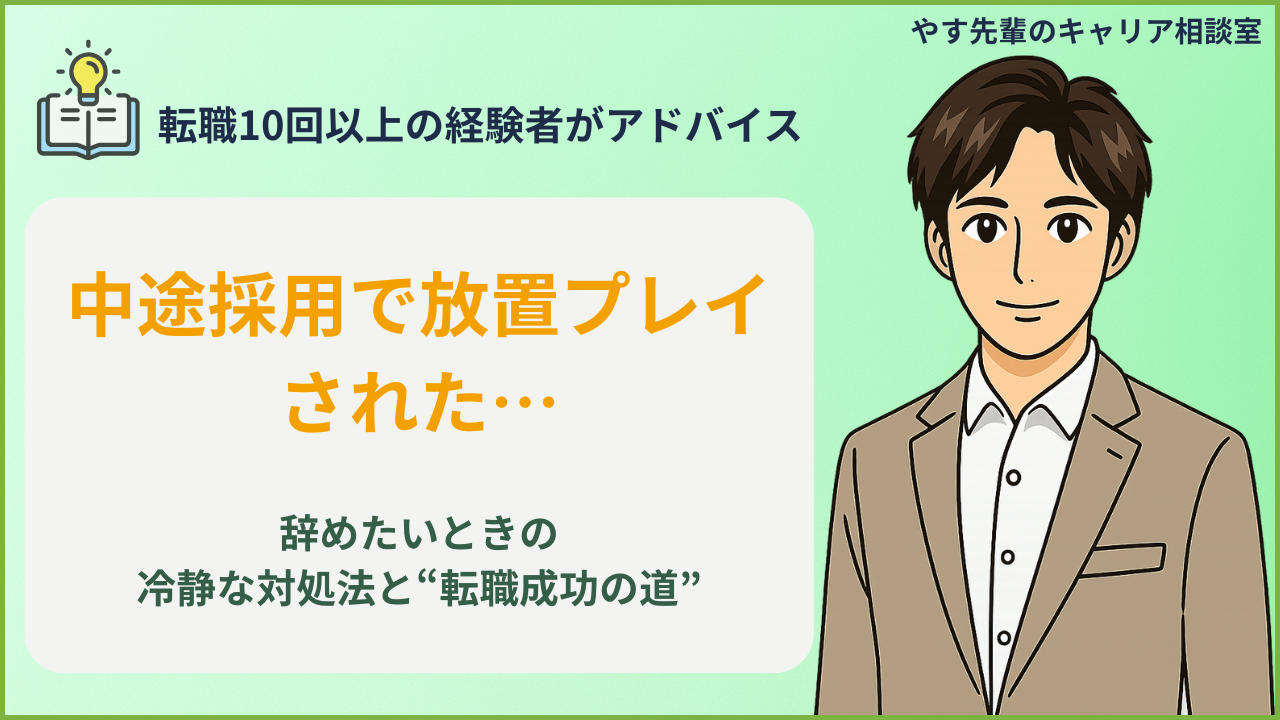
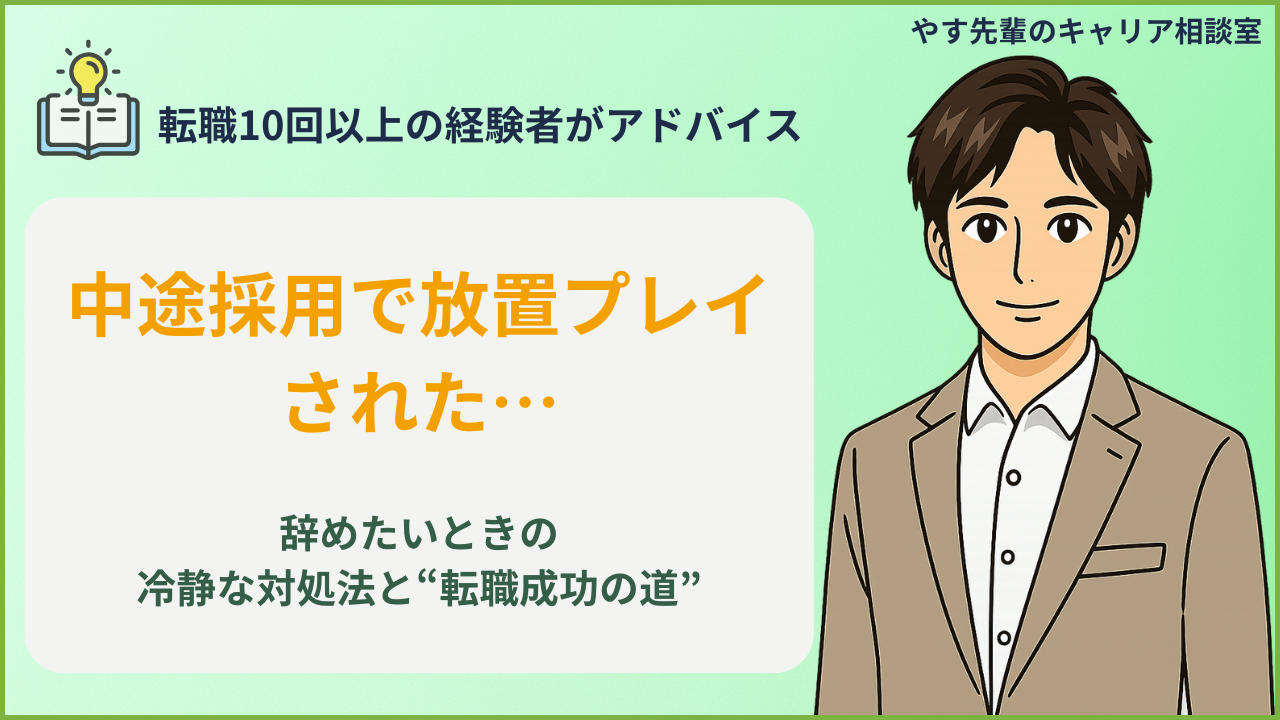
引き抜き・スカウト時の注意点と法律リスク
「引き抜き」と聞くと、どこかグレーな響きがあります。
しかし、実際にはすべての引き抜きが違法なわけではありません。
問題は、“どんなやり方で” “どんな情報を持ち出したか”。
ここでは、スカウト・ヘッドハンティングの正しい理解と、トラブルを防ぐための実務ポイントを整理します。
引き抜きとヘッドハンティングの“定義と違い”
まず、混同されがちな「引き抜き」と「ヘッドハンティング」は、アプローチの主体と目的が異なります。
| 項目 | 引き抜き | ヘッドハンティング |
|---|---|---|
| 主体 | 元同僚・上司・知人など、個人ルート | 専門のヘッドハンター・企業の人事 |
| 接点 | 元職場・同業・顧客関係など | 職務経歴書・スカウトなど |
| 目的 | 即戦力の確保・チーム再編 | 高難度ポジションのピンポイント採用 |
| リスク | 元会社との関係悪化・情報流出リスク | 契約やコンプライアンス管理が明確 |
つまり、
引き抜き=個人レベルのスカウト、
ヘッドハンティング=企業・エージェント主導の正式アプローチ。



“誘われた=悪”じゃない。
大事なのは、誰がどう誘ったか、何を持ち出したか。
境界を理解していれば、堂々とキャリアを選べる。
引き抜きが“違法”になるケース(競業避止・秘密保持)
法律上、転職や引き抜き自体は原則自由(職業選択の自由)が守られています。
しかし、次のような行為を伴うと「不正競争防止法」「労働契約法」などに抵触する可能性があります。
違法になるおそれがある行為
- 在職中に他社員へ転職を勧誘(営業妨害・就業義務違反に該当)
- 顧客リストや取引価格など営業秘密の持ち出し
- 競業避止義務契約を無視して同業他社へ転職
- 秘密保持契約(NDA)に反する情報の共有
注意すべきポイント
- 競業避止義務は「職種・期間・地域・対価」が明示されていないと無効になるケースもある
- 転職先に「前職情報の利用禁止」を明文化しておくとトラブル防止に有効
- スカウト側(誘う側)も、“現職の業務時間中”の勧誘は避ける



“知ってる人を誘う”ときほど慎重に。
法律よりも、信頼を失うリスクの方が大きい。
「引き抜き バレる」リスクを最小化する行動
引き抜き転職で最も多いのが、情報伝達のタイミングミスによる誤解・炎上。
悪意がなくても、「バレ方」が悪いと関係を壊します。
バレる典型パターン
- 転職先がリリースで人事発表を早めに公開
- SNSやLinkedInで近況投稿をしてしまう
- 同僚への相談が噂になり、上層部に伝わる
リスクを減らす3ステップ
- オファー確定前には誰にも話さない(社内外問わず)
- 退職意思は直属上司→人事→関係部署の順で伝える
- 発表のタイミングを転職先とすり合わせる(入社2〜3日前が理想)
補足:在職中のやり取りで注意すべき点
- メール・Slack・Teamsなど社内システムで転職関連の話はNG
- 社外とのやりとりは個人アカウント+私物端末を使う
- 転職先とのやり取り内容はログ保全しておくと安心(トラブル防止用)



“バレる”のは悪いことじゃなく、“バレ方”が悪いと炎上する。
静かに動く力=社会人の知性です。
円満退職と再出発のマナー
引き抜き転職で最も評価されるのは、去り方の美しさ。
どれだけ有能でも、最後の印象が悪ければ、その後のキャリアに響きます。
円満退職の基本ステップ
- 1ヶ月前には上司へ口頭で相談(書面より前に“予告”を)
- 引き継ぎ資料を構造化(プロジェクト別・連絡先・期限)
- 最終出社日までの“貢献期間”を意識(手を抜かない)
- 感謝+学び+次の目標を伝えて締める
再出発のマナー
- SNSで現職批判は絶対NG(業界評判に直結)
- 前職メンバーとは感謝ベースで繋がりを維持
- 「戻れる関係」を残しておく(実際、出戻り成功は増加中)



辞め方が次のチャンスを作る。
僕は“円満退職=最大のブランディング”だと思ってる。
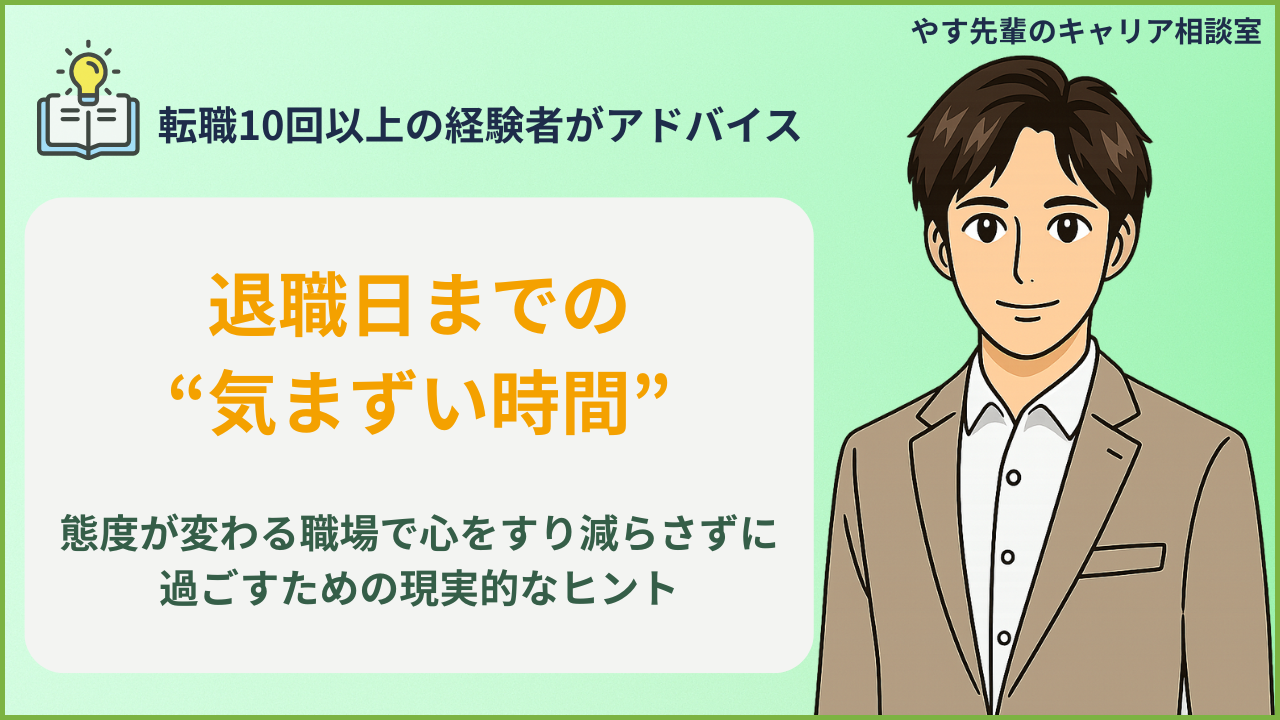
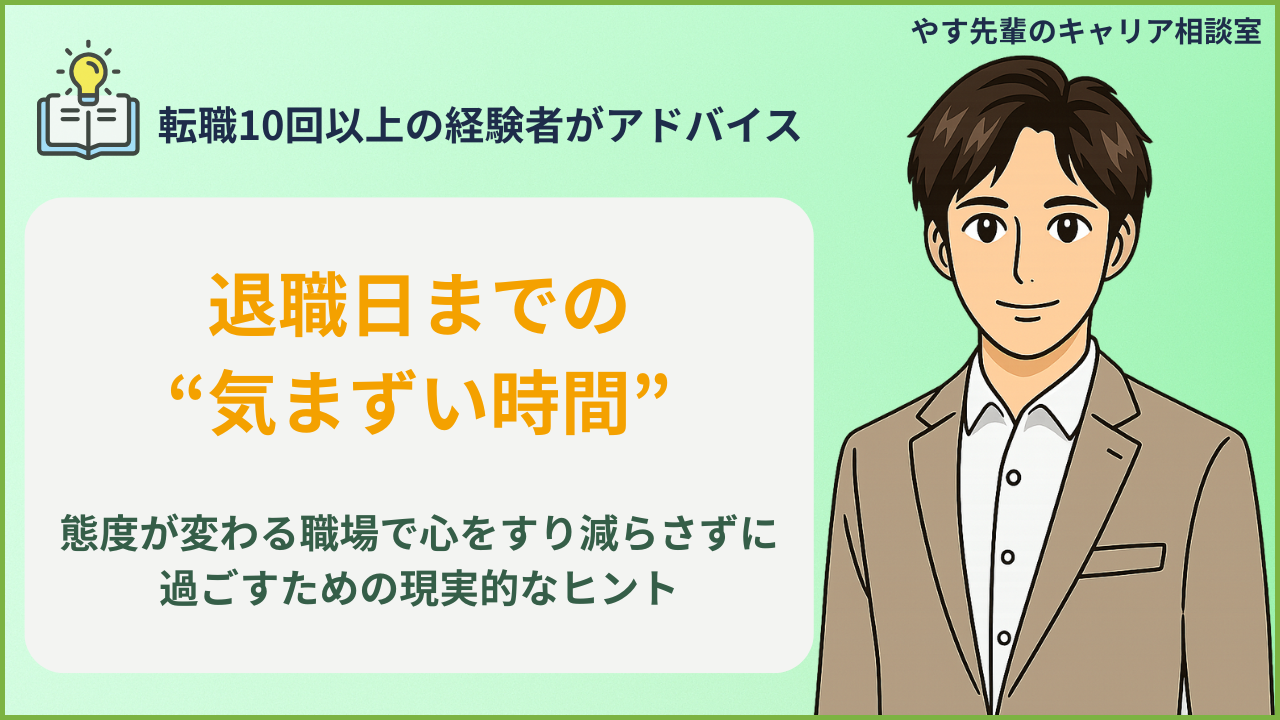
やす先輩の体験談|スカウトされた部下の決断と、僕の本音
当時の状況:他社からスカウトを受けた部下が突然の相談
数年前、僕のチームにいた若手の部下が、ある日こう切り出しました。
「やす先輩、実は他社からスカウトの話があって……」
その子は社内でも特に成長が早く、僕が次のリーダーに育てようと思っていた存在でした。
正直、青天の霹靂。
彼女は淡々としていましたが、その奥に「決意」が見えた瞬間、
ああ、これは本気なんだなと悟りました。
そのとき頭をよぎったのは、「なぜ相談の前に決めたんだ?」という焦り。
けれどすぐに思い直しました。
スカウトされるほどの人材に育ったこと自体が、僕のチームの誇りだと。



“抜かれる側”になるほどの人材を育てられたなら、それはマネージャーとしての成功でもある。
感じたこと:嫉妬と誇らしさが入り混じった瞬間
正直に言えば、嫉妬もありました。
自分の手で育てた部下が、他社に評価されるというのは、うれしさと寂しさが同時に来るんです。
心のどこかで「自分がもっと環境を整えてあげられたら」とも思いました。
でも、彼女の目を見た瞬間、
その表情には「今のままでは成長が止まる」という危機感があった。
僕はその覚悟を、上司として応援すべきだと感じました。
“嫉妬”は一瞬、“誇らしさ”は一生。
そう思うようになったのは、この出来事があったからです。



優秀な部下が辞めるとき、心がざわつくのは当然。
でも、“その成長を支えたのは自分”と誇れる上司になれたら、それでいい。
行動:引き止めず、本人のキャリアを最優先に支援
僕はその場で「無理に引き止めない」と決めました。
転職の理由を聞くと、「もっと裁量を持ちたい」「新しい環境で挑戦したい」とのこと。
ならば、自分が壁になるより、背中を押す側に回ろうと。
具体的には、
- 面接でアピールできる強みを一緒に棚卸し
- スキルや成果の“可視化シート”を作成(次職に活かせる形で)
- 最終日まで通常通りタスクを任せ、「送り出す空気」をチーム全体で作った
社内では「あんなに優秀な人をなぜ止めないのか」と言われました。
でも僕は、「辞める瞬間こそ、その人への最後の教育」だと思っていました。



引き止めより“送り出し方”が人を育てる。
次の環境で活躍してこそ、上司としての仕事は完結する。
結果:その部下は新天地で活躍し、数年後に出戻り
その後、彼女は転職先で見事に結果を出しました。
業界は違えど、持ち前の分析力と粘り強さで成果を上げ、2年後にはマネージャーに昇進。
そしてある日、SlackのDMに一通のメッセージが。
「やす先輩、実はまた一緒に働きたいと思ってます。」
まさかの出戻りオファー。
それも、彼女の方から。
驚いたと同時に、少し泣きそうになりました。
“辞める=終わり”じゃなかった。
関係の質さえ保てば、人はいつでも戻ってくる。
そう実感した瞬間でした。



信頼で繋がった人は、時間を置いても戻ってくる。
だから、最後まで誠実でいることが一番の投資なんです。
学び:「辞める=終わり」ではなく、「信頼関係の形を変える」ことが大切
この経験を通して学んだのは、
「辞める」という出来事は、関係を断つことではなく、形を変えることだということ。
- その人が去る理由を“裏切り”ではなく、“成長”として受け止める
- 最後まで誠実に関わることで、信頼は残り続ける
- 人材流動の時代において、「去る=負け」ではなく、「再会の伏線」にできる
実際、今の職場でも「辞めた人がまた戻ってくる」ケースは珍しくありません。
“辞める瞬間の対応”が、その後の関係性を決めるんです。



辞める人を責めない。むしろ、“また一緒に働ける日を楽しみにしてる”と言える上司でいたい。
それが僕の中での“プロの送り出し方”です。
引き抜かれる人になるための自己成長アクション
「引き抜かれる人」は、偶然選ばれるわけではありません。
彼らは日常の中で“声がかかる準備”をしている。
つまり、成果を出せる仕組み・信頼される姿勢・広がる関係・市場感覚を持っています。
ここでは、あなたが明日から実践できる「引き抜かれる人になるための4つの自己成長アクション」を紹介します。
どんな環境でも成果を出せる“型”を持つ
引き抜き転職・社内異動で最も求められるのは、「環境が変わっても再現できる力」です。
優秀な人ほど、“才能”ではなく“再現性”を武器にしています。
成果を再現する人の共通点
- 自分の仕事をプロセス化(How)+判断基準(Why)で整理している
- 「感覚でやっている」を言語化・マニュアル化して後輩に共有している
- トラブル時に「どこで間違えたか」を構造で説明できる
これができる人は、異動しても転職しても強い。
どんな部署・上司に当たっても、自分の“勝ち筋”を持って動けるからです。



“成果の型”を持つ人は、環境が変わっても沈まない。
それが“人事異動 出世コース”に乗る人の共通点です。
信頼を積む「報連相+共有」の精度を上げる
どんなにスキルが高くても、信頼を築けない人は引き抜かれない。
逆に言えば、「この人と仕事すると安心」と思われるだけで、声は自然とかかります。
信頼を積むコミュニケーション習慣
- 報告は「結論→根拠→提案」で3行以内にまとめる
- 連絡は“関係者全員が迷わない”粒度で(CC文化ではなく共有文化)
- 相談は“丸投げ”でなく“選択肢提示+意見”を添える
さらに、“共有の質”を高めると影響力が一気に広がります。
週1で成果・失敗・学びをSlackや社内SNSに共有するだけで、他部署の目に止まりやすくなる。
これが、社内スカウトや人事異動のチャンスにつながるんです。



“報連相”って義務じゃなく、“信頼の貯金”。
丁寧にやってる人ほど、社内で“また一緒に働きたい人”になる。
他部署・他社との接点を日常的に増やす
「優秀な部下 異動」には理由があります。
評価が高い人ほど、“社外でも通用するコミュニケーション力”を持っている。
つまり、閉じない働き方をしている人です。
接点を増やすための行動例
- 社内プロジェクト・横断MTGに積極的に参加
- 業界セミナー・ウェビナーで発言する
- 他社の担当者と情報交換ランチを月1で実施
重要なのは、「知識交換」ではなく、「信頼を積む会話」を意識すること。
その結果、あなたがいなくても「あの人に頼もう」という声が上がる。
これが、引き抜きの最初の一歩です。



“引き抜き”って、実は“信頼のネットワーク効果”。
だから、普段から声をかけ合う関係を作ることが一番の近道。
ミイダスで“市場が評価する自分”を定期チェック
どんなに社内で評価されていても、市場での価値を知らないまま働くのは危険です。
あなたが思う「普通」が、他社では“即戦力”かもしれない。
だからこそ、定期的に自分の市場価値を可視化する習慣が必要です。
▶ ミイダスを使った成長アクション
- 経歴・スキルを入力して“市場価値診断”を実施
- スカウトが届く業界・職種を分析し、自分の強みを再確認
- 年1回、自分のレジュメをアップデート(現職の棚卸しになる)
特に、“声がかかる人”はこの情報を社内評価にも活用しています。
「市場ではこう見られている」と数字で提示することで、社内でも正当に評価されやすくなるんです。



“ミイダス”は転職ツールじゃなく、自己分析の鏡。
社内の評価だけに頼らない人が、結局一番成長する。
まとめ
引き抜かれる人は、目立つ人ではなく、信頼と再現性を積み重ねている人です。
「この人なら任せられる」と思われるのは、
単に成果を出したからではなく、“どんな環境でも成果を出せる型”を持っているから。
そして、その姿勢が上司・他部署・他社に伝わり、自然とスカウトの声につながります。
一方で、スカウトの声がかかる人は、常に自分の市場価値を理解しています。
「今の自分のスキルが、どんな環境で一番輝くのか」を数字やデータで把握し、
感情ではなく戦略でキャリアを選択できる人です。
そのためにミイダスのようなサービスで定期的に“市場からの評価”を確認し、
外の視点を持つことが、自分を見失わないための武器になります。
そして最後に伝えたいのは、
「環境を選ぶことは逃げではなく、自分の成長を守る行動」だということ。
合わない環境に無理して留まるより、
自分を認め、挑戦を後押ししてくれる場所を選ぶことの方が、よほど前向きです。
信頼を積み、再現性を磨き、外の世界を知る。
その3つを意識するだけで、あなたも「引き抜かれる人材」に近づけます。



“必要とされる人”は、結果じゃなく“信頼の積み方”で決まる。
だから、どんな環境でも腐らずに、人と仕事に誠実であること。
それが最強のキャリア戦略だと思っています。
よくある質問
- 引き抜き転職とスカウトの違いは?
-
引き抜きは、元同僚・上司・取引先など「人のつながり」から直接誘われるケース。
一方、スカウトは企業やエージェントが経歴データベース(ミイダス・転職エージェントなど)を通して能動的にアプローチする仕組みです。
前者は信頼関係ベース、後者は市場評価ベースの違いがあります。 - 社内引き抜きに応じるのは裏切りになる?
-
いいえ、裏切りではなく“正当なキャリア選択”です。
社内引き抜きは、人事異動や出世コースの一形態でもあり、
「他部署から必要とされる=実力が認められた証拠」。
ただし、現上司への報告・感謝の伝え方を誤ると関係がこじれやすいので、
先に直属上司へ相談し、誠実に段取りを踏むのが大切です。 - 引き抜きオファーを断る時の正しい伝え方は?
-
ポイントは、「感謝+理由+関係維持」の3点。
具体的には、- 「お声がけいただき光栄です」とまず感謝
- 「今は現職のプロジェクトに集中したい」など前向きな理由
- 「またご一緒できる機会があればぜひ」と関係を残す一言
これで、断っても信頼を失わない断り方になります。
「即NG」「既読スルー」は、次のチャンスを閉ざすNG行動です。 - 引き抜かれた転職で後悔しないためのポイントは?
-
最も多い後悔は「期待値のズレ」です。
入社前に、- 成功とみなされる“最初の90日目標”
- 裁量範囲と意思決定ライン
- 評価の比率(成果:挑戦:協働)
を明確にしておくことが重要です。
また、待遇ではなく“上司の質と文化”を見ること。
挑戦を評価する文化がない会社では、どれだけスキルがあっても埋もれます。 - 自分も“引き抜かれる人材”になりたい。何から始めるべき?
-
まずは、今の自分が市場からどう見られているかを知ることです。
ミイダスでスキル・経歴を入力すると、あなたに興味を持つ企業からスカウトが届きます。
これは単なる転職ツールではなく、“自分の市場価値を数値で見える化”できるキャリア鏡。
自分の評価軸を把握することで、社内での交渉力や方向性も明確になります。