 やす先輩
やす先輩40代半ば、転職10回の管理職。上場もベンチャーもブラックも経験してきました。失敗も学びも交えながら、キャリアや働き方に悩むあなたへ“現実的な解決策”を届けます。
⇒詳しいプロフィール
「転職したい気持ちはあるけど、今はまだ早いかな……」
そう考えているうちに、気づけば時間だけが過ぎていく。
そんな状態に、心当たりはありませんか?
実はこの“迷っている時間”こそが、あとから一番後悔しやすいポイントです。
結論から言えば、転職は「十分に準備が整ってから」ではなく、迷い始めたタイミングがいちばん早いことが多い。
特に20〜30代は、スキルや経験を伸ばしながらキャリアを広げられる“伸びしろ期”。
行動を先延ばしにするほど、「選べる仕事」「評価される条件」は少しずつ狭まっていきます。
とはいえ、勢いだけで転職するのも不安ですよね。
だから大切なのは、「早く辞めるか/まだ残るか」を感情で決めるのではなく、今の自分の立ち位置を客観的に知ったうえで判断することです。
この記事では、
・「転職は早いほうがいい」と言われる本当の理由
・年代・状況別に見たベストな転職タイミング
・後悔しない人が必ずやっている判断の仕方
を、現実ベースで整理します。
もし今、
「今の仕事に迷いがある」
「市場で自分がどれくらい通用するのか分からない」
と感じているなら、まずはミイダスで市場価値を確認してみてください。
数分で、想定年収や転職市場での評価が見えると、「今動くべきか」「もう少し経験を積むべきか」を感情ではなく判断軸で考えられるようになります。
この記事で、“早すぎて後悔”も“遅すぎて後悔”もしない選択を一緒に整理していきましょう。
転職は早いほうがいい?その理由をデータで解説


若いうちは「未経験転職」のチャンスが多い
転職市場において、20代の転職は圧倒的に有利です。
厚生労働省の「転職者実態調査」やリクルートワークスの分析でも、20代前半〜中盤は企業が“ポテンシャル採用”を重視する傾向が明確に示されています。
たとえば、リクルートワークス研究所の調査によると、
25〜29歳の転職成功率は50.3%と、全年代平均を上回っています(出典:Mynavi NEXT「転職成功率データ」)。
また、求人動向を見ると、「未経験者歓迎」や「ポテンシャル採用」を掲げる求人が最も多いのも20代です。
一方、30代以降になると企業は「即戦力」を求める傾向が強まり、
“未経験でもOK”なポジションは少しずつ減少します。
ポイントまとめ
- 20代は「ポテンシャル」で勝負できる
- 30代以降は「経験・スキル」が求められる
- 若いうちの挑戦ほど“選べる幅”が広い



僕も20代後半で転職したとき、“まだ伸びる”と思ってもらえたのを感じました。年齢を重ねてからでは、同じ動き方でも“即戦力”が前提になります。挑戦のハードルは年齢とともに上がる。だからこそ、若いうちの一歩が大きな差になります。
転職市場では“ポテンシャル採用”が優遇される
企業が20〜30代前半に求めているのは、“完成されたスキル”ではなく「伸びしろ」と「適応力」です。
調査によると、「20代の採用で業界・職種経験を問わない」と回答した企業は約7割(69%)にのぼり、多くの企業が“経験よりも可能性”を重視していることが分かります(出典:PR TIMES「20代採用に関するアンケート調査」)。
このように“ポテンシャル採用”が広がる背景には、次のような企業ニーズがあります。
- 新しい環境にすぐ馴染める柔軟さ
- 自発的に学び、成長できる姿勢
- チームと協働できる人間性
さらに、アデコの調査では採用担当者の86.6%が「スキルより人柄を重視する」と回答しており(出典:ヒトクル「採用で重視するポイント調査」)、採用現場では“人としての適応力や前向きさ”がますます重要視されています。
一方で、年齢を重ねるにつれて企業は「即戦力」を求める傾向が強まり、
ポテンシャルで採用されるチャンスは確実に減少します。
つまり、「早めの転職=評価されやすいタイミングを逃さない」という合理的な選択なのです。



“経験が足りない”と悩むより、“伸びる力がある”と伝えるほうが企業には響きます。僕も20代後半で転職したとき、“まだ成長できる”と思ってもらえたことが、採用の決め手でした。
「3年我慢」はもう古い!時代に合わない考え方
かつては「石の上にも3年」という言葉がありましたが、
今のビジネス環境ではその考え方が完全に時代遅れです。
理由はシンプルで、
- 技術や業界トレンドの変化が早すぎる
- キャリアの“賞味期限”が短くなっている
- 働き方の価値観(リモート、副業など)が多様化している
つまり、「3年我慢してから考える」ではなく、
“違和感を覚えた瞬間に動く”方が合理的なのです。
統計的にも、転職満足度が高い層は「入社1〜2年で転職した人」という結果が出ています。
早期の決断は「忍耐不足」ではなく、“自己判断ができる人”のサインでもあります。



“3年我慢”でメンタルを壊す人を何人も見てきました。
合わない環境にしがみつくより、“学べる環境”に早く身を移す方が、結果的に成長が早いですよ。
転職するなら何月がいい?【ボーナス・繁忙期・採用動向で解説】


採用が増える「1〜3月」「9〜11月」が狙い目
年間の採用市場を見てみると、「1〜3月」と「9〜11月」が最も求人が活発になる時期です。
理由はシンプルで、企業の新年度・下期に向けた組織再編や人員補強が行われるからです。
特にこの2つの時期は以下のような特徴があります
- 1〜3月:新年度(4月)入社を見据えた採用強化期
- 9〜11月:年末退職・異動を見越した人員補充期
逆に、4〜5月や12〜1月は採用活動が一時的に鈍化しやすく、
「求人の選択肢を増やしたい」「好条件を狙いたい」という人は、
3月・10月を中心に動くのが最も効率的です。



僕も過去10回の転職で、最もオファーが多かったのは“3月と10月”。
採用企業が積極的な時期に動くと、書類選考も通りやすくなります。
ボーナス後の転職が最も効率的
もう一つの狙い目は、「ボーナスをもらってから動く」というタイミングです。
一般的にボーナスは6〜7月(夏)・12〜1月(冬)に支給されるため、
受け取った直後の7月・1月は転職活動のスタートに最適。
この時期を選ぶメリットは3つ
- 生活資金に余裕ができ、落ち着いて活動できる
- 企業側も「即戦力」を求めているため採用スピードが早い
- ボーナスを受け取ってから退職することで“損をしない”
一方で、「ボーナスをもらってすぐ辞めるのは印象が悪いのでは?」という心配もありますが、
実際は多くの人がそのタイミングで動いており、むしろ一般的な流れになっています。



ボーナスをもらって辞めるのは非常識じゃありません。
むしろ“損しない賢い選択”。自分の生活を守るのも立派な戦略ですよ。
「転職時期」は“求人量×自分の準備度”で決める
採用動向やボーナス時期を意識することは大事ですが、
最も重要なのは、“自分の準備が整っているかどうか”です。
理想の転職タイミングを見極めるポイントは以下の3つ
- 職務経歴書やポートフォリオの準備が整っている
- 退職の意思を上司に伝えるタイミングを想定できている
- 次に何を得たいか(給与・成長・環境)が明確になっている
つまり、求人量が多くても「自分の軸」が固まっていないと、
せっかくのチャンスを逃してしまうのです。



“良い時期”はあくまで市場側の話。
あなた自身の“動ける準備”ができたときこそ、最適な転職タイミングです。
年代別の最適な転職タイミング【20代・30代・40代】
20代は「伸びしろ」で勝負。早めの決断が正解
20代の転職は、経験よりもポテンシャルが評価される“ゴールデンタイム”です。
企業はこの年代に対して「まだ育てられる」「将来性がある」と判断するため、
未経験職種へのチャレンジやキャリアチェンジがしやすい時期です。
特に25〜27歳は市場価値の伸び率が最も高いゾーン。
20代後半になると即戦力としての期待値も上がり、給与アップの転職もしやすくなります。
一方で、「もう少し今の会社で頑張ろう」と迷って動かないと、
あっという間に30代に突入し、“未経験歓迎”の求人枠が減っていくのが現実です。



20代の転職で大事なのは“完璧さ”よりも“行動の早さ”。
スキルが足りないから動けない…ではなく、“伸ばせる環境”を探すのが正解です。
30代は「経験の棚卸し」で“軸”を明確に
30代の転職では、20代のようなポテンシャル採用よりも「実績と再現性」が求められます。
そのため、まずやるべきは自分のキャリアの棚卸し。
- これまでの成果・スキル・強みは何か
- どんな環境で力を発揮できるか
- 次の職場に求める条件・価値観は何か
この「キャリア軸」を明確にしておくことで、面接でも一貫性のある話ができ、
採用側に“信頼できる人材”として伝わります。
また、30代前半はまだ成長ポジションを狙いやすく、
中盤以降(35歳〜)になるとマネジメント・専門職枠の比率が増える傾向です。



30代の転職は“勝負の分かれ道”。
勢いだけじゃなく、これまでの経験を“どう活かすか”を言語化できる人が成功します。
40代は「専門性と人間力」で市場価値を高める
40代になると、求められるのは「経験の深さ」+「人を動かす力」です。
特定分野での実績・スキルだけでなく、
チームをまとめる力や課題解決の姿勢といった“人間力”が評価されるステージです。
また、40代転職=マネジメント層の交代要員という見られ方もあり、
転職成功のカギは「即戦力」よりも“再現性のあるリーダーシップ”にあります。
その一方で、「40代はもう遅い」と諦める必要はありません。
いまはリモートワークや業務委託など、柔軟な働き方の選択肢も増えています。
自分の強みを明確にし、ポジションの合う企業を選べば十分チャンスはあります。



40代の転職は“若さ”より“信頼の積み重ね”が価値になる時期。
年齢を武器に変えるには、“人を育ててきた経験”をしっかり伝えることがポイントです。
「転職が早すぎる」と言われる不安をどう乗り越える?
「早すぎる転職=悪」ではない理由
「3年は働かないとダメ」「すぐ辞めたら印象が悪い」
そんな言葉を耳にしたことがある人も多いはず。
しかし現実には、転職が早い=マイナス評価という考え方はもう古いです。
近年の転職市場では、
- 1〜2年で次のキャリアに挑戦する人が増加
- 転職回数よりも“一貫した軸”が重視される
という傾向があります。
採用担当者が見ているのは「辞めた回数」ではなく、
“なぜ転職したのか”と“その結果、何を得たのか”。
早期転職でも、目的が明確であればむしろ“行動できる人”としてプラスに映ります。



“早く辞める=逃げた”ではなく、“早く決断できた”と考えましょう。
今の時代、“行動力のある人”こそ評価されます。
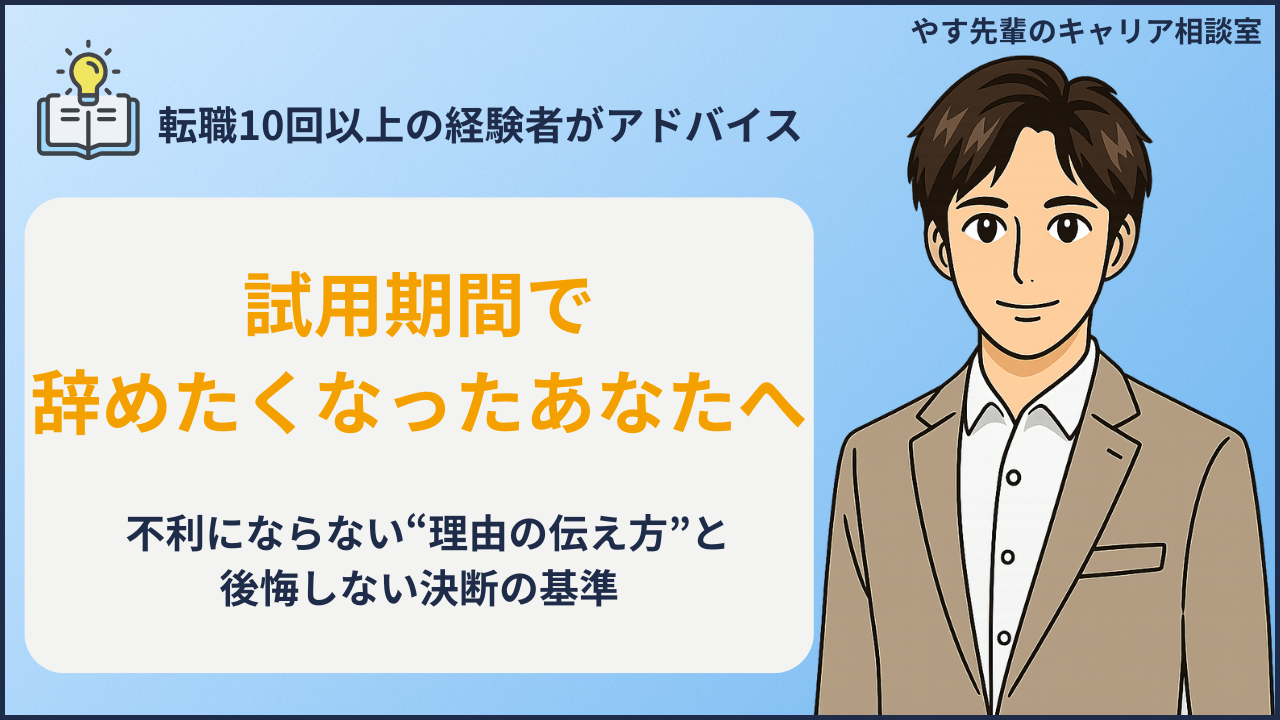
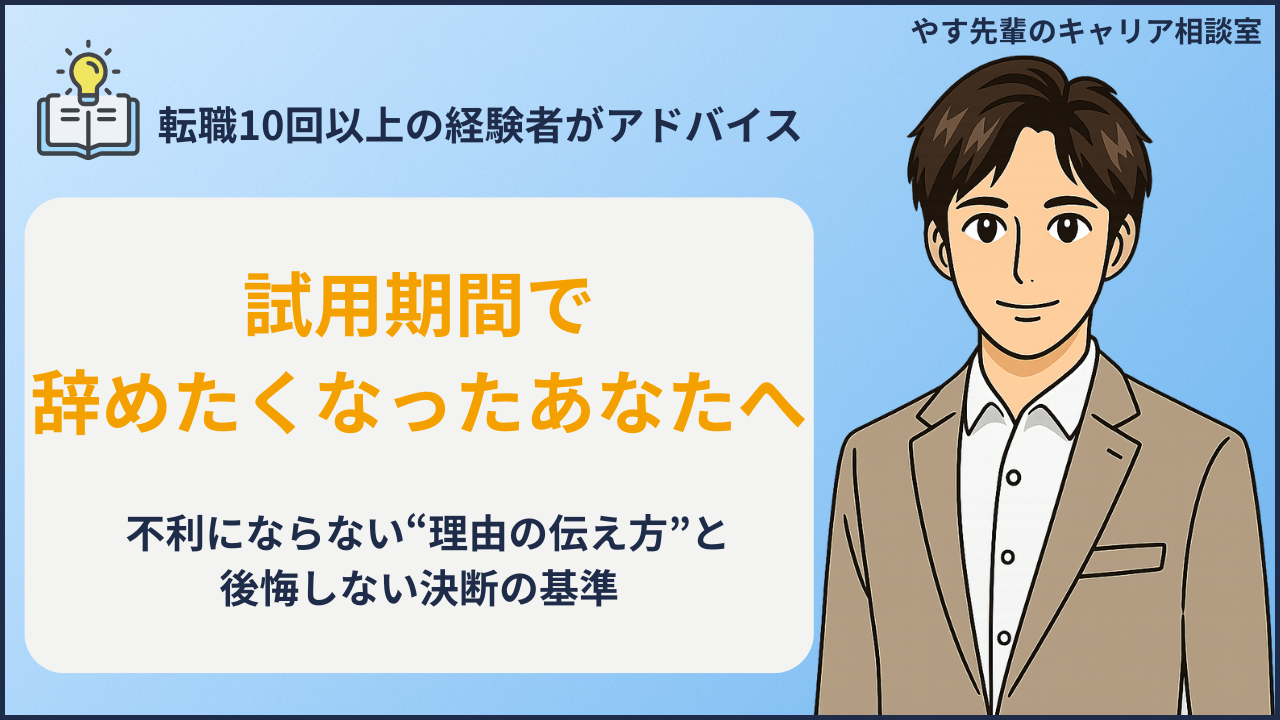
「成長を止める職場」からの離脱は前向きな決断
「もう少し頑張ったほうがいい」と言われても、
学びがなく、努力が報われない環境に居続けることこそリスクです。
たとえば、
- 教えてもらえない、評価されない職場
- アイデアが通らず、裁量がないポジション
- 上司のマイクロマネジメントで動けない環境
こうした“成長を止める職場”に長くいると、
転職のタイミングを逃し、市場価値が下がってしまうこともあります。
つまり、早い段階で「合わない」と気づき、
自分の成長を取り戻すために動くことは“逃げ”ではなく戦略的な判断です。



僕も“あと少し頑張れば”を繰り返して遠回りしました。
違和感を感じた時点で動ける人ほど、キャリアのスピードが上がります。
「転職を繰り返す人」にならないための3つの工夫
一方で、転職を繰り返してしまう人にはいくつかの共通点があります。
それは「辞める理由が常に外的要因」「次を決めずに辞める」「軸が定まっていない」こと。
同じ失敗を防ぐためには、以下の3つを意識しましょう。
- 辞める前に“転職理由”を言語化する
→「何が嫌か」ではなく「何を得たいか」を整理する。 - 次の職場に求める条件を3つに絞る
→給与・人間関係・裁量など、優先順位を決めておく。 - 第三者の客観的な視点を入れる
→ミイダスなどの「市場価値診断」を使うと、自分の強みが明確になる。
この3つを押さえるだけで、次の転職が“逃げ”ではなく“選択”に変わります。



転職は“回数”よりも“意味”が大事。
自分の軸を持って動けば、何度転職してもキャリアは積み上がります。
転職が遅い人の末路|後悔のパターンと共通点
「気づいたらキャリアが停滞」するサイン
転職のタイミングを逃す人の多くは、「今のままでも大きな不満はない」と感じているうちに、気づけば数年が経過しています。
しかしその“現状維持”こそが、キャリア停滞のはじまりです。
たとえばこんなサインが出ていませんか?
- 3年以上、仕事内容も評価も変わっていない
- 「自分じゃなくてもできる仕事」を続けている
- 上司・組織の都合に合わせるのが当たり前になっている
この状態を放置すると、成長の機会が失われるだけでなく、自信も奪われていく。
「このままでいいのかな?」と思った瞬間こそが、
本当は“転職を考えるべきタイミング”なのです。



現状維持は“安心”じゃなくて“停滞”。
僕も昔、変化を恐れて動けずにいた時期がありました。
でも動いた瞬間に、景色が一気に変わりました。
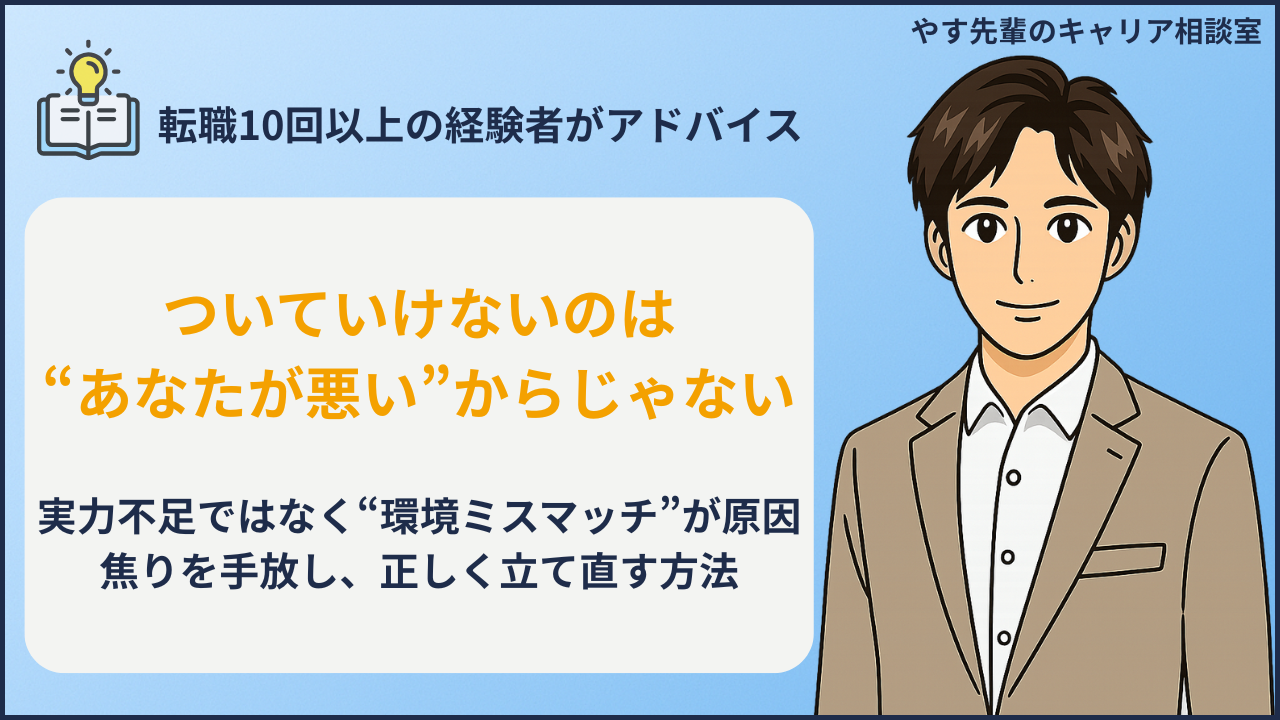
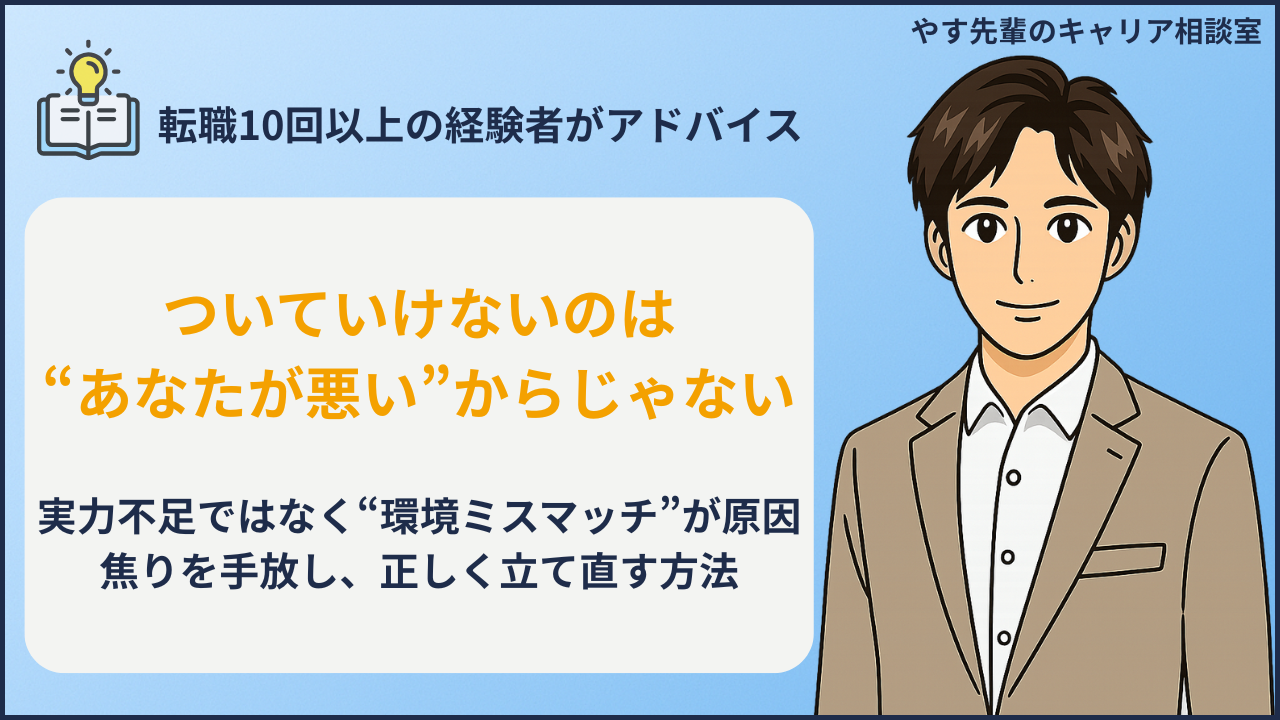
年齢が上がるほど“ポテンシャル枠”が消える
転職市場では、20代はポテンシャル採用、30代以降は即戦力採用が主流です。
つまり、年齢が上がるほど「未経験分野への挑戦」や「キャリアチェンジ」が難しくなります。
実際、転職サイトのデータでも
- 20代後半の内定率:約70%
- 30代後半では約40%に低下
という明確な差が出ています。
さらに40代になると、求められるのは「マネジメント経験」「専門スキル」「成果実績」。
ポテンシャルではなく、“実績で証明できる人材”しか採用されにくくなるのです。



“もう少し頑張ってから”が口グセの人ほど、動けなくなります。
タイミングは“完璧”じゃなくて、“まだ若干早い”くらいがベストです。
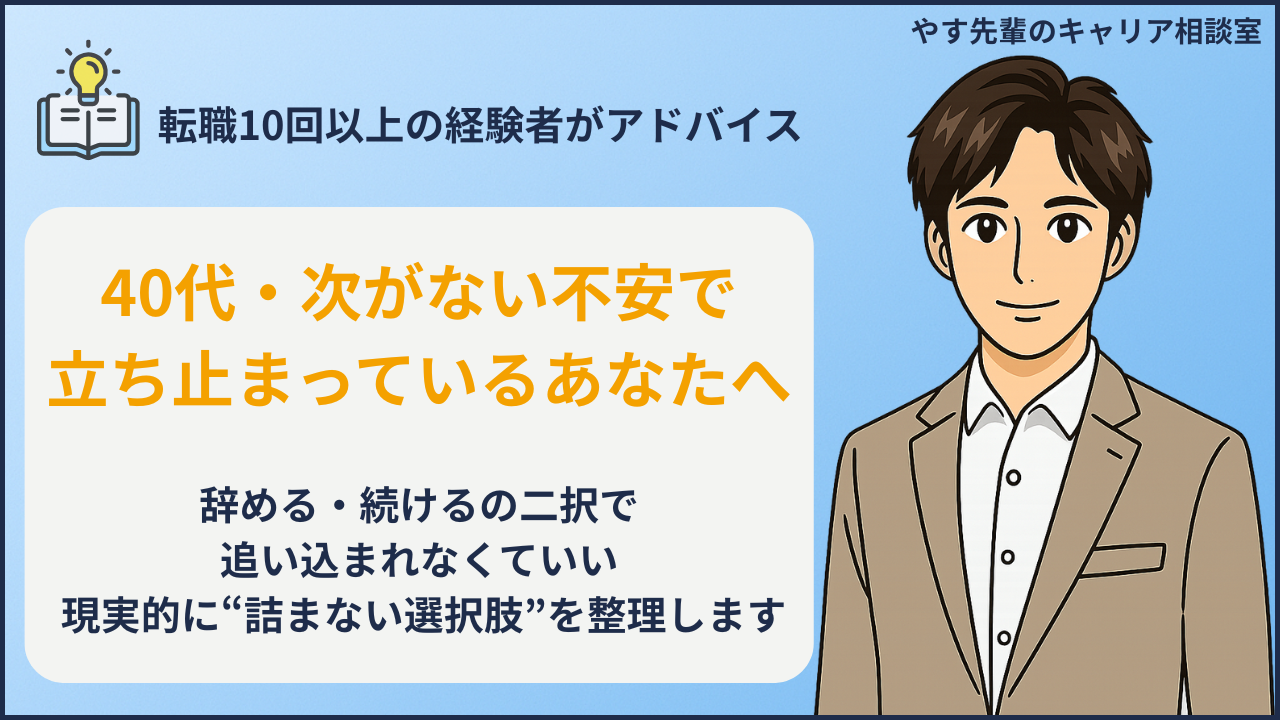
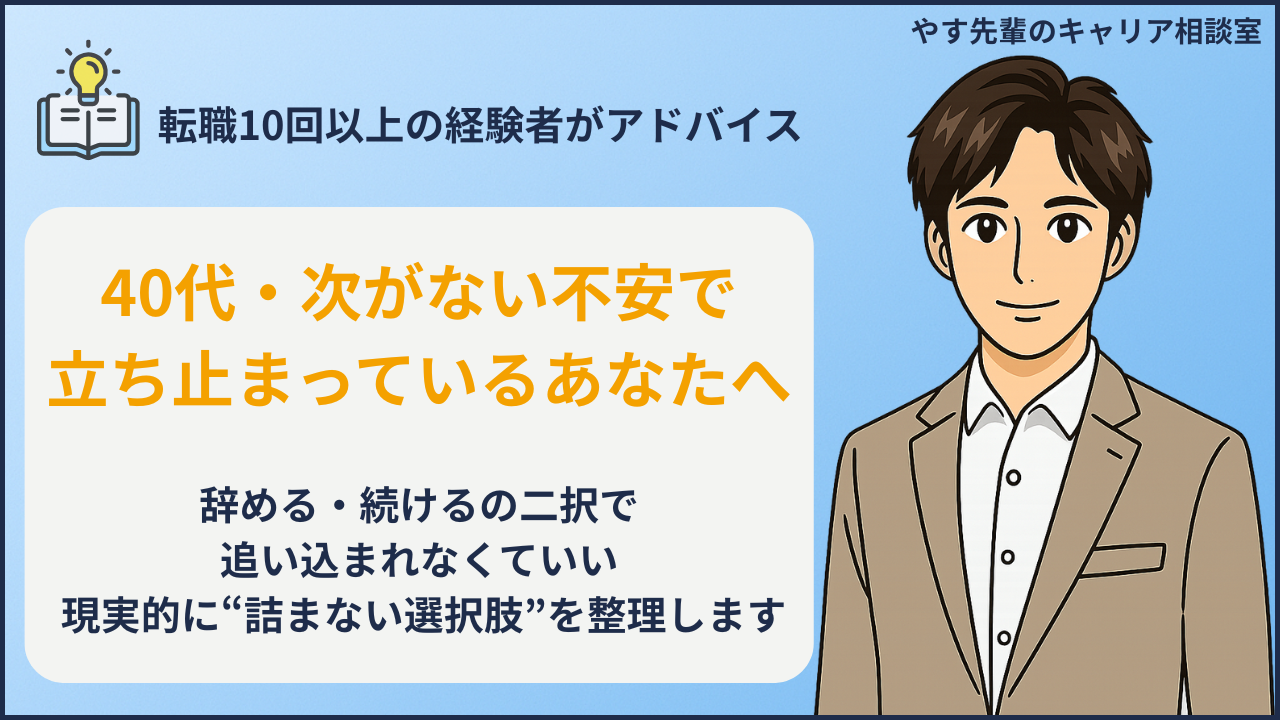
「転職しないリスク」にも目を向けよう
「転職はリスクがある」と言われがちですが、
実は“転職しないリスク”のほうが深刻な場合もあります。
たとえば:
- スキルが会社の中でしか通用しなくなる
- 同期がどんどんキャリアアップして焦りが募る
- 給与が上がらず、生活の選択肢が狭まる
このように、動かないことで「市場価値の低下」「成長の鈍化」「収入格差」という代償を払うことになります。
一方で、早めに動けば、
- 自分の強みを再確認できる
- キャリアの軌道修正ができる
- 次の環境での成功確率が上がる
という大きなメリットが得られます。



“今すぐ転職するかどうか”よりも、“転職できる状態を保つこと”が大切。
市場価値を定期的に確認しておけば、チャンスを逃さずに動けます。
やす先輩の体験談|「早く転職してよかった」と心から思えた理由
当時の状況:上司との関係悪化でモチベーションが限界
当時の職場では、上司のマイクロマネジメントと理不尽な評価に疲れきっていました。
毎日のように報告の細かさを指摘され、成果より「やり方」を責められる日々。
次第に自分の意見を言うのも怖くなり、「このままでは壊れる」と感じていました。
周りに相談しても、「もう少し我慢したら?」と言われるばかり。
でもその“もう少し”を続けた結果、朝起きるのがつらくなり、仕事が手につかなくなったんです。



職場の空気が悪くなったとき、人は“自分が悪いのかも”と思いがち。
でも、環境が合っていないだけというケースも多いんです。
行動:迷わずビズリーチ経由で転職活動を開始
限界を感じた僕は、すぐにビズリーチに登録してキャリア相談を受けました。
転職サイトを眺めるより、スカウトを通じて“市場価値を客観的に知る”ことを重視。
ヘッドハンターから「その経験なら年収700万クラスも狙えますよ」と言われ、
初めて“自分の価値”を再認識できました。
結果的に、在職中のままでも効率よく情報収集できたことで、
焦らず冷静に次の会社を選ぶことができました。



転職サイトをただ見るだけでは、自分の“相場”はわかりません。
ビズリーチのように、第三者の目線で客観評価してもらうのが近道です。
結果:3ヶ月で年収+80万円、リモートOKの職場へ
動き出してからわずか3ヶ月。
最終的に決まったのは、リモートワークOK+裁量の大きいSEO職でした。
年収も前職より80万円アップ。何より、上司との信頼関係が築ける職場に出会えたのが一番の収穫です。
前職では「自分が悪い」と思っていたことが、
実は“環境のミスマッチ”だったと気づきました。



転職の結果よりも、“自分を取り戻せた”ことがいちばん大きい。
職場が変わるだけで、心の余裕も生産性もまるで別人になります。
学び:行動の早さは“後悔の少なさ”に直結する
転職で感じた最大の学びは、「迷っている時間が一番もったいない」ということ。
数ヶ月早く動いていれば、もっと早く次のステージに行けたはず。
そう思うほど、行動の早さ=後悔の少なさだと実感しました。
転職に“完璧なタイミング”はありません。
でも、“自分の違和感に気づいた瞬間”こそがベストなタイミングです。



転職で人生が劇的に変わることもある。
でも本当に大事なのは、動く勇気。迷っている間にも、人生の時計は進んでいます。
転職を考えたら最初にやるべき3ステップ
ミイダスで市場価値を把握
まず最初にやるべきことは、「自分の市場価値を知る」ことです。
転職を成功させる人は、いきなり応募を始めるのではなく、
「自分が今どんな市場ポジションにいるか」を数値で把握しています。
そこでおすすめなのがミイダス市場価値診断。
職務経験やスキルを入力するだけで、あなたの想定年収や評価されるスキルを
企業データベースに基づいて自動算出してくれます。
数字で可視化することで、
- 自分に合う業界・職種の方向性が明確になる
- 今の会社に留まるべきか、動くべきかの判断がつく
という“転職の起点”を作れます。



市場価値を知らないまま転職すると、“なんとなく不安”のまま動くことになる。
まずはミイダスで“今の自分がどれくらい戦えるか”を把握しよう。
ビズリーチで求人動向をリサーチ
次のステップは、ビズリーチで“求人のリアル”を知ること。
転職サイトを眺めるだけでは分からない、
「企業がどんな人材を求めているのか」を知るのに最適なサービスです。
ビズリーチはスカウト制なので、
登録しておくだけでヘッドハンターや企業から直接声がかかります。
これにより、
- 自分のスキルがどの業界で評価されやすいか
- 年収レンジや待遇の相場感
を、受け身で得られるのが大きなメリット。



“今の自分を欲しがる会社がある”と分かるだけで、
不安よりも“次へのワクワク”が勝ちます。
登録するだけでも、情報収集として価値がありますよ。
マイナビジョブ20’sでキャリア相談
最後は、転職のプロに客観的な意見をもらうことです。
特に20代や第二新卒の方には、マイナビジョブ20’s がおすすめ。
特徴は、すべての求人が「未経験OK・ポテンシャル採用中心」で、
さらにキャリアアドバイザーが強みや希望を整理しながら求人を紹介してくれる点です。
「自分に合う会社がわからない」
「職場の人間関係で辞めたいけど次が不安」
そんなときでも、あなたの性格や志向を踏まえて最適な方向を示してくれます。



僕が20代のときに使っていたら、もっと早くいい会社に出会えてたと思う。
キャリア相談=転職じゃなくて、“自分を客観視する時間”として使うのがコツです。
まとめ|転職は「早い=有利」。行動こそ最大のリスク回避
転職は、「タイミングを待つもの」ではなく、「動いた人からチャンスを掴むもの」です。
「もう少しスキルを積んでから」「次の評価を待ってから」と考えているうちに、
市場は常に変化し、若さ・ポテンシャル・求人の幅は少しずつ狭まっていきます。
一方、早めに動いた人は
- 自分の“市場価値”を正しく把握し、
- “比較できる選択肢”を持ち、
- “焦らず次を選べる余裕”を手に入れています。
つまり、「早い転職=浅い決断」ではなく、
「早い行動=後悔の少ない選択」なのです。



僕も“もう少し頑張ろう”を繰り返して時間をムダにした経験があります。
動くことが怖いのは当然。でも、動かなかった後悔のほうがずっと重いですよ。
行動の第一歩におすすめ!
[ミイダスで自分の市場価値をチェック]
→ 客観的に“今の自分の立ち位置”を知る。
[ビズリーチで年収アップ求人を確認]
→ 条件のいい求人を見ながら、“今の自分でも通用する企業”を把握。
[マイナビジョブ20’s キャリア相談してみる]
→ プロに相談して、“自分に合う職場”を見つける最短ルート。
よくある質問
- 転職は早いほうが本当に有利ですか?
-
はい、特に20代〜30代前半までは「ポテンシャル採用」が多く、
経験よりも柔軟性や成長意欲が評価されます。
スキルが十分でなくても、“伸びしろ”を武器にできるのがこの時期の強みです。
一方で、年齢が上がるほど即戦力・専門性重視になるため、
「早い=選択肢が広い」という意味で確実に有利です。 - 3年未満で転職すると不利になりますか?
-
昔は「3年我慢」が常識でしたが、今はそうではありません。
成長環境がない・上司との相性が悪い・業務内容が合わないなど、
明確な理由がある転職はマイナス評価になりません。
むしろ、自分の方向性を早めに軌道修正できる人のほうが、
キャリア形成がスムーズに進むケースが多いです。 - ボーナスをもらってから辞めたほうが得?
-
金銭面では確かに得ですが、転職市場の波を逃すリスクもあります。
たとえば1〜3月・9〜11月は求人数が多く、
ボーナス時期にこだわると良い求人を逃す可能性も。
「ボーナスを取るか、キャリアのチャンスを取るか」で考えるのが賢明です。 - 20代後半の転職は遅いですか?
-
まったく遅くありません。
20代後半は、経験×柔軟性のバランスが取れた“転職適齢期”です。
第二新卒よりも実績があり、30代ほど即戦力を求められないため、
「キャリアの方向転換」も十分可能です。 - 40代の転職は厳しいって本当?
-
たしかに難易度は上がりますが、「厳しい=無理」ではありません。
40代はマネジメント経験や専門スキルが評価される層。
特にリーダー・管理職・専門職では需要が高く、
企業によっては「即戦力+人間力」を重視するケースも増えています。
大切なのは、“経験をどう価値化するか”の整理です。

