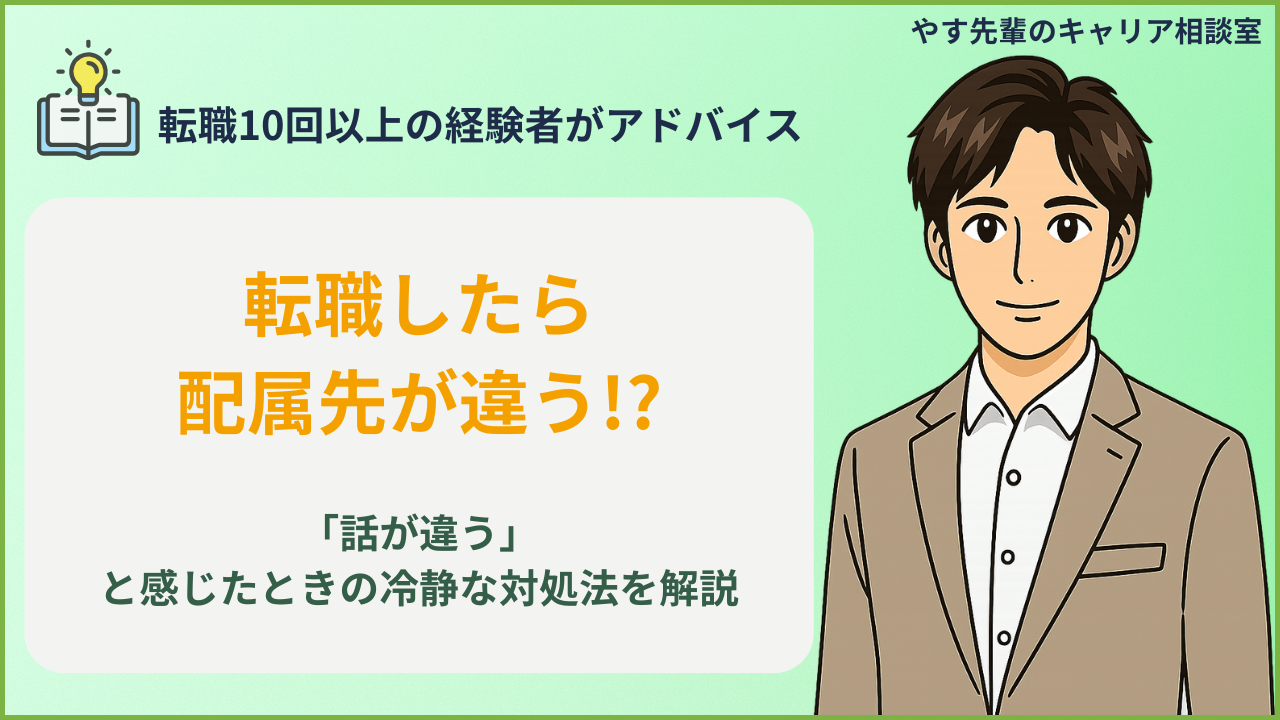やす先輩
やす先輩40代半ば、転職10回の管理職。上場もベンチャーもブラックも経験してきました。失敗も学びも交えながら、キャリアや働き方に悩むあなたへ“現実的な解決策”を届けます。
⇒詳しいプロフィール
「転職したのに、配属先が希望と違う」「聞いていた仕事と全然違う」。
そんな“想定外の配属”にショックを受ける人は少なくありません。
実はこのトラブル、転職者の約3人に1人が経験しているという調査もあります。
とはいえ、すぐに辞めるのはリスクもあり、冷静な判断が大切です。
この記事では、
- 転職したら配属先が違う原因と企業の事情
- 「話が違う」ときの正しい対処法
- 辞めてもいいケース・待つべきケースの見極め方
を、マネージャー経験のあるやす先輩がわかりやすく解説します。
もし今の配属先に納得できないなら、まずは「市場価値」を見える化しよう。
ミイダス市場価値診断を使えば、“自分に本来合う職種・年収ライン”を客観的に把握できます。
⇒ミイダス市場価値診断を試してみる
転職したら配属先が違うのはなぜ?企業が希望を通さない3つの理由
転職していざ出社したら、求人票や面接時に聞いていた配属先と違う。
このような「想定外の配属」は、実は珍しいことではありません。
企業にはそれぞれ事情や戦略があり、“希望が通らない理由”には一定のパターンがあります。
ここでは、転職後に「配属先が違う」と感じる主な3つの背景を解説します。
① 採用時の説明と実際の業務にズレがある
面接時に説明された業務内容が、実際の配属先で違う。これは採用段階での情報共有不足が原因です。
人事担当と現場責任者の間で“求めるスキルや仕事内容の認識”がずれていたり、
入社直前で組織変更が行われたりすると、想定外の職務にアサインされることがあります。
求人票には「配属予定部署」と書かれていても、「確定」ではないケースが多い点も注意が必要です。
特に中途採用では「まずは全体を見てもらってから配属を決定」とする企業もあります。



“聞いてた話と違う”と感じたら、まずは冷静に確認を。
採用担当ではなく、直属の上司に“なぜこの部署なのか”を聞くと状況が整理できます。
② 会社都合の人員配置で希望部署に入れない
企業は常に“人手が不足している部署”を優先的に補充する傾向があります。
つまり、スキルや希望よりも組織バランスや緊急性を重視した配属になることがあるのです。
たとえば、
- 前任者が退職して欠員が出た部署
- 新規プロジェクトで急募されたポジション
- 他部署の業務が一時的に増加しているタイミング
などでは、希望部署ではなく「即戦力として配置できる部署」へ回されることがあります。
この場合、あなたの能力を評価しているがゆえの配属という可能性もあります。
企業にとって「すぐ戦力になる人材」は、最も頼りにされる存在です。



“会社都合”に見えても、意外と自分の市場価値を認められての配属だったりします。
まずは3ヶ月、冷静に“成長の種”を探してみて。
③ 「まず現場で経験を積ませたい」という育成方針もある
とくに大手企業や総合職採用の場合、最初の配属は“教育的配置”の意味合いを持つことがあります。
会社としては「いきなり専門部署より、まず現場を知ってから」と考えるパターンです。
実際、リクルートワークス研究所の調査でも、
約4割の企業が「配属先を教育目的で決める」と回答しています。
これは「希望を無視」しているのではなく、将来的なキャリア形成を意図したステップである場合も多いです。



僕も“現場スタート”で悩んだけど、結果的にその経験がマネジメントに活きました。
“今の経験がどこでつながるか”を意識すると、気持ちが軽くなります。
「話が違う」と感じたときの正しい対処法


転職してすぐに「聞いてた話と違う」「求人内容と業務が違う」と感じたとき、
多くの人が真っ先に「辞めたい」と思ってしまいます。
しかし、ここで感情的に動いてしまうと、自分にとって不利な判断につながることも少なくありません。
まずは冷静に状況を整理し、「何が」「どのくらい」違っているのかを明確にしましょう。
その上で、正しい順序で行動すれば、無駄なストレスや後悔を防ぐことができます。
① 感情的に動く前に“事実関係”を整理する
「話が違う!」と感じた瞬間ほど、冷静さが大切です。
まずは、入社前に提示された情報と実際の業務内容のギャップを具体的に整理しましょう。
確認すべきポイントは以下の3つです
- 求人票・雇用契約書・労働条件通知書の内容
- 面接時に上司・人事が伝えた業務範囲や勤務地
- 実際に割り当てられている業務内容
これらを照らし合わせると、「完全に契約違反」なのか、それとも「一時的な配置」なのかが見えてきます。
もし曖昧な部分が多い場合は、入社時のメールやメモなど、証拠を残しておくことも重要です。
これは後で人事や労働相談機関に相談する際に、有効な資料になります。



“話が違う”と感じたら、まずは“どの点が違うのか”を書き出す。
感情よりも、事実ベースで整理すると次の行動が見えてきます。
② 配属理由や今後のキャリアパスを上司に確認
次に行うべきは、直属の上司に配属理由を聞くことです。
「なぜこの部署なのか」「どのくらいの期間この業務を担当するのか」など、
上司に確認することで、“会社側の意図”を理解できることがあります。
特に以下のように尋ねると、対立を避けつつ建設的な会話になります
「自分のキャリアプランを考える上で、この配属の意図を教えていただけますか?」
この言い方なら、“不満”ではなく“前向きな確認”として受け止めてもらえます。
また、今後のキャリアパスが明確になることで、異動や昇進のチャンスが見えることもあるのです。
もし「将来的な異動予定もない」「理由の説明が曖昧」な場合は、
その時点で“信頼できる職場かどうか”を見極めるサインにもなります。



“文句”ではなく“確認”として伝えることがポイント。
上司の反応次第で、会社の本気度や誠実さがわかります。
③ 異動願い・部署変更のタイミングを見極める
配属先が希望と違う場合でも、すぐに辞めるのは早計です。
まずは最低3ヶ月〜半年ほど様子を見る期間を設けましょう。
多くの企業では、人事異動や部署調整が四半期・半期単位で行われるため、
短期間で環境が変わることもあります。
異動願いを出す場合は、感情的に「辞めたい」と言うよりも、
「○○分野での経験を積みたい」「自分の強みを活かせる部署に貢献したい」
といった形で“前向きな理由”を添えるのが鉄則です。
それでも改善の兆しが見えない、または上司や人事が誠実に対応しない場合は、
「転職の再検討」も視野に入れるタイミングです。



“違う配属”をただ我慢するのではなく、“次の動きを決めるための観察期間”と捉えると気持ちが楽になります。
勤務地が希望と違うときの対応策と交渉ポイント
「勤務地は東京と聞いていたのに、いきなり地方配属と言われた」
「面接で“希望考慮”と聞いていたのに、全く違う支店に飛ばされた」
こうした“勤務地トラブル”は、転職後に起こりやすい代表的なケースです。
多くの場合、企業側の事情(人員配置・急な欠員補充・組織改編など)が背景にありますが、
中には契約内容の不備や説明不足が原因で、法的に問題があるケースも存在します。
ここでは、勤務地が希望と違う場合に取るべき3つのステップを、実務的な観点から解説します。
① 雇用契約書・労働条件通知書を必ず確認
まず最初に確認すべきは、雇用契約書と労働条件通知書です。
求人票や面接での口頭説明は、法的な拘束力が弱いため、
“勤務地”や“勤務エリア”がどのように記載されているかが、最も重要な判断材料になります。
たとえば、以下のような文言がある場合は注意が必要です
- 「会社の定める場所」
- 「業務上の必要に応じて転勤を命ずることがある」
- 「勤務地は全国各拠点のいずれか」
これらは全国転勤型の包括的な契約を意味し、希望と異なる配属でも“契約違反”にはなりません。
一方で、次のように勤務地が明記されている場合は、状況が変わります。
- 「勤務地:東京都渋谷区〇〇本社」
- 「転勤なし(勤務地限定社員)」
この場合、入社後に異なる勤務地へ一方的に配属されたら、
労働契約法15条の「契約内容の不利益変更」にあたる可能性があります。



“求人票に書いてあったから”ではなく、“契約書に書いてあるか”が基準。
まずは冷静に、書面の一行一行を見直してみましょう。
② 通勤時間・家庭事情など正当な理由を整理して伝える
契約書上は合法でも、実生活に支障をきたすケースでは、柔軟な交渉の余地があります。
たとえば
- 片道2時間以上の通勤で心身に負担が大きい
- 家族の介護や子育てで転居が難しい
- 通勤費や生活費が大幅に増える
このような場合、「個人的な感情」ではなく「合理的な理由」として伝えることがポイントです。
上司や人事に伝える際は、次のようなフレーズが効果的です。
「業務には全力で取り組みたいのですが、現在の勤務地では家庭との両立が難しく、
通勤や生活面で継続勤務が困難な状況です。何か調整の余地はありますでしょうか?」
このように伝えると、“わがまま”ではなく“誠実な相談”として受け取られやすく、
異動・リモート勤務・短期出向などの代替案が検討される可能性もあります。



会社は“困っている社員”よりも、“解決策を持って相談する社員”を動かしやすい。
『無理です』より『こうすれば続けられます』と伝えるのがコツです。
③ どうしても難しい場合は「配置転換願い」を検討
話し合いでも改善が見込めない場合は、正式に「配置転換願い」を提出しましょう。
これは「異動を希望します」という意思表示であり、会社側も無視できません。
提出のポイントは次の3つです。
- 感情的な文面にせず、事実と希望を淡々と書く
- 「退職を避けるための異動希望」という建前を明確にする
- 提出先は直属の上司→人事部→総務部の順で正式ルートを踏む
また、人事面談や社内相談窓口での記録を残すことも重要です。
のちにトラブルになった場合、正式な申し出があったことの証明になります。
それでもなお改善が見られず、体調不良やストレスが続く場合は、
労働基準監督署や労働局の「総合労働相談コーナー」に相談することも選択肢の一つです。
(厚生労働省「総合労働相談コーナー」公式ページ)



“辞める前に相談する”のが大事。正式なルートを使えば、
一方的な異動でも会社に改善を促すチャンスがあります。
配属先が希望と違うとき「辞めてもいい」ケースとは?
「面接で聞いていた仕事内容と違う」「希望した職種とまったく別の仕事を任された」。
配属のズレは誰にでも起こり得ますが、問題はそれが“一時的なギャップ”なのか、“構造的な不誠実さ”なのかです。
結論から言えば、以下の3つの条件に当てはまるなら、転職・退職を検討しても構いません。
「我慢すること」=「忠誠」ではありません。自分のキャリアを守るための行動こそが、長期的には正解です。
① 契約内容と実際の職務が明確に異なる
最も深刻なのは、労働契約上の約束と実際の業務内容が明確に異なるケースです。
たとえば
- 契約書に「Webマーケティング業務」とあるのに、実際は「営業職」や「テレアポ」中心
- 「転勤なし」と明記されているのに、いきなり地方支店への異動を命じられた
- 面接時に「本社配属」と言われたのに、別部署で全く違う業務を担当
これらは労働契約法第15条(労働条件の明示)や民法の信義則(誠実義務)に反する可能性があります。
つまり、「聞いていた話と違う」ではなく「契約違反」にあたるレベルです。
このような場合、まずは社内の上司・人事に正式に確認し、改善が見込めない場合は、
労働基準監督署や労働局(総合労働相談コーナー)への相談を検討してください。



“話が違う”と感じたら、まずは書面を確認。求人票ではなく、契約書に何と書かれているかを基準に判断しましょう。
それが食い違っているなら、辞める選択も“逃げ”ではなく“正当防衛”です。
② 成長機会・キャリア形成が阻害されている
次に注目すべきは、「今の配属が自分のキャリアを潰しているかどうか」です。
企業には「人材を総合的に育てる」という建前がありますが、
実際には“人手不足部署への穴埋め”として、希望と違う職種へ配属されることが少なくありません。
たとえば
- 本来やりたかった企画・マーケティング業務から、完全に外れたルーティン業務ばかり
- 成果を出しても異動のチャンスが与えられない
- 上司から「今後もこの部署で頑張ってほしい」と一方的に言われる
このように「努力しても報われない」「スキルが成長しない」と感じる環境は、
“キャリアの機会損失”という見えないダメージを与えます。
転職市場では、「どんな会社にいたか」より「どんなスキルを積んだか」が評価される時代。
自分の成長が止まっていると感じたら、それは“辞めるサイン”と捉えていいでしょう。



“今の経験が未来につながっているか?”を自問してみて。
答えが“ノー”なら、今いる場所を変えるタイミングです。
③ ストレスで心身に支障が出ている
最後に最も重要なのは、心と体のサインを見逃さないことです。
配属先が合わないことで、慢性的なストレスを抱える人は非常に多く、
特に以下のような兆候がある場合は、早めの判断が必要です。
- 毎朝出社がつらい・眠れない
- 上司や同僚との関係悪化で気持ちが沈む
- 頭痛・胃痛・倦怠感などの体調不良が続く
これは単なる「やる気の問題」ではなく、適応障害やメンタル不調の初期症状であることもあります。
無理をして働き続けるよりも、一度立ち止まって環境を変えるほうが回復が早いのです。
もし心身に限界を感じているなら、
といった“出口戦略”を取るのが現実的です。



僕も“合わない部署”で体調を崩した経験があります。
“もう少し頑張れば”より、“これ以上壊さない”を優先してほしい。
やす先輩の体験談|転職後に配属先が違ってもチャンスに変えた話
当時の状況:希望のマーケ部署ではなく営業配属に
転職先では「Webマーケティング部でSEO戦略を担当」と聞いて入社しました。
しかし、いざ辞令が出ると配属はまさかの営業部門。
求人票にも「配属は希望を考慮」と書かれていたため、正直、頭の中が真っ白になりました。
最初の数日は、「配属ガチャに外れた」「話が違う」と悔しさばかり。
“転職は失敗だったかもしれない”という不安に押しつぶされそうになりました。



“自分の希望じゃない部署”に配属されたとき、最初に湧くのは“納得いかない”という感情です。
でも、怒りや落胆のまま過ごすと、その時間すら自分のキャリアを削ってしまうんですよね。
感じたこと:モチベ低下と「やってられない」という焦り
営業職に回された僕は、数字とプレッシャーの世界に戸惑いました。
毎朝の朝礼での進捗報告、同行営業、上司の詰め、すべてが未知の領域。
「自分はマーケがやりたくて転職したのに、なぜ…」という思いが募り、
次第に仕事へのモチベーションも落ちていきました。
しかし、ふと気づいたんです。
「SEOも、結局“顧客心理を読み解く”仕事だ」と。
営業の現場には、ユーザーのリアルな反応が山ほどある。
「ここから学べることがあるかもしれない」と思い直し、気持ちを切り替えることにしました。



配属先に不満を抱いたら、“この経験はどんなスキルに変えられるか”と考えること。
不満を燃料にできる人が、一番強いです。
行動:営業経験をSEO視点で分析し、改善提案を出す
僕が最初にやったのは、営業活動を“マーケティングデータ”として分析することでした。
顧客がどんな言葉で商品に興味を示すか、どんな資料に反応するか、どんな瞬間に離れるか。
それらをすべてエクセルで整理し、「営業現場での顧客行動×SEOキーワード分析」という資料を作成。
社内ミーティングで発表したところ、上司から「この視点は新しい」と評価されました。
さらに、社内ブログの企画にも参加し、営業視点からの記事を提案したことで、
マーケティング部の部長の目に留まり、話す機会を得たのです。



“違う部署”に配属されたときほど、自分の専門性を別角度で活かすチャンスがあります。
“自分の強みを新しい場所でどう使えるか”を意識して動くのがコツです。
結果:半年後、社内異動で希望職種へ転属
その後、半年間の営業実績と改善提案が認められ、ついにSEO担当としてマーケティング部へ異動。
しかも、営業部で培った“顧客理解力”が評価され、異動後すぐに主要案件を任されました。
当初は「配属ミスだ」と思っていた営業経験が、結果的に僕のキャリアの武器になったのです。



キャリアは一直線じゃなくていい。
“遠回りに見える経験”が、あとで“最短ルート”に変わることがある。
学び:「違う配属」も“経験の幅”と考えれば武器になる
配属先が希望と違うとき、人はどうしても「自分が否定された」と感じてしまいます。
でも、実はそれは「新しい視点を得るチャンス」でもあります。
僕がマーケで成果を出せたのは、営業時代に身につけた「ユーザー視点」「現場感覚」があったから。
あのとき腐らずに、“違う環境でも成長できる自分”を証明したことが、後の大きな転機になりました。



配属ガチャは“運”じゃなく“対応力”で乗り越えられる。
たとえ希望と違っても、その経験を“次に活かすネタ”に変えられた人が最後は勝ちます。
「もう限界」と感じたら転職を検討すべきサイン
転職後、「聞いていた話と違う」「希望の配属先じゃない」と感じても、
多くの人は「せっかく入社したし」「もう少し我慢しよう」と踏みとどまります。
けれど、“我慢が正解ではない”ケースも存在します。
放置すればキャリアが停滞し、心身をすり減らしてしまうリスクさえあります。
ここでは、「もう限界」と感じたときに“転職を検討すべき3つのサイン”を、実例を交えながら詳しく解説します。
① 契約・求人票と職務内容が著しく異なる
最初に確認すべきは、「自分が採用された条件と、実際の仕事内容が一致しているか」です。
たとえば
- 求人票では「マーケティング職」と書かれていたのに、実際は「テレアポ中心の営業職」
- 面接では「転勤なし」と言われたのに、入社初日に「地方支店勤務」と告げられた
- 契約書に「業務内容:経理事務」と明記されているのに、実際は「総務・庶務全般」
こうしたケースは単なる「会社都合」ではなく、労働契約法第15条に基づく“契約内容の不一致”に該当する可能性があります。
企業には「採用時に明示した条件を守る義務」があり、著しい乖離がある場合は、
「退職を検討する正当な理由」となります。
もし、「話が違う」と感じた場合は、次のステップを踏みましょう
- 労働契約書・求人票・面接メモを確認(証拠を整理)
- 上司・人事に説明を求める(感情的ではなく、事実ベースで)
- 改善が見込めない場合は、労働局や専門機関に相談



“求人票に書いてあった”ではなく、“契約書に何が書かれているか”がすべて。
もしそれすら無視されているなら、それは“話が違う”ではなく“信頼関係の崩壊”です。
② 上司や人事に相談しても改善の見込みがない
次に見るべきサインは、「会社側に改善意志があるかどうか」です。
たとえ最初の配属が希望と違っても、
- 「半年後には異動を検討します」
- 「今は研修期間として現場経験を積んでほしい」
といった前向きな説明があるなら、まだ望みはあります。
しかし、次のような対応が続く場合は、“改善の見込みなし”と判断していいでしょう
- 「うちは配属は会社が決めるもの」と取り合わない
- 異動願いを出しても放置される
- 相談後にむしろ評価が下がる・関係が悪化する
このような企業では、「社員のキャリアを育てる文化」よりも、「会社都合の人事運用」が優先されています。
この状態が続くと、努力しても報われず、“キャリアの浪費期”に突入してしまいます。



“今は仕方ない”が口癖の上司がいる職場は要注意。
本当に社員を大切にする会社は、“いつ・どう変えるか”を明確に話してくれます。
③ メンタルや体調に影響が出ている
そして、最も見逃してはいけないサインが、心と体からのSOSです。
配属先のストレスが限界を超えると、
- 朝、出社前に動悸や吐き気がする
- 眠れない・食欲がない
- 「自分が悪いのでは」と過剰に自責する
といった症状が出てきます。
これは単なる「やる気の低下」ではなく、適応障害やうつ状態の初期症状である場合もあります。
もしすでにこの段階にいるなら、
「頑張る」より「離れる」ことが最優先の対処法です。
まずは心療内科や産業医への相談を行い、診断書が出た場合は、
会社に「休職」または「配置転換の希望」を正式に提出しましょう。
それでも改善が見込めない場合は、
- 退職代行サービス「トリケシ」で即日退職の手続きを行う
- ミイダスで自分の市場価値を診断して転職準備を始める
- ビズリーチ/マイナビジョブ20’sで“信頼できる環境”を探す
といった「次の一手」を早めに動くことをおすすめします。



“体調を崩すほどの我慢”は、キャリアを守るどころか壊してしまいます。
“逃げる”じゃなく、“自分を守るために離れる”と考えてください。
配属ミスマッチからの再出発におすすめの3ステップ
配属が希望と違って落ち込むのは当たり前。大事なのは「次にどう動くか」です。ここでは、迷いを整理して最短で再出発するための3ステップを提案します。順番はシンプル。現状把握→選択肢の可視化→プロと戦略設計。この流れを押さえるだけで、感情に振り回されず実務的に前進できます。
① ミイダスで市場価値をチェックして“次の方向性”を把握
まずは土台づくり。今の年齢・職歴・スキルで、市場があなたにいくらの値を付けているかを数字で知りましょう。
ミイダスは想定年収レンジやマッチしやすい職種を可視化してくれるので、「入社後 職種が違うけど、自分は本来どこで戦えるのか」を客観視できます。
おすすめは診断結果から強みキーワードを3つ抽出し、職務経歴書の見出しと面接トークに転用すること。配属先 希望と違う転職の相談でも、主観ではなく市場データを根拠に話せると説得力が段違いです。



僕もまず数字で現実を見るところから始めました。「悔しい」より「どう勝つか」。データは迷いを削ってくれます。
② ビズリーチで希望職種・勤務地の求人をリサーチ
方向性が見えたら、選択肢を広げます。ビズリーチでは希望職種や勤務地、年収帯でスカウト傾向を確認できます。転職 業務内容が違う悩みを抱えている人ほど、求人票の「配属部署」「職務内容の具体例」「異動の想定」を必ずチェック。過去に配属先 希望と違う転職で失敗しないために、企業へは事前に次の3点を質問しましょう。
- 初期配属の確度と想定期間
- 異動の判断基準と時期の目安
- 職種変更が起きやすい過去事例
この3点が曖昧な会社は、再び「話が違う」を招きやすい。エージェント経由の指名スカウトは採用温度が高いので、条件交渉の余地が生まれやすいのも利点です。



求人の数より質。配属や業務内容の運用ルールを先に詰めると、入社後のズレが減ります。
③ マイナビジョブ20’sでキャリアカウンセリングを受ける
20代中心なら、面接対策まで伴走してくれる マイナビジョブ20’s が効率的です。入社後 職種が違う経験は面接で突っ込まれがちですが、言い訳にせず「学びと選択」を語れば加点になります。カウンセラーと一緒に、面接の核を整えましょう。
例)
・事実:当初の職種と実務のギャップ
・行動:そこで得た学びや成果(定量)
・選択:なぜ次はこの職種と勤務地なのか(定性)
さらに、企業別の配属運用傾向や面接官の評価ポイントも教えてくれるので、配属ミスマッチ再発のリスクを事前に下げられます。



独りで悩むより第三者の目線を入れると一気に整います。トークが整理されると自信が戻るんですよね。
【3ステップの使い分けのコツ】
1で基準を作り、2で選択肢をふやし、3で勝ち筋を固める。並行で動いてOKですが、必ず「市場データ→求人実態→面接戦略」の順で精度を上げるのがポイント。配属先 希望と違う 転職の再挑戦は、感情を整えつつ、情報と準備で勝ちにいきましょう。
まとめ|転職後の配属違いは“失敗”ではなく“再構築のチャンス”
転職後に「聞いていた配属先と違う」「想定していた仕事ができない」と感じたとしても、
それはあなたの実力や判断ミスではありません。
多くの場合、企業側の組織バランス・人員計画・経営判断による“配属ロジック”が背景にあります。
つまり、あなたが悪いのではなく、仕組みのズレによる“ミスマッチ”が起きているだけ。
本当に大切なのは、
「なぜこうなったのか」を嘆くことではなく、
“今からどう軌道修正するか”を考える姿勢です。
経験上、配属が希望と違っても、
・そこで得たスキルを次の転職で活かせる人
・状況を冷静に分析して行動に移せる人
は、その後のキャリアをむしろ加速させています。
やす先輩自身も、営業への予期せぬ配属からマーケ職へ戻り、
結果的に「顧客理解×SEO戦略」で前職より評価を上げました。
つまり、配属ミスマッチ=キャリアの再構築チャンスでもあるのです。
もし今、「このままでいいのかな」と感じているなら、
“我慢”ではなく“見直し”に舵を切ってください。
以下の3ステップで、キャリアの軌道を現実的に取り戻せます。
ミイダスで自分の市場価値をチェックする
┗ 今のスキルが市場でどう評価されているかを客観的に把握。
ビズリーチで希望の求人を探す
┗ 自分に合ったポジションと年収アップの両立を狙う。
マイナビジョブ20’s でプロにキャリア相談する
┗ 未経験職種やキャリアチェンジも含めた相談が可能。



“違う配属”は遠回りのようで、後から“自分の武器”になることも多い。
だからこそ、環境を責めるより、行動で未来を変えよう。
よくある質問
- 転職したら配属先が違ったのですが、これは違法ですか?
-
配属が希望と違うだけでは違法とは言えません。
ただし、求人票や労働契約書に明記された職務内容・勤務地と実際の業務が著しく異なる場合は、労働契約法第15条に抵触する可能性があります。
契約内容を確認し、まずは人事に正式な説明を求めましょう。 - 入社後、職種が違うことに納得できない場合どうすれば?
-
感情的に退職を考える前に、配属理由やキャリアパスの説明を上司に確認してください。
「育成目的」「短期的な配置転換」であることも多く、期間を明確にすることで見通しが立ちます。
もし明確な説明がなく改善も見込めない場合は、転職を含めて再検討しましょう。 - 希望の勤務地と違う場所に配属されました。拒否できますか?
-
勤務地の指定が労働契約書に明記されているかどうかで対応が変わります。
記載がある場合は交渉余地がありますが、勤務地欄に「会社の定める場所」とある場合は、会社側に裁量が認められます。家庭の事情(介護・育児など)がある場合は、その理由を添えて「配置転換願い」を提出しましょう。 - 「思っていた仕事と違う」と感じたとき、どのくらい我慢すべき?
-
半年〜1年ほど経験してから判断するのが一般的ですが、キャリア形成を阻害される・メンタルに負担が出る場合は別です。限界を感じる前に、ミイダスなどで自分の市場価値を把握し、
「次にどう動くか」の選択肢を持っておくと冷静に判断できます。 - 配属先が合わずに辞めるのは“甘え”でしょうか?
-
決して甘えではありません。
会社の都合で配属が変わることは多く、ミスマッチを見極めて動くのも立派な判断力です。
自分を責めるより、「どんな環境なら成長できるか」を考えましょう。