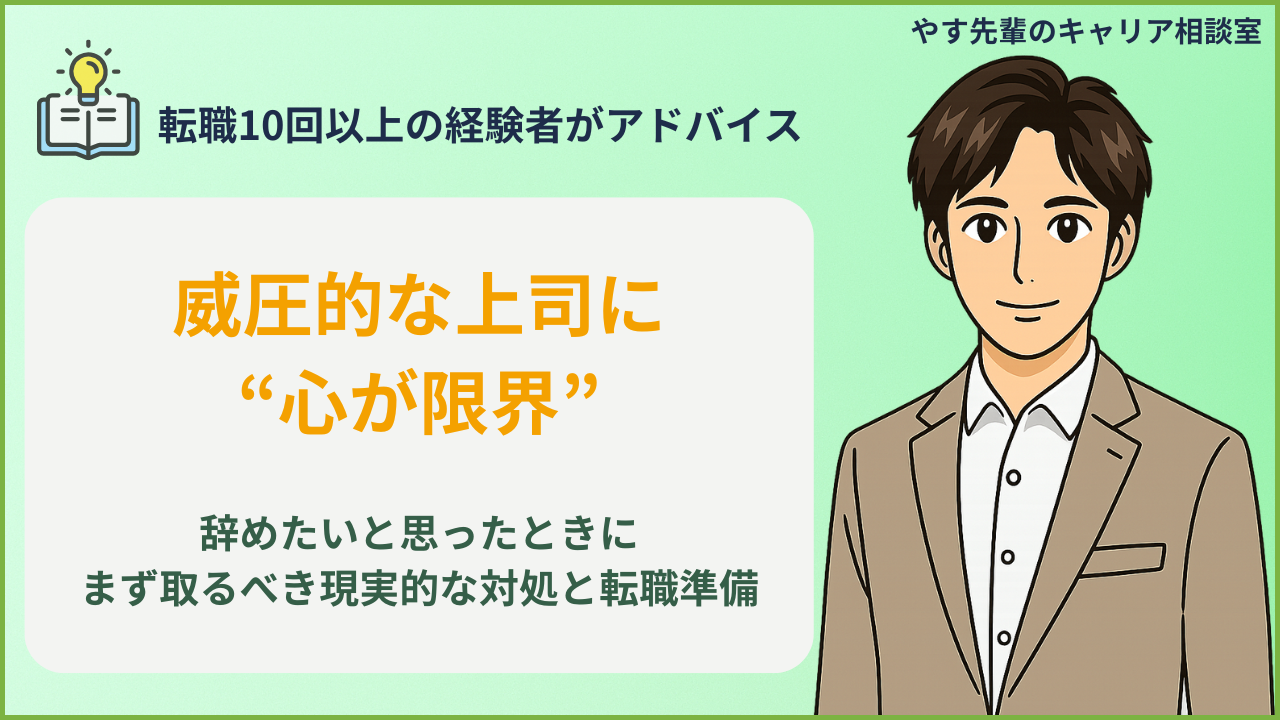やす先輩
やす先輩40代半ば、転職10回の管理職。上場もベンチャーもブラックも経験してきました。失敗も学びも交えながら、キャリアや働き方に悩むあなたへ“現実的な解決策”を届けます。
⇒詳しいプロフィール
「上司が威圧的で、もう辞めたい。」
毎日のように怒鳴られる。
理不尽な態度を取られる。
存在そのものを否定されるような言葉を浴び続ける。
そんな環境にいると、気づかないうちに心も体も削られていきます。
朝になると会社に行くのが怖くなり、電車に乗るだけで胃が痛くなる。
それは、あなたが弱いからではありません。
僕自身も、威圧的な上司のもとで働き、「これ以上続けたら壊れるかもしれない」と感じた経験があります。
あのとき一番つらかったのは、辞めたい気持ちと、辞めた後が不安で動けない状態でした。
だからこそ、先に伝えます。
威圧的な上司に耐え続けることは、成長ではありません。
大切なのは、感情で限界を迎える前に、現実的な対処と“次の選択肢”を同時に準備することです。
この記事では、
・なぜ上司が威圧的になるのか
・今すぐできる現実的な対処法
・本当に辞めると決めたときの準備と進め方
・次の職場で同じ失敗を繰り返さない考え方
を、やす先輩の実体験を交えて整理します。
もし今、
「辞めたいけど、次が見えなくて動けない」
「自分はどこへ行っても通用しないのでは」
と感じているなら、まずは自分の市場価値を客観的に知ってください。
今の上司の評価と、社会からの評価は別物です。
「逃げ道がある」と分かるだけで、恐怖に支配されず、冷静な判断ができるようになります。
この記事で、自分を壊さずに抜け出すための判断軸を一緒に整理していきましょう。
上司が威圧的で辞めたいと感じる理由
精神的ストレスの悪循環
威圧的な態度は、ただ「嫌な気分になる」だけでは終わりません。強い声や圧力を繰り返し浴びることで、脳と体は常に緊急事態モード(防衛モード)に入ってしまいます。
すると、交感神経が過剰に働き、眠っても休まらず、頭も体も常に緊張状態が続くのです。その結果、集中力や判断力はどんどん低下し、小さなミスを繰り返すようになります。そして、そのミスをまた叱責される…という悪循環に陥ってしまいます。
さらに怖いのは、こうした状態が長引くと、「どうせまた怒られる」→「だったら何も言わないでおこう」→「指示待ちになる」という流れが強まることです。本来の能力が発揮できなくなり、仕事の評価も下がってしまう。これが続けば、自信を失い、心が追い詰められていきます。
つまり、威圧的な上司のもとで働き続けることは、単なる「我慢」では済まされない問題なんです。精神的にも肉体的にも消耗し、キャリアにまで悪影響が及ぶからこそ、早めに対処法を取ることが必要になります。



僕も当時、会議で怒鳴られると、その後しばらく頭が真っ白になってた。自分のせいだと思い込んでたけど、実際は「体が防衛反応で動けなくなってた」んだよね。これは弱さじゃなくて、人間として自然な反応なんだ。




自分を責めてしまう心理
威圧的な上司に繰り返し接していると、やがて「自分が至らないから怒られるんだ」と考えてしまいがちです。これは一種の学習された反応で、強い立場の人から否定され続けると、「自分に原因があるに違いない」と思い込むようになる心理現象です。こうした思考が続くと、少しの失敗でも「やっぱり自分はダメだ」と過度に落ち込み、自己肯定感を失ってしまいます。
しかし実際には、あなたの能力や人間性そのものが否定されているわけではありません。上司の威圧的な態度は、上司自身の不安やマネジメント力の欠如から来ていることが多く、あなたが原因ではなく、相手の振る舞いが許容ラインを超えているだけです。つまり「自分が悪い」という解釈は事実ではなく、歪んだ認知にすぎません。
こういうときは、「これは上司の問題であって、自分の価値とは関係ない」と言葉に出すことが効果的です。また、信頼できる同僚や友人に状況を話して客観的な意見を聞くと、「やっぱり自分だけの問題じゃなかった」と気づけることもあります。自分を責める思考を和らげることは、心を守るために欠かせないステップです。



僕も「自分がダメだから上司に怒られるんだ」と何度も思ってた。でも後で振り返ったら、同じ上司は他の人にも同じ態度をとってたんだよね。つまり“僕のせい”じゃなくて、その人のスタイルの問題だったんだ。そう気づいたとき、心がふっと軽くなったよ。
やす先輩の体験談
威圧的な上司に押しつぶされそうになった日々



僕もかつて「威圧的な上司」の下で働いていたことがあります。
毎日のように大きな声で怒鳴られ、細かいことまで詰められて、「お前は使えない」「なんでこんなこともできないんだ」と言われ続ける。
気づけば自分の存在を否定されているように感じて、会社に行くだけで胃が痛くなるようになりました。
ある日、朝の電車に乗ろうとしたとき、足がすくんで動けなくなったんです。「このまま会社に行ったら、自分は壊れるかもしれない」と本気で思いました。
夜は眠れず、休みの日も頭の中から上司の顔が消えない。心も体もすっかり追い込まれていました。
そんな状況を変えるきっかけになったのは、「記録を残す」という行動でした。上司に言われた言葉をノートにメモしておいたり、メールを保存したり。
最初は何の意味があるのかと思っていましたが、後から見返すと「自分が悪いんじゃない、相手の態度がおかしいんだ」と冷静に気づけるようになったんです。
そのうち、人事や信頼できる先輩に相談する勇気も出ました。証拠を見せながら話すと「これはパワハラに近い状況だ」と認めてもらえて、部署異動の話が出たんです。
すぐに解決したわけではありませんが、「相談してもいいんだ」と思えた瞬間から、気持ちはずいぶん楽になりました。
今振り返ると、あのときの経験があったから「自分を守る行動を取ることの大切さ」を強く学べました。
威圧的な上司の下で苦しんでいる人に伝えたいのは、「一人で抱え込まないでほしい」ということです。記録を残す、相談する、そして転職の準備を少しずつ進める。どれか一つでも行動すれば、必ず状況は変えられます。
上司が威圧的なときに現れるサイン
精神的なサイン
- 夜眠れない
- 気分の落ち込みが続く
- 仕事を考えると動悸や不安が強くなる
威圧的な上司の下で働き続けると、まず心に強いストレス反応が現れます。代表的なのは睡眠障害です。「夜になると考え込んで眠れない」「眠れても何度も目が覚める」など、睡眠の質が著しく低下します。休息が取れないことで疲労感が蓄積し、翌日の仕事にも支障が出てしまいます。
さらに、気分の落ち込みが慢性的に続くのも危険なサインです。「会社に行きたくない」「朝起きた瞬間に気分が沈む」といった状態が習慣化すると、軽いうつ症状につながる可能性があります。
もう一つ多いのが、動悸や不安感です。出社前や会議の直前になると心臓が早く打ち、呼吸が浅くなったり、冷や汗が出ることがあります。これは体が「危険から逃げたい」と訴えている証拠で、決して甘えではありません。



僕も朝の電車に乗るだけで動悸がして、途中下車したことがあるよ。最初は「自分が弱いんだ」と思ったけど、実際は体が限界を教えてくれてただけだったんだ。
身体的なサイン
- 胃痛や頭痛
- 肩こりや体のこわばり
- 朝起きられない
威圧的な上司と接する時間が続くと、心のストレスは必ず体に表れます。代表的なのは胃痛や頭痛です。上司の顔を見るだけで胃がキリキリする、会議の前になると偏頭痛が出る…こうした症状は心身のSOSサインです。薬で一時的に抑えることはできますが、根本的には環境を変えない限り改善しにくいのが特徴です。
また、常に緊張しているために肩こりや体のこわばりが慢性化する人も多いです。呼吸が浅くなり、自律神経が乱れることで「休んでいるのに疲れが取れない」状態になります。さらに悪化すると、朝になってもベッドから起き上がれない、体が重く動かないといった深刻な状態に発展することもあります。こうした体の不調は、精神的ストレスが限界に近づいているサインと受け止めるべきです。



僕もある時期、毎朝胃薬を飲むのが習慣になってた。気合いじゃ治らなかったんだよね。医者に「ストレス性」と言われて初めて、これは環境の問題だと気づけたんだ。
行動的なサイン
- 遅刻や欠勤が増える
- 家に帰ってから何もできない
- 友人や家族との交流が減る
心と体が追い込まれていくと、行動面にも変化が出てきます。例えば遅刻や欠勤が増えるのは典型的なサインです。「会社に行こうとすると体が動かない」「駅の改札で足が止まる」といった経験をする人もいます。これは怠けではなく、体が危険を回避しようとしている自然な反応です。
また、仕事が終わって家に帰っても、疲れ果てて何もできない。趣味や好きなことに手をつける気力が湧かず、ただ横になって時間が過ぎる。こうした状態が続くと、生活の充実感が失われ、さらに気持ちが落ち込みやすくなります。さらに深刻なのは、家族や友人との交流が減ってしまうことです。人とのつながりを断ってしまうと、自分を支えてくれるはずの大切な存在からも遠ざかり、孤独感が強まります。



僕も当時は、仕事が終わったら家でひたすら寝るだけ。友達の誘いも断り続けて、人間関係まで細くなってたんだ。今思えば、あれは完全に「限界サイン」だった。
今すぐできる現実的な対処法


距離を作る
威圧的な上司と日常的に接していると、知らず知らずのうちに心と体がすり減ってしまいます。だからこそ、まず取り組みたいのが「距離をつくる」という意識です。もし会社がリモート勤務や席替えに柔軟であれば、業務に支障が出ていることを理由に相談すると受け入れられやすいでしょう。直接的に「上司が嫌だから」と言わなくても、作業効率や体調面を切り口にすれば交渉しやすくなります。
物理的な距離を取ることが難しい場合は、心理的な距離を置く工夫が必要です。例えば、勤務時間外は通知をオフにする、帰宅後はパソコンを開かない、家族や友人との会話で上司の話題を避けるなど、生活の中に境界線を引くことです。また、趣味や運動、日記など「自分の世界に集中できる時間」を持つことは、意識を上司から切り離す有効な方法になります。
上司を意識する時間が少なくなると、思っている以上に心が軽くなります。「あの人のことばかり考えて1日が終わってしまう」という悪循環から抜け出すためにも、小さな遮断習慣を積み重ねていきましょう。



僕も当時は、家に帰ってからも上司の顔や言葉が頭から離れなかった。だけど“家ではスマホを別の部屋に置く”だけで、気持ちが少しラクになったよ。小さな習慣が積もると、心の余白が戻ってくるんだ。
記録を残す
威圧的な上司の言動は、その場では「ただ嫌な気分」で終わってしまいがちですが、必ず記録に残すことが重要です。なぜなら、証拠がなければ後で相談や交渉をしても「言った・言わない」の水掛け論で終わってしまうからです。ノートに発言内容や日時をメモするだけでも立派な証拠になりますし、メールやチャットはフォルダ分けして保管、必要に応じてスクリーンショットを残しておきましょう。
また、言葉だけでなく上司の態度や状況も添えるとより有効です。例えば「会議中に大声で叱責された」「周囲の社員が黙り込んでいた」といった記録があると、外部相談機関や人事に伝える際に具体性が増します。スマホの録音機能を活用する人もいますが、法的な扱いは微妙なため、まずは文字・画像での記録を基本にするのがおすすめです。
記録を残すことは、単に「証拠を集める」だけでなく、自分の気持ちを客観視する作業にもつながります。「やっぱり自分が悪いんじゃないか」という思考から抜け出すきっかけにもなるので、精神的なセルフケアの意味でも効果がありますよ。



僕も当時「こんなの書き残しても意味あるかな」と思ったけど、後から見返したときに「やっぱり自分じゃなくて上司がおかしい」と気づけた。あの瞬間に、気持ちが少しラクになったんだ。
相談窓口を利用する
上司の威圧的な態度に悩んでいるとき、「こんなことで相談しても大げさかな」と感じてしまう人は多いです。でも、相談はあなたの正当な権利であり、決して恥ずかしいことではありません。まずは社内の人事部やコンプライアンス部署に事実ベースで伝えるのが第一歩です。感情的に「つらい」と言うよりも、「◯月◯日にこういう発言があった」と具体的に話すことで、受け止めてもらいやすくなります。
社内で解決が難しい場合は、労働局の総合労働相談コーナーや、弁護士の無料相談を利用するのも有効です。外部の窓口は、匿名で相談できたり、法的にどう対応すべきかを客観的に教えてくれるので心強い存在になります。どんなに小さな出来事でも、あなたがつらいと感じた時点で十分相談する理由になるのです。



僕も最初は「自分が弱いだけなんじゃないか」と思って黙ってた。でも人事に事実を伝えたら、意外と早く動いてくれた。外の相談機関に話を聞いてもらっただけでも、「一人じゃない」と安心できたよ。
辞めたいと思ったらやっておきたい準備
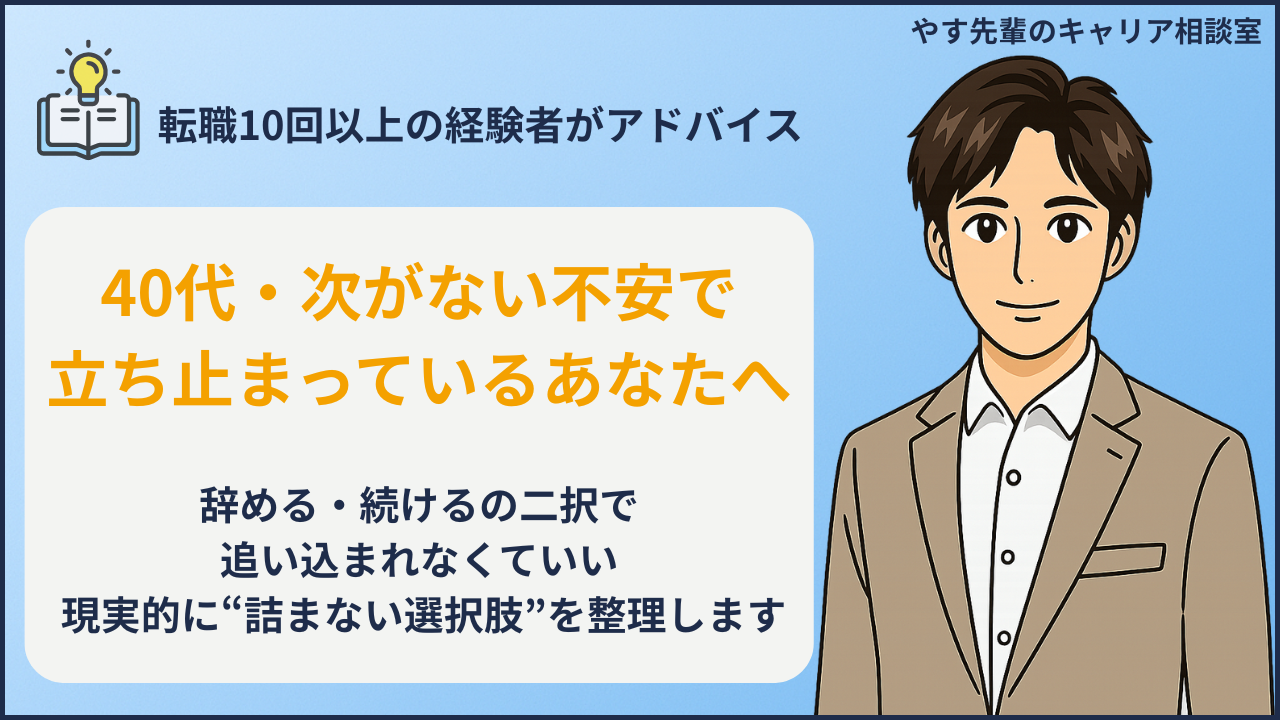
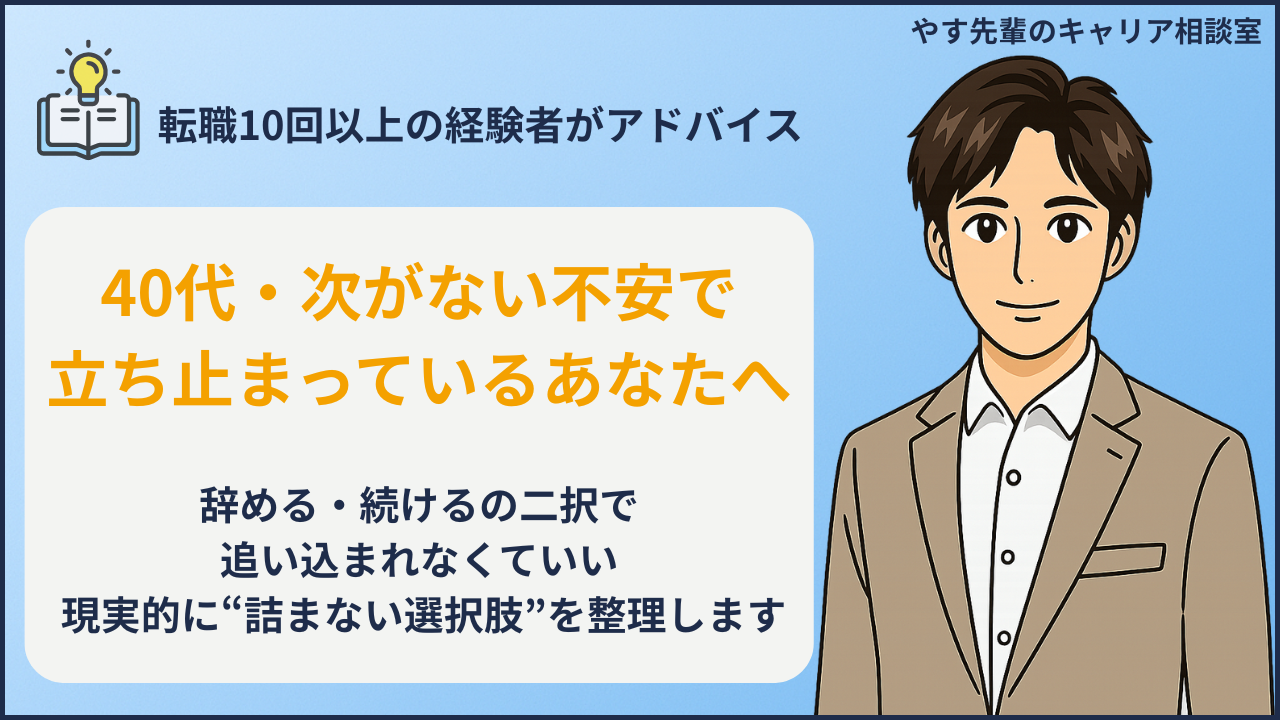
市場価値を把握する
「もう限界だから辞めたい」と思ったときにまず大事なのは、感情的に動く前に自分の市場価値を客観的に把握することです。これをしないまま転職活動を始めると、「どんな求人に応募すればいいのか」「自分の希望年収は妥当なのか」が分からず、選択を誤ってしまう可能性があります。
例えば、ミイダス市場価値診断を使えば、これまでの経験やスキルを入力するだけで想定年収レンジや強みが数値化されます。診断結果は職務経歴書のアピールポイントにそのまま活用できますし、「自分にはこんな強みがあったんだ」と気づくきっかけにもなります。実際に僕も診断を受けたときは、思っていた以上に市場価値が高く出て、自信を取り戻せた経験があります。
また、数字として客観的なデータを得ておくことで、エージェントと年収交渉するときにも説得力が増します。「業界平均よりも自分は高めに評価されている」と分かれば、無理に妥協せずに交渉できる材料になります。
威圧的な上司から逃げたい気持ちが強いときこそ、「辞めた後にどう動けるか」を冷静に把握することが心の支えになります。まずは市場価値診断で現実を数値として確認し、次の一歩につなげましょう。



僕も最初の転職は「辞めたい一心」で突っ走って失敗した。けど、市場価値を確認してから動いた転職は、自信を持って年収交渉までできたよ。数字で裏付けがあると、気持ちが全然違うんだ。
転職先の実態を調べる
求人票に書かれている条件は、あくまで表面的な情報にすぎません。年収や福利厚生、休日数は見えても、実際の上司がどんなタイプなのか、職場の雰囲気がどうなのかまでは分かりません。ここを見落とすと「条件は良いのに人間関係でまた失敗した」というケースに陥りやすいのです。
そこで役立つのが OpenWorkの口コミ です。現場社員や元社員が匿名で投稿しているため、実際の働き方やマネジメントスタイル、残業の実態、社風などに踏み込んだ情報を得られます。特に、「上司との関係性」や「評価制度」に関する口コミは要チェックです。面接だけでは分からないリアルな情報を補ってくれるので、ミスマッチを防ぐ強力な手がかりになります。
また、口コミは一件だけを鵜呑みにせず、複数を見比べて「共通して書かれている点」を重視することが大切です。ポジティブ・ネガティブ両方の意見を参考にすれば、転職先の全体像が立体的に見えてきます。求人票と口コミを照らし合わせて「自分に合うかどうか」を判断すれば、次の職場で同じ失敗を繰り返すリスクを大幅に減らせるでしょう。



僕も昔は求人票だけで決めて失敗したけど、OpenWorkで「実際は残業が多い」とか「上司が放任型」と知って助かったことがあるよ。条件だけじゃなくて、中の雰囲気まで調べるのは本当に大事だね。
書類・面接の準備
「辞めたい」と思って転職活動を始めても、多くの20代がつまずくのが書類作成や面接準備です。職務経歴書や自己PRは「何を書けばいいのか分からない」と悩む人も多いでしょうし、面接では緊張して自分の強みをうまく伝えられないケースも少なくありません。
そんなときに頼りになるのが マイナビジョブ20’s です。20代に特化した転職支援サービスなので、まだ経験が浅い人でも安心して利用できます。特におすすめできるポイントは次の通りです。
- 職務経歴書・履歴書の添削:強みが伝わる表現に修正してくれる
- 模擬面接のサポート:質問にどう答えれば印象が良くなるか具体的に指導
- 未経験歓迎求人が豊富:ポテンシャル採用に強い
- 適性診断で自分に合う業界を提案:書類作成に直結する強み分析が可能
自分一人で悩むよりも、プロのサポートを受けて仕上げた方が、書類の通過率や面接の成功率は大きく変わります。「実力不足だから…」と落ち込んでいる人ほど、まずは相談してみてほしいです。



僕も20代のころ、自己PRが空回りして面接で落ちまくった。でもキャリアアドバイザーに「ここを強調しよう」と指導を受けてから一気に通過率が上がったよ。やっぱりプロの視点は強い!
退職を切り出すときの注意点


円満退職を目指す場合
- 直属上司にまずは口頭で伝える
- 退職届は書面で提出する
- 引き継ぎ資料を作っておく
威圧的な上司が相手でも、可能であれば波風を立てずに退職できるに越したことはありません。トラブルを避け、社内人脈を将来に活かすためにも「円満退職」を意識して進めましょう。
まずは、直属の上司に口頭で退職の意向を伝えるのが基本です。このとき感情的な理由ではなく「体調不良」「キャリアチェンジ」など、客観的かつ前向きに受け取られやすい理由を用いるとスムーズです。次に、退職届を正式に書面で提出します。口頭だけでは撤回されたり握り潰されたりする可能性があるため、必ず文書で残すことが大切です。
さらに、引き継ぎ資料を作っておくと信頼度がぐっと上がります。仕事内容、担当案件の進捗、取引先の連絡先などを整理し、後任が困らないようにまとめておきましょう。これにより「最後まで責任を持った人」という印象を残すことができ、辞めた後の評価にもつながります。



僕も退職するとき、正直「早く辞めたい」一心だったけど、引き継ぎだけは丁寧にやった。そしたら意外と「ありがとう」と言ってくれる人が多くて、救われた気持ちになったよ。最後の印象って意外と残るものなんだ。
トラブルを避けたい場合
- 有給休暇の取得を計画的に進める
- 残業代・退職金の確認
- 感情的なやり取りは避け、事実だけを伝える
退職の場面では感情的なやり取りやお金の問題が絡みやすく、思わぬトラブルに発展することもあります。余計な摩擦を減らすためには、あらかじめ冷静に準備しておくことが大切です。
まずは有給休暇の取得を計画的に進めることです。退職が決まった後にまとめて申請すると「引き継ぎが終わらない」と揉めることもあります。できるだけ早めに申請し、上司や人事とすり合わせて、スムーズに消化できるように段取りを組みましょう。
次に、残業代や退職金などの未払いがないかを確認することも重要です。特に威圧的な上司の下では、サービス残業が常態化しているケースもあります。給与明細や勤怠記録を確認し、不明点があれば人事や労務担当に直接聞いておくのが安心です。トラブルが発覚した後に交渉するよりも、事前に確認しておく方がはるかにスムーズです。
そして何より大事なのは、感情的なやり取りを避け、事実だけを伝えることです。威圧的な上司と最後まで衝突すると「辞めたのに後味が悪い」状態になりやすいので、「◯月末で退職します」「引き継ぎ資料はこの内容です」と淡々と伝える姿勢を心がけましょう。必要ならメールや書面で残しておくと、余計な言い争いを防げます。



僕も昔、感情的にぶつかって余計にこじれた経験があるんだ。その時に学んだのは、「感情は持ち帰って、事実だけを置いてくる」ってこと。そっちの方が自分も消耗せずに済むよ。
退職代行という選択肢
どうしても自分で上司に伝えるのが難しい場合、退職代行サービスを使うのは立派な選択肢です。特に、威圧的な上司が相手だと「切り出すこと自体が精神的に不可能」というケースもあります。そのまま無理をして体調を崩すくらいなら、専門サービスの力を借りてでも退職の一歩を踏み出した方が、結果的に自分を守ることにつながります。
ただし、サービス選びには注意が必要です。最近は退職代行業者が増えているため、中には法的知識が不十分なところもあります。おすすめは、弁護士が監修・運営しているサービスを選ぶこと。違法性のリスクを避けられるだけでなく、未払い残業代や有給消化などの交渉にも強いので安心感が違います。
費用は数万円程度が一般的で、即日対応してくれる業者も多いです。会社に出向かずに退職手続きが進むので、「もう明日から会社に行きたくない」という切羽詰まった状況でも利用できます。実際、退職代行を利用したからといって次の転職活動に不利になるケースはほとんどありません。



僕も一度、どうしても退職を切り出せずに苦しんだときがあった。結局は第三者の力を借りて辞めたけど、それで心身が守られて次の転職に集中できた。逃げじゃなくて、“守りの戦略”だと思っていいんだよ。
辞めたあとの不安を減らすには
転職した後の生活やキャリアが不安で、一歩が踏み出せない人も多いです。
そんなときは、以下の準備をしておくと安心できます。
- 生活費の確保:失業保険や貯金を計算して、最低3か月の生活費を見積もる
- キャリアの棚卸し:これまでの経験をリスト化して、「次の職場でどう活かすか」を整理
- 支えを作る:家族や友人、信頼できる人に転職活動のことを話しておく
「この上司のもとではもう無理だ」と思っても、次の一歩を踏み出す勇気が出ないのは自然なことです。「生活は大丈夫か」「転職先でまた失敗しないか」と不安が膨らみやすいもの。でも、事前に準備をしておくことで不安は大きく和らぎます。
まずは生活費の確保です。失業保険の給付額や期間を確認し、貯金と合わせて「最低3か月は生活できる」ラインを計算しましょう。これだけでも「もし転職先がすぐに決まらなくても生きていける」という安心感につながります。
次にキャリアの棚卸しです。これまで経験してきた業務や成果を一度リスト化し、「自分はどんなスキルを持っていて、次の職場でどう活かせるか」を整理しましょう。この作業は自己PRの基礎になるだけでなく、「自分はまだ戦える」という自信にもつながります。
そして、支えを作ることも大切です。家族や信頼できる友人に転職活動のことを話しておくだけで、孤独感はぐっと減ります。また、同じように転職を経験した人から体験談を聞けると、現実的な安心材料にもなります。



僕も最初の転職では「路頭に迷ったらどうしよう」と毎日不安で眠れなかった。でも生活費を計算して、キャリアを整理して、友人に相談したら「意外となんとかなるかも」と思えたんだ。準備って、不安を小さくする薬みたいなものだよ。
まとめ|「辞めたい」は次の一歩の合図
威圧的な上司に毎日さらされていれば、「辞めたい」と思うのは当然です。
それは弱さではなく、限界を知らせるサインです。
まずは応急処置として距離を取り、記録を残しながら相談できる場所を確保しましょう。
そして少しずつ転職の準備を進めれば、「逃げる」ではなく「次に進む」選択ができるようになります。
今日できるのはひとつだけでいい。小さな行動を積み重ねて、自分の未来を守っていきましょう。
よくある質問
- 上司の威圧的な態度はパワハラになりますか?
-
反復・継続して精神的苦痛を与える行為はパワハラに該当する可能性が高いです。記録を残して専門機関に相談しましょう。
- 辞める前に必ずやるべきことは?
-
市場価値診断、転職先の口コミ確認、最低限の生活費確保。この3つを済ませてから辞めるのがおすすめです。
- 退職代行を使ったら次の転職に不利になりますか?
-
基本的に採用側は退職理由の詳細までは把握しません。不利になることはほとんどありません。
- 転職活動と並行して心療内科に通っても大丈夫ですか?
-
問題ありません。むしろ診断書があれば転職活動の説明にも使える場合があります。