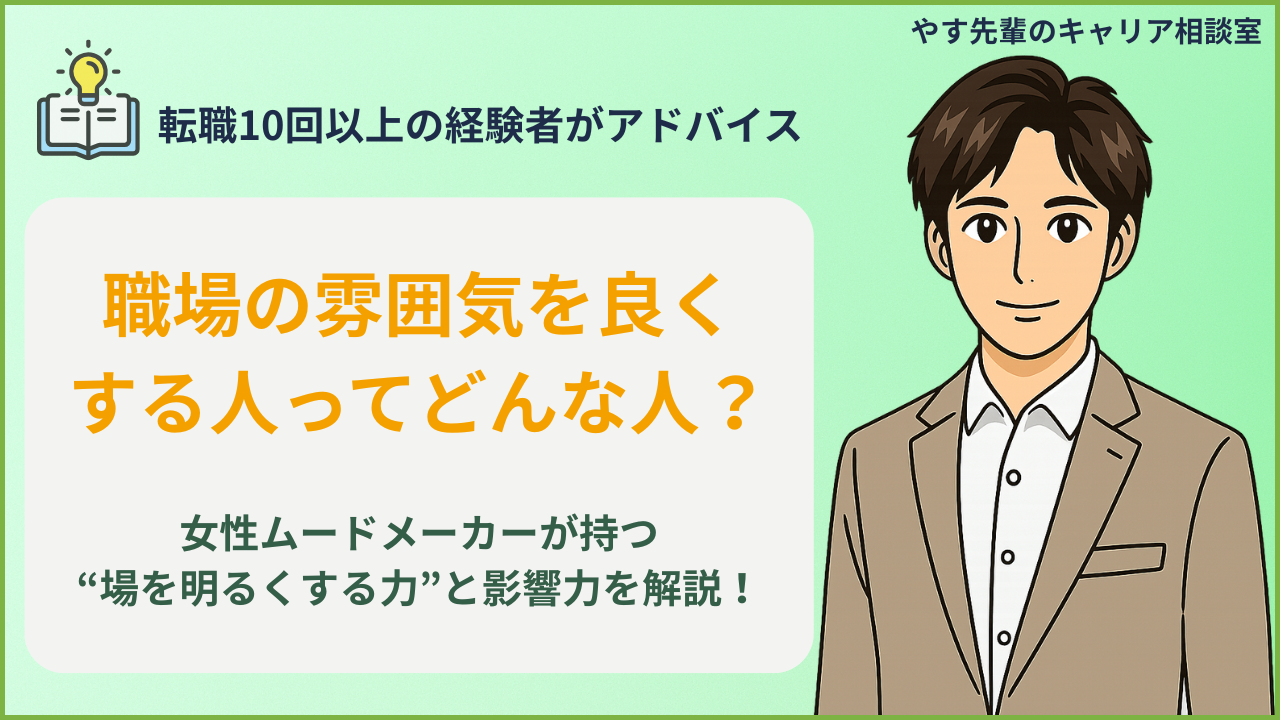やす先輩
やす先輩40代半ば、転職10回の管理職。上場もベンチャーもブラックも経験してきました。失敗も学びも交えながら、キャリアや働き方に悩むあなたへ“現実的な解決策”を届けます。
⇒詳しいプロフィール
「この職場、なんだか雰囲気が悪いな…」
そう感じるとき、実は職場には「雰囲気を悪くする人」もいれば、「職場の雰囲気を良くする人」もいます。結論から言えば、良い雰囲気を作る人の存在はチームの働きやすさや成果に直結し、あなた自身がそうなれる工夫もあります。
なぜなら、職場の空気は人の行動や態度によって大きく左右されるからです。
- 嫌な仕事を率先してこなす
- ミスした人をさりげなくフォローする
- 冗談で重い空気を和ませる
こうした人がいるだけで、チームは自然と前向きになります。
逆に、雰囲気を悪くする人に囲まれてばかりでは、自分まで疲弊してしまいます。そんなときは「自分が雰囲気を良くする人になる」か、思い切って「雰囲気の良い職場に移る」という選択肢も大切です。
この記事では、職場の雰囲気を良くする人の特徴や習慣、悪くする人との違い、そして良い雰囲気の会社で働くための方法まで解説します。最後には市場価値診断や転職エージェントも紹介するので、今の環境に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
職場の雰囲気を良くする人の特徴はこれ!
職場の雰囲気は、そこにいる人のちょっとした言動で大きく左右されます。特に「職場の雰囲気を良くする人」とは、目立つ成果をあげる人よりも、日常の小さな場面で周囲を助け、気持ちを和ませることができる人のことを指します。
例えば、嫌がられる雑務を引き受けたり、失敗した同僚をさりげなく励ましたり、誰の味方にもなれる姿勢を貫いたり。そうした行動は評価されにくいですが、実際にはチーム全体の空気を変える大きな力を持っています。ここでは、そんな人たちの具体的な特徴を紹介します。
同僚が嫌がる仕事を率先してやってくれる人
「誰もやりたがらない雑務」を率先して引き受ける人は、職場で自然と信頼を集めます。コピーや備品の補充、掃除や片付け、資料の下準備などは、地味で評価されにくいものの、確実に職場全体を支えている仕事です。これらを自ら進んでやる人がいると、他のメンバーは気持ちよく業務に集中でき、感謝や尊敬の念が生まれます。
- 自分に直接利益のない仕事を快く引き受ける
- 「やっておきますよ」と声をかけてくれる
- 雑務をこなす姿勢が周囲のモチベーションを上げる
- 自然に「信頼できる人」という評価につながる
このような姿勢は、職場の雰囲気を明るく、協力的な空気に変えていく原動力となります。



嫌がられる雑務を進んでやる人は本当に貴重。周囲が“ありがとう”と言える空気が生まれるんですよね。
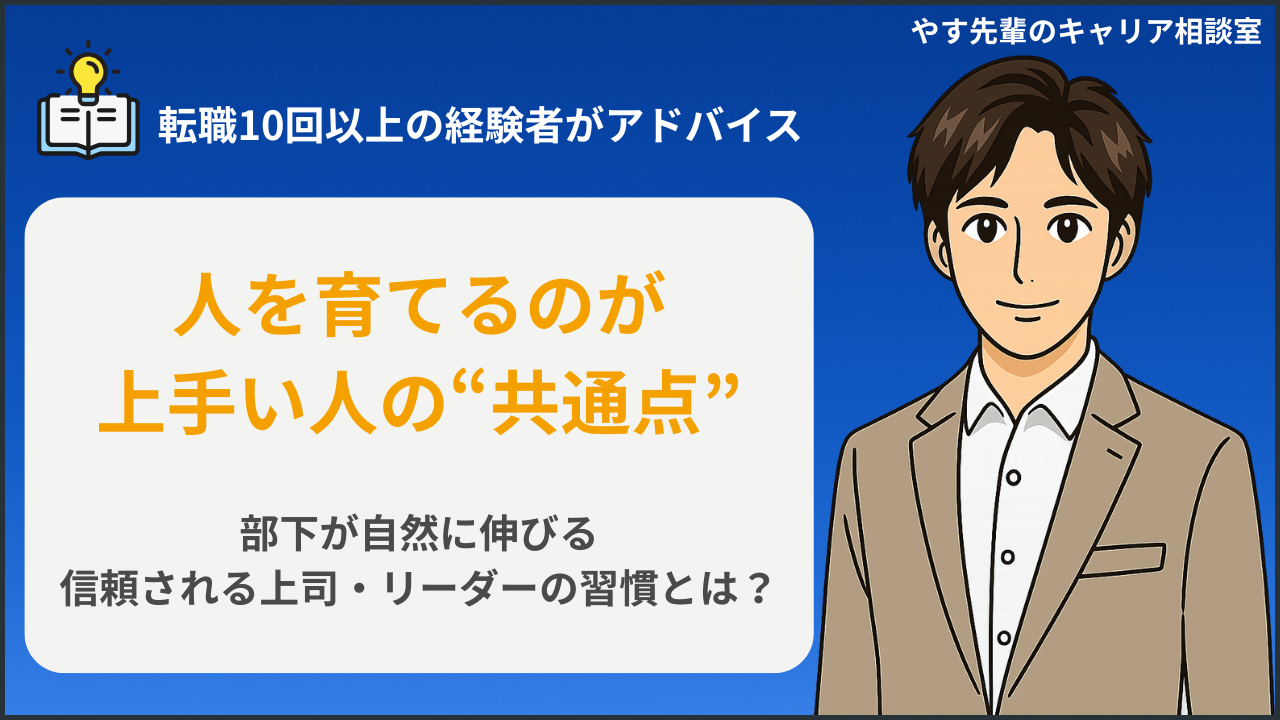
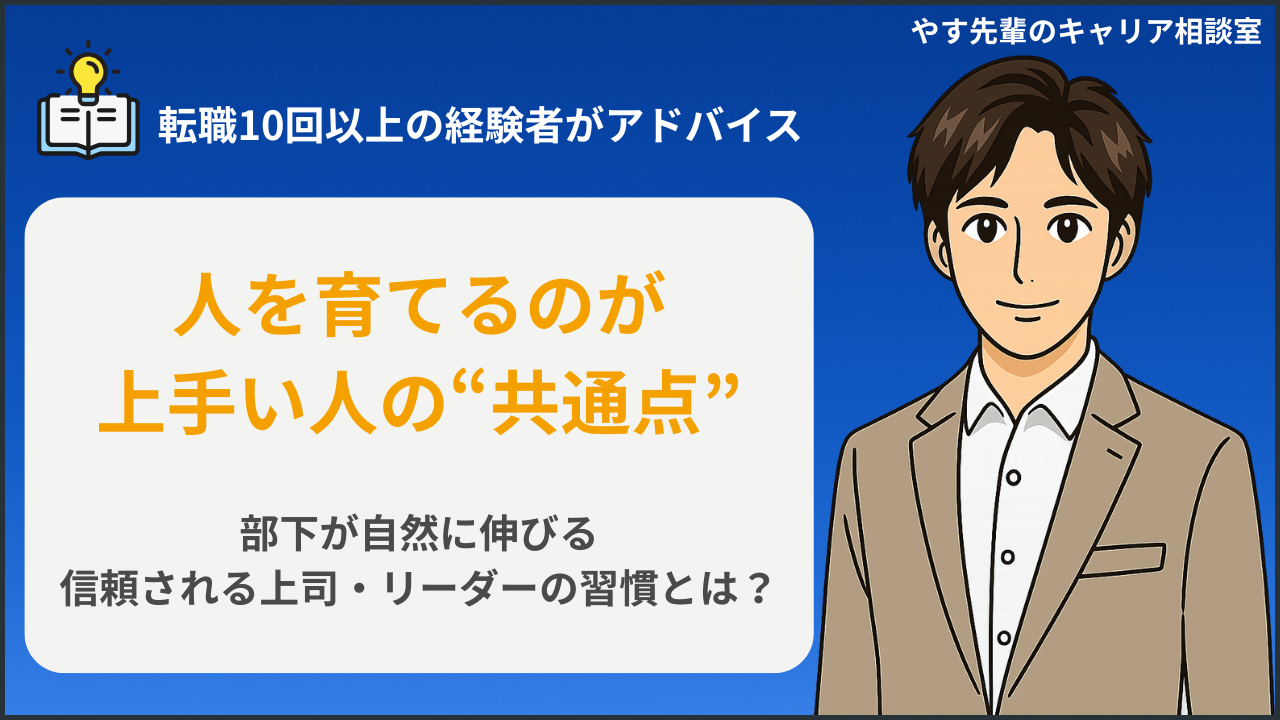
仕事でミスした人を精神的にケアできる人
仕事のミスは誰にでも起こり得ますが、その後のフォローによって雰囲気は大きく変わります。失敗した人を責め立てるのではなく、精神的にケアできる人がいると、安心感が広がり、チームは健全な空気を保てます。例えば「誰にでもあることだから気にしないで」と声をかける、解決策を一緒に考える、あるいは冗談を交えて相手を和ませるなど、ほんの少しの気遣いで救われる人は多いのです。
- ミスを責めずに寄り添える
- 「一緒に挽回しよう」という姿勢を示す
- 相手の自尊心を傷つけないよう言葉を選ぶ
- ネガティブを前向きに変えるムードメーカー
こうした行動は、失敗を恐れず挑戦できる職場文化をつくり、長期的には組織の成長につながります。



僕も新人の頃に大きなミスをしました。その時“気にすんな”と励ましてくれた先輩のおかげで立ち直れたんです。
いつも中立で攻撃的な発言をしない人
職場には、対立を煽る人や一方的に誰かを批判する人もいます。そうした空気を和らげるのが、いつも中立で冷静に発言できる人です。攻撃的な発言をせず、むしろ双方の意見を整理して橋渡しする役割を担う人は、チームに安心感を与えます。特に会議やトラブルの場面で「どちらの意見にも一理ある」と認めつつ、前向きな解決策に導く姿勢はとても重要です。
- 感情的にならず冷静に話を聞ける
- 対立した両者の間に立ち、公平な立場で調整する
- 否定よりも肯定をベースに発言する
- 結果的に「この人がいると場が落ち着く」と信頼される
このような人の存在は、無用な摩擦を避け、安心して意見交換ができる土壌をつくります。



どちらにも偏らず冷静に場をまとめる人は、信頼されやすいですよね。攻撃的じゃない人の安心感は大きいです。


職場の雰囲気を良くする女性の魅力
職場で「雰囲気を良くする人」と聞くと、自然に女性を思い浮かべる人も多いでしょう。特に親しみやすく、明るく、周囲を笑顔にできる女性は、チームに大きな安心感をもたらします。彼女たちは必ずしも特別なスキルを持っているわけではありません。ちょっとした気配りや愛嬌、自然な笑顔が人の気持ちを和ませ、職場の空気を変えていくのです。ここでは、職場の雰囲気を良くする女性の具体的な魅力を掘り下げます。
親しみやすく愛嬌のある女性の存在感
親しみやすさや愛嬌は、職場において大きな力を持ちます。声をかけやすい、笑顔で接してくれる、冗談を交えながら場を和ませてくれる。そんな女性がいると、自然にコミュニケーションのハードルが下がります。特に新人や内向的な社員にとっては「話しかけても大丈夫だ」と思える人がいることは心強いものです。
- 明るい挨拶で場を柔らかくする
- 笑顔や相槌で会話をスムーズにする
- 誰にでもフラットに接することで安心感を与える
- ちょっとしたユーモアで気まずい空気を和ませる
愛嬌のある人の存在は「安心して働ける職場」をつくる基盤となります。



親しみやすさや愛嬌はスキル以上に職場を明るくします。自然体で接してくれる人は本当にありがたいですね。
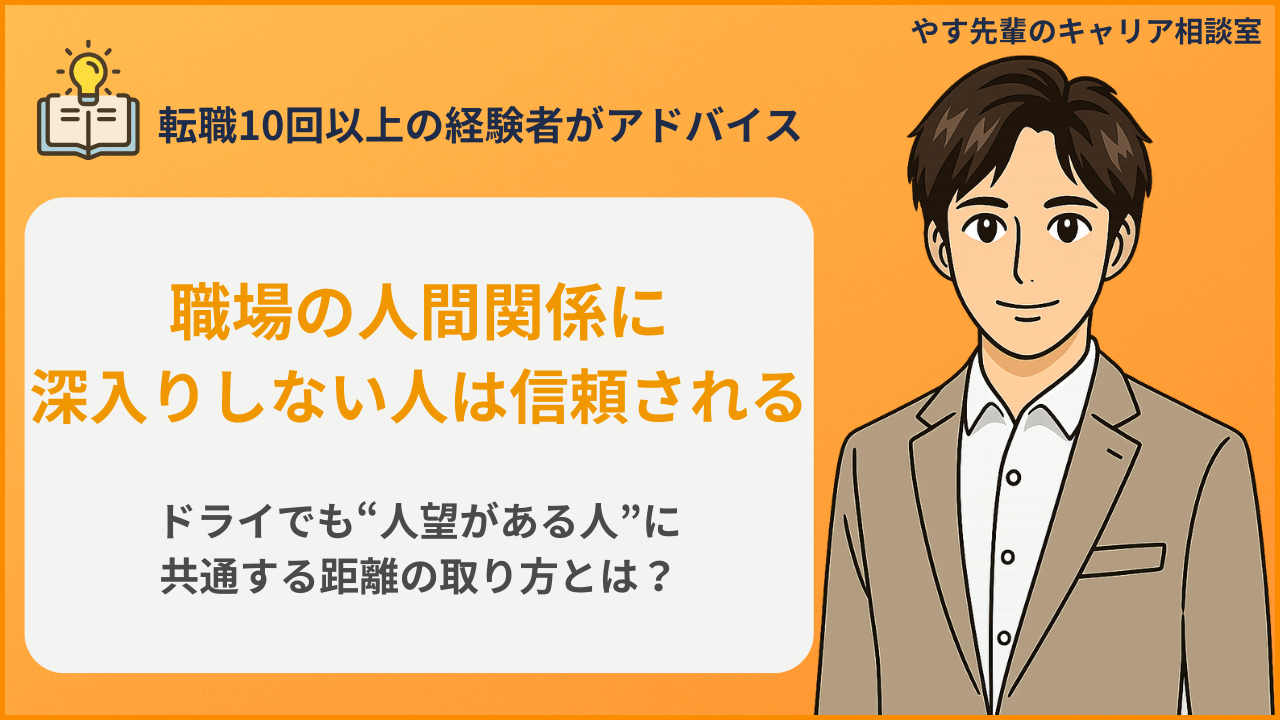
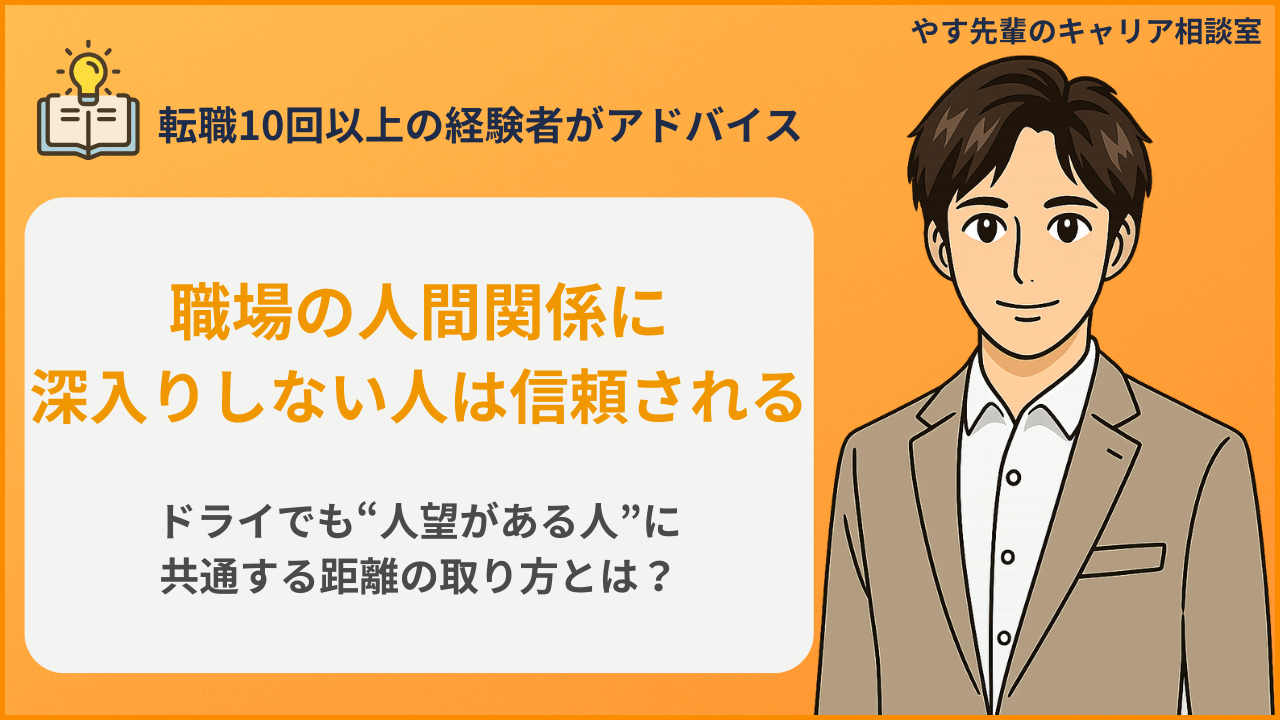
明るい女性は場を和ませて周りを笑顔にする
明るい性格の女性が職場にいるだけで、重苦しい空気が一気に和らぎます。特に仕事で行き詰まっているときや、チーム全体が疲れているときに「ちょっとした冗談」や「前向きな声かけ」をしてくれる人は貴重です。彼女たちの存在は、周囲の人に安心感を与え、自然と笑顔を引き出します。
- 場が沈んでいるときに声をかける
- 失敗した同僚を笑顔で励ます
- 前向きな言葉でモチベーションを支える
- 自分自身も楽しそうに働く姿を見せる
明るさは周囲に伝染します。こうした女性は「太陽みたいな人」と表現されることも多く、その場全体を和ませる効果を持っています。



明るい人の笑顔は本当に伝染します。落ち込んでいた空気が一瞬で和らいだ経験、僕もたくさんあります。
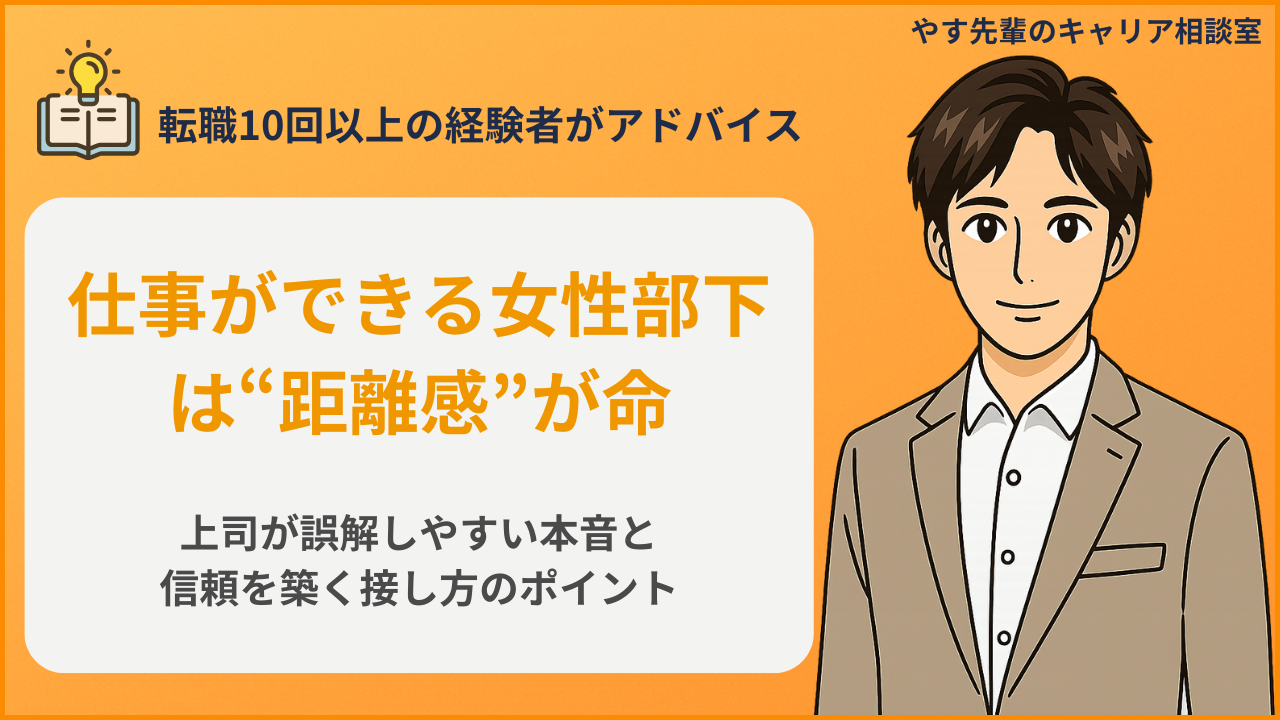
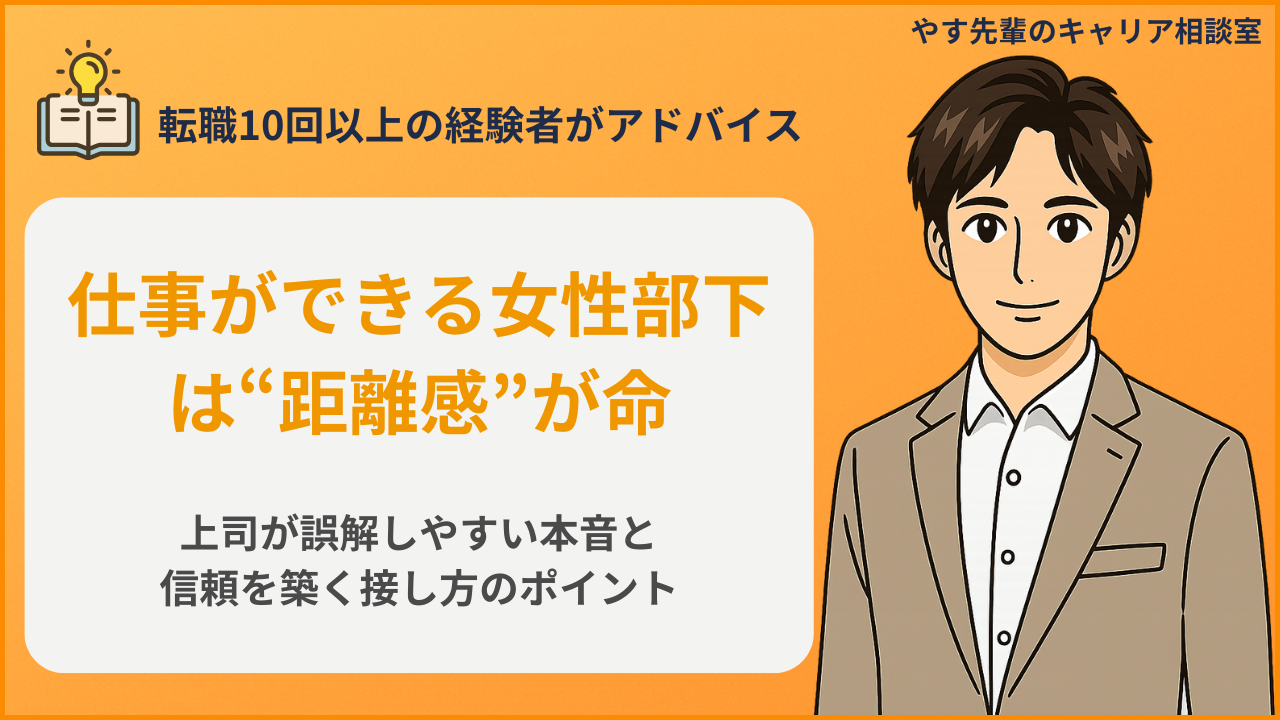
愛嬌のある女性がいると上司が温厚になる理由
愛嬌のある女性がいることで、上司の態度が柔らかくなることがあります。これは決して媚びではなく、周囲を自然に和ませる力が働いているからです。上司も人間ですから、職場の雰囲気に大きく影響されます。険悪なムードでは感情的になりやすいですが、笑顔や愛嬌のある雰囲気が広がれば、自然と指導や会話のトーンも穏やかになるのです。
- 部下とのやり取りが円滑になる
- 上司自身も安心して会話できる
- 叱責よりも建設的な指導が増える
- 職場全体の人間関係が良くなる
つまり、愛嬌のある女性は「上司をも優しくする力」を持ち、職場全体に良い連鎖をもたらします。



上司だって雰囲気に影響されます。愛嬌ある人がいると、場が柔らかくなり自然と声のトーンまで変わるんですよね。


職場が和むのは女性ムードメーカーのおかげだという理由
職場が和む背景には、女性ムードメーカーの存在があることが多いです。彼女たちは特別にリーダーシップをとるわけではなくても、雑談や笑顔、さりげないサポートで雰囲気を支えています。その姿勢が自然とチームの安心感を生み、緊張やストレスを和らげているのです。
- 会話のきっかけをつくってくれる
- 相手の気持ちを察して場を調整する
- 「一緒に頑張ろう」と自然に励ます
- その場にいるだけで緊張を和らげる
このように、女性ムードメーカーは目立たないところで雰囲気を調整し、チームを円滑にする影響力を持っています。



女性ムードメーカーがいると本当に場が和みます。派手なことをしなくても“安心できる空気”を作れるんですよね。
職場の雰囲気を良くする男性の特徴
職場の雰囲気を良くするのは女性だけではありません。男性にも、場を盛り上げたり安心感を与えたりできる人が存在します。特に「声が大きくいつも前向き」「冗談で重い空気を和ませる」「人の気持ちを察して代弁できる」などの行動は、チームに活力をもたらします。ここでは、そんな男性の特徴を具体的に解説していきます。
声が大きくいつも前向きな男性
職場でよく響く大きな声は、それだけで雰囲気を活気づける効果があります。もちろんただ声が大きいだけでは逆効果になりかねませんが、そこに「前向きさ」が加わると、一気に職場の空気が明るくなるのです。朝の挨拶をハキハキとする、会議で積極的に意見を出す、成果が出たらチームを称賛する。こうした姿勢は周囲の士気を高め、「自分も頑張ろう」という連鎖を生み出します。
- 朝の挨拶でチーム全体を活気づける
- 積極的に意見を述べて前向きな空気をつくる
- 小さな成果でもチームで喜びを共有する
- ネガティブ発言をポジティブに変換できる
声が大きく、常にポジティブな男性の存在は、まさに「エンジン」のようにチームを動かしてくれるのです。



前向きで声の大きい人がいると、自然と職場に勢いが出ますよね。暗い空気を吹き飛ばす力は本当に大きいです。


重い空気のときでも冗談を言って笑わせてくれる人
トラブルや失敗で職場の空気が沈んでいるとき、軽い冗談で笑いを生む人は貴重です。冗談といっても、誰かを傷つけるものではなく「場の重さを取り除くためのユーモア」であることがポイントです。会議で険悪なムードになったときに一言で和ませたり、ミスをした同僚をさりげなくフォローしたり。そうした一瞬の笑いが、空気をリセットしてくれます。
- 失敗や緊張を和らげるユーモアを持つ
- 相手を傷つけずに笑いを提供する
- 会議や打ち合わせで緊張をほぐす役割を果たす
- 困難な場面でも前向きな雰囲気に変える
ユーモアは人間関係を円滑にする最高の潤滑油です。笑いがある職場には、自然と協力や安心感が生まれます。



冗談を交えて場を和ませる人がいると、自然と息抜きできます。笑いがあるだけで、空気がガラッと変わるんですよね。
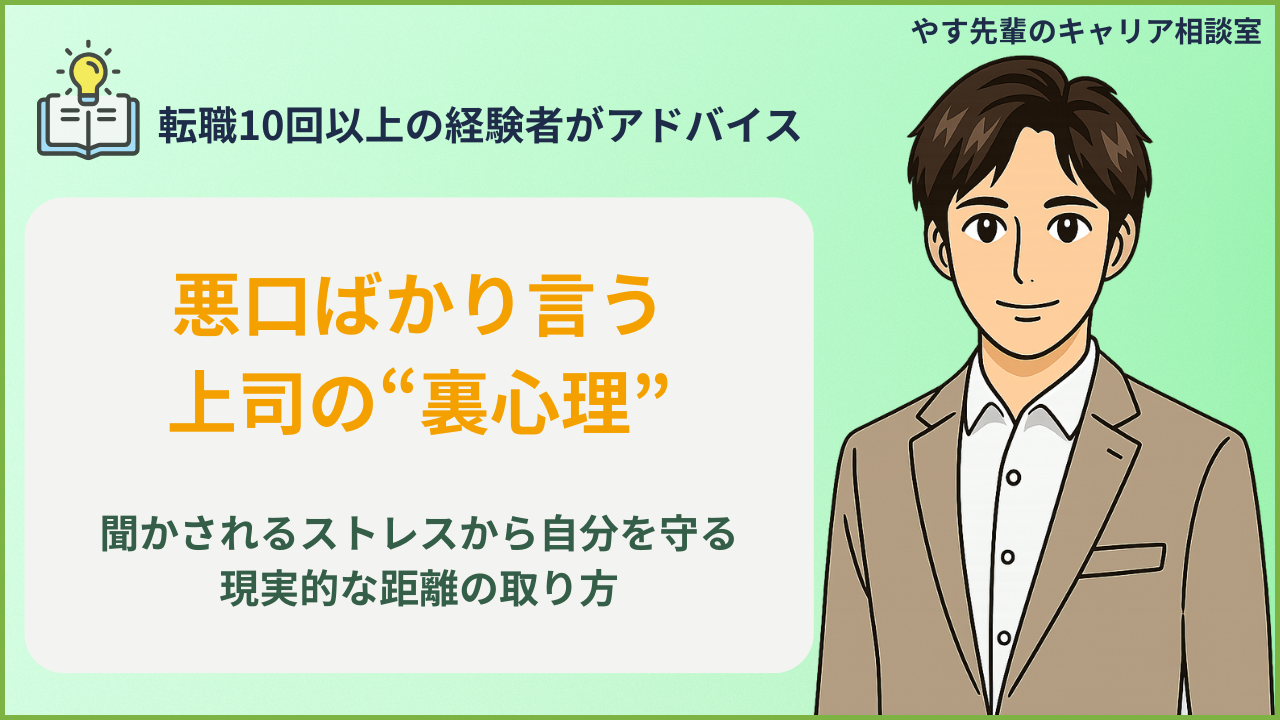
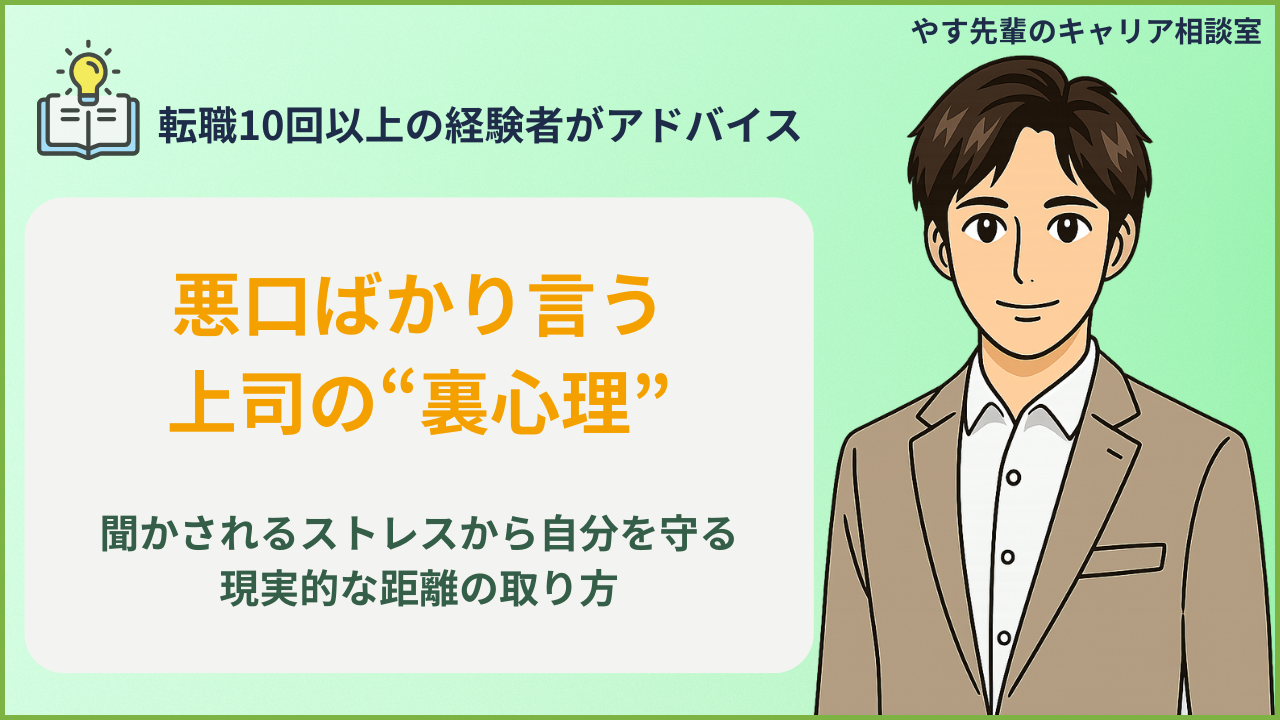
人の気持ちを察して言いにくいことを代弁できる人
多くの人が感じていても口に出せないことを、代わりにうまく表現してくれる人は、職場の雰囲気を良くする大きな存在です。例えば「このスケジュールだと厳しいのでは?」とみんなが思っているのに言えない場面で、勇気を持って代弁できる人がいれば、チーム全体が救われます。相手を傷つけず、場の空気を壊さない言い方をできることがポイントです。
- 多くの人が思っていることを言葉にできる
- 言いにくいことを柔らかい表現で伝える
- チームの声をまとめて上司に届ける
- 「代弁してくれてありがとう」と感謝される存在
こうした人は、心理的安全性を高め、職場に安心して発言できる環境を築く大きな力になります。



代弁してくれる人がいると、“自分だけじゃなかった”と安心できます。勇気を出して言える人は本当にありがたいですね。
ムードメーカーの存在と職場への影響
職場において「ムードメーカー」と呼ばれる人は、目立つ役職やスキルを持っていなくても、チーム全体に欠かせない存在です。彼らは明るさやユーモアで場を和ませるだけでなく、困難な状況を乗り越えるための空気づくりにも貢献します。組織の中で評価されにくい部分ではありますが、心理的安全性やチームワークを考えたとき、その役割の大きさは計り知れません。ここでは、ムードメーカーの存在が職場に与える影響を具体的に見ていきます。
会社のムードメーカーが辞めるとどうなる?
会社のムードメーカーが辞めると、職場の雰囲気は一気に変わります。冗談や明るい声かけがなくなり、以前より静かで重い空気が漂うようになるケースも少なくありません。特に、日常的に場を和ませていた人がいなくなると「自分たちで盛り上げなきゃ」と意識する人が減り、気づけばギスギスした雰囲気に逆戻りすることもあります。
- 笑い声が減り、会話が少なくなる
- 報告や相談がしにくい雰囲気になる
- 仕事のミスを責めやすい空気が生まれる
- チーム全体の士気が下がる
ムードメーカーが抜けることで、改めてその存在の大きさを実感するのです。



ムードメーカーが辞めた後の空気の変化は本当に大きい。何気ない一言や笑顔がどれほど支えていたか痛感します。
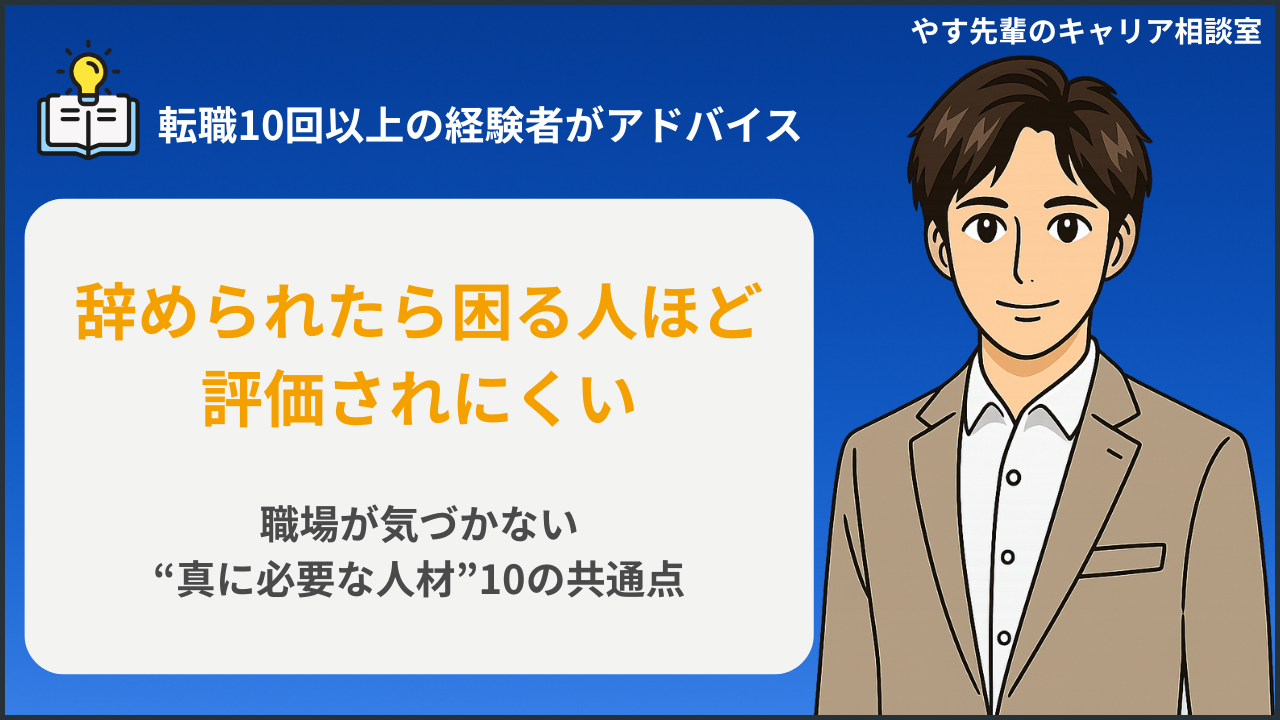
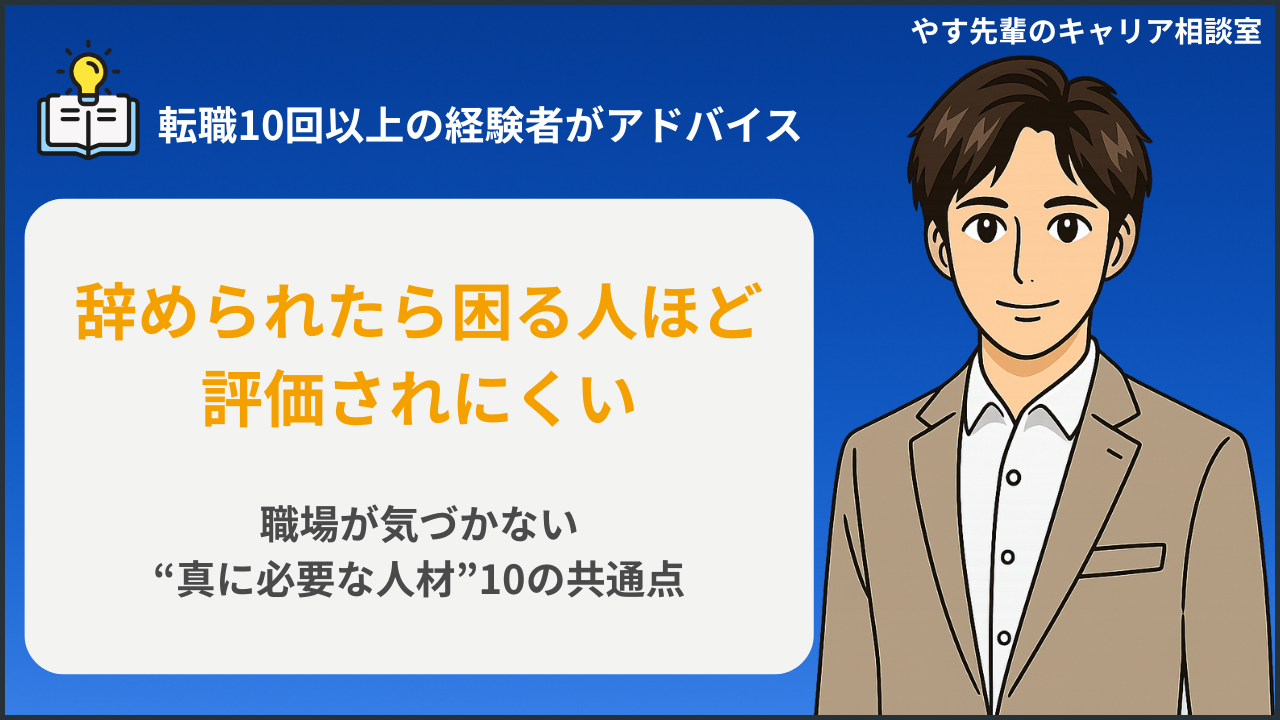
チームの雰囲気を良くする人の役割
チームの雰囲気を良くする人は、単なる盛り上げ役ではありません。彼らは空気を読んで、適切な場面で発言したり、緊張を和らげたりすることで、メンバーが安心して働ける環境をつくります。例えば、上司の厳しい発言の後に場を和ませたり、黙り込んだ会議で誰かに発言のきっかけを与えたり。小さな行動の積み重ねが、チームの結束力やモチベーションを高めるのです。
- 緊張した空気をほぐす役割
- 発言しやすい雰囲気をつくる
- 落ち込んだ仲間を励ます
- メンバー同士の橋渡しをする
彼らがいることで「この職場は安心できる」と感じられる環境が保たれます。



雰囲気を良くする人は“潤滑油”みたいな存在。彼らがいるからこそ安心して自分の意見を言えるんです。
職場の雰囲気を変える人の力とは?
職場の雰囲気を変える人は、単に場を明るくするだけでなく、組織全体の方向性にも影響を与える力を持っています。たとえば、ポジティブな言葉を日常的に使う人がいると、自然と周囲も前向きな言葉を選ぶようになります。逆に、誰かが不満を口にすれば、そこから職場全体にネガティブが広がってしまう。つまり、一人の存在がチーム全体の「空気の色」を変えてしまうのです。
- 前向きな発言が連鎖してチームが活気づく
- ネガティブ発言を和らげて軌道修正できる
- 日常の小さな声かけが大きな雰囲気の差を生む
- 一人の行動が周囲のモチベーションに影響する
「雰囲気を変える力」は肩書きや年齢に関係なく、誰にでも発揮できるものです。



職場の雰囲気は結局“人”で決まります。前向きな人が一人いるだけで、全体の空気が変わるのを何度も見てきました。


職場の雰囲気を良くする人になるための習慣


「職場の雰囲気を良くする人」は、生まれつきの性格や才能だけで決まるものではありません。誰でも日常のちょっとした心がけや習慣を積み重ねることで、周囲に安心感や前向きさを与える存在になれます。ポイントは「自分の言動が周囲にどんな影響を与えるか」を常に意識することです。ここでは、職場の雰囲気を良くする人になるために実践できる習慣を紹介します。
自分の雰囲気を良くする方法(日常で意識できること)
まずは自分自身の雰囲気を整えることが大切です。日常のちょっとした工夫だけで、周囲から「話しかけやすい人」「一緒にいて心地いい人」という印象を持たれるようになります。
- 明るい声で挨拶する
- 相手の目を見て笑顔で会話する
- 相槌やリアクションを大きめにとる
- 相手の話を最後まで聞く
こうした小さな工夫を続けることで、自然と「雰囲気がいい人」と認識され、職場全体にも前向きな空気が広がります。



挨拶や笑顔は誰にでもできる基本。でもそれだけで“雰囲気のいい人”だと思われるんですよね。
雰囲気作りが上手い人の行動パターン
雰囲気作りが上手な人には共通した行動パターンがあります。彼らは無意識のうちに場の空気を読み取り、その場に必要な言動を自然にとれるのです。
- 場が重ければ軽い冗談を挟む
- 会議で沈黙が続けば誰かに話を振る
- 落ち込んでいる人を見つけたら声をかける
- 人の成果を積極的に認め、称賛する
これらの行動は派手ではありませんが、確実に職場の雰囲気を柔らかくします。結果として「この人がいると安心できる」と思われる存在になるのです。



雰囲気作りが上手い人って、“場を読む力”がすごい。自然体で空気を整えてくれる人は信頼されますね。
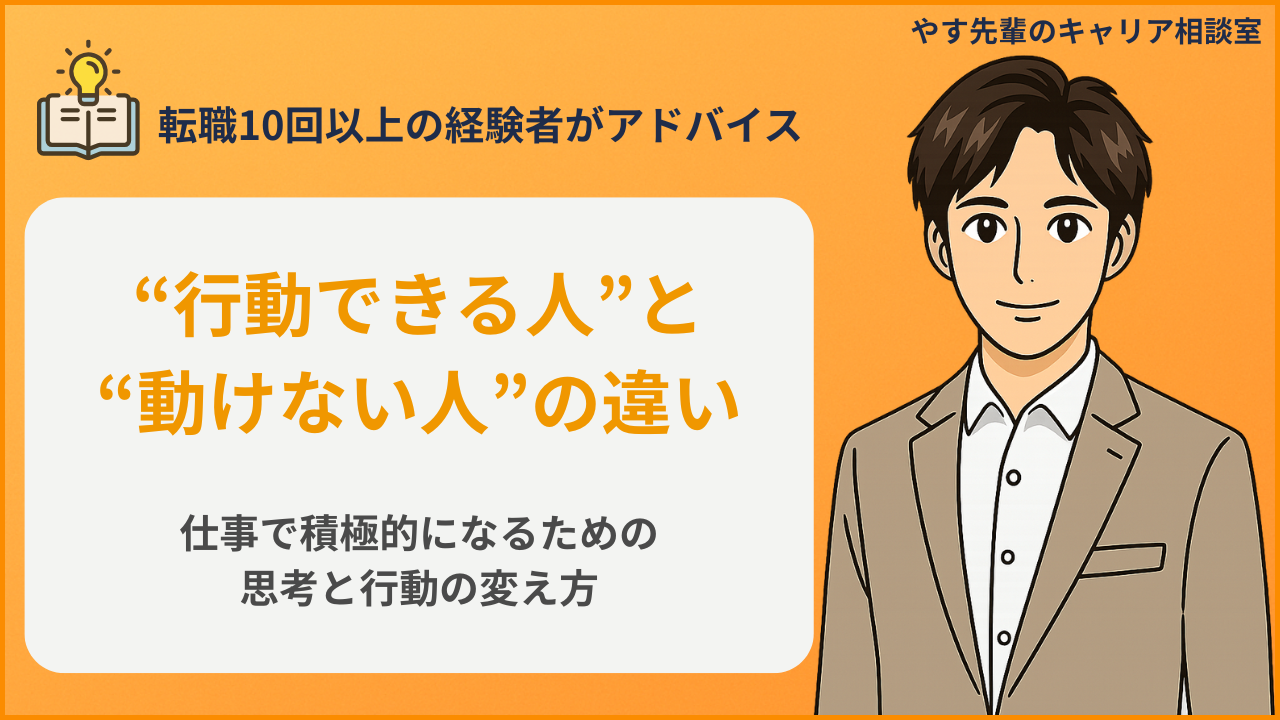
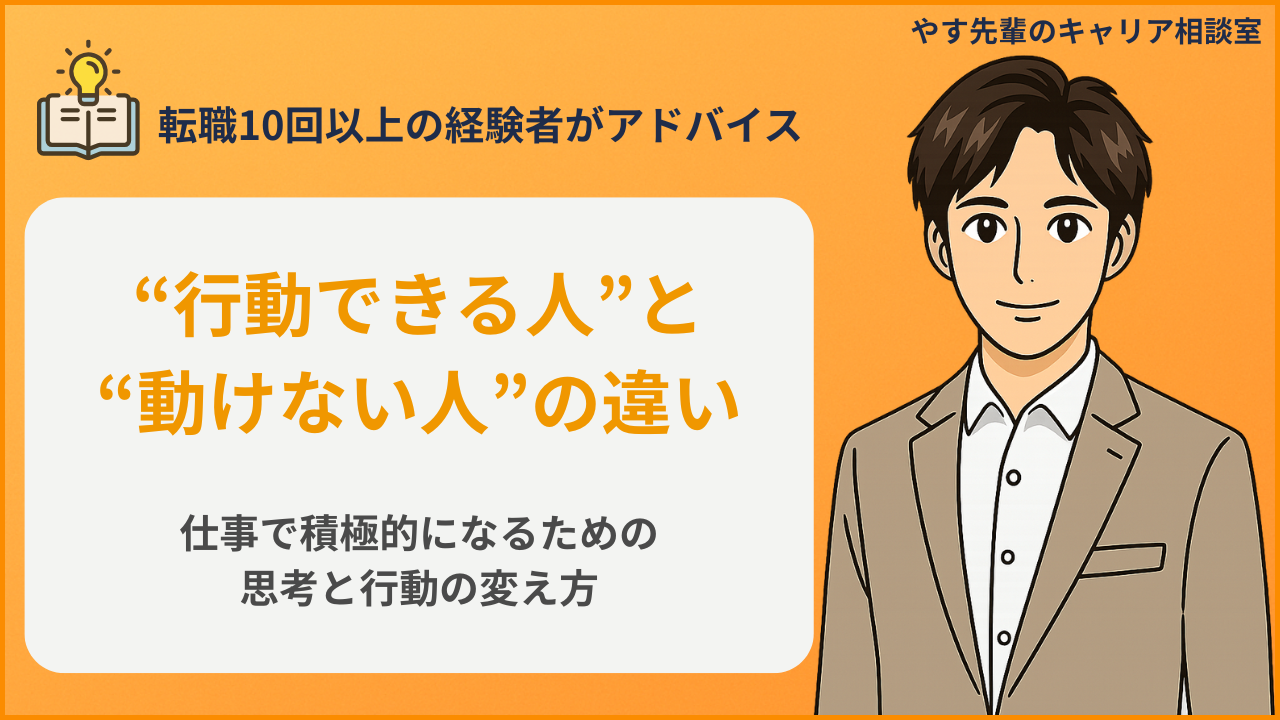
小さな習慣が積み重なって雰囲気を変える
大きなことをしなくても、日々の小さな習慣が積み重なれば職場の雰囲気は変わります。重要なのは「続けること」です。
- ありがとうを欠かさず伝える
- 毎日一度は誰かを褒める
- ネガティブな言葉を避け、前向きな言葉を選ぶ
- 雑務や小さな手伝いを自然に引き受ける
こうした習慣は目立たないかもしれませんが、周囲の信頼と安心感を確実に育みます。長期的には「この人のおかげで職場が明るい」と感じてもらえる存在になれるのです。



結局は“積み重ね”なんですよね。小さな気遣いや言葉選びの継続が、雰囲気を大きく変えていきます。
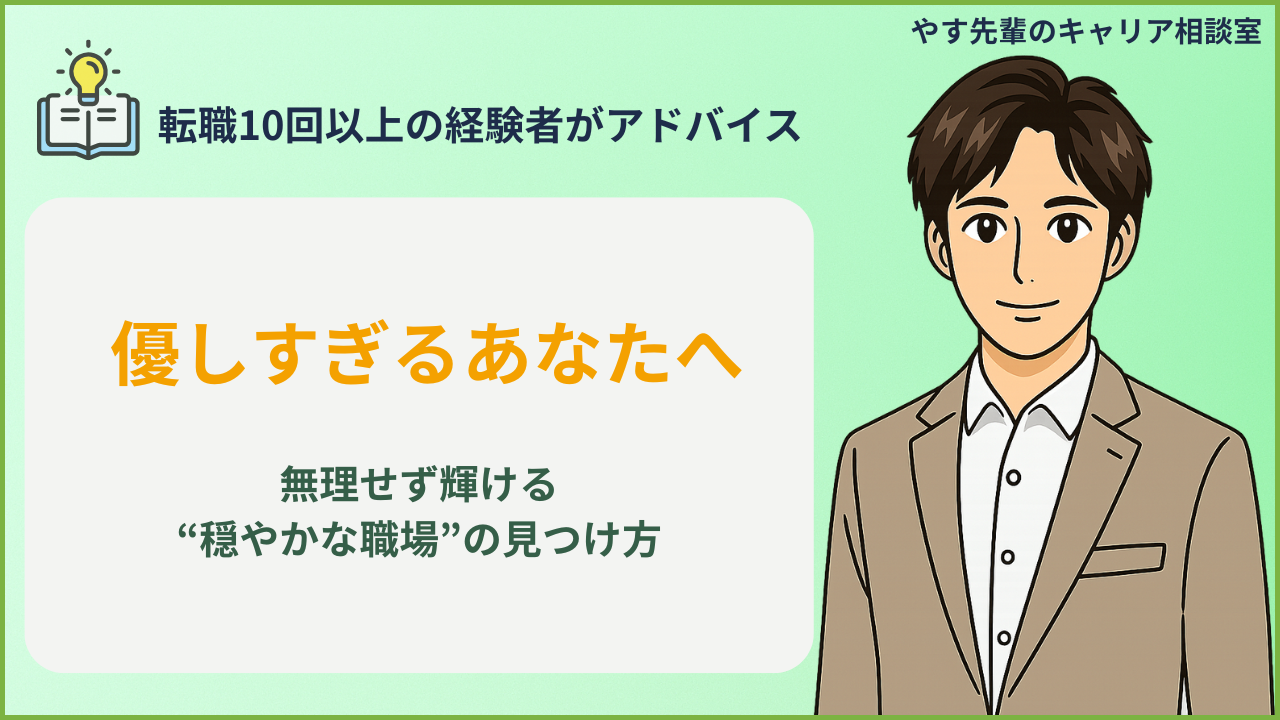
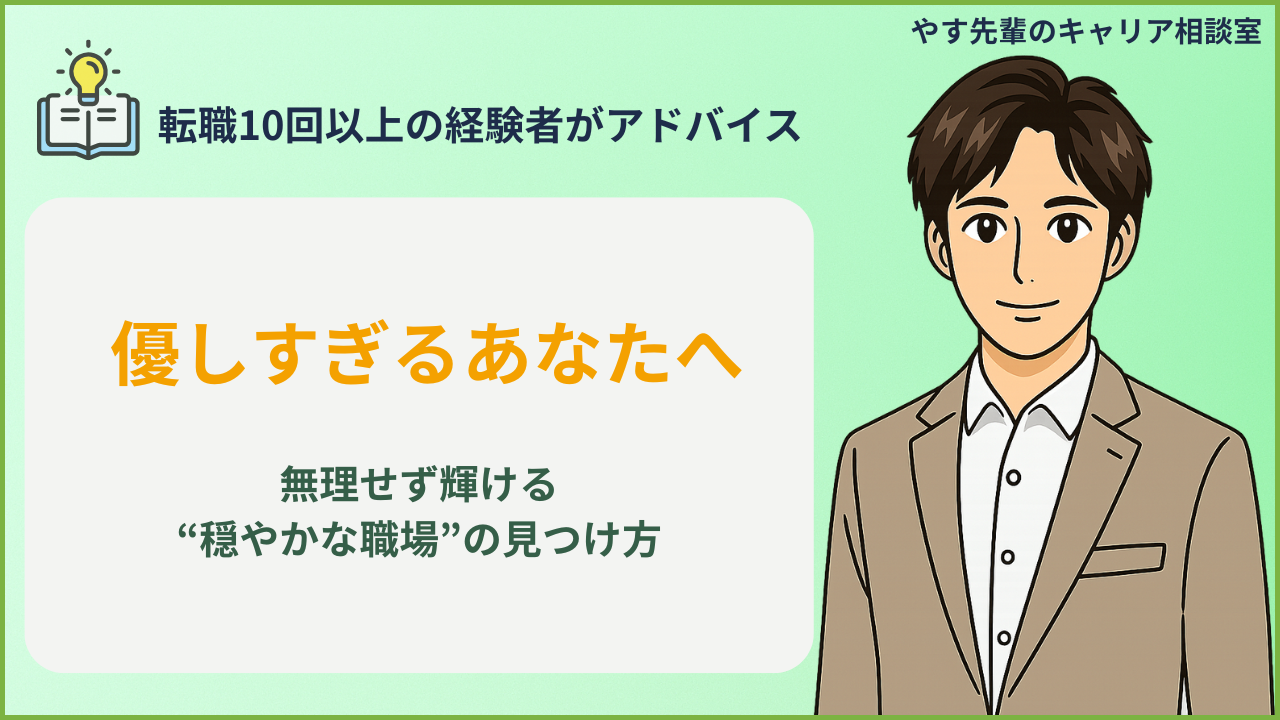
職場の雰囲気を良くする人が与える影響と効果
「職場の雰囲気を良くする人」がいることで、ただ和やかな空気になるだけではありません。実は組織にとって非常に大きなメリットを生み出しています。人は雰囲気に敏感で、ポジティブな空気の中では行動も前向きになりやすいものです。そのため、彼らがいるだけでチーム全体のモチベーションや生産性、人間関係の安定、さらにはストレスの軽減にまで効果が及びます。ここではその具体的な影響を掘り下げていきます。
モチベーション向上と生産性アップ
雰囲気を良くする人は、チームのモチベーションを底上げし、結果的に生産性を高めます。例えば、ポジティブな声かけや小さな成果を一緒に喜ぶだけでも、メンバーは「自分は認められている」と感じやすくなります。そうすると、さらに頑張ろうという気持ちが生まれ、良い循環が始まるのです。
- 成果や努力を見逃さずに評価する
- 前向きな声かけで士気を高める
- チーム全体の雰囲気を明るく保つ
- 生産性の底上げにつながる
「雰囲気がいい職場は成果も出やすい」と言われるのは、心理的に安全な環境がモチベーションに直結しているからです。



雰囲気がいいと“頑張ってみよう”って自然に思えるんです。数字だけじゃ測れない効果が確実にありますね。
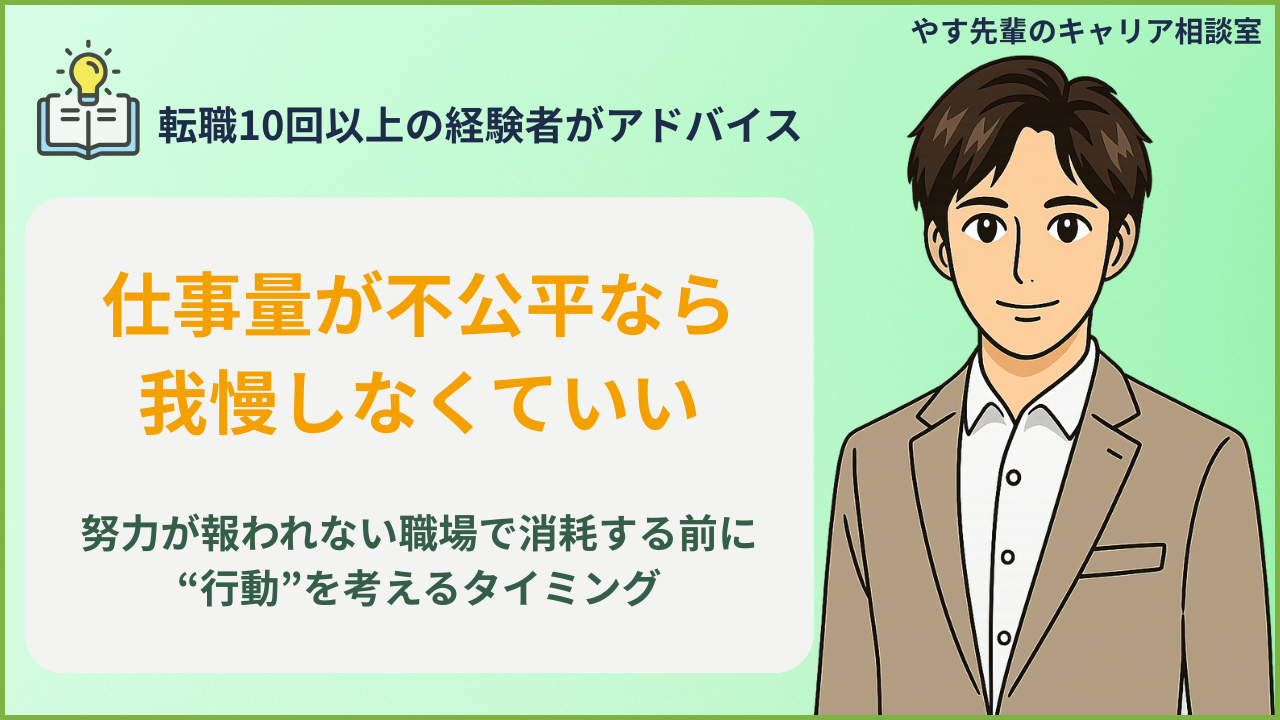
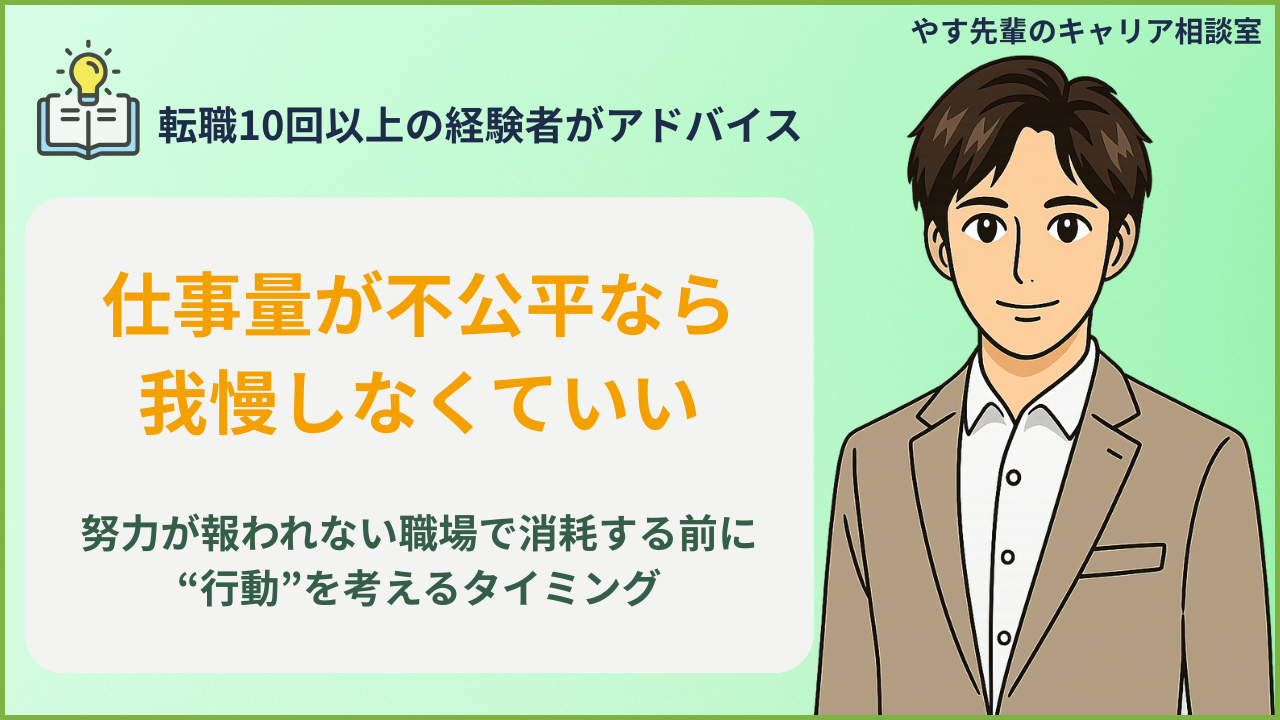
人間関係のトラブルを防ぐクッション役
職場で起こりがちな人間関係のトラブルも、「雰囲気を良くする人」の存在によって和らげられます。対立が生まれそうな場面で間に入ったり、冗談で重さをほぐしたり、双方の意見を整理して伝えたりする。いわば「クッション役」として、摩擦を和らげるのです。
- 意見がぶつかった場面を和ませる
- 双方の考えを受け止めて調整する
- 緊張を冗談でリセットする
- 小さな摩擦が大きな対立に発展するのを防ぐ
クッション役がいることで、職場の雰囲気は安定し、余計な人間関係のストレスを抱える人が減ります。



トラブルが大きくならないのは、間に入ってくれる人がいるから。空気を和ませる人は本当にありがたい存在です。
職場全体のストレスを減らす効果
雰囲気を良くする人は、職場全体のストレスを大幅に軽減します。ネガティブな空気が蔓延すると、それだけで心身に負担がかかりますが、前向きな雰囲気の中では「多少の負荷なら頑張れる」と思えるのです。ちょっとした声かけや笑顔の共有が、日常的なストレスを和らげます。
- ネガティブな空気をポジティブに変える
- 安心感を与えてストレスを和らげる
- 笑顔やユーモアで心理的負担を軽減する
- メンタル不調の予防にもつながる
職場全体の空気が明るくなることは、長期的に社員の健康を守り、定着率を上げる大きな効果をもたらします。



雰囲気が悪いと小さなことでもしんどくなりますよね。逆に明るい空気は、ストレスを軽くする力があります。


職場の雰囲気を悪くする人との違い
「職場の雰囲気を良くする人」がいる一方で、その逆に雰囲気を悪くしてしまう人も存在します。彼らの特徴や行動は、チームのモチベーションを下げたり、人間関係をこじらせたりする大きな原因になります。しかし、その存在を完全に排除することは難しいため、正しく理解し、うまく付き合う方法や対策を身につけることが重要です。ここでは、職場の雰囲気を悪くする人との違いを具体的に見ていきましょう。
職場の雰囲気を悪くする人・上司・女の特徴
職場の雰囲気を悪くする人にはいくつかの典型的な特徴があります。例えば、常に否定的な発言をする人、相手の失敗を責め立てる人、感情的に振る舞う上司、または陰口や派閥づくりをする同僚などです。特に「職場の雰囲気を悪くする女」と呼ばれるケースでは、陰口や噂話で周囲を巻き込むパターンが多く見られます。
- ネガティブな言葉ばかりを使う
- 人の失敗や弱みを攻撃する
- 上司の場合は感情的な叱責を繰り返す
- 噂や派閥で職場を分断させる
こうした人たちは、周囲の信頼を失うだけでなく、組織全体の生産性やモラルにも悪影響を与えます。



雰囲気を悪くする人は一瞬で空気を変えます。否定や陰口が多い人には周囲も疲れてしまいますね。


空気を悪くする人の対処法とハラスメントケース
空気を悪くする人への対応で大切なのは、正面からぶつからないことです。感情的に反応するとさらに対立を深めるだけなので、冷静に距離を取り、必要なときだけ関わるのが基本です。また、行動がハラスメントに該当する場合は、個人で抱え込まず、上司や人事部、外部の相談窓口に相談することが必要です。
- 直接反論せずに距離を置く
- 事実を記録し、証拠を残す
- 必要に応じて上司や人事に相談する
- ハラスメントは一人で抱え込まない
こうした対応を徹底することで、自分のメンタルを守りつつ、職場全体の改善につなげることができます。



僕もハラスメントに近い発言を受けたことがあります。冷静に証拠を残しておいたおかげで、後から状況が改善されました。
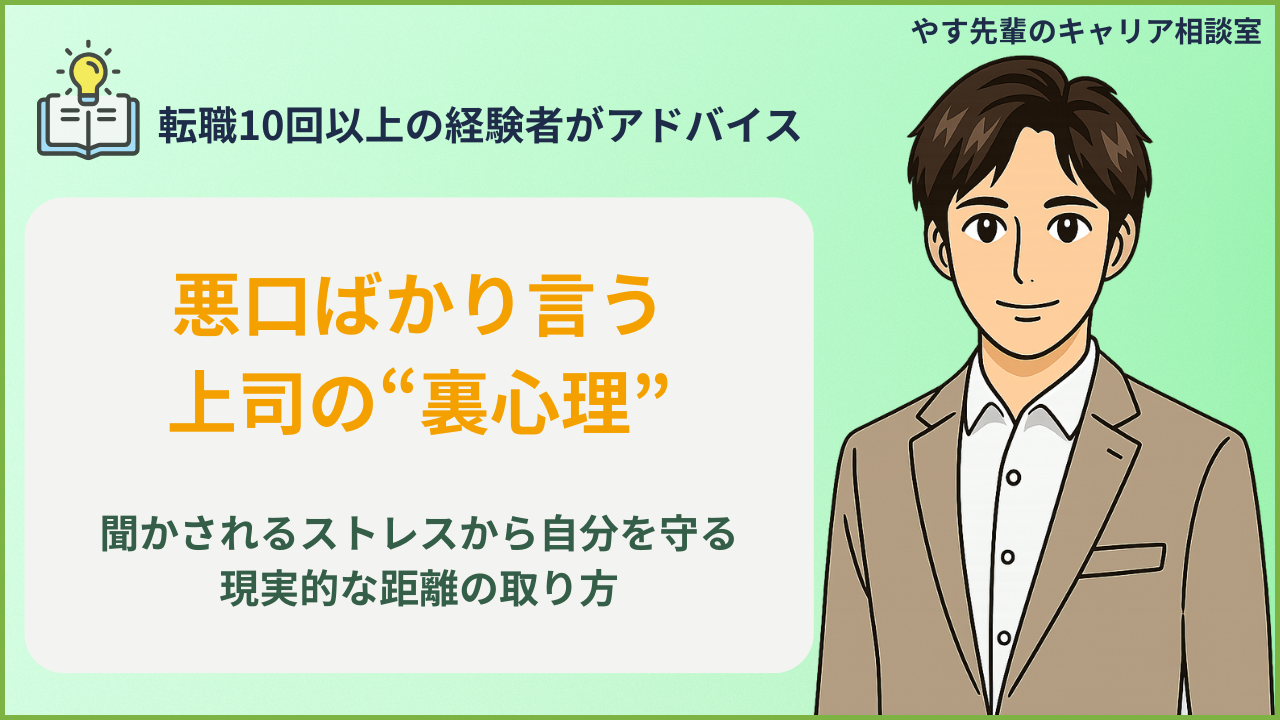
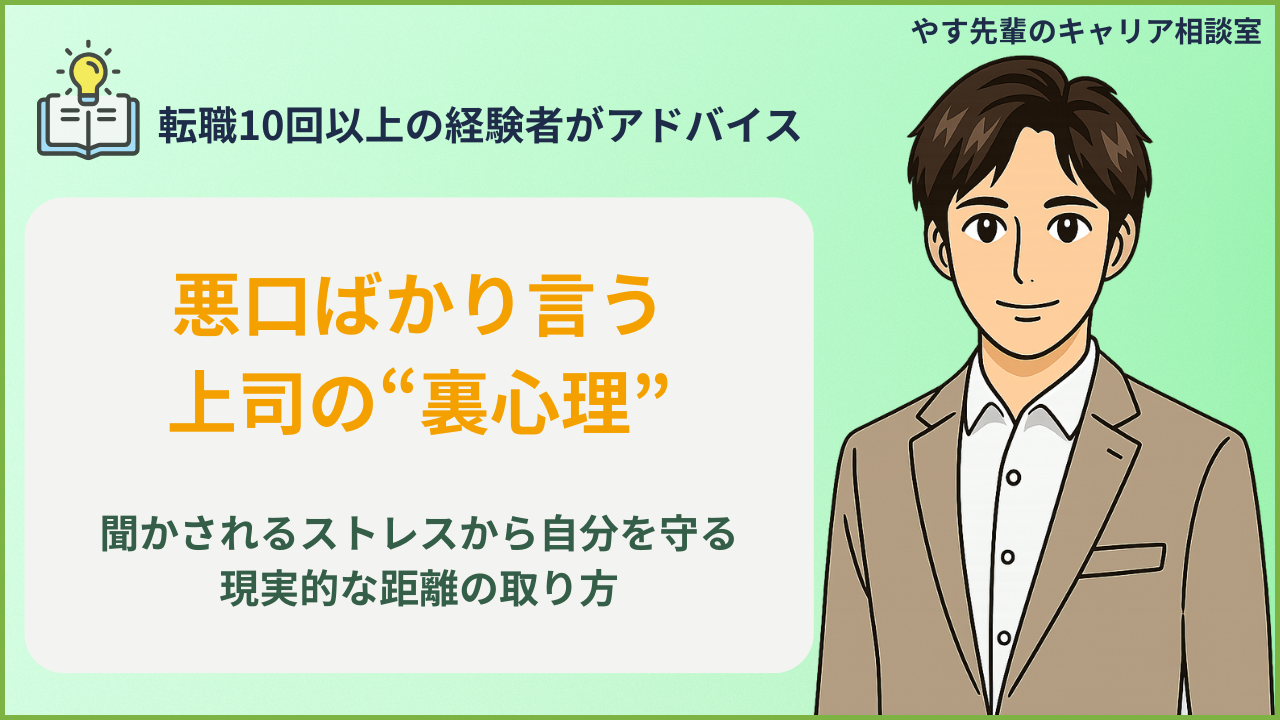
自分のせいで職場の雰囲気が悪いと感じたときの改善法
時には「もしかして自分のせいで雰囲気を悪くしているのでは?」と不安になることもあるでしょう。そんなときは、自分の言動を客観的に振り返り、小さな改善を意識することが大切です。
- ネガティブな言葉をポジティブに言い換える
- 相手の話を遮らず、最後まで聞く
- 感情的になったら一呼吸おいてから発言する
- 「ありがとう」を習慣にする
完璧を目指す必要はありません。少しずつ言葉や態度を意識することで、周囲の印象は確実に変わっていきます。



僕も一時期、無意識に不機嫌さを出していたことがあります。でも意識して変えると、周囲の反応が驚くほど変わりました。
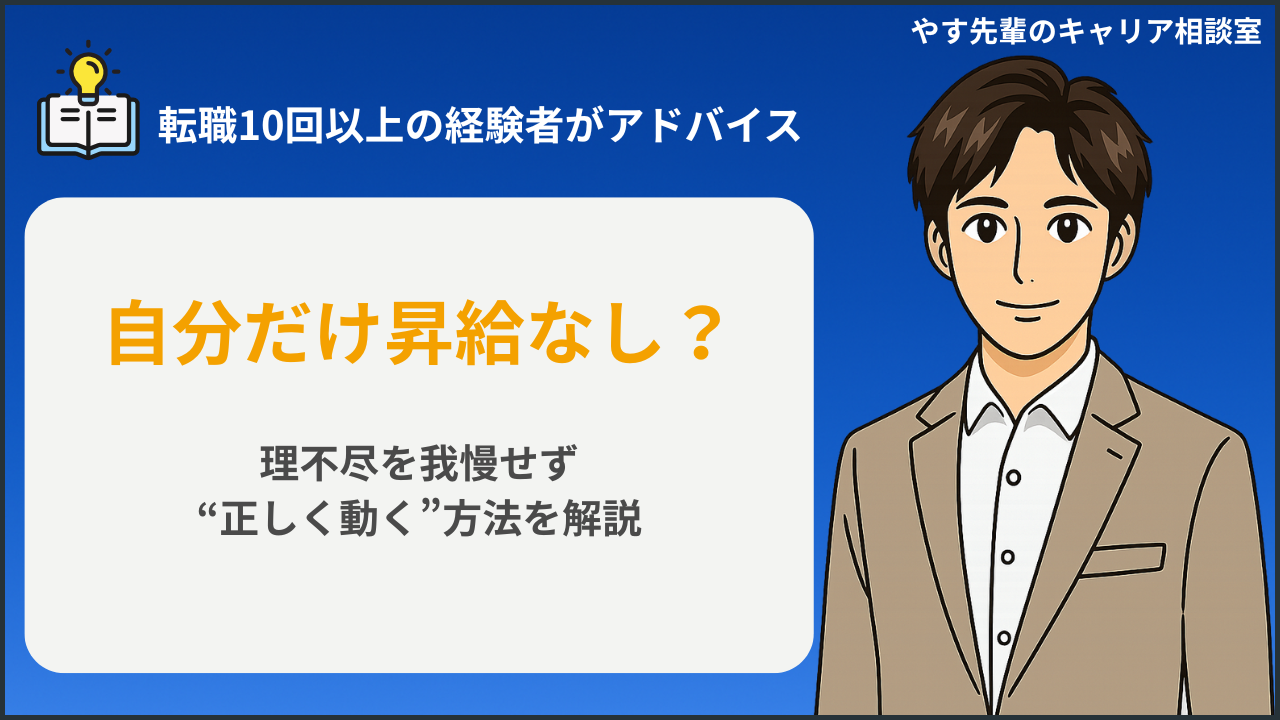
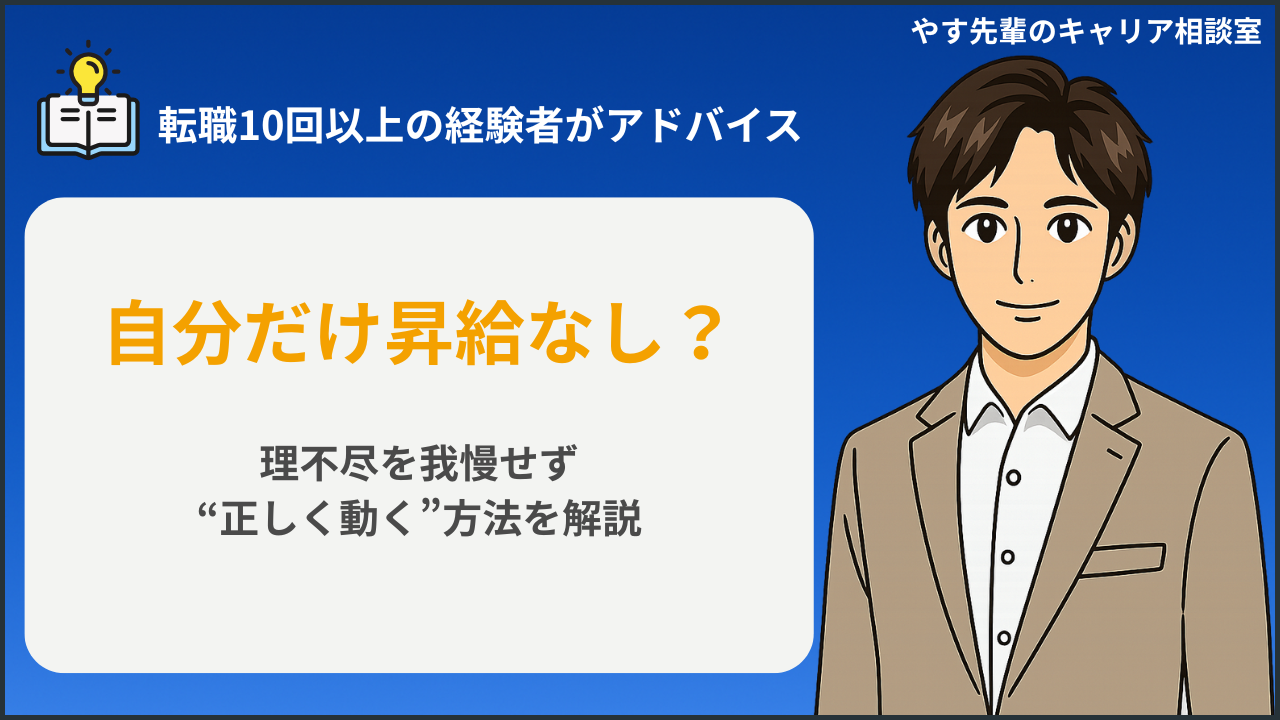
職場をダメにする人を避けるための対策
「職場をダメにする人」とは、協力を拒み、他人を攻撃し、組織の信頼関係を崩す人のことです。こうした人に巻き込まれないためには、なるべく距離を保ち、必要以上に関わらないことが有効です。また、周囲に信頼できる仲間を持ち、自分の居場所をつくることも重要です。
- 相手に深く巻き込まれないようにする
- 必要最低限の関わりにとどめる
- 信頼できる同僚と関係を築く
- 職場全体で健全な雰囲気をつくる努力をする
自分一人で雰囲気を変えることは難しいですが、悪影響を最小限に抑える工夫は必ずできます。



避けられるものは避けるのも大事です。信頼できる仲間がいるだけで、職場での安心感が全然違いますよ。
やす先輩の体験談
場を和ませる人に救われた日



僕が30代前半の頃、ある職場で働いていたときの話です。
その職場は業績が落ち込み始めていて、上司も部下もピリピリ。毎日のように「誰の責任か」を追及する空気が流れていました。
会議では怒号が飛び交い、昼休みですら皆が黙々と食事をしてすぐ席に戻る。正直、出社するだけで胃が痛くなるような環境でした。僕自身も表情が暗くなり、同僚のちょっとした発言にも苛立ちを覚えてしまうほど、職場全体が重苦しい雰囲気に包まれていたのです。
そんなある日、新しく異動してきた一人の女性社員が雰囲気を大きく変えてくれました。彼女は特別なスキルを持っていたわけではありません。
でも、朝の「おはようございます!」の声は明るく響き、誰にでも気さくに話しかけ、ちょっとした冗談を交えて笑わせてくれる。
会議で空気が凍りついたときには「まあまあ、ここは一度深呼吸しましょう」と和ませる言葉を自然に出せる。彼女がいるだけで、場の重さが少しずつ解けていくのを肌で感じました。
気づけば、怒鳴ることが多かった上司の声も以前より穏やかになり、同僚同士の会話も増えていました。
僕自身も、彼女に「大丈夫ですよ、やす先輩の努力はちゃんとみんな見てますから」と声をかけられたことで心が軽くなり、もう少し頑張ってみようと思えたのです。
人一人の影響がこれほど大きいのかと驚きましたし、同時に「雰囲気を良くする人は組織にとって必要不可欠だ」と強く実感しました。
この経験から学んだのは、「人の力で職場は確かに変わる」ということです。制度や仕組みを整えるのも大事ですが、毎日のちょっとした声かけや態度が積み重なって職場の空気を作っているのだと気づきました。
そして、自分自身も誰かにとってそういう存在になれるように、小さな気遣いを心がけるようになったのです。
最後に、今この記事を読んでいるあなたに伝えたいのは、「職場の雰囲気に悩んでいるのはあなただけじゃない」ということです。
もし今の環境がつらいなら、周囲に目を向けて「雰囲気を良くする人」から学んでみるのもいいし、逆にあなた自身が小さな一歩を踏み出してみるのもいい。
そしてどうしても耐えられないなら、新しい環境を探す選択肢もあります。大切なのは、自分の心を守りながら前に進むことです。
良い雰囲気の職場で働くためにできる行動
職場の雰囲気を良くする努力はもちろん大切です。しかし、いくら自分が工夫しても、根本的に人間関係や組織文化が悪い場合、個人の力だけでは限界があります。そんなときは「環境を変える」という選択肢を持つことも、自分を守るうえで重要です。ここでは、転職やキャリア診断を通じて、より良い雰囲気の職場を探すための行動を紹介します。
市場価値診断で自分に合う職場を探す【ミイダス】
「自分はどんな職場に向いているのか分からない」「今の会社でしか通用しないのでは?」と不安を抱える人は多いものです。そんなとき役立つのがミイダス市場価値診断。簡単な質問に答えるだけで、あなたのスキルや経歴に基づいた年収予測やマッチする業界が提示されます。
- 自分の強みや弱みを客観的に把握できる
- 想定年収が数値で分かり、自信につながる
- 自分に合った求人や働き方の方向性が見える
現状を客観視することは、職場選びで迷わないための第一歩です。



僕もミイダスを使ったとき、自分の市場価値を数値で見て驚きました。客観的な評価は自信につながりますよ。


若手向けにキャリアを見直す【マイナビジョブ20’s】
20代の若手社員に特化した転職支援がマイナビジョブ20’s。新卒で入った会社の雰囲気に馴染めない、職場環境がギスギスしていて成長できる気がしない…。そんな悩みを抱えているなら、一度相談してみる価値があります。
- 20代に特化しているから初めての転職でも安心
- 専任アドバイザーが丁寧にサポートしてくれる
- ブラックな職場を避け、キャリア形成を見直せる
「まだ若いから環境を選び直せる」というのは大きな武器です。



20代はキャリアの土台を築く大事な時期。無理して合わない職場に居続けるより、思い切って環境を変えるのも大切です。
高年収と良い職場環境を狙うなら【ビズリーチ】
「雰囲気の良さは大事。でも収入も上げたい」という人におすすめなのがビズリーチ。ハイクラス向けのスカウト型転職サービスで、企業やヘッドハンターから直接オファーが届きます。
- 年収600万以上を目指せる求人が多数
- 自分のキャリアを評価してくれる企業から声がかかる
- 給与と働きやすさを両立できる可能性がある
環境だけでなく待遇も改善したい人にはぴったりの選択肢です。



僕も収入を上げたい時期にビズリーチを利用しました。環境だけじゃなく、待遇も改善できるのは大きな魅力です。


今すぐ限界を抜け出したいなら【トリケシ】
「もうこれ以上は耐えられない」と感じているなら、退職代行サービス「トリケシ」を使う選択肢もあります。職場の雰囲気が悪すぎて心身に限界が来ている場合、自分で辞めると伝えるのはとても大きな負担になります。そんなときにプロに任せることで、スムーズかつ安全に退職できます。
- 直接上司に会わずに退職できる
- 即日対応だから限界を感じている人でも安心
- メンタルを守りながら次のステップに進める
逃げることは恥ではなく、自分を守る大切な行動です。



僕も限界を感じたときに“逃げてもいい”と気づいて救われました。心を壊す前に動くのは立派な選択です。
まとめ|雰囲気を変えるのは人の力
職場の雰囲気は、決して「自然に決まるもの」ではありません。そこにいる人たちの言葉や態度、日々の小さな行動の積み重ねによってつくられていきます。だからこそ、「職場の雰囲気を良くする人」が一人いるだけで、空気が和らぎ、チームが協力しやすくなり、生産性まで高まるのです。
一方で、雰囲気を悪くする人が強い影響力を持ってしまうと、どれだけ頑張っても働きにくい環境になることがあります。そんなときは「自分が雰囲気を良くする人になる」工夫をしてみるのも大切ですし、それでも難しいなら「環境を変える」という選択肢を持ってください。
この記事で紹介したように、
- 日常の習慣を工夫して自分自身が雰囲気を良くする人になる
- 良い雰囲気をつくる人の影響を理解し、周囲から学ぶ
- 今の環境が限界なら市場価値診断や転職支援を活用する
こうした行動は、あなた自身の未来を守る大切な一歩になります。
雰囲気を変えるのは「人の力」です。そして、その「人」には、あなた自身もなれるのです。無理をせず、自分の心を大切にしながら、少しずつ前に進んでいきましょう。
よくある質問
- 職場の雰囲気を良くする女性の特徴は?
-
親しみやすさや愛嬌があり、自然に笑顔で接することができる女性です。場を和ませる会話やちょっとした気配りができ、上司や同僚をリラックスさせる存在は「雰囲気を良くする人」として大きな影響を与えます。
- ムードメーカーの言い換えは?
-
ビジネスシーンでは「場を和ませる人」「雰囲気作りが上手い人」「チームの潤滑油」などが自然な言い換えです。単に盛り上げ役ではなく、周囲を安心させ前向きに導ける存在を指す言葉として使うと効果的です。
- 職場の雰囲気を悪くする人の典型的な特徴は?
-
否定的な発言が多い、失敗を責める、陰口を言う、感情的な態度をとるなどです。特に上司の場合は叱責が多くなる傾向があり、職場全体にストレスを与えます。小さなネガティブ言動が雰囲気を大きく悪化させます。
- 自分の雰囲気を良くするには何を意識すればいい?
-
まずは笑顔と明るい挨拶を心がけることです。さらに「ありがとう」を口にする習慣や、相手の話を遮らずに聞く姿勢が加われば、自然と周囲に安心感を与えられます。小さな積み重ねで「雰囲気がいい人」と見られます。
- 会社のムードメーカーが辞めたらどうなる?
-
笑いや前向きな声かけが減り、会話や相談がしにくい雰囲気になることがあります。結果的に士気が下がり、人間関係がギスギスするケースも多いです。だからこそ、残ったメンバーが意識して空気をつくる必要があります。