 やす先輩
やす先輩40代半ば、転職10回の管理職。上場もベンチャーもブラックも経験してきました。失敗も学びも交えながら、キャリアや働き方に悩むあなたへ“現実的な解決策”を届けます。
⇒詳しいプロフィール
「同じ部署なのに、自分だけ昇給がなかった」
この事実に直面したとき、悔しさや不信感を覚えるのは当然です。
真面目に働いてきたからこそ、「自分の何がダメだったのか」「もう評価されていないのでは」と、自分を責めてしまう人も多いでしょう。
でも、はっきり言います。
昇給がなかった理由は、あなたの努力不足とは限りません。
評価基準が曖昧だったり、上司ごとの判断軸がバラバラだったり、そもそも「昇給させない前提の制度」になっている会社もあります。
この記事では、
・なぜ「自分だけ昇給なし」が起きるのか
・黙って損をしないために取るべき行動(話す/見直す/動く)
・昇給ゼロから、転職で年収アップした実体験
を、現実ベースで整理します。
もし今、
「理由が分からないまま評価されない」
「この会社に居続けていいのか不安」
と感じているなら、一度“会社の評価”ではなく“市場の評価”も見てみてください。
ミイダスを使えば、あなたの経験が他社ではどのくらいの年収で評価されるのかが見えます。
会社に黙って損をし続けるか、自分の価値を知った上で選び直すか。
判断の主導権を、あなたの手に取り戻しましょう。
なぜ「自分だけ昇給なし」になるのか?
「自分だけ昇給がなかった」と気づいた瞬間、
誰もが「なぜ自分だけ?」という不信感と焦りを抱きます。
しかし、そこには感情ではなく“仕組み”の問題が潜んでいることが多いです。
ここでは、昇給が自分だけ反映されない3つの典型的な理由を整理していきましょう。
上司や評価者の“主観評価”が強い職場
昇給は「数値」より「上司の印象」で決まってしまう職場も少なくありません。
特に、明確な人事評価制度がない中小企業や古い体質の会社では、
上司の好き嫌いや主観が評価に直結する傾向があります。
たとえば
- 同じ成果でも「積極的に報告する人」だけが評価される
- 評価基準が明文化されておらず、「上司が納得すれば昇給」状態
- 上司の異動・交代によって、前年より基準が曖昧になる
つまり、“評価制度”があるようで実は「上司の裁量」で左右されているのです。



どれだけ努力しても、“伝わっていない努力”は評価されない。
数字と印象、両方で見せていくことが大切です。
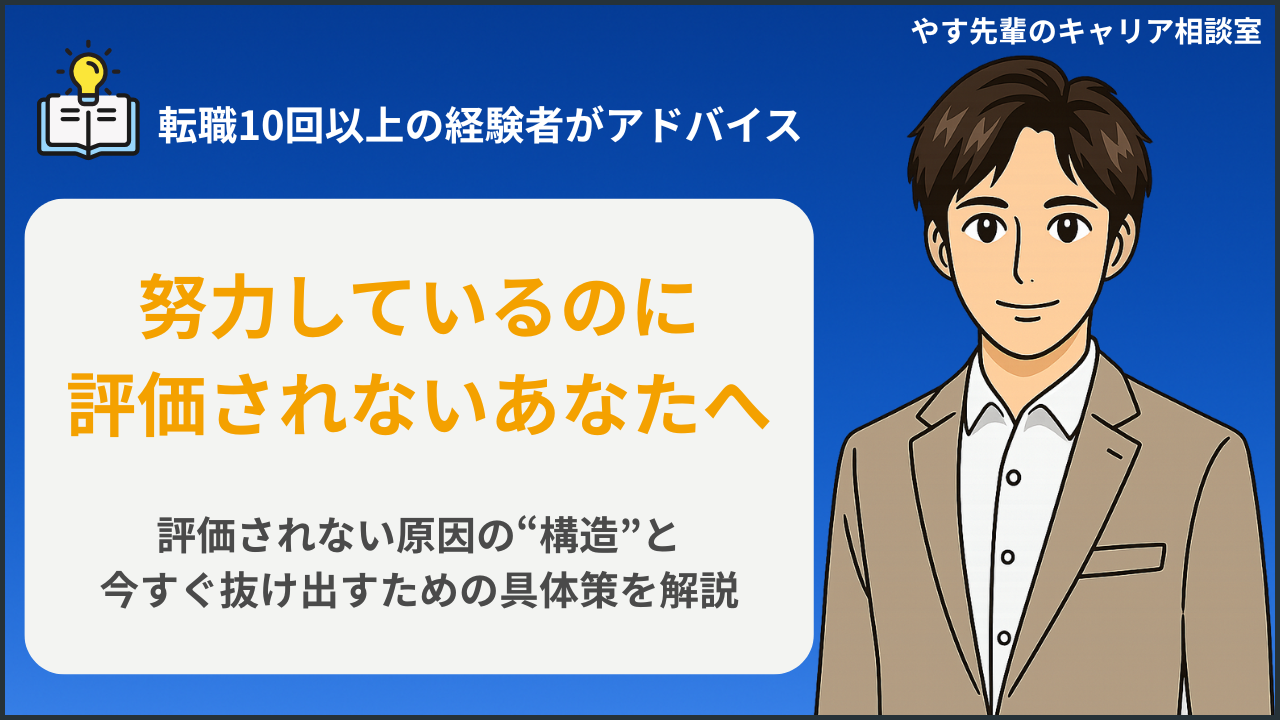
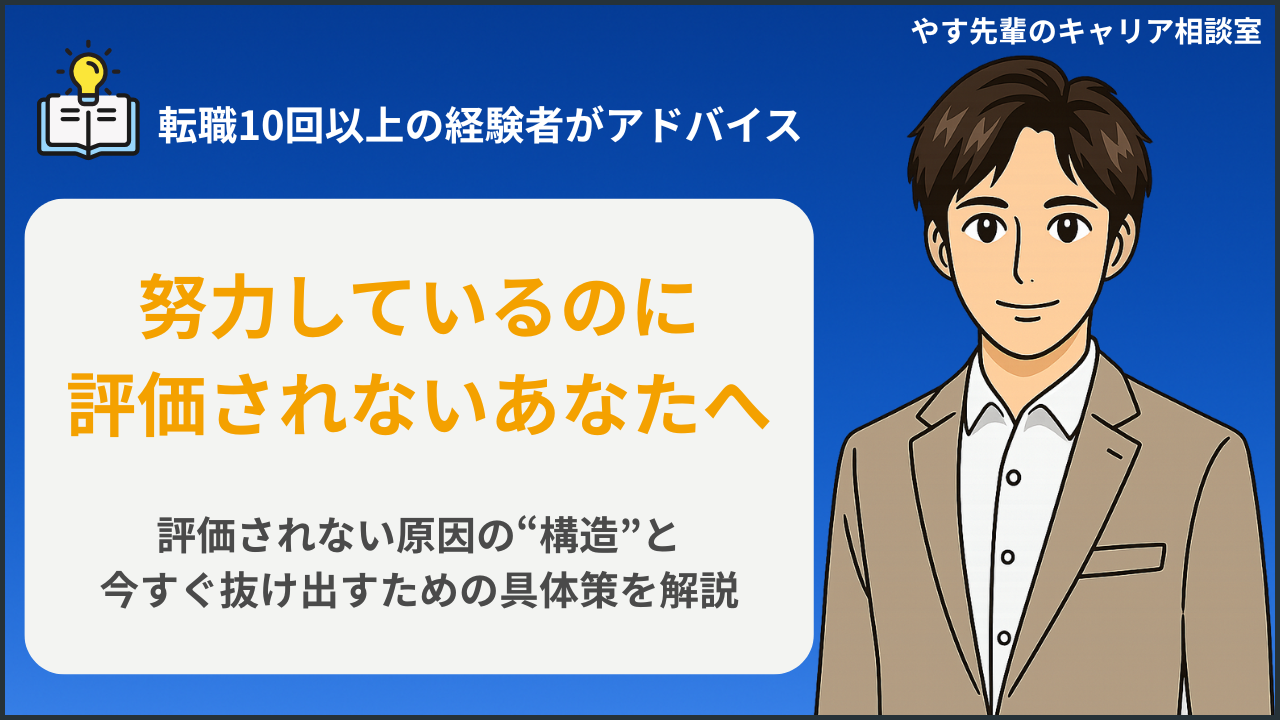
成果の「見せ方」が足りず、努力が伝わっていない
多くの人が誤解していますが、昇給は“努力”そのものではなく、
努力の成果をどれだけ“認識されているか”で決まります。
たとえば
- 裏方業務や調整業務など、目立ちにくい貢献をしている
- 成果を口頭でしか伝えず、数値化・資料化していない
- 「頑張っている姿勢」は評価されても、成果が見えない
こうしたケースでは、上司が評価に反映させる材料を持てていないのです。
定期面談や評価シートでは、「具体的な改善成果」「数値で見える業務貢献」を短く整理して伝えることが重要。
例:「新しいマニュアル化で作業時間を20%削減しました」
例:「引き継ぎ制度を整備し、トラブル件数をゼロにしました」
見える形に残す=評価の土台を作ることにつながります。



“伝える力”が弱いと、“実力がない”と勘違いされる。
数字・資料・報告、この3つを味方につけよう。
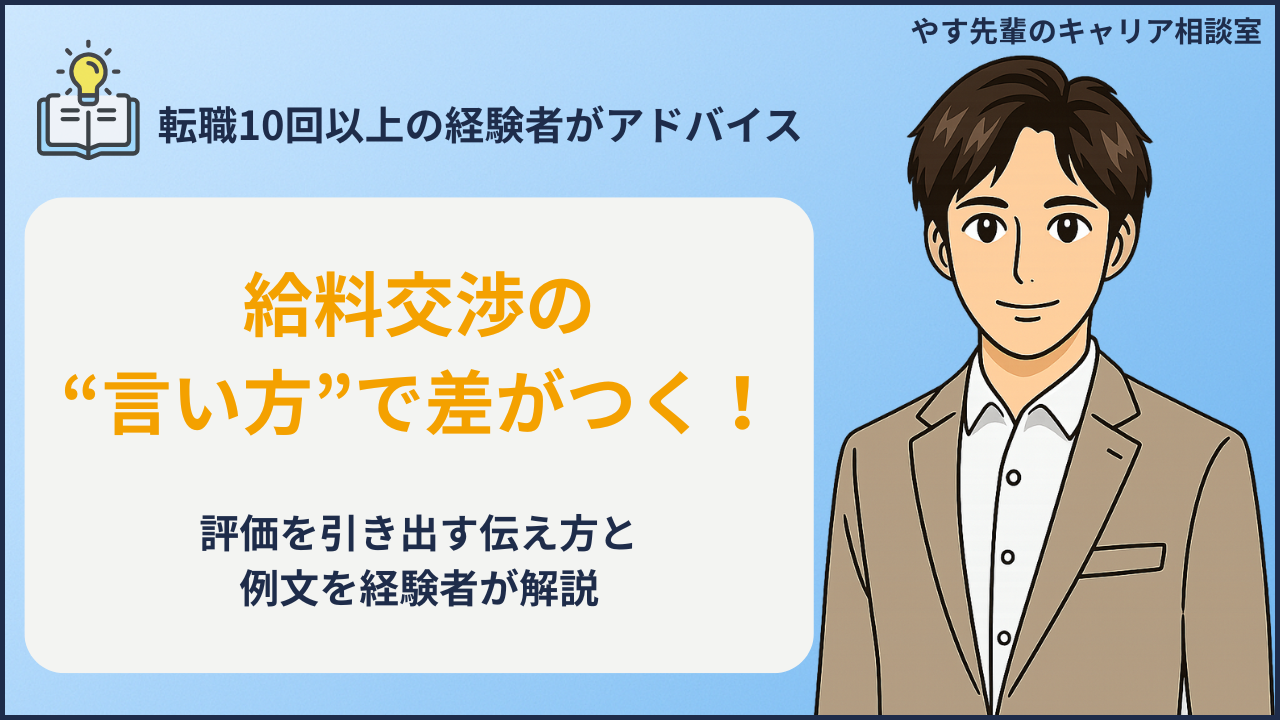
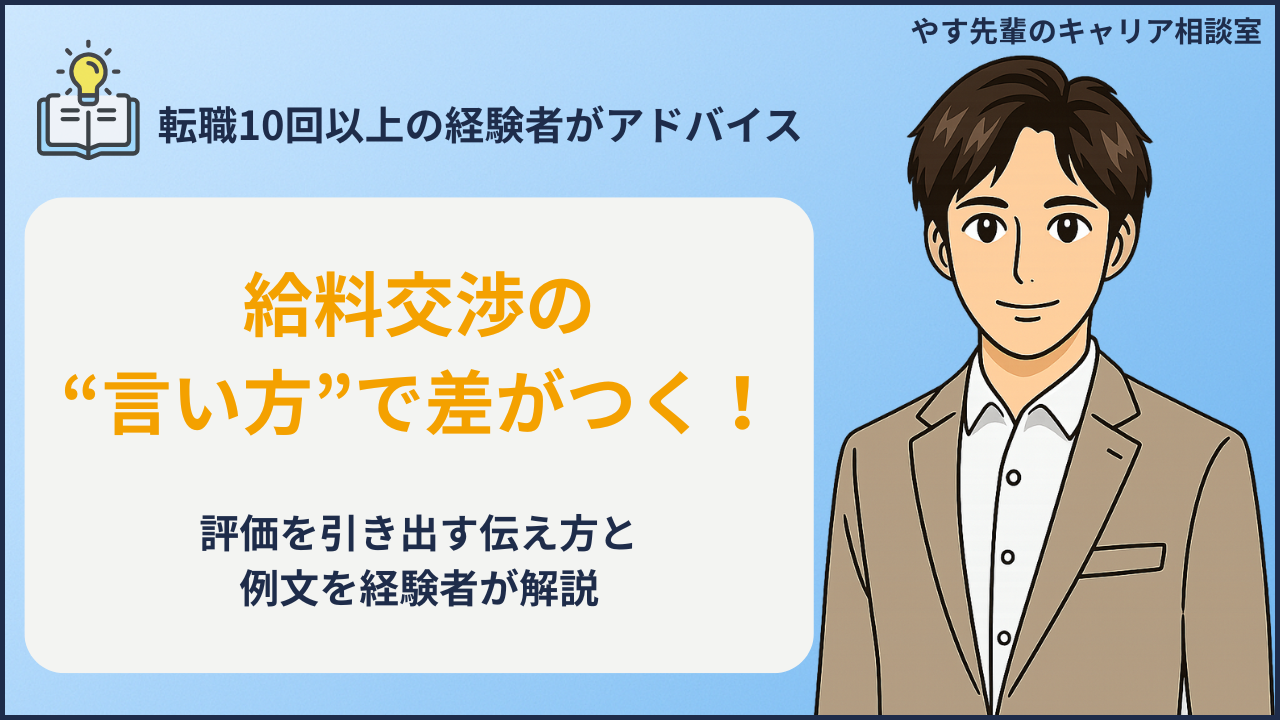
会社の業績や部署業績によって昇給枠が偏る
昇給は「個人の頑張り」だけで決まるものではありません。
会社や部署の業績が悪化している場合、昇給自体が制限されることもあります。
特に、
- 売上や利益率が前年比マイナス
- 昇給枠が部署ごとに配分される
- 管理職・営業部門に昇給を優先している
このような構造では、あなた個人の成果が十分でも、
「昇給の順番が回ってこない」という現象が起こります。
一見「自分だけ上がっていない」と思えても、
実際には「部署単位で昇給が止まっている」ことも多いのです。



会社の数字が落ちているときは、“個人の頑張り”より“全体の帳尻”が優先されがち。
だからこそ、“市場の中で評価される力”を磨くことが一番の防御策です。
昇給ありなのに自分だけ上がらない…その背景
求人票や面接で「昇給あり」と聞いて入社したのに、
いざフタを開けてみると「自分だけ昇給なし」「説明もない」そんなケースは少なくありません。
実はこの“昇給あり”という言葉、会社によって意味がまったく違うのです。
ここでは、その曖昧な表現の裏側と、納得のいく説明を引き出すためのポイントを解説します。
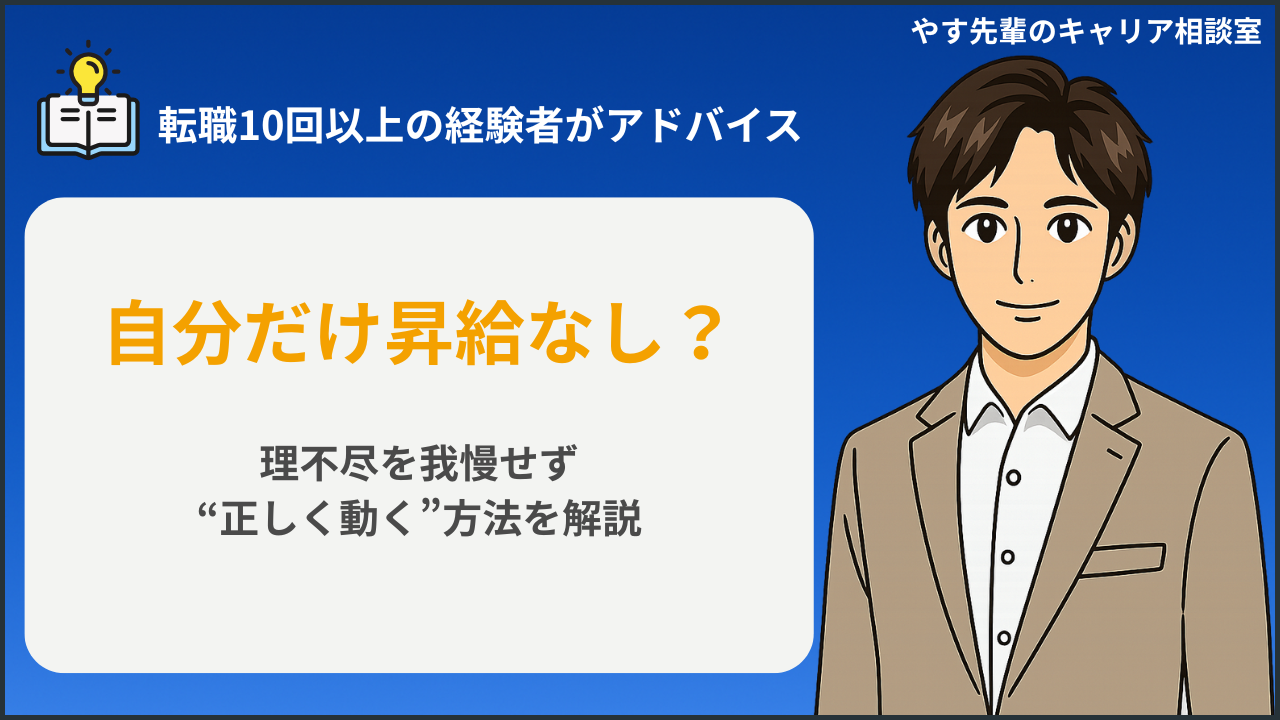
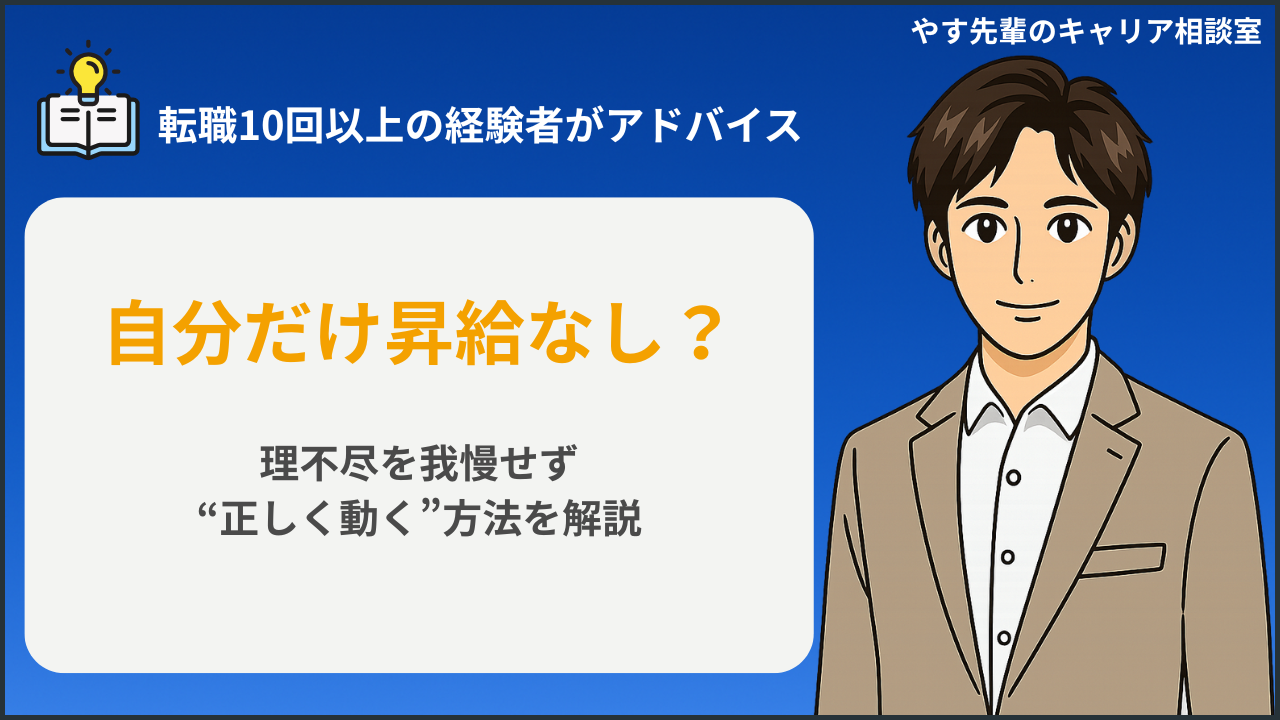
「昇給あり=実績次第」の“建前トリック”に注意
求人票にある「昇給あり」は、法律上「必ず上がる」ことを保証していません。
実際、多くの企業では「昇給の可能性がある」=“条件付き”という意味で使われています。
たとえば:
- 「会社業績や個人評価によって昇給を決定」
- 「昇給制度はあるが、実績ゼロの年もある」
- 「昇給対象は正社員のみ」「契約社員は除外」
つまり、“昇給制度の存在”と“実際の昇給実績”は別問題なのです。
この曖昧さを利用して、実質的に昇給しない会社でも「昇給あり」と記載できるのが現状。
実際、国民生活センターや求人情報適正化の相談窓口でも、
「求人票と実際の待遇が違う」という相談は毎年増えています。



“昇給あり”は“年に一度、上がる”じゃなく、“制度がある”という意味。
制度があっても“動かない制度”なら、あなたの努力は報われません。
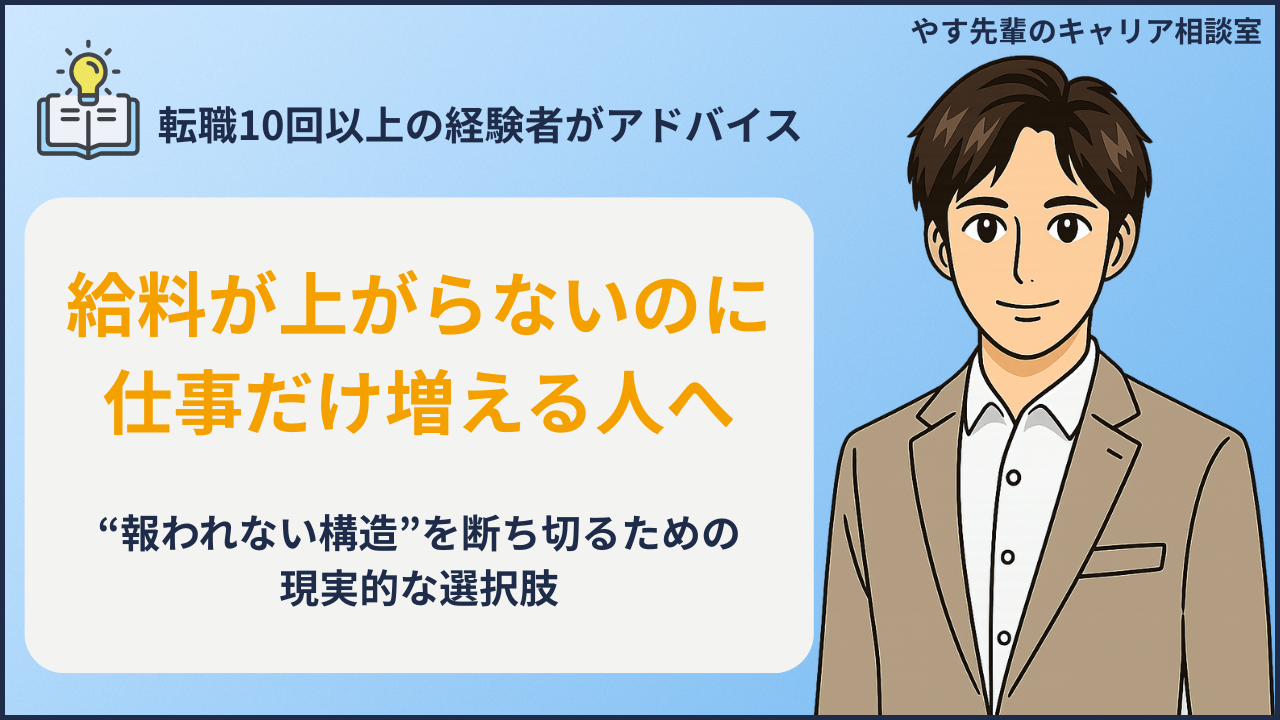
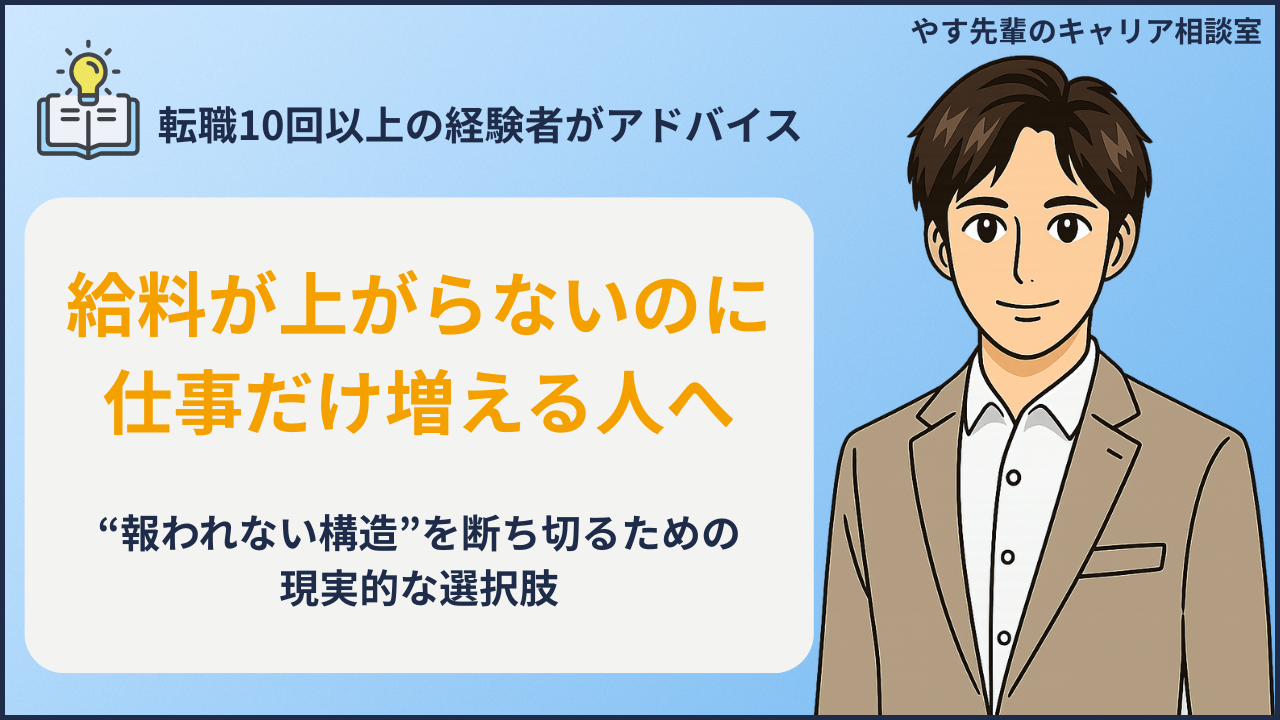
面談で「昇給しない理由」を聞く際のポイント
「なぜ自分だけ昇給しなかったのか?」を確認するのは、勇気が要るもの。
ただし、聞き方を間違えると“クレーム”と受け取られ、逆効果になってしまいます。
上手に聞くポイントは以下の3つです。
① 「昇給を希望する理由」を前向きに伝える
「自分も昇給したいです」ではなく、
「今後の成長のために、どの部分を改善すれば昇給につながるか教えてください」
という形で“成長意欲”を軸に話すと、印象が良くなります。
② 「評価基準」を具体的に聞く
「何を達成すれば昇給対象になるのか」を数字で確認しましょう。
例:
「昨年度の評価指標(KPI)はどのように反映されましたか?」
「次回評価までに達成すべき目標値を教えていただけますか?」
③ 「改善計画」を言葉でまとめる
話し合いのあと、自分の理解をその場で復唱しておくと効果的。
「つまり、次の評価で○○を達成すれば、昇給の可能性があるという認識でよろしいでしょうか?」
と確認すれば、記録にも残せます。



“なぜ上がらなかったのか”じゃなく、“どうすれば上がるのか”を聞くと、
相手も前向きに答えざるを得ないんです。
「前年度実績なし」の求人は要チェック
転職活動中に「昇給あり」の文言を見たら、必ず“前年実績”を確認してください。
たとえば求人票に、
「昇給あり(前年度実績:なし)」
と書かれていた場合、それは昇給制度は存在するが、誰も昇給していないという意味です。
これは業績が悪い会社だけでなく、
- 評価制度が未整備
- 昇給額が一律1,000円〜3,000円程度
- 管理職だけ昇給して一般社員は据え置き
といったケースでも見られます。
また、求人票に「業績による」と記載がある場合は、
個人の評価よりも会社全体の利益に依存する昇給構造になっていることが多く、
頑張っても成果が反映されにくい環境といえます。



“昇給あり”と“昇給実績あり”はまったく別物。
転職サイトでは“前年昇給率”や“平均昇給額”も必ずチェックしよう。
「昇給なし」でモチベーションが下がったときの考え方
「こんなに頑張っているのに、給料が上がらない…」
その悔しさや虚しさは、誰にでも訪れます。
でも、昇給が止まった瞬間こそ、“自分の価値を見直すサイン”です。
焦って空回りするより、戦略的に「モチベの再設計」をする方が、
結果的にキャリアのリターンは大きくなります。
ここでは、昇給が止まった時期に心をすり減らさず前に進むための、3つの考え方を紹介します。
頑張っても上がらない時期は“充電期間”と割り切る
昇給が止まる時期は、実力不足ではなく“企業の都合”によることがほとんどです。
たとえば、会社の業績悪化・評価制度の改定・上司の異動など、
「あなたがコントロールできない要因」で評価が停滞することは珍しくありません。
この状況で無理に頑張り続けると、
- 成果が出ない努力で疲弊する
- 上司に“焦っている人”という印象を与える
- 結果的に評価にも悪影響が出る
という“悪循環”に陥る危険があります。
むしろ、こうしたときは「充電期間」と割り切って、
次の成長に向けた種まきをする方が合理的です。
- 新しいスキルを学ぶ
- 社外ネットワークを広げる
- 副業や資格に挑戦して“別の成果軸”を作る



昇給しないときは、“戦略的に力を貯めるターン”。
焦らず、自分のステージを整える期間だと思えば、前向きになれます。
「会社に合わせる」より「自分の価値を上げる」
モチベーションを保つ最大のコツは、評価の軸を会社ではなく自分に置くことです。
昇給が止まるたびに「上司のせい」「会社が悪い」と感じていると、
感情だけが疲弊して、行動が止まってしまいます。
代わりに、
「自分のスキルは市場でいくらの価値があるのか?」
という“外の物差し”を持つことで、冷静に現実を見られるようになります。
実際、ミイダスなどで市場価値を診断すると、
「会社では評価されていないけど、市場では年収+50〜100万円の価値がある」
というケースも珍しくありません。
つまり、“昇給なし”を嘆くより、
“評価される場所”を探す方が早く人生が変わるということです。



会社に評価されないなら、“市場に評価される自分”を作ればいい。
評価軸をずらすだけで、心のバランスが一気に楽になります。
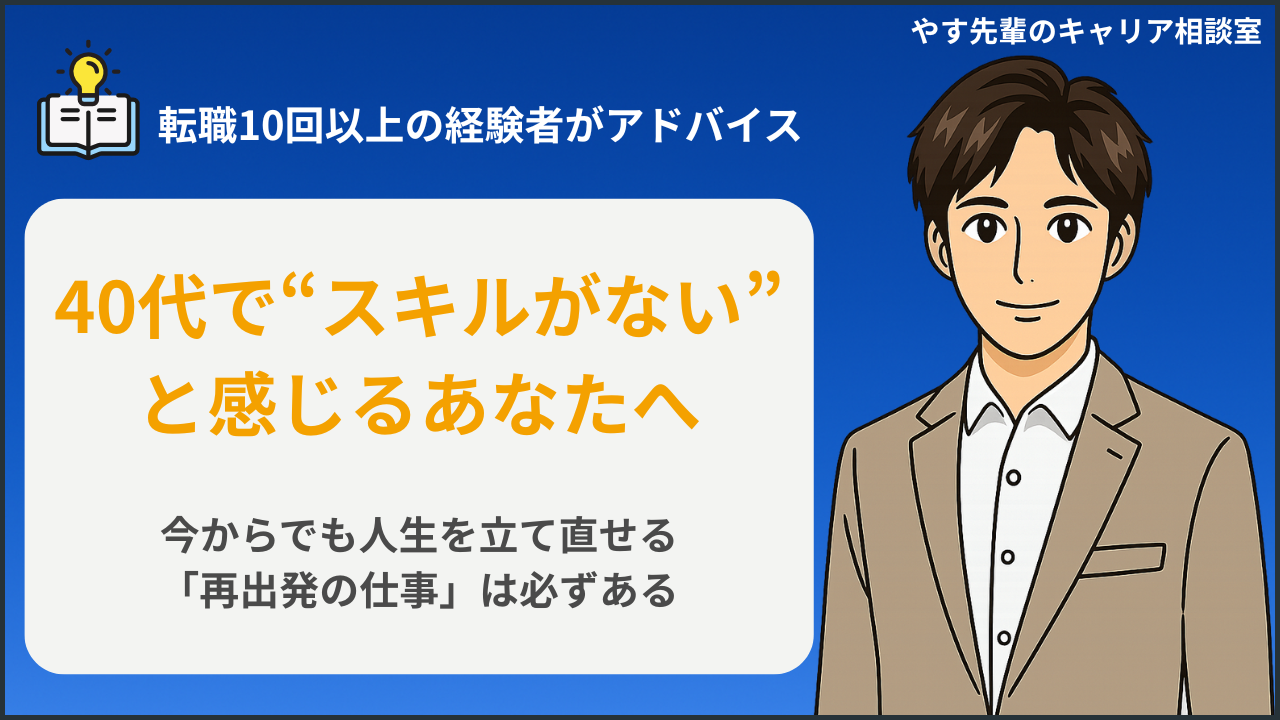
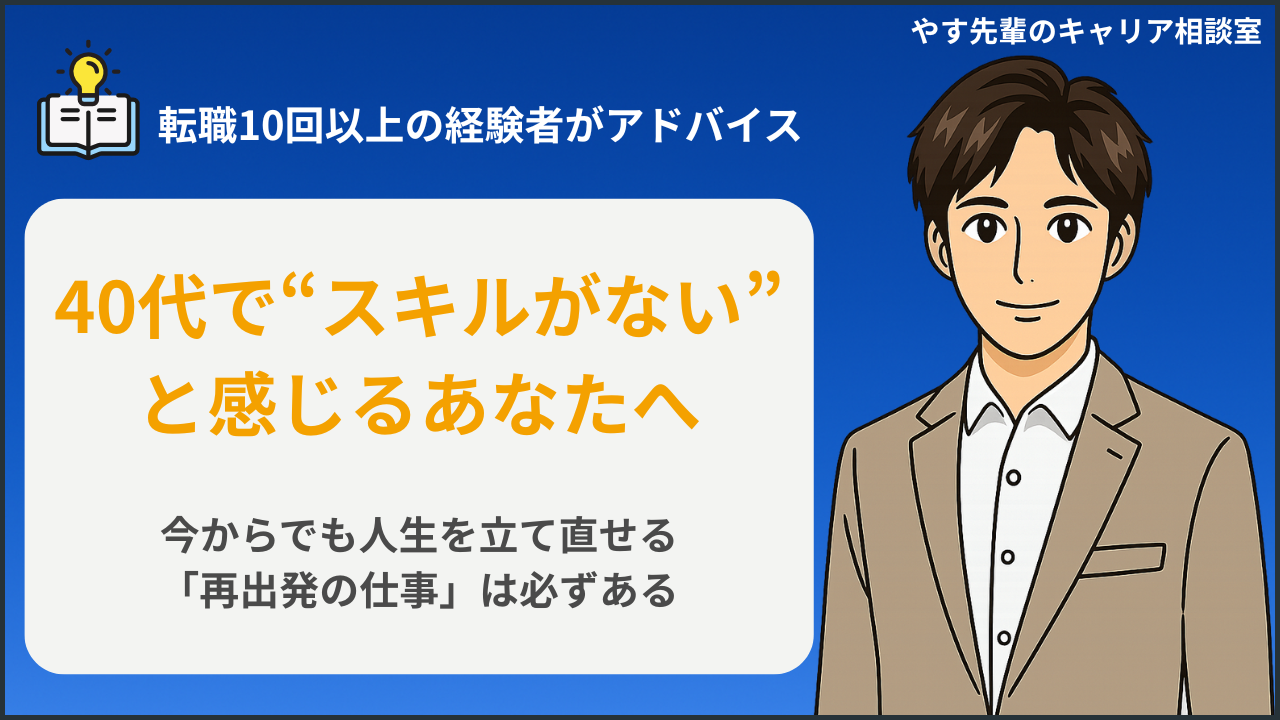
モチベを保つための3つのセルフマネジメント術
昇給が止まると、やる気も下がりがちです。
しかし、心の持ち方次第で「停滞期」も“成長の助走期間”に変わることができます。
以下の3つを意識してみてください。
① 「できること」を1日1つ積み上げる
大きな成果が出ない時期ほど、小さな達成感が心を支えます。
日報・タスク管理アプリ・ToDoリストを使って、
「今日も一歩前進した」と感じられる仕組みを作りましょう。
② 成果を“見える化”して自信を保つ
自分の実績をスプレッドシートやメモにまとめておくと、
「自分はちゃんと成果を出している」と可視化できます。
これは後々の評価面談や転職活動でも強力な武器になります。
③ 会社以外の承認軸を持つ
社内で報われないときほど、社外活動・副業・資格勉強が効果的。
「自分を認めてくれる場所」を複数持てば、精神的にも安定します。



モチベって、会社がくれるものじゃなく、自分で育てるもの。
“自分の軸”を持った人だけが、昇給の波に流されずに生き残れるんです。
昇給なしが続く会社の特徴とリスク
「もう何年も昇給していない」「昇給額が毎年ほぼゼロ」
このような会社に長くいると、キャリアも年収も“ゆっくり衰退していく”危険があります。
昇給が止まるのは、偶然ではなく“組織構造のサイン”です。
ここでは、昇給が続かない会社の3つの典型的な特徴と、そのリスクを具体的に解説します。
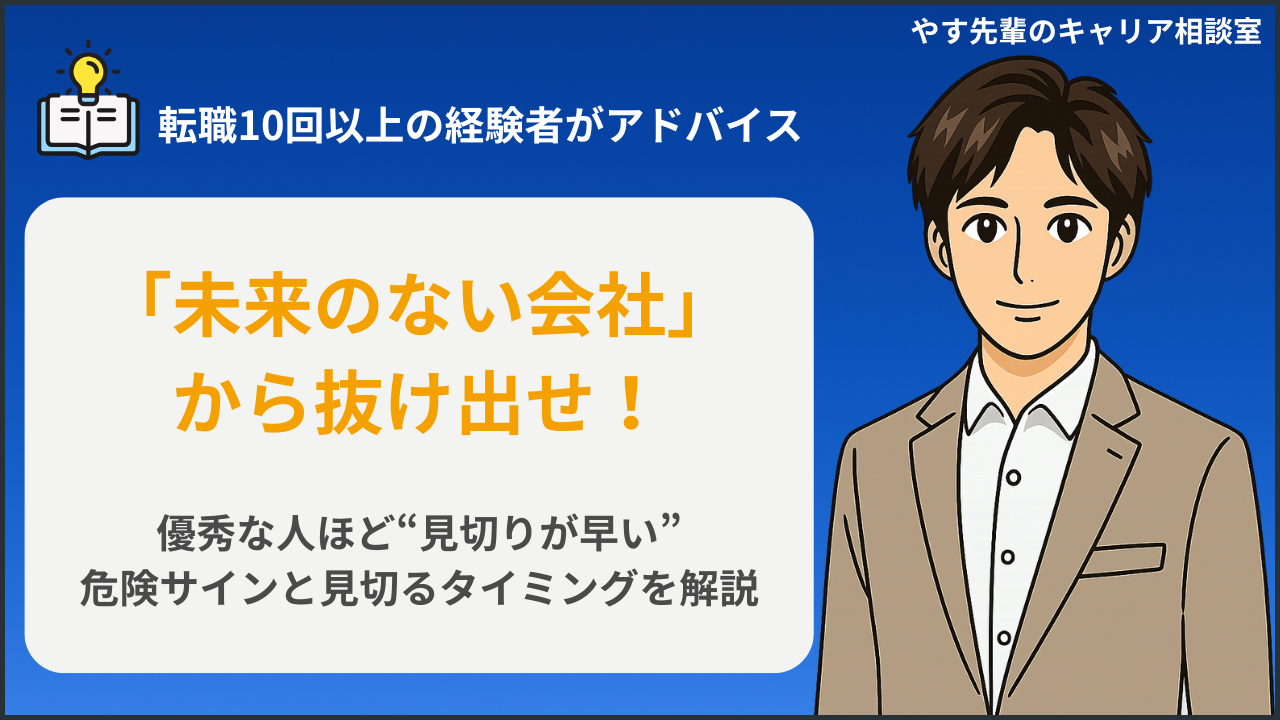
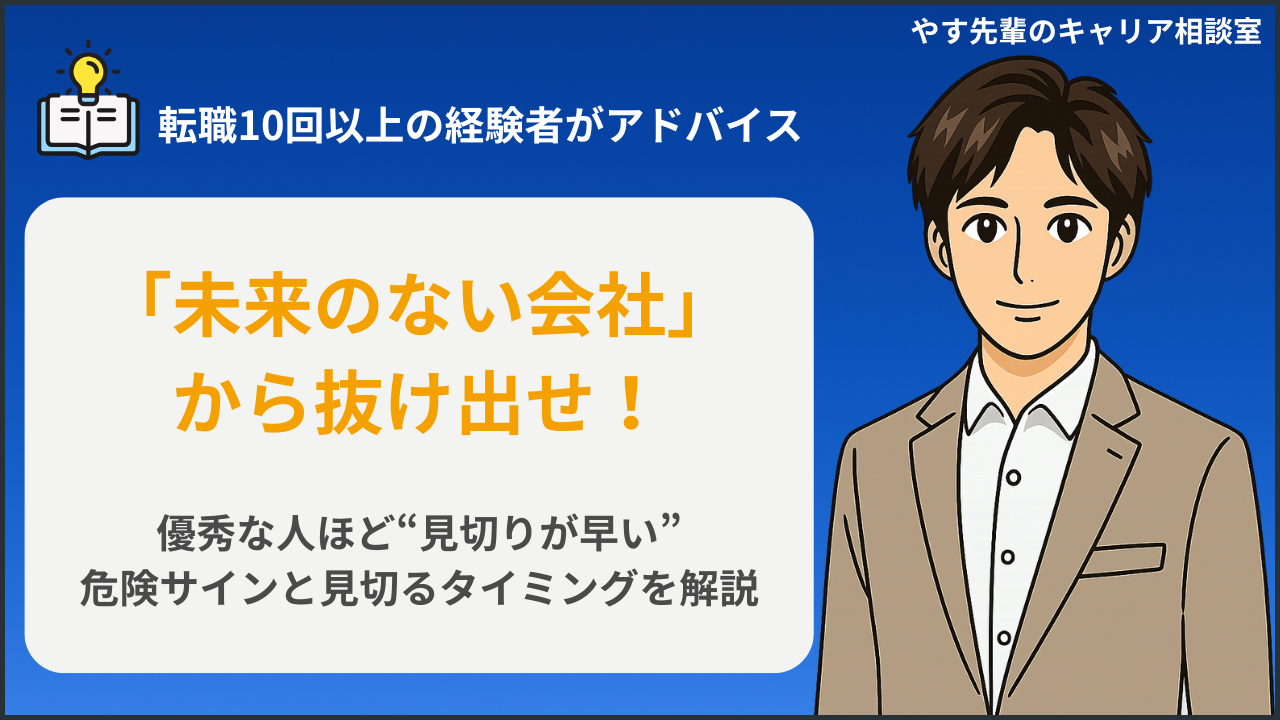
昇給の仕組みが明文化されていない
最も危険なのが、「昇給制度があるようで、実際には存在しない」タイプの会社です。
このような職場では、評価の基準があいまいで、昇給が上司の裁量や空気で決まります。
典型的なパターンは以下の通り
- 「昇給基準」は存在するが社員に共有されていない
- 評価シートが形骸化しており、上司の印象で決まる
- “業績が悪い”を理由に毎年見送りになる
つまり、「何を頑張れば上がるのか」が分からない状態です。
努力と昇給の因果関係が不明確だと、社員はモチベーションを失い、
「頑張っても報われない」職場文化が根付きます。



昇給のルールが見えない職場は、“頑張る方向”を見失いやすい。
目標が曖昧なままでは、努力も評価もズレ続けるんです。
管理職の昇給も鈍化している“成長停滞企業”
昇給が止まる会社のもう一つの特徴は、「上が詰まっている」構造です。
つまり、管理職層の昇給・昇進が鈍化し、若手・中堅にしわ寄せが来ている状態です。
よくある構図
- 役職者が長く居座り、ポストが空かない
- 管理職の給与が上がらず、組織全体が“固定費化”
- 利益が出ても「人件費の見直し」が後回しになる
このような企業は、組織の成長が止まり、給与テーブルも動かない傾向にあります。
中小企業や老舗企業に多く、「若手の昇給原資が確保されない」構造が常態化しています。
結果として、
- 「給与テーブルが10年前から変わっていない」
- 「管理職手当が数千円レベル」
- 「賞与や昇給の根拠が“慣例”になっている」
というケースも珍しくありません。



上が動かない会社は、下も育たない。
“自分の未来が見えない”と感じたら、それは会社の成長が止まっているサインです。
「離職率が高い」「賞与カット常習」は危険信号
昇給が止まる企業の末路は、人が定着せず、組織がスカスカになることです。
特に、以下のような傾向がある会社は要注意。
- 離職率が高く、毎年同じ時期に人が辞める
- 業績悪化を理由に「賞与カット」「昇給見送り」が恒常化
- 新卒や中途が入っても数ヶ月で退職
- 経営層のメッセージが“守りの姿勢”ばかり
こうした会社は、すでに「人件費を削って延命するフェーズ」に入っている可能性があります。
つまり、昇給どころか、今後は賞与削減・人員整理が進むリスクすらあるということです。



“昇給なし”は、沈みかけた船のサインかもしれません。
会社を変えるより、自分の未来を守る行動を先に取るべきです。
やす先輩の体験談|「自分だけ昇給なし」から抜け出した話
当時の状況:3年連続で昇給ゼロ、評価理由も曖昧
以前、僕(やす先輩)が所属していた会社では、3年連続で昇給ゼロという状態が続いていました。
しかも、上司からの評価コメントは「全体的に良く頑張っている」「引き続き期待している」など、抽象的な言葉ばかり。
同期の中には昇給している人も多く、
「なぜ自分だけ?」という疑問と焦りが積み重なっていきました。
残業もこなし、成果も出しているつもりなのに、給与面では変化なし。
“努力が形にならない虚しさ”に、次第に心がすり減っていったのを覚えています。



一番つらいのは、“何が足りないのか分からない”状態。
評価の基準が見えないと、努力の方向すら分からなくなるんです。
感じたこと:「努力が空回りしてる」と気づく瞬間
ある日、同僚が何気なく「俺、今年5,000円昇給だったわ」と話しているのを聞いたとき、
胸の奥がズシンと重くなりました。
そこではじめて、
「どれだけ頑張っても、会社の評価軸に自分の努力が乗っていない」
という現実を直視しました。
その瞬間から、僕は考え方を変えました。
「上司の評価を待つより、“市場の評価”を見よう」
昇給がない=自分がダメなのではなく、
「その会社では、上がる仕組みがない」だけかもしれないと気づいたのです。
行動:ミイダスで市場価値を確認 → ビズリーチで転職活動
まずは冷静に、自分の“現在地”を知ることから始めました。
ミイダスで市場価値を診断すると、年収ベースで+70万円の提示額が出ました。
この瞬間、「評価されていなかったのは、自分の力不足ではなく“環境のミスマッチ”かもしれない」と確信しました。
その後、ビズリーチに登録し、実際にスカウトを受け始めると、
自分のスキルに興味を持ってくれる企業がいくつも現れました。
それまでの「昇給なし=自分のせい」という思い込みが、
「動けば変わる」という確信に変わった瞬間でした。



“ミイダス→ビズリーチ”の流れは、昇給しないモヤモヤを“データで見える化”する最短ルートです。
結果:半年後、年収+80万円&リモートOKの環境に転職
転職活動を始めて約半年後、年収+80万円&リモートワークOKの企業に転職しました。
前職よりも仕事量は少し多いですが、裁量があり、成果がダイレクトに給与に反映される環境。
何より、「努力が正当に報われる」という感覚が戻ってきました。
以前は“昇給なし”に苦しんでいたのに、今では“自分で年収を上げられる仕組み”の中で働けています。
学び:「上司に評価されない」より「市場に評価される自分」を選ぶべき
この経験を通して、僕が学んだのはたった一つ。
「上司や会社に評価されなくても、“市場に評価される”自分を作ればいい」
昇給が止まっても、あなたの価値が下がったわけではありません。
むしろ、今の会社で昇給しないことに気づいた瞬間が、
キャリアを立て直すチャンスの始まりです。



“昇給なし”を放置すると5年後には後悔します。
会社が上げないなら、自分で上げにいく。それが、令和の働き方です。
昇給なしに気づいたときの行動ステップ
「自分だけ昇給なし」に気づいた瞬間はつらい。でも感情で動くより、手順で動いた方が早く状況は変わります。やることは三つ。まず事実確認でモヤモヤを可視化し、次に自分の価値を数値で示して再提示、最後に市場の基準で選択肢を持つ。この順番を外さないだけで、上司の主観に振り回されず、昇給可否に関係なく年収を上げる道筋が見えてきます。
① 面談で冷静に昇給理由を確認する
最初にやるのは「なぜ上がらなかったのか」の事実整理。感情は横に置き、面談では三点を聞き出します。
- 評価指標の中で不足していた項目と配点
- 次回評価までに達成すべき具体目標と数値水準
- 昇給決定のスケジュールと関係者言い方は前向きに。「昇給したい」ではなく「次回、どの成果をどの水準で出せば昇給対象になりますか」と聞く。面談後は議事メモを要点三行でまとめ、上司に共有。認識ずれが起きたらその場で修正します。会社都合で見送りの場合は、部署原資や業績要因の説明を求め、個人要因と切り分けましょう。
② 自分の成果を数値で整理して再アピール
評価者は「見える材料」がないと点を入れにくい。普段から成果を数値化した一枚資料を作り、面談や週次で添付できる状態に。テンプレはKPI前後比較、改善率、再現手順の三段構成。
例
・問い合わせ対応フロー改定により平均処理時間を32分から24分へ短縮、稼働8人分で月間24時間の削減
・ナレッジ化10本で新人の独り立ち期間を20日から14日へ短縮
さらに「チーム貢献」「再現性」「波及効果」を一言で添えると評価に刺さります。裏方業務や調整業務は特に可視化が命。日々の業務ログから月次ハイライトを抜き出し、数値と証憑リンクで武装しましょう。
市場価値を知り、転職も含めて選択肢を持つ
社内の評価が揺らいだら、外の物差しで現在地を測る。ミイダスで提示年収レンジと強みキーワードを把握し、現職の評価軸と照合。
乖離が大きければ、社内交渉と並行して外の選択肢を持つのが合理的です。ビズリーチでは希望年収や職種でスカウト傾向を観察し、「前年昇給率」「評価制度の運用実績」を面接前に確認。
20代中心なら マイナビジョブ20’sで面接トークをブラッシュアップし、「昇給なしをどう乗り越えたか」を成長ストーリーに変換。残るか辞めるかは、年収だけでなく裁量、成長機会、ワークライフの三点合意で決めましょう。



昇給なしで心が折れそうな時こそ、手順が味方になります。事実を取りに行く、数字で示す、外の基準で選ぶ。感情で消耗せず、淡々と勝ち筋を作っていきましょう。
まとめ|「自分だけ昇給なし」は、“見直しの合図”
「自分だけ昇給なし」と聞くと、誰だって落ち込みます。
でも、それは「あなたの価値が低い」からではなく、「評価される環境を選べていない」だけの話です。
昇給とは、努力の結果ではなく「評価制度 × 経営構造 × 上司の裁量」で決まるもの。
つまり、“仕組み側の問題”であるケースが圧倒的に多いのです。
たとえば、
- 評価シートがあっても運用されていない
- 上司の主観で判断される
- 会社全体が昇給抑制フェーズに入っている
そんな状況では、どれだけ頑張っても報われません。
むしろ、“昇給なし”を経験した今がチャンス。
それは「自分のキャリアを外の基準で見直すタイミング」です。



昇給が止まった瞬間こそ、“キャリアの定期点検”をする時期です。
焦らず、自分の価値を見える化して、次の一手を決めましょう。
行動することでしか、モヤモヤは解消しない
ミイダスで自分の市場価値をチェックする
┗ 今のスキルが市場でどう評価されているかを客観的に把握。
ビズリーチで希望の求人を探す
┗ 自分に合ったポジションと年収アップの両立を狙う。
マイナビジョブ20’sでプロにキャリア相談する
┗ 未経験職種やキャリアチェンジも含めた相談が可能。
よくある質問
- 「自分だけ昇給なし」はパワハラになりますか?
-
原則として「昇給の有無」だけではパワハラには該当しません。
ただし、明確な理由もなく特定の個人を意図的に昇給対象から外している、または「嫌がらせ的な評価操作」が行われている場合は、人事権の濫用や不当な差別にあたる可能性があります。
まずは評価基準と実績データを照合し、社内の人事または労働相談窓口に確認するのが第一歩です。 - 昇給がない会社に居続けるメリットはある?
-
昇給が止まっている会社に留まる理由は、スキルを積める環境があるかどうかで決まります。
もし仕事の幅が広がる、経験が蓄積できる、業務外で副業や資格勉強の余地がある――
このような条件があるなら、一時的に「環境を利用する」という選択もアリです。
逆に、成長実感も得られない・昇給制度も不透明なら“損失時間”が増えるだけ。転職を前提に準備を始めましょう。 - 昇給なしの理由をどう聞けば角が立たない?
-
伝え方のポイントは、“感情”ではなく“改善意欲”をベースにすること。
言い回し例:「今回昇給対象外になった理由を学びとして理解したいのですが、
次回昇給のためにどんな成果やスキルを意識すべきでしょうか?」この聞き方なら、攻撃的に見えず、前向きな成長姿勢として受け取られます。
面談後はフィードバックをメモし、3〜6ヵ月後の再評価時に具体的な成果として提示できるようにしましょう。 - 「昇給なし=頑張らなくていい」と割り切るのはOK?
-
短期的な“心の防衛”としてはOKですが、長期的にはリスクです。
モチベが切れると、スキル・実績の蓄積ペースも落ち、結果的に市場価値も下がるからです。
「会社のために頑張る」のではなく、「将来の自分のために努力を続ける」意識に切り替えるのがベスト。
会社に見切りをつけても、“自分の成長”は止めないでください。 - 給料が上がらないとき、転職と副業どちらが得?
-
結論:「まずは市場価値を確認してから判断」が正解です。
- 年収アップの転職が見込めるなら → 転職が効率的
- 現職に残りながら収入を増やしたいなら → 副業スタートも現実的
まずはミイダスで市場価値を可視化し、
ビズリーチで求人年収を比較。
さらに、20代ならマイナビジョブ20’s でキャリア面談を受け、
「副業 or 転職」どちらが自分に合うか整理しましょう。