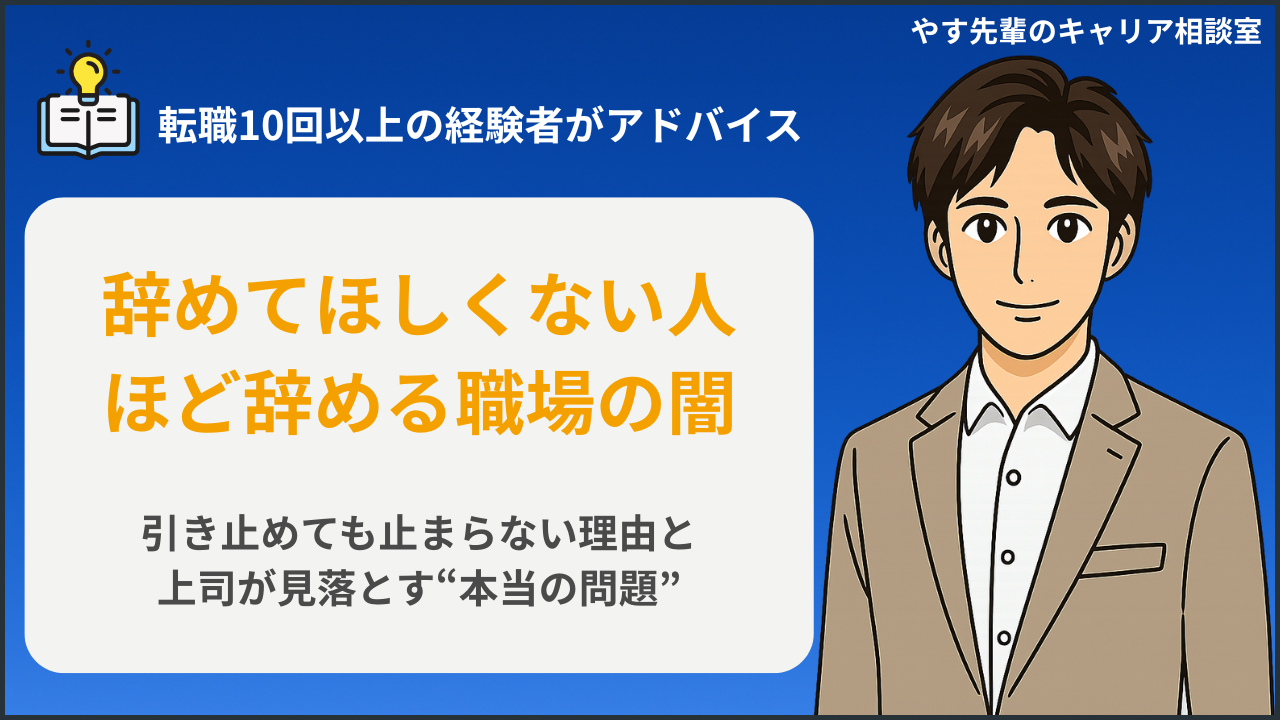やす先輩
やす先輩40代半ば、転職10回の管理職。上場もベンチャーもブラックも経験してきました。失敗も学びも交えながら、キャリアや働き方に悩むあなたへ“現実的な解決策”を届けます。
⇒詳しいプロフィール
「あの人に辞めてほしくなかったのに」
優秀で人望もある社員、チームの中心だったパートさん、誰からも信頼されていた派遣スタッフ。
そんな“辞めて欲しくない人”ほど静かに去っていく。
一方で、問題を抱える人ほど残り続ける。
それは偶然ではなく、職場の構造とマネジメントの在り方が生み出す必然です。
本記事では、なぜ“辞めて欲しくない人が辞める”のか、その心理・職場の特徴・引き止め方の限界を深掘りします。
さらに、「本当に守るべき人をどう支えるか」「辞められない職場をどう作るか」まで、実体験を交えて解説します。
ミイダスでチームメンバーの市場価値を知ると、“どんな人が辞めやすいか”も見えてきます。辞めてから気づく前に、「評価と環境のズレ」を把握しましょう。
⇒ミイダス市場価値診断を試してみる
辞めて欲しくない人が辞める理由とは
理由① 「頑張る人ほど損をする」構造になっている
辞めて欲しくない人ほど、責任感が強く、仕事を抱え込みやすい。
「自分がやらなければ回らない」と思い、周囲のミスや欠員もフォローしてしまう。
しかしその結果、頑張る人に負担が集中する“構造的な損”が生まれます。
本来は「成果に応じた評価」や「負担の分散」が必要なのに、
現実は「できる人がさらに仕事を振られる」仕組みが放置されがちです。
この状態が続くと、どんなに優秀でも報われなさと不公平感で心が離れていきます。



“あの人なら大丈夫”が、一番危険な言葉。
頑張る人を守らない職場は、いずれ優秀な人から去っていきます。
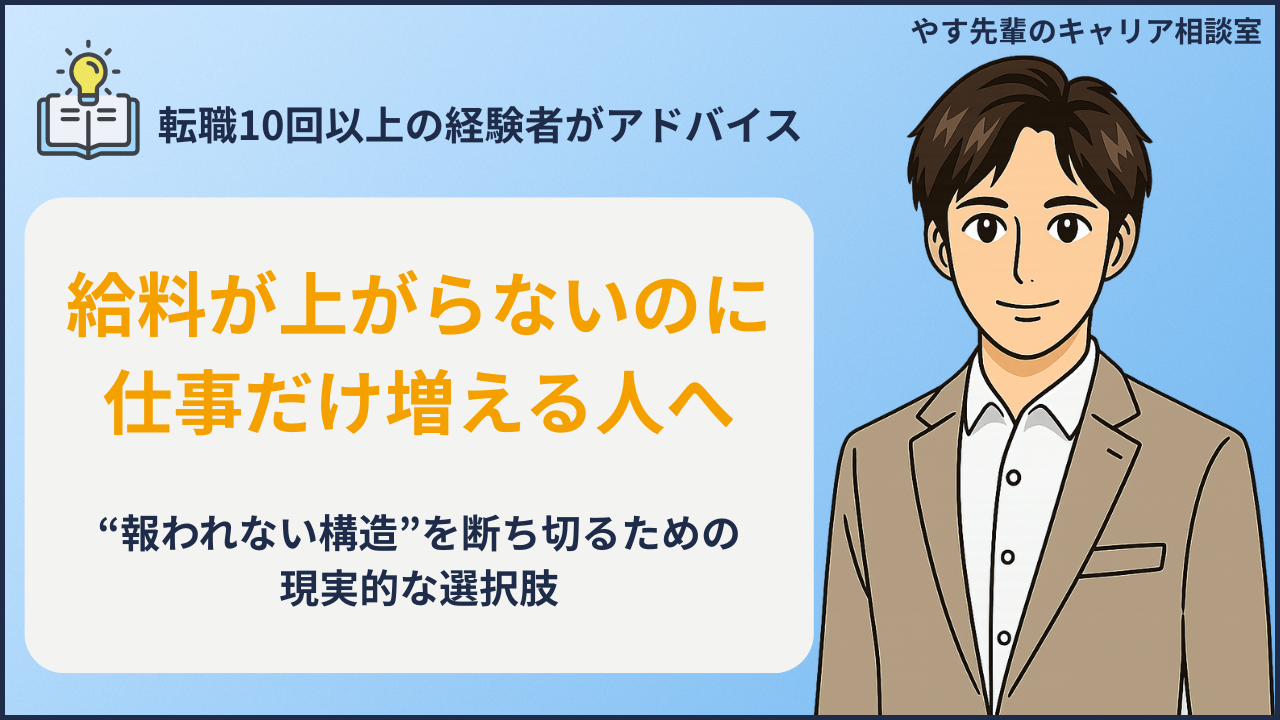
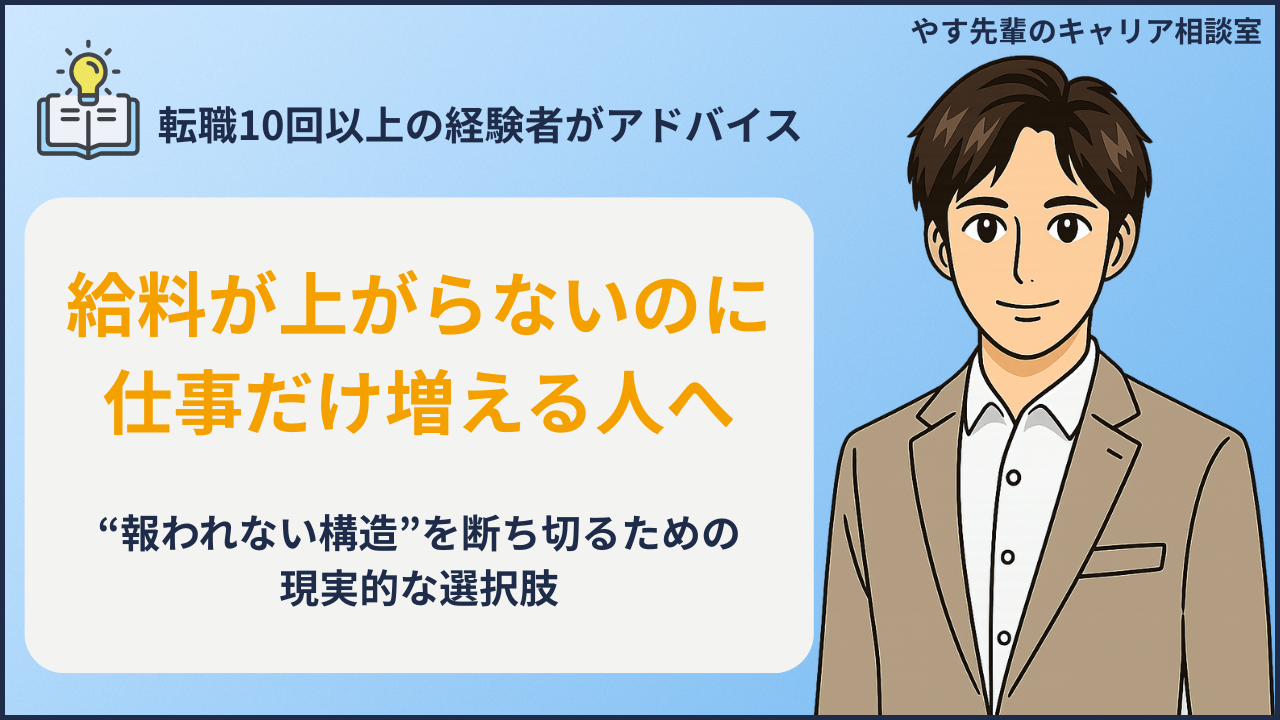
理由② 承認・評価より“我慢”が求められる職場
多くの人が辞める理由は、給料や業務量ではなく“認められない苦しさ”です。
辞めて欲しくない人ほど「もっと任せたい」「頼りにしてる」と言われながらも、
実際には感謝や評価が言葉にならないまま、日々の我慢を続けている。
組織が「問題を起こさない人」より「目立つ人」を評価していると、
誠実で支えるタイプほど報われない無力感を覚えます。
やがて「ここではもう自分の努力が意味を持たない」と悟った瞬間に、退職を決意します。



“文句を言わない人”を都合よく使っていないか。
我慢の上に成り立つチームは、静かに崩れていきます。
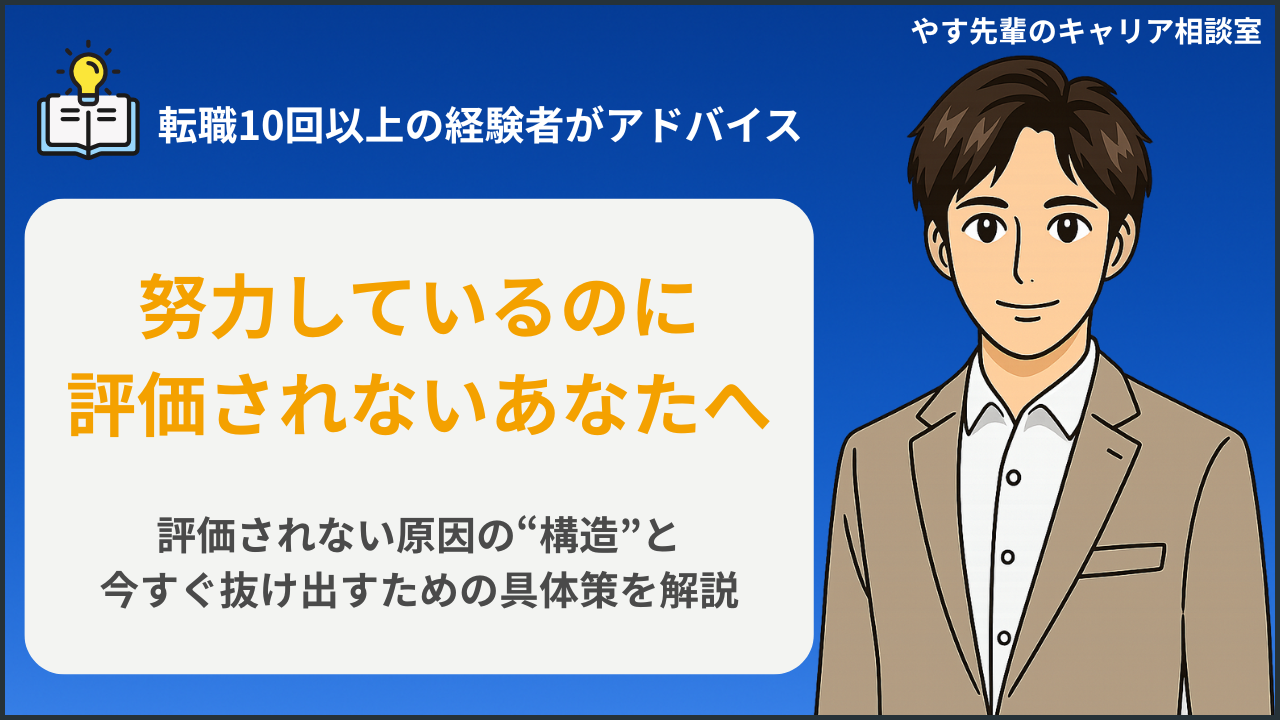
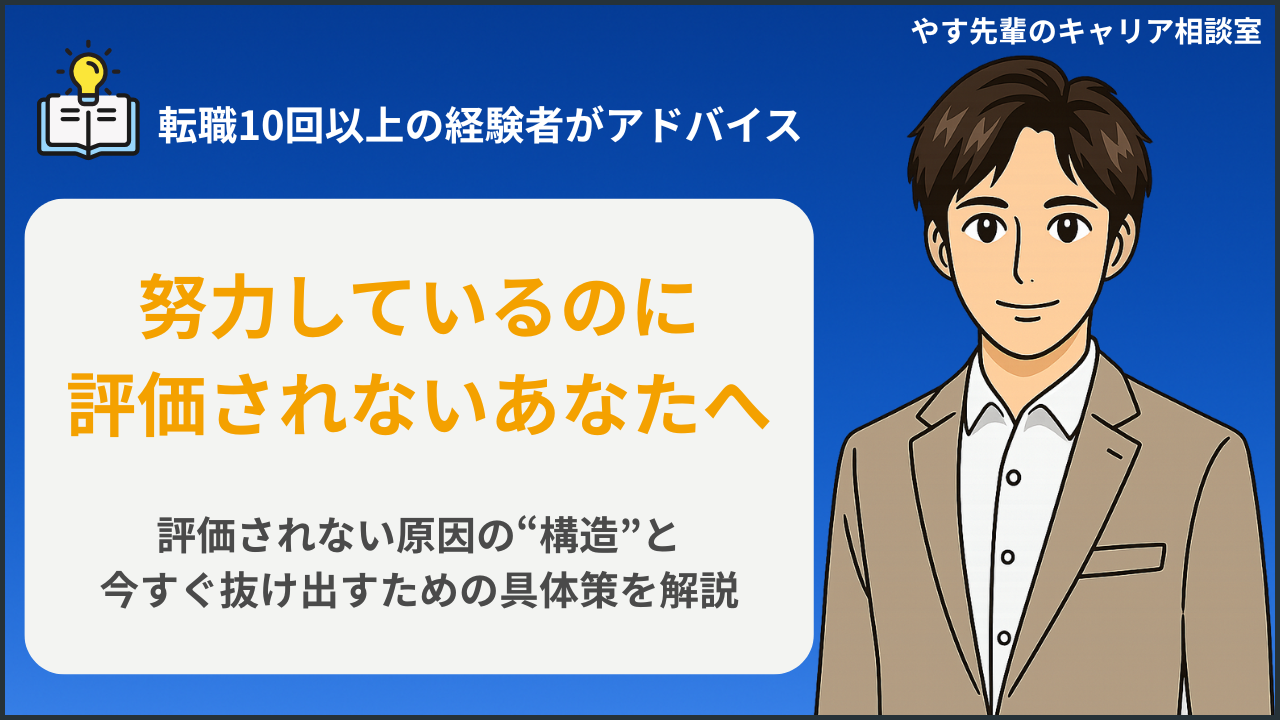
理由③ 上司・同僚の無関心が「限界サイン」を見逃す
優秀な人ほど、辞める前まで普段通りに見えるものです。
不満を口にせず、静かに限界を迎える。
上司や同僚がその“サイン”を見逃すと、気づいた時にはもう退職届が出ています。
よくあるのが、
- 発言が減る
- 雑談を避ける
- 残業が増えるのに愚痴を言わない
これらはすべて「もう頑張り切った」サインです。
関係が遠いと「大丈夫そう」と勘違いしやすく、
最も支えるべき人が一番孤立していく。それが“離職ドミノ”の始まりです。



“静かに辞める人”ほど、職場への信頼を失っていた。
相談されないのは、もう期待されていなかったということ。


理由④ 辞めて欲しくない人ほど「辞めたい」を言えない心理
責任感の強い人は、「辞めたい」と言うことを裏切り行為のように感じます。
「自分が抜けたら迷惑をかける」「タイミングが悪い」そうやって自分を後回しにし続け、
限界まで我慢して、ある日突然“限界スイッチ”が入る。
その瞬間には、すでに心が離れているため、引き止めても戻れません。
「もっと早く相談してくれれば」と言われても、
本人は“何度もサインを出していた”ことが多いのです。
辞めて欲しくない人を失うのは、「話せる空気」を作れなかった組織の責任です。



“辞めたい”と言える環境をつくることが、
“辞めたくならない職場”をつくる第一歩なんです。


辞めてほしくない人を引き止める前にやるべきこと
引き止めるより、まず“辞めたくなる原因”を探る
引き止め交渉をいきなり始めると、多くの場合は条件闘争にすり替わり、短期延命で終わります。先にやるべきは、「なぜ辞めたいのか」を構造で分解すること。
原因の棚卸しフレーム(5W1G)
- Work(仕事内容):役割のズレ、裁量の不足/過多、スキル不一致
- Workflow(プロセス):属人化、無駄、判断の遅さ、責任境界の曖昧さ
- With(人間関係):上司の指導スタイル、チームの衝突、孤立
- Wage(待遇):給与・等級・評価ロジックの不透明さ
- Well-being(健康):残業負荷、メンタル、私生活との両立
- Growth(成長):学習機会、キャリアの道筋、次の挑戦の不足
まずはこの6領域で“何点の不満が何個あるか”を可視化。総量よりも最も深刻な1~2点を特定し、そこに施策を当てるのが筋。
避けるべき失敗
- 「頑張ってくれてるのは分かってる」など抽象的な共感だけで終了
- 目先の昇給・肩書の付け替えでごまかす(根治にならない)
- 上司自身が原因なのに“組織の都合”で片付ける



“何が嫌?”ではなく“どこが壊れてる?”と聞ける上司が、離職を止められる。
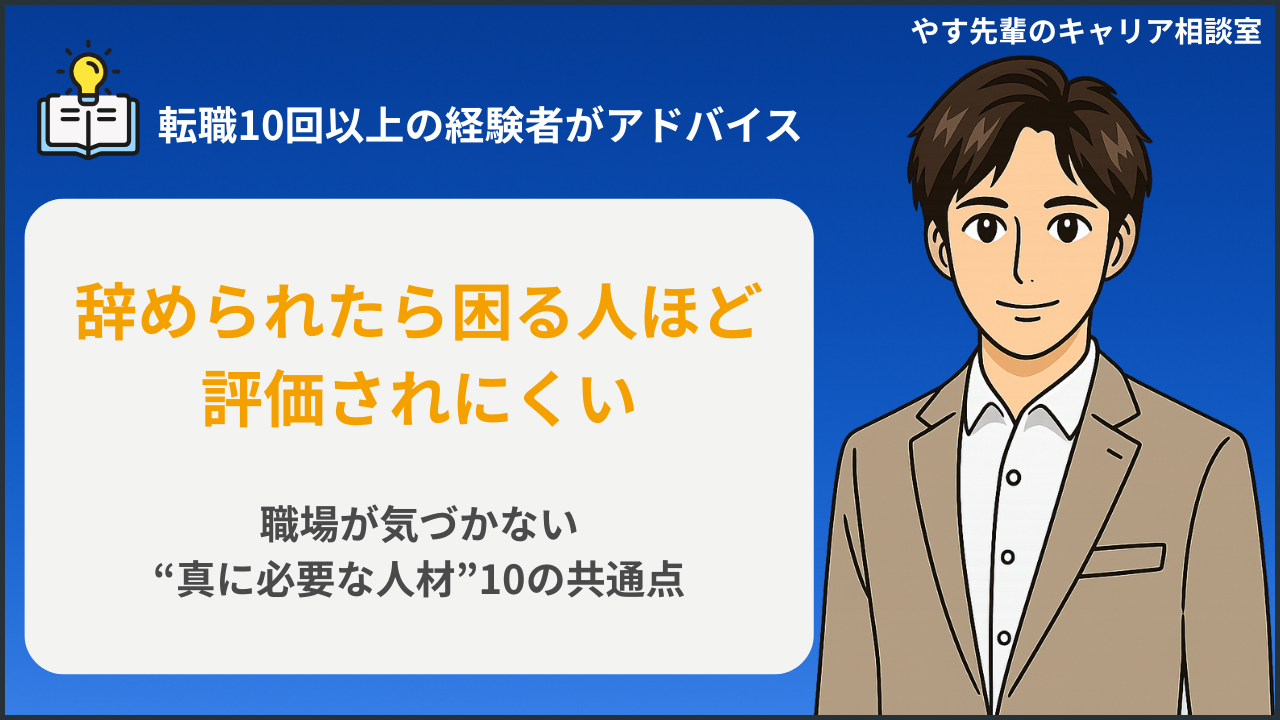
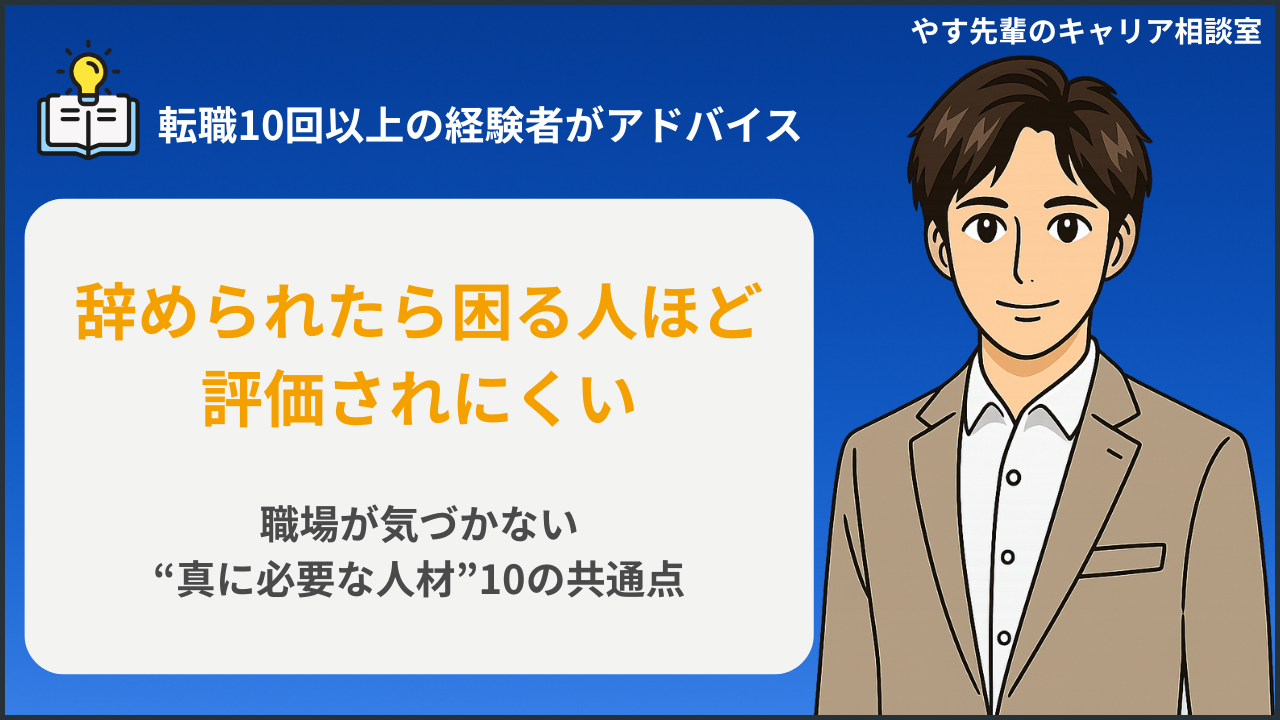
本音を引き出す1on1の質問例(例文付き)
本音は、「残ってほしい」と詰めるほど出てきません。評価や防衛心が働かない問いで、相手に語ってもらう設計が必要。
1on1(導入30秒)
- 「今日は評価でも説得でもなく、状況の整理を一緒にしたい。結論は今日出さなくていい。」
掘る質問(実例)
- 事実の確認:「最近“これが辛い”と感じた具体的な出来事を3つ、時系列で教えて」
- 良かった点の抽出:「この1年で“楽しかった瞬間”や“誇りに思えた仕事”は?」
- 差分の特定:「“続けたい理由”と“辞めたい理由”を比率で表すと何:何?」
- 理想状態の言語化:「半年後、“最高の状態”は何がどう変わっている?」
- 阻害要因の特定:「それを邪魔している“人/ルール/プロセス”は?」
- 可変領域の合意:「この中で僕(上司)に変えられることはどれ?」
- 短期アクション:「来週から始められる、小さな改善を一緒に3つ決めよう」
NGワード
- 「うちの事情も分かって」:相手の事情を無効化
- 「みんな我慢してる」:個人の声を埋没させる
- 「辞めたい気持ちを一旦忘れて」:感情の否認



「今の話を要約すると、役割の曖昧さと評価の不透明さが核。合ってる?」認識合わせが信頼になる。
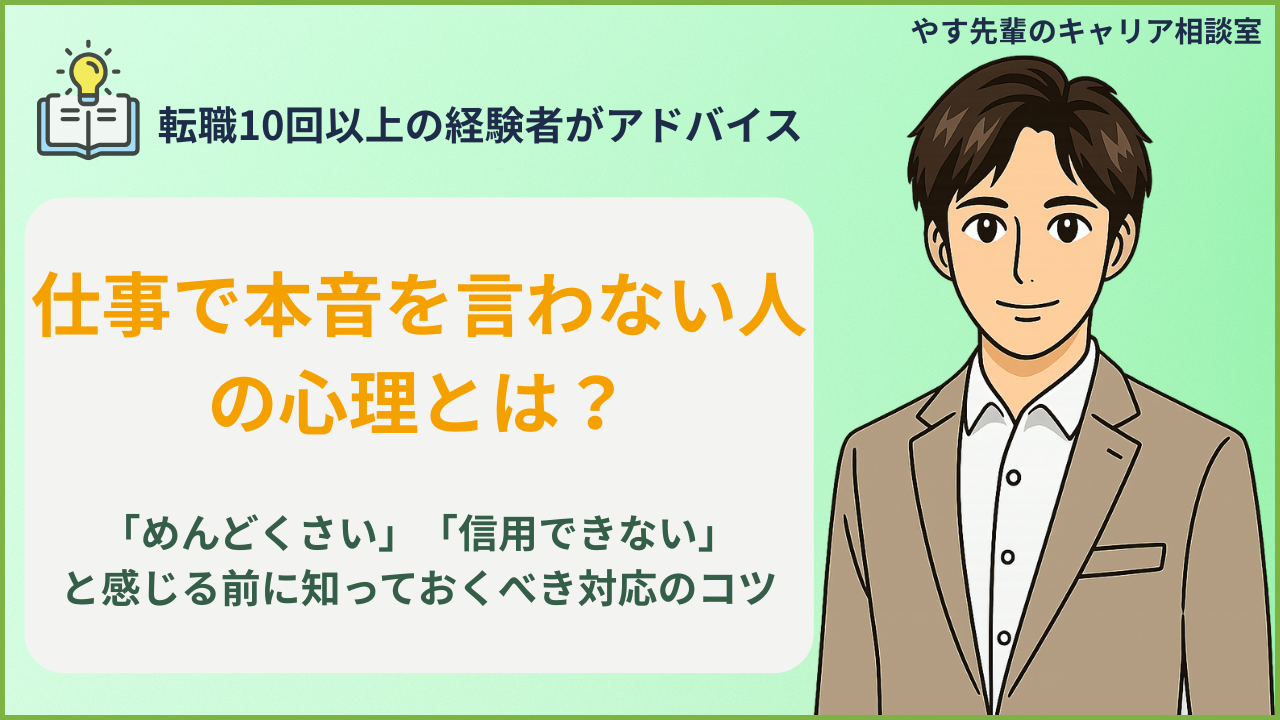
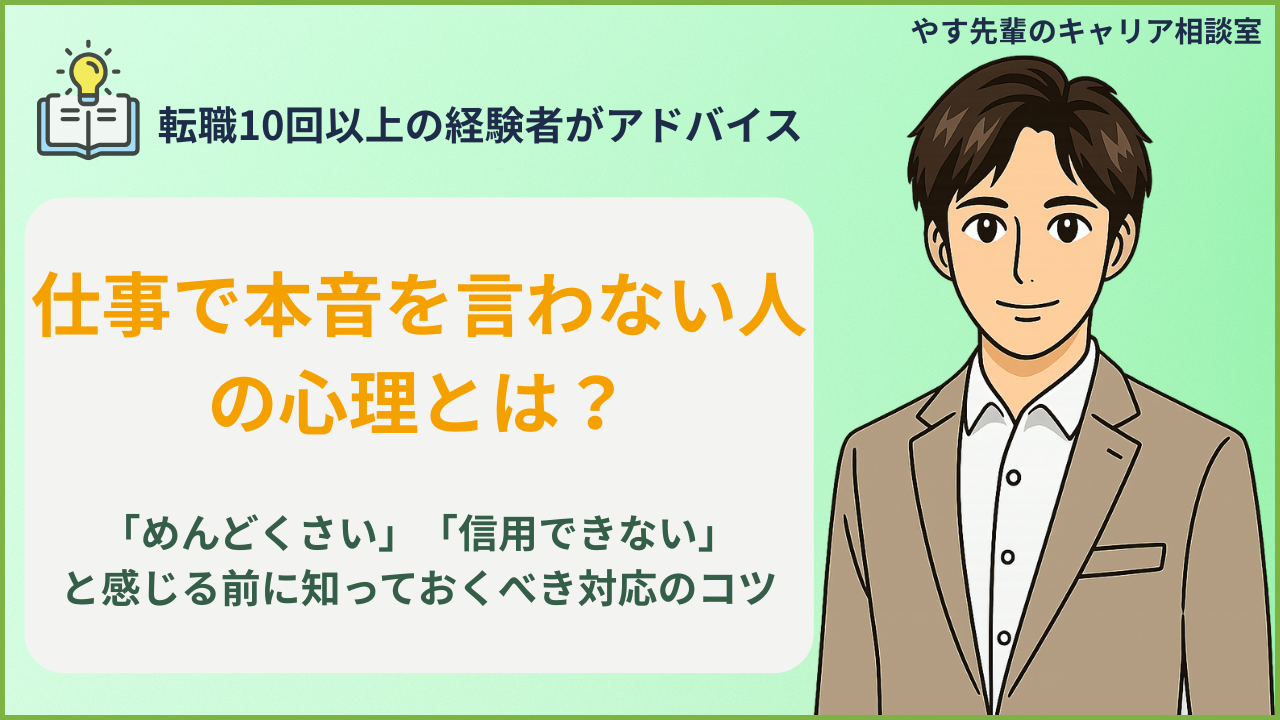
「給料」「人間関係」「やりがい」どれがボトルネックかを見極める
離職要因は大きく報酬(Pay)/関係(People)/仕事(Purpose)の三本柱。どれが主因かで処方箋が変わります。
① 給料(Pay)が主因
- 症状:同業比で低い/昇給ロジックが不明/成果と報酬が連動しない
- 処方:透明な等級テーブルの提示/半年以内の補正計画/成果連動の特別ボーナスの暫定導入
- 指標:市場中央値への乖離率、社内昇給決定までのリードタイム
② 人間関係(People)が主因
- 症状:上司のマイクロマネジメント、対話不足、心理的安全性の欠如
- 処方:上司のチェンジorメンター併走/担当替え/週次1on1(15分)の定着
- 指標:1on1実施率、eNPS(推奨度)変化、相談→改善までの平均日数
③ やりがい(Purpose)が主因
- 症状:成長実感がない/同じ業務の繰り返し/成果の意味が見えない
- 処方:ストレッチ課題の付与/プロジェクト兼務/役割定義の再設計(Job Crafting)
- 指標:学習時間、新スキルの獲得、成果に紐づく顧客価値の可視化



“全部です”に見えても、一本の太い根がある。そこを外すと、離職の熱は下がる。
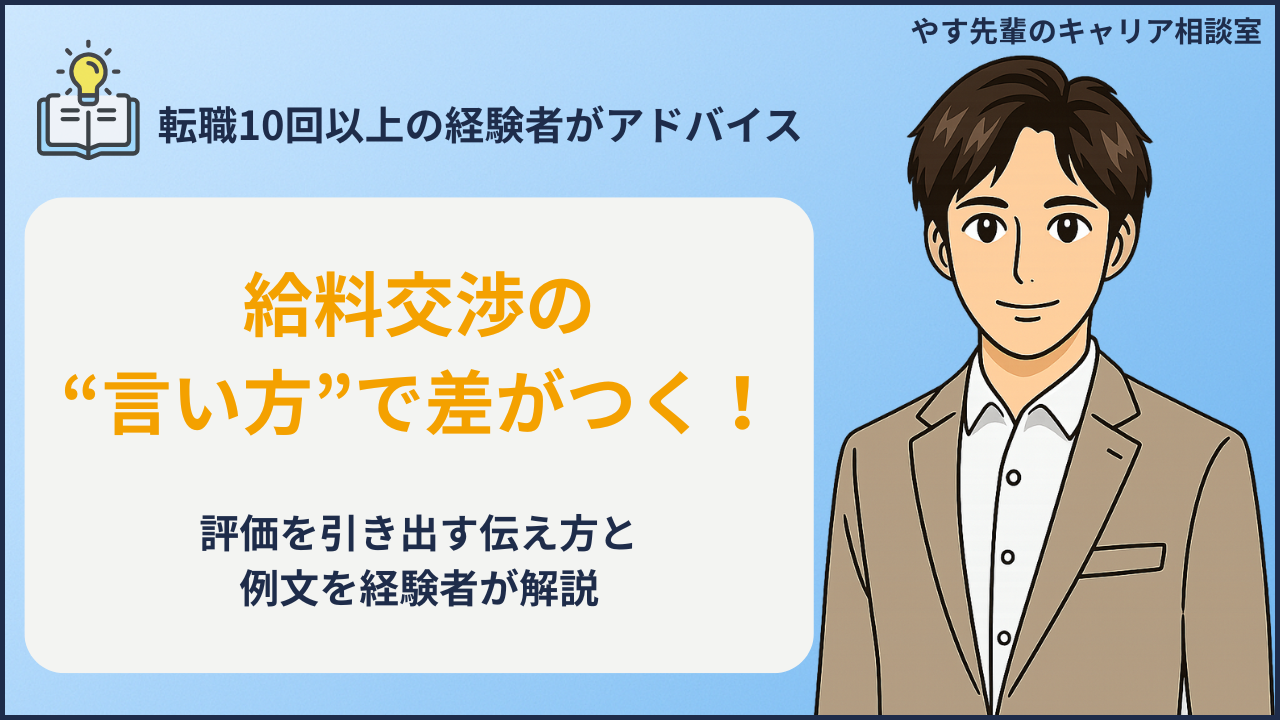
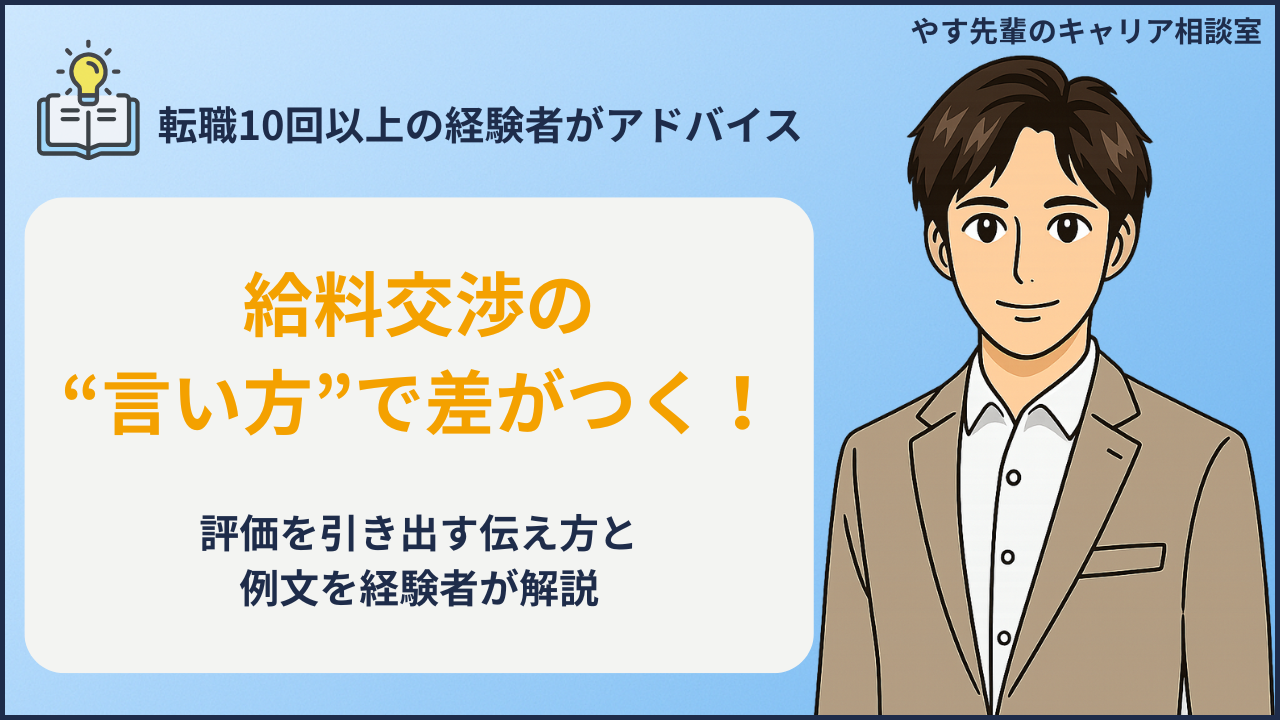
辞めてほしくない人を“評価で守る”職場文化の作り方
離職防止は口説きではなく制度と日常の積み上げ。“評価で守る”とは、個人の努力が見える→認める→報いるまでを仕組みにすること。
仕組み① 可視化
- 成果の定義を文字化(例:KPI+再現行動)
- 貢献ログ:週1で「やったこと→影響」を60秒記入(上司が承認スタンプ)
- 称賛の公募:月1でチーム相互のThanksカード収集・公開
仕組み② 承認
- 1on1で“良かった→理由→次の活かし方”の順に言語化
- 会議冒頭3分のWin共有(成功・工夫・支援の感謝)
仕組み③ 報酬
- ピアボーナス(少額でも即時性のあるインセンティブ)
- 役割手当の再設計(調整・教育・品質など“目に見えない貢献”に対価)
- キャリア選択肢の複線化(専門職/マネジメントの同格昇進)
現場で今日からできる2アクション
- “見えない仕事”リスト化:新人サポート、議事録、調整、品質レビュー。
誰が担っているかを洗い出し、責務化&手当化。 - 退職予防の定点観測:発言頻度・残業推移・1on1記録を月次レビュー。静かなサインを早期に拾う。



“残ってほしい”は言葉。“残りたくなる”は設計。 日々の小さな可視化と承認が、最大の引き止め策になる。
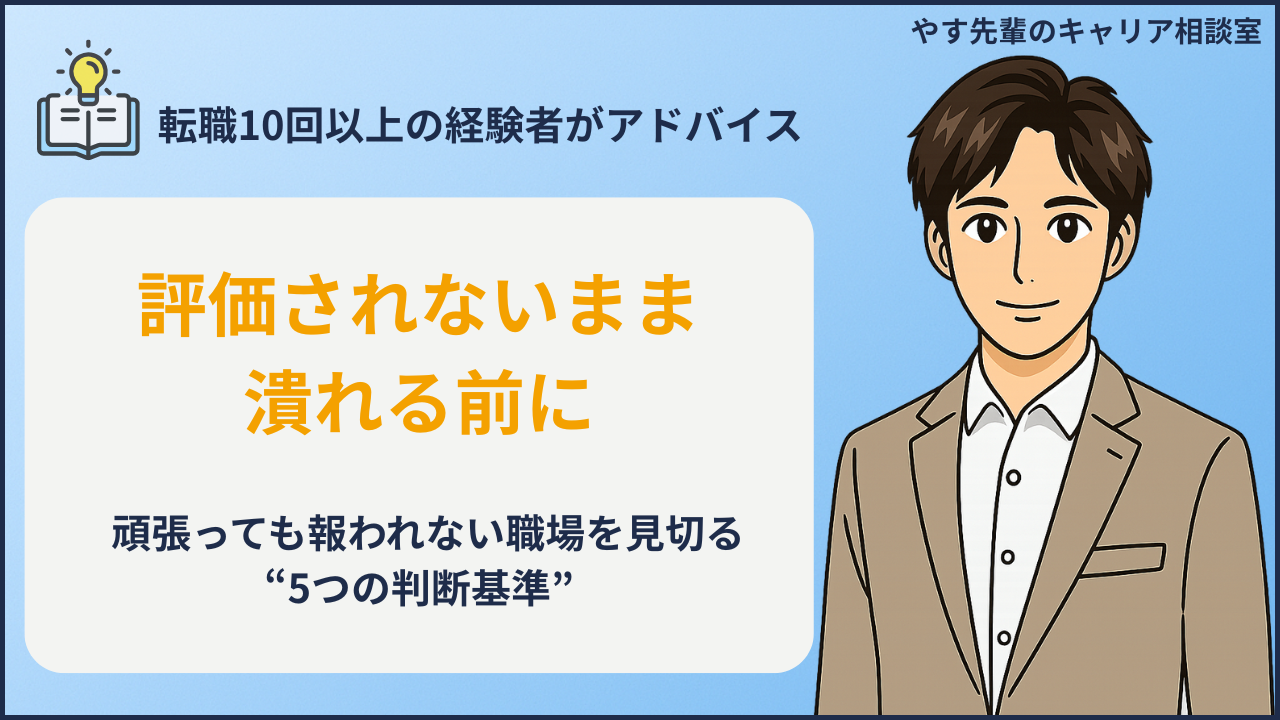
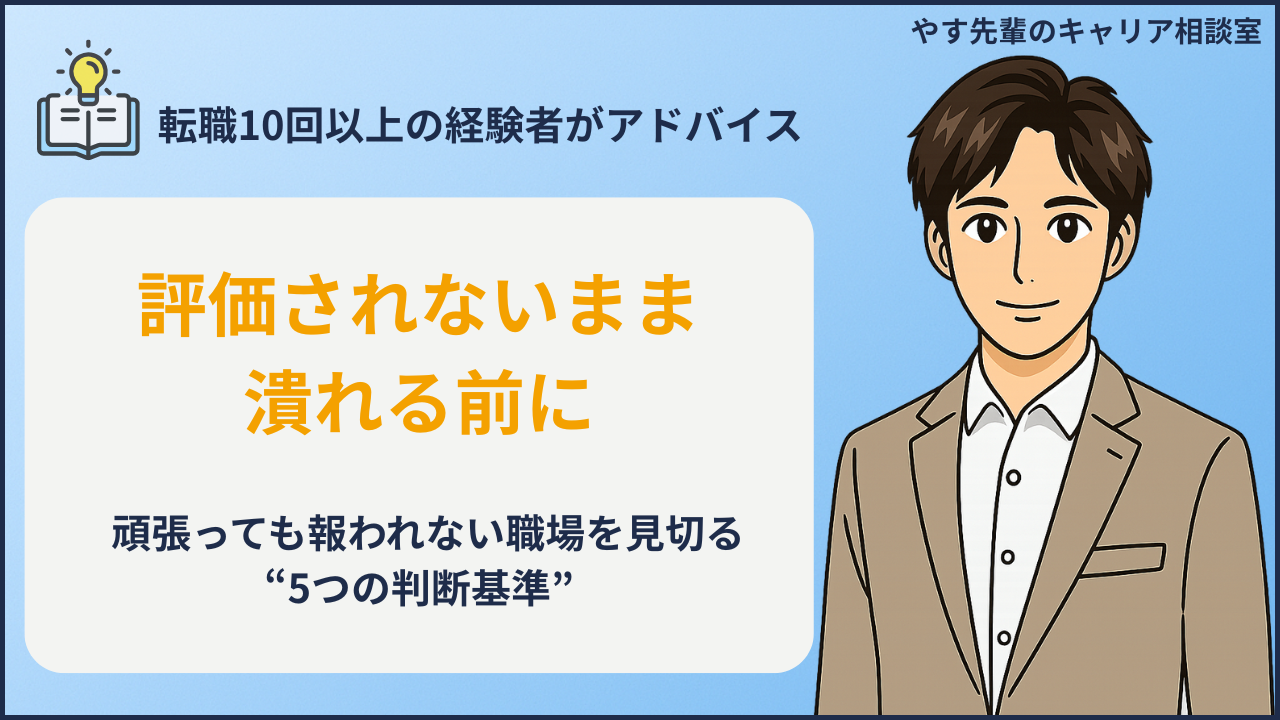
辞めて欲しくない人の特徴と兆候
特徴① 「責任感が強く、限界まで抱え込むタイプ」
辞めてほしくない人の多くは、「自分がやらなければ」と思い込む責任感の強いタイプです。
仕事が増えても「大丈夫です」と笑い、チームのフォローも率先して行う。
しかしその裏で、自分を追い込み、心の余裕を失っていることが少なくありません。
彼らは「迷惑をかけたくない」「周りに頼れない」という思いから、助けを求めるのが遅れる傾向があります。
表面上は穏やかでも、内面では疲弊し、限界を超えた瞬間に突然「退職」という決断を下すケースが多いのです。



“任せて安心”の裏には、“誰にも頼れない孤独”が隠れてる。
その人の“我慢”が、チームの支えになっていることを見落とさないで。
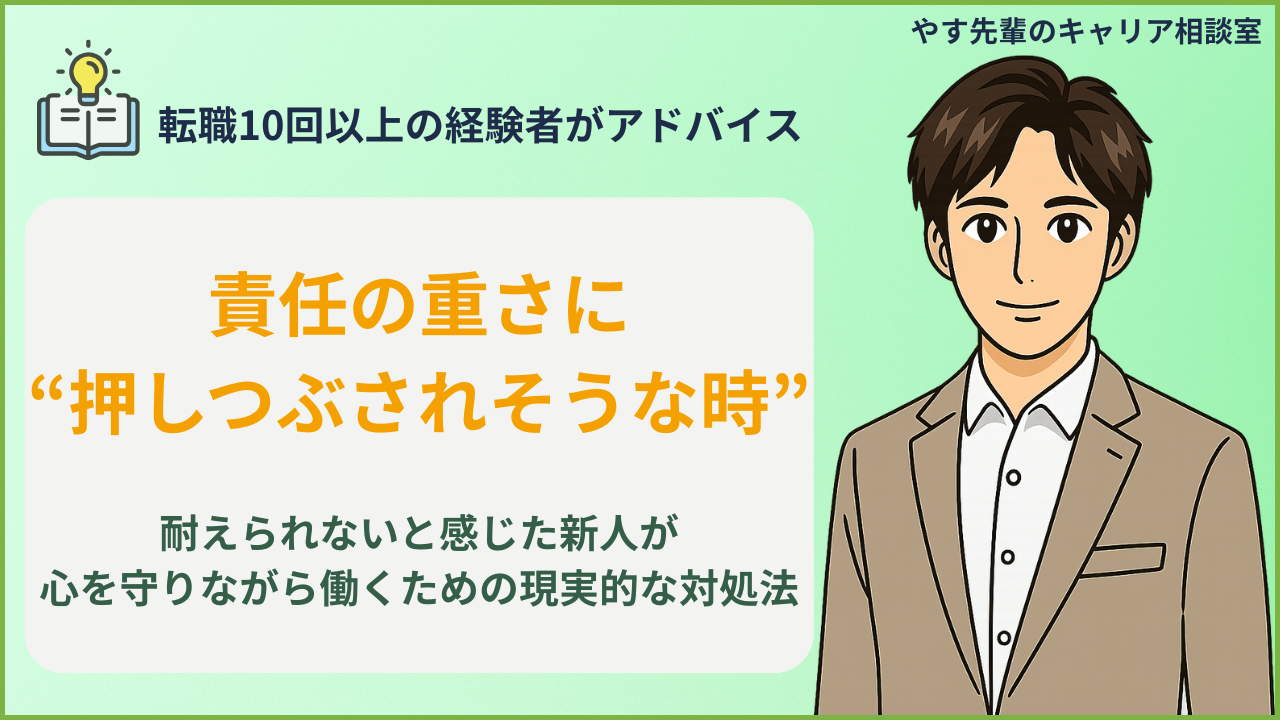
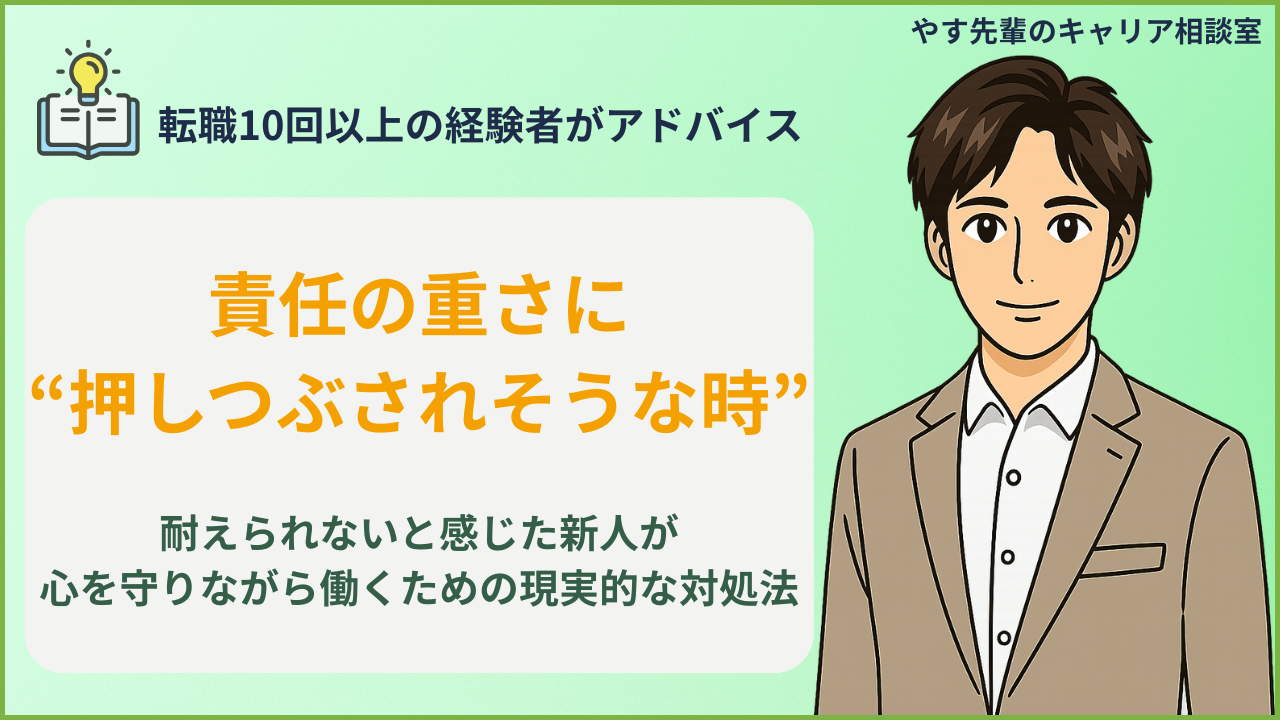
特徴② 「空気を壊さない“調整型リーダー”」
辞めてほしくない人ほど、周囲との調和を保つ“潤滑油”のような存在です。
意見がぶつかれば間に入り、誰かが困っていればフォローに回る。
組織の中では頼られ、表面上は安定して見えるものの、実際は感情のバランスを常に調整しているストレスフルな立場にあります。
この“調整型リーダー”が辞めると、チームの空気が一気に崩れるのが特徴です。
なぜなら、彼らの存在は「誰にも見えない安心感」を支えているから。
その存在を軽視し、感謝や評価を伝えないまま放置すると、
「自分がいてもいなくても同じ」と感じ、静かに去っていきます。



“空気を読む人”ほど、空気に傷ついてる。
優しさに甘えすぎると、その優しさごと職場からいなくなる。
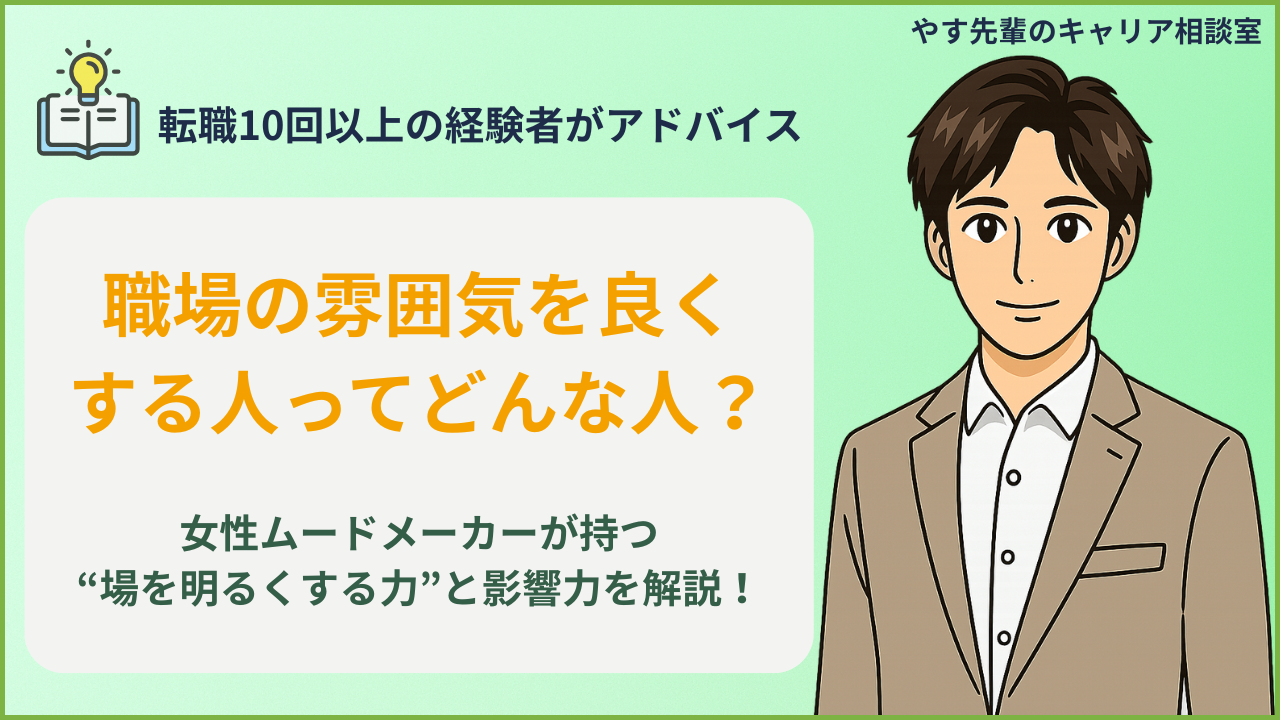
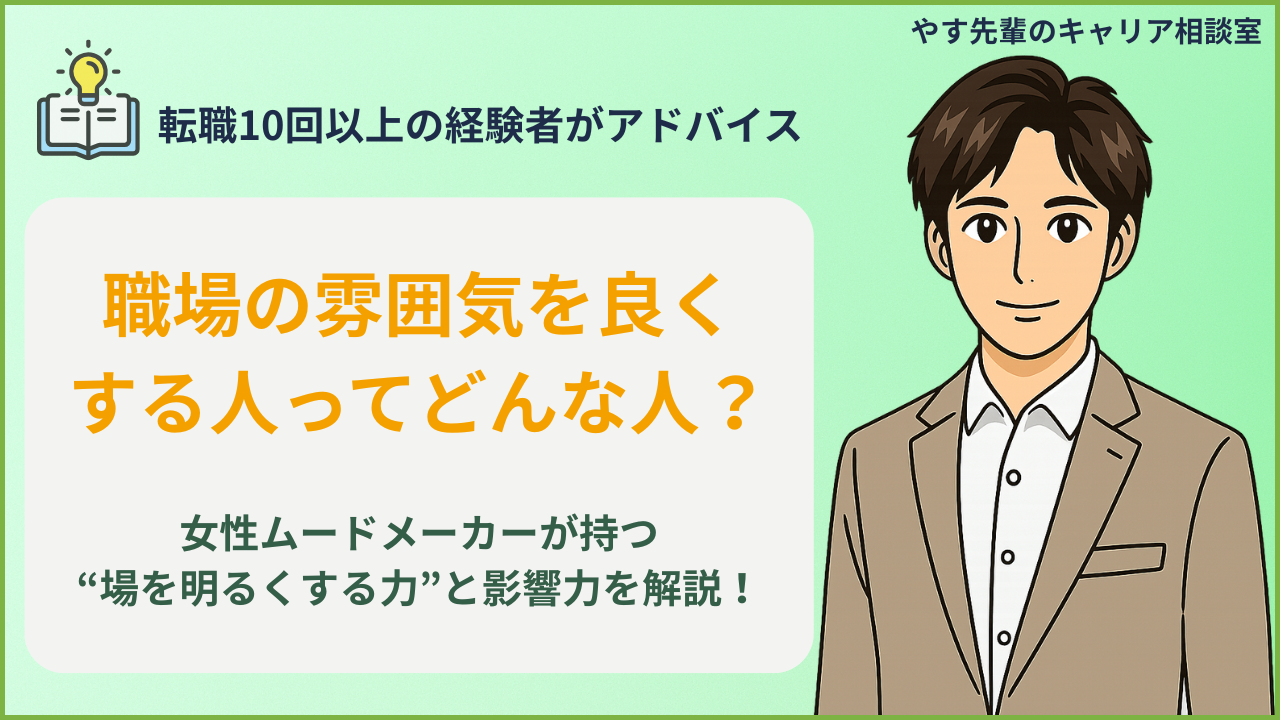
特徴③ 「辞める直前まで普段通りに振る舞う」
「辞める人ほど、前日まで普通に働いていた」これは多くの上司が経験する“離職の鉄則”です。
辞めてほしくない人は、最後まで責任感とプロ意識を捨てないため、退職を決めても周囲に気を遣って隠す傾向があります。
だからこそ、突然の退職報告が衝撃に感じられるのです。
実際には、その何ヶ月も前から“予兆”は出ており、
- チャットの返信が短くなる
- 休暇の取り方が変わる
- 自分の仕事を他人に共有し始める
といった小さな行動変化が見えています。
このサインを「忙しいだけ」「一時的なこと」と軽視すると、取り返しがつかなくなります。
普段通りの中にこそ、“静かなSOS”が隠れているのです。



“急に辞める人”なんていない。
ただ、周りが“見ようとしてなかった”だけなんです。
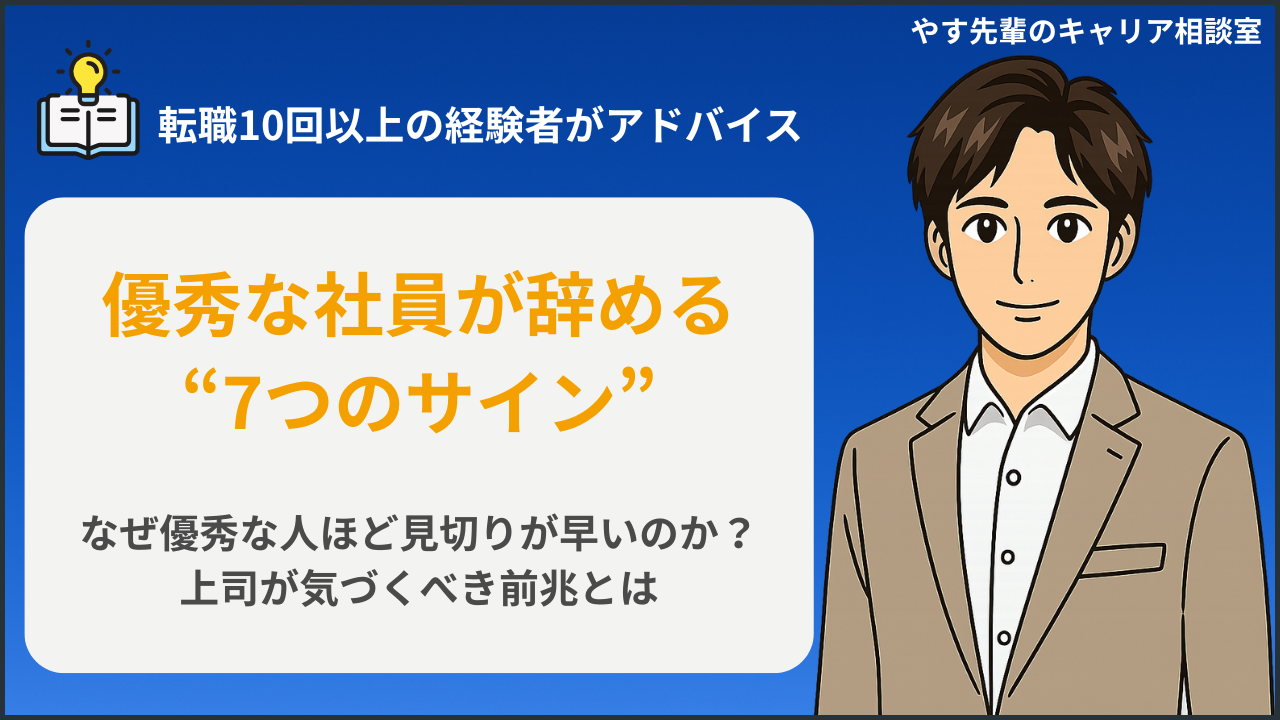
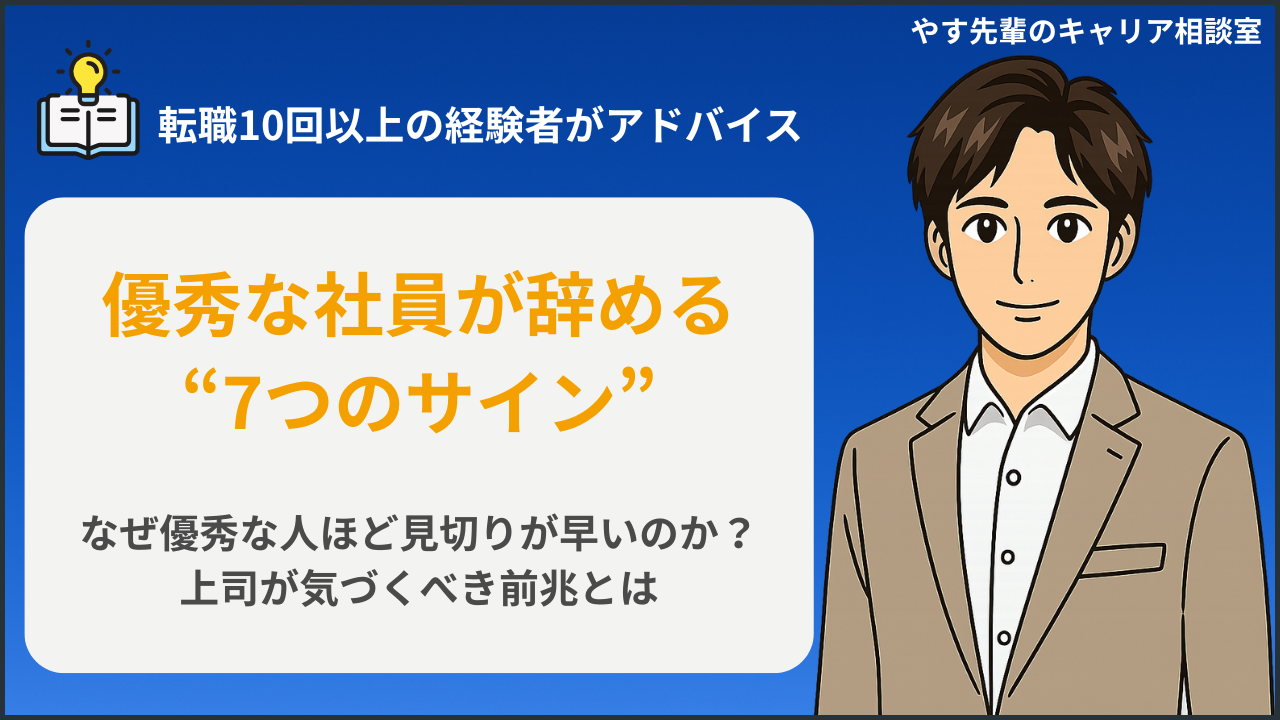
兆候チェックリスト:沈黙・残業・発言減少が危険信号
「辞めてほしくない人」が発しているサインを早期に気づくために、
以下の5つのチェックリストを定期的に見直すことをおすすめします。
✅ 辞める予兆チェックリスト
- 雑談や意見発言が減った(関心より“距離”を取り始めている)
- 残業や休日出勤が増えた(抱え込み/仕事整理のサイン)
- 他部署との関わりが減った(視野が縮まり、エネルギー低下)
- 小さなミスや遅延が増えた(集中力・心の余裕の欠如)
- 「感謝」「評価」に反応しなくなった(心が職場から離れている)
1つでも当てはまるなら、“要観察”。
2つ以上なら、“早期介入”。
3つ以上なら、“面談・サポートが必須”の状態です。
放置すると、本人は「もう何を言っても変わらない」と諦め、
退職という最終手段でしか環境を変えられなくなる。



“辞める前兆”は静かに現れる。
その沈黙を放置する職場は、優秀な人ほど去っていく。
辞めてほしくないパート・派遣社員の離職防止策
パート:感謝より「時間の尊重」と「公平な評価」
パート社員にとって最大のモチベーションは、“感謝の言葉”よりも「時間を無駄にしない職場」であること。
家庭・子育て・介護など、さまざまな事情を抱える中で働いているからこそ、
「急なシフト変更」「不公平な仕事配分」「曖昧な評価」は、最も離職につながる要因になります。
特に多い不満は、次の3つです:
- 長く勤めても昇給がない(貢献の見えない不公平)
- 一部の人だけが優遇される(評価基準の不透明さ)
- 意見を言っても反映されない(“戦力”として扱われない)
離職を防ぐには、「感謝」+「ルールの明確化」がセットで必要です。
- 評価シートを形式だけでなく実際に運用する
- 1on1やミーティングで希望を聞く時間を設ける
- 急な呼び出し・残業を避ける“時間の約束”を守る



パートの人たちは“補助”ではなく“戦力”。
感謝より“誠実な約束”が、信頼を育てる一番の近道です。
派遣:待遇よりも「信頼関係」と「相談できる空気」
派遣社員の離職理由で最も多いのは、“待遇”ではなく「孤立」です。
どんなに時給が高くても、「相談できる人がいない職場」では長く続きません。
多くの派遣社員が抱えるストレスは、
- 「正社員との壁」
- 「意見しても聞いてもらえない距離感」
- 「責任だけ増えて権限がない」
という“見えない不平等感”です。
これを防ぐには、形式上の「仲間入り」ではなく、実質的な「信頼関係の構築」が鍵です。
たとえば、
- 定例会やチャットに同じ立場で参加できる設計
- 「派遣だから…」という言葉を社内文化から消す意識
- 成果・提案を正社員と同じ基準で認める評価基準
そして何より、上司が「困った時に話せる存在」であること。
この“相談のハードル”を下げるだけで、派遣の定着率は驚くほど上がります。



“派遣だから”という線引きは、信頼を奪う言葉。
人は待遇より、扱われ方で辞めるんです。


辞めてほしくない女性社員の“モチベーション維持法”
女性社員の離職は、出産・育児などライフイベントだけでは説明できません。
実際には、「頑張っても報われない」「意見しても変わらない」などの“心理的な天井”が原因で辞めていくケースが多いのです。
モチベーションを維持するには、“貢献の可視化”と“キャリアの選択肢”が鍵です。
- 成果やプロジェクト貢献を上司が代弁して伝える文化
- 「管理職」だけでなく「専門職」「時短リーダー」などの複線型キャリア制度
- 子育て・介護・学び直しなどの一時的な中断をキャリアダウンにしない設計
また、上司側の“共感コミュニケーション”も不可欠です。
「大変だね」ではなく、「どうすれば今の状況を一緒に改善できるか?」という伴走型の姿勢が、信頼につながります。



女性の離職は“意識の温度差”で起きる。
理解より“共に考える姿勢”があれば、辞める理由は一気に減ります。
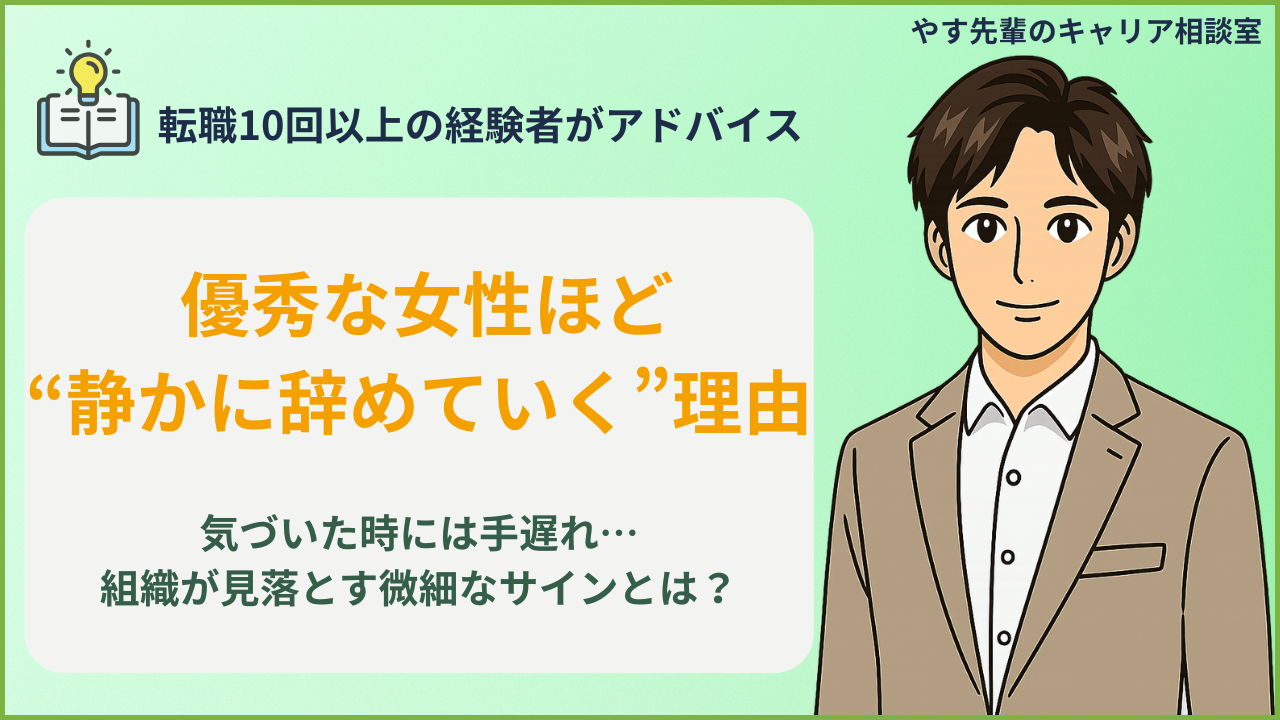
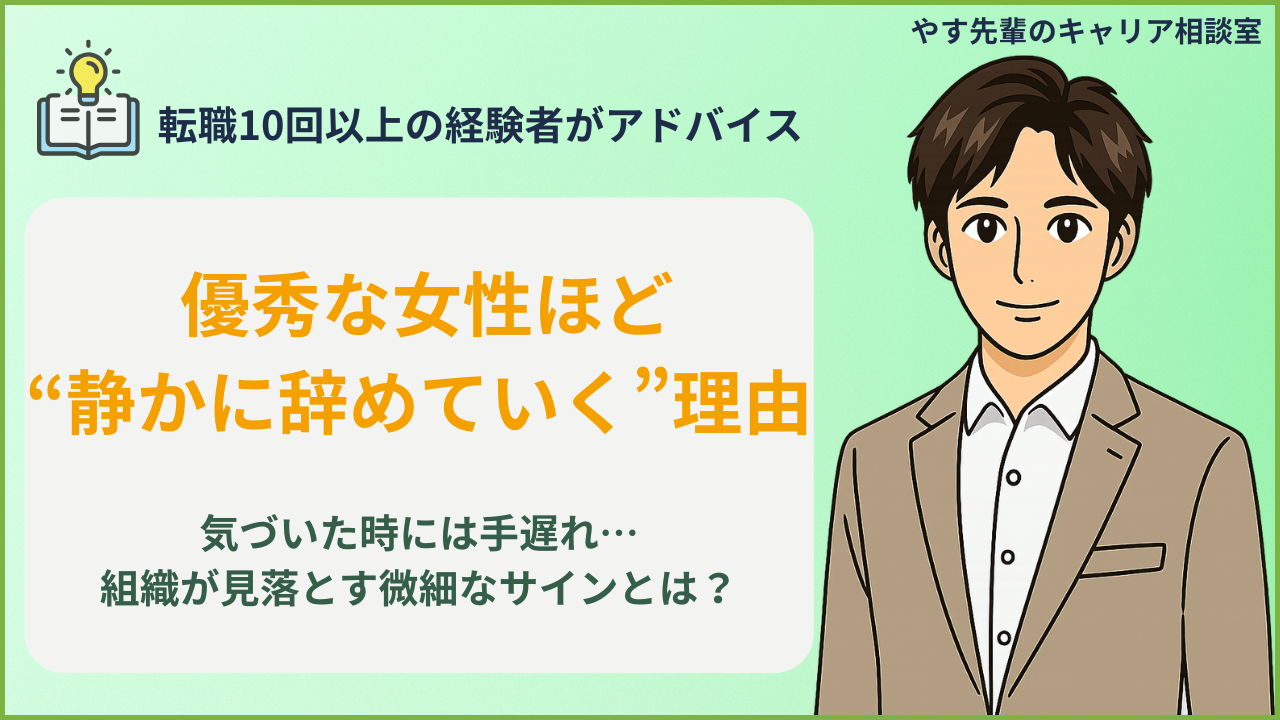
優秀な人が辞めないためのチームの関わり方
どれだけ制度を整えても、最終的に人が辞めるかどうかを左右するのは“人間関係の温度”です。
辞めてほしくない人を守るために、チーム全体で意識すべきは次の3点です。
- 「当たり前」を言葉にする文化
「いつもありがとう」「助かった」「あなたがいて良かった」
これを言わない職場ほど、離職率は高い。 - 小さな成功を一緒に喜ぶ
月次報告や日報で、数字ではなく行動や工夫を称賛する。
“評価”ではなく“共感”で支える意識が重要。 - 孤立を防ぐ“ケアの分散”
上司だけで支えず、チーム全員で見守る仕組みを作る。
「最近あの人元気ないね」と言い合える文化は、離職防止のセンサーになります。



辞めてほしくない人を残すには、特別な制度より“普通の温かさ”が必要。
それを日常で積み重ねられるチームが、強い職場をつくります。
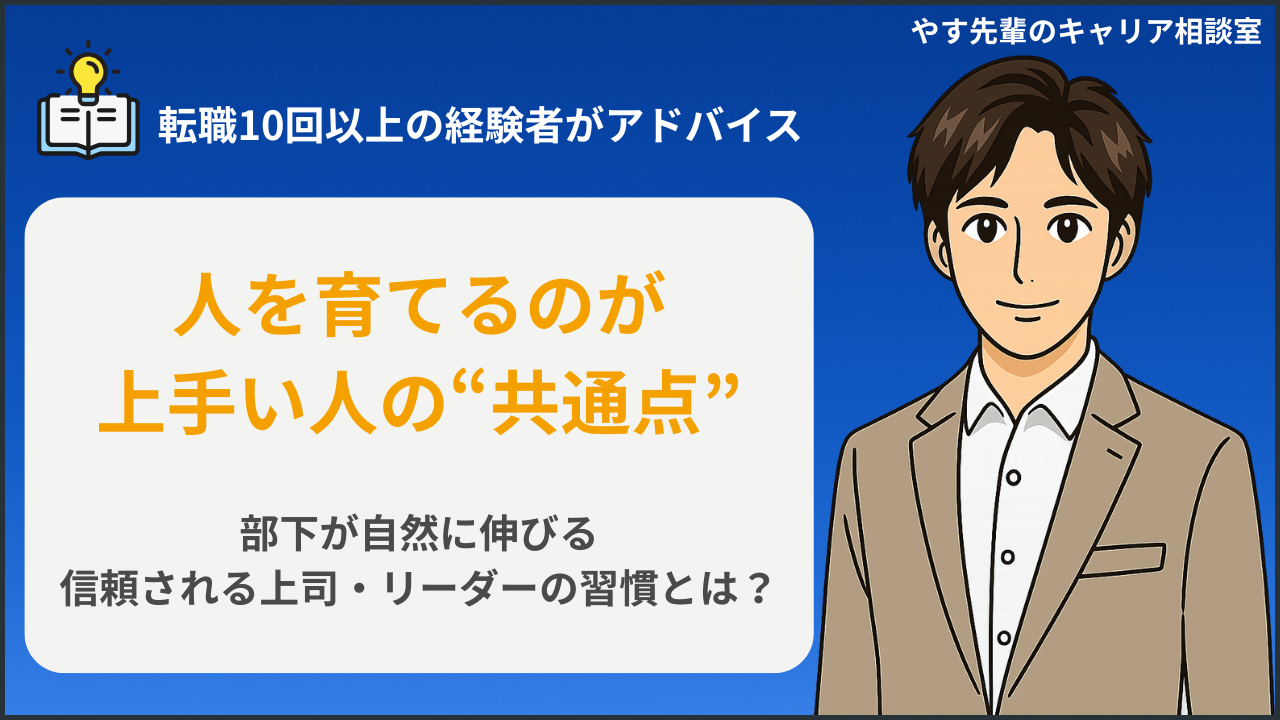
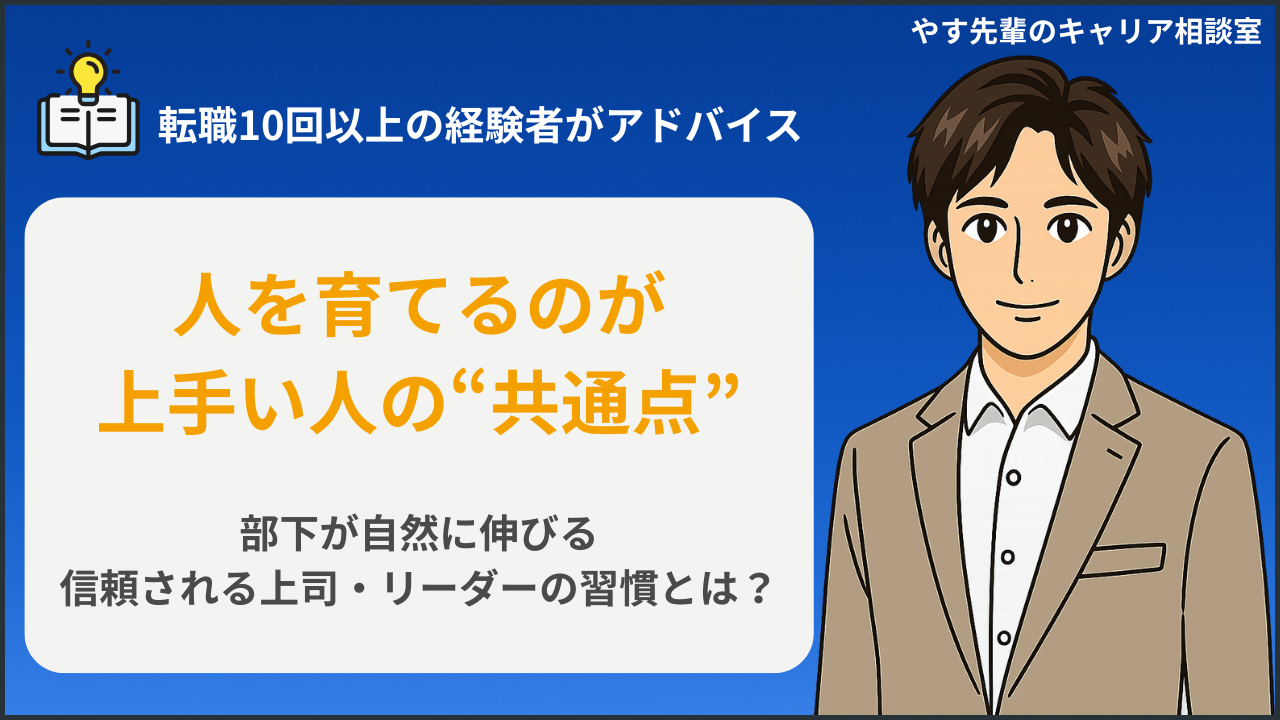
やす先輩の体験談:辞めてほしくない人が去った日
当時の状況:チームの中心だった後輩が突然退職
その後輩は、火消しも新規も淡々とこなす“静かな柱”でした。
朝一で共有、昼に進捗、夕方にリスクと依頼。誰も気づかない穴を先回りで埋めるタイプ。
ある日、「今月いっぱいで退職します」と一行のスラック。会議室で理由を聞いても、表情は穏やかで、恨み言はゼロ。
「ここでは、私の“良い仕事”が“当たり前”になっている気がして」とだけ。



“辞めてほしくないと 言われた”経験、彼にも過去にあった。
でも『普段は何も変わらないのに、辞める時だけ言葉が増える』。その温度差が、決定打になる。
感じたこと:引き止められないのは“信頼を失ったサイン”
引き止めの言葉は用意できる。でも、言葉が届く相手は、まだ職場を信じている人だけ。
彼はもう、信頼の口座を空にしていた。
週次1on1はやっていたけれど、成果の称賛より手戻りの指摘が多かった。
相談も「忙しいから後で」になる日が続き、小さなSOSを受け止めきれなかった。



“引き止められない”のは、こちらの誠実さの残高がゼロということ。
引き止めは“最後の会話”じゃなく、それまでの会話の総和で決まる。
行動:残るメンバーの声を聴き、改善提案を上層部へ
まずやったのは、“原因探し”ではなく“感情の回収”。
チームに匿名フォームを用意して、嬉しかったこと/しんどかったこと/変えてほしいことを募集。
集まったのは、「調整や教育の見えない仕事が評価に反映されない」「在宅と出社の負担差が放置される」など、静かな不公平の声。
これをデータ化して上層部へ提案。
- 評価指標の更新:KPIに“調整・教育・品質”の再現行動を追加(配点を明示)
- 称賛の制度化:月1回、Thanksカードとピアボーナスを導入
- 1on1の設計変更:議題を「良かった→理由→次の活かし方→困りごと」の順に固定
- 業務の見える化:誰が何を抱えているかをカンバンで可視化、抱え込みをチームで検知



“優秀な人が辞める理由”は個別に見えるけど、制度で直せる共通項が必ずある。
結果:職場の風土が少しずつ変化
3か月で数字が動き出した。1on1満足度は3.1→4.2、ピアボーナス件数は月5→28、
会議冒頭の“Win共有3分”で称賛の語彙が増え、発言者が固定されなくなった。
「辞めたいときに早めに相談できた」「調整の仕事に点が入るのが嬉しい」という声も上がる。
離職がゼロになったわけではないが、“静かに去る”が“事前に話せる”に変わった。これは大きい。



風土は合言葉で変わる。『当たり前を言葉にしよう』を合言葉にしたら、
“ありがとう”が増えて、残業時間も自然と減った。
学び:「辞めさせないマネジメント」は“居心地づくり”から始まる
結局、彼を引き止めることはできなかった。
でも、彼が残してくれた問いは大きい。“良い仕事を当たり前にしないために、何を仕組みに入れるか”。
人は報酬だけで残らない。尊重・予見可能性・成長の見取り図があって初めて、職場を「居場所」と呼べる。
具体策はシンプルだ。
- 見えない貢献に名前と点をつける
- 小さな成功を、全員の前で言語化する
- 困りごとを言っても評価が下がらない空気を守る



『辞めないで』は願い。『残りたくなる』は設計。
マネジメントの仕事は、“居心地の構築”なんだと、彼に教わった。
あなたの職場は「辞めたくなる構造」になっていないか?
仕事量・評価・感謝のバランスは崩れていないか
“仕事量だけ右肩上がり、評価は横ばい、感謝は口約束”になっていませんか。
人は負荷×不公平×不可視が重なると静かに心が離れます。まずは次を棚卸し。
- 仕事量:誰のタスクが慢性的にオーバーか(可視化:WIPボード・稼働率)
- 評価:成果だけでなく調整・教育・品質の貢献に点が入っているか(配点の明文化)
- 感謝:週次で“行動”に対する称賛が言語化されているか(Win共有3分)



“頑張り=当たり前”の職場から離れるのは、個人のわがままじゃない。
構造が人を手放しているサインだよ。
誰か1人に負担や調整を任せすぎていないか
「頼めば早い人」に調整・火消し・新人フォローが集中していないか。見えない仕事は、最初に人を削ります。
- 誰が“感情の緩衝材”になっているかを列挙(会議後のフォロー、雑用、窓口役)
- 役割の責務化+手当化(調整・教育に役割名と配点を与える)
- 重要会議は議事録→アクションの持ち主まで明確化(属人化を防ぐ)



“あの人がいるから大丈夫”は、時間差の爆弾。
分散こそ最大のリスクヘッジ。
「辞めたい」を言い出せない空気がないか
“辞めたい”と言った瞬間に評価が下がる、陰で責められる。そんな職場では、サインは必ず地下に潜ります。
- 1on1の導入文を固定:「今日は説得しない。状況整理だけ一緒に」
- 退職相談を減点対象にしないルール化(社内規定・運用を文章に)
- 「辞めたい理由」を構造課題として議事化(個人の問題で終わらせない)



“辞めたい”を言える職場が、辞めなくて済む職場になる。
内省チェック(3分)
- 最後に“ありがとう”を言語化したのはいつ?(行動+理由まで添えたか)
- 評価会議で“見えない仕事”の配点を話したか?
- 直近30日で静かになった人は誰?(発言・雑談・リアクションの変化)
- 退職相談の運用は明文化されているか?(減点なし・守秘・リードタイム)
- 上司以外の“駆け込み先”はあるか?(メンター/人事/外部相談)
1つでも該当すれば、早期介入ゾーン。今日から小さく直そう。
ビズリーチでスカウトを受けてみると、
自分や部下の市場価値を再確認でき、
視点が“辞められる側”から“選ばれる側”へと切り替わります。
社外基準を知ることは、社内の歪みを直す最短ルートでもあります。
まとめ
辞めてほしくない人が辞める。それは偶然でも裏切りでもありません。
多くの場合、その背景には「個人の限界」ではなく「職場の構造の限界」があります。
人が職場を去るとき、その理由は「最後の不満」ではなく、
“何度も見過ごされた小さな失望”の積み重ねです。
感謝されなかった瞬間、意見を無視された会議、努力が当たり前にされた日々。
そうした“日常のほころび”が、静かに信頼を削り取っていきます。
だからこそ、離職防止の本質は「引き止めの言葉」ではなく、
“毎日の関わり方”と“扱われ方”を整えること。
人は給料だけでなく、自分が尊重されている実感で働き続けます。



人は“去りたい職場”からではなく、“自分が大切にされない場所”から離れる。辞められない組織ではなく、“離れたくない職場”をつくることが、本当のマネジメントです。
よくある質問
- 辞めて欲しくない人を引き止める言葉は?
-
「辞めないで」と感情的に訴えるより、「あなたの存在がチームにとってどれだけ大きいか」を具体的に伝えることが大切です。「あなたがいることで〇〇の案件が円滑に進んでいる」「周囲の信頼が厚い」と、本人の貢献を事実で伝えると気持ちは動きます。
- 辞めたい部下に「残ってほしい」と伝えるタイミングは?
-
退職届を出されてからでは遅いです。
「最近どう?」と声をかけるなど、違和感を感じた“予兆段階”での面談が理想。
また、1on1の目的を「評価」ではなく「対話」に切り替えるだけでも、離職の芽を早期に拾えます。 - パート・派遣社員の離職を防ぐには?
-
制度よりも“扱い方”が9割です。
パートには「時間の尊重」と「公平な評価」、派遣には「信頼関係」と「相談できる空気」が不可欠。
また、「派遣だから」「パートだから」という線引きを無くし、チームの一員として称賛・共有に参加させる仕組みを整えることが離職防止につながります。 - 優秀な人ほど辞める職場の特徴は?
-
頑張る人ほど報われず、声を上げる人が浮く職場です。
成果を出す人ほど業務が集中し、サポートが薄く、承認がない。
そんな環境では「成長したい人」から順に去っていきます。
優秀な人を残すには、「誰が支えているか」を可視化し、称賛と評価の仕組みを一致させることが重要です。 - 「無能ほど辞めない」と言われるのは本当?
-
一部のケースでは事実です。
責任を負わず、変化を避ける人ほど“現状維持”を選ぶ傾向があります。
一方で、成長意欲が高い人ほど「ここでは限界」と感じて辞める。
だからこそ離職は「危機」ではなく、組織を見直すチャンスでもあります。