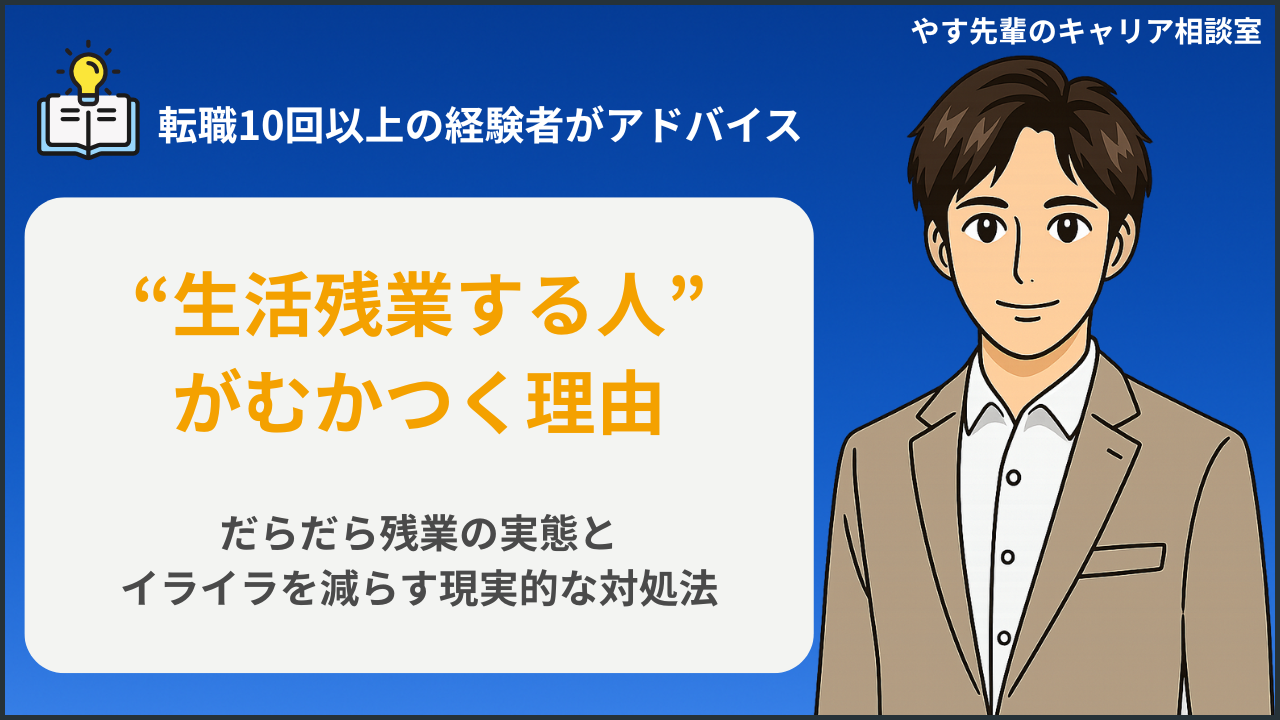やす先輩
やす先輩40代半ば、転職10回の管理職。上場もベンチャーもブラックも経験してきました。失敗も学びも交えながら、キャリアや働き方に悩むあなたへ“現実的な解決策”を届けます。
⇒詳しいプロフィール
「仕事はもう終わっているのに、なぜか帰らない人がいる」
「明らかにだらだら残業して、残業代を稼いでいるように見える」
そんな生活残業に、モヤモヤしたことはありませんか?
あなたがイライラするのは、心が狭いからではありません。
生活残業は、
・頑張って定時で終わらせる人ほど損をする
・生産性が上がらないのに残業が常態化する
・職場に不公平感と不信感が広がる
という、組織にとってかなり深刻な問題だからです。
しかも厄介なのは、「本人は悪気がない」「上司も見て見ぬふりをしている」というケースが多いこと。
結果として、まじめに働く人だけが消耗し、評価も報われないそんな職場になってしまいます。
この記事では、
・生活残業をする人の心理と行動パターン
・「むかつく」と感じるのが自然な理由
・黙認してはいけない本当の理由
・上司・同僚・人事として取るべき現実的な対処法
を、やす先輩の実体験とデータをもとに整理します。
もし今、
「この職場、頑張るほど損をする構造では?」
「生産性より残業時間が評価されていないか?」
と感じているなら、一度“職場の外の評価基準”も確認しておくことをおすすめします。
ミイダスを使えば、成果やスキルを重視する会社では、あなたがどう評価されるかが見えてきます。
今の職場に居続けるかどうかを決めるためにも、感情ではなく客観的な判断材料を持っておきましょう。
生活残業とは?意味と「何が悪いのか」を整理しよう
生活残業の定義と“だらだら残業”との違い
「生活残業」とは、本来の業務を終えているのに生活費を補うために残業を続けることを指します。
つまり、“残業手当ありきの働き方”であり、仕事の必要性ではなく金銭的事情が動機になっている点が特徴です。
似た言葉で「だらだら残業」という表現もありますが、こちらは「特に目的なく残業時間を引き延ばす行為」。
一方、生活残業は「経済的理由で残業せざるを得ない」ケースが多く、一種の“構造的な働き方依存”とも言えます。
たとえば
- 残業代を含めて家計が成り立っている
- 定時に帰ると“やる気がない”と見られる職場
- 上司が率先して残業している
こうした環境では、「帰れない空気」+「残業手当で稼ぐ文化」がセットで存在しており、
本人の意思だけでは抜け出せなくなるケースも少なくありません。



僕も前職で“残業しないと生活できない”人を多く見てきました。
でもそれって“仕組みの欠陥”であって、本人が悪いわけじゃないんですよね。
「残業で稼ぐ」は会社・本人どちらにもリスクがある
「残業で稼ぐのは悪いこと?」と疑問に思う人もいますが、実は会社と本人の双方にデメリットが大きいです。
会社側のリスク
- 人件費が膨張し、経営効率が低下する
- 生産性指標が悪化し、業務改善が進まない
- “残業が当たり前”の風土が定着し、若手離れを招く
本人側のリスク
- “長時間労働”による健康リスク(過労・メンタル不調)
- 定時で成果を出せない人と見なされる評価リスク
- 将来的に残業規制が強まった際、収入が激減するリスク
実際、厚生労働省の「働き方改革実行計画」では、
“残業を前提とする賃金構造”そのものを是正する動きが進んでおり、
“残業で稼ぐ”働き方は今後さらに厳しくなっていくと見られます。



残業代に頼る働き方は、短期的には安心でも“キャリアの負債”になります。“時間”ではなく“成果”で評価される働き方にシフトするのが理想です。
生活残業を黙認する職場が抱える3つの問題
生活残業は、会社が黙認することで構造化していくのが最大の問題です。
“本人が望んで残業してるからいいじゃないか”では済まない理由が3つあります。
① 公平性が崩れる
定時で帰る社員との間に評価・収入格差の不満が生まれ、チームの雰囲気が悪化します。
結果として「残業してる人=頑張ってる人」という歪んだ評価構造が定着します。
② 生産性が低下する
長時間労働が常態化すると、業務の優先順位や効率化の意識が失われるため、
残業時間が増えるほど成果が落ちるという逆転現象が起きます。
③ コンプライアンスリスクが高まる
管理職が生活残業を黙認・推奨している場合、
労働基準監督署からの是正指導につながる恐れもあります。
特に「残業削減を指示しているのに、実際は放置」という状態は、
“管理責任の不履行”と見なされるリスクがあります。



“うちの会社は昔からこうだから”で片付けるのが一番危険。
生活残業を放置する会社は、気づかないうちに“人もコストも失ってる”んです。
生活残業をする人の特徴と心理


「帰りづらい職場」「残業代依存」が原因になりやすい
生活残業をする人の多くは、「帰りづらい職場」や「残業代に依存する給与構造」の中で働いています。
つまり、本人の怠慢ではなく、職場文化と経済的な仕組みが生活残業を生み出しているのです。
たとえば
- 上司や同僚が毎日遅くまで残っている
- 定時で帰ると「やる気がない」と陰口を言われる
- 基本給が低く、残業代を足してようやく生活できる
こうした環境では、「自分だけ帰るのは気まずい」「定時退社は悪」といった空気が蔓延します。
結果、業務が終わっていてもPCを閉じられず、“残業が評価される構造”に自ら合わせてしまうのです。



“残業するのが普通”って空気は本当に厄介です。
僕も昔、“帰るのが早い人=サボってる人”みたいな職場にいて、
あれは精神的に一番つらかったですね。
生活残業する人の共通点と“自己防衛思考”
生活残業をする人には、ある共通した心理パターンがあります。
それは「評価されたい」「職場で浮きたくない」「生活を守りたい」という自己防衛思考です。
具体的には以下のような特徴が見られます。
- 責任感が強く、仕事を途中で切り上げるのが苦手
- “みんな頑張ってるから自分も”と同調圧力を受けやすい
- 成果より「努力を見せる」ことで安心を得ようとする
- 残業を“忠誠心”の表れだと考えている
このように、生活残業は「怠け」ではなく、“真面目すぎるがゆえの悪循環”でもあります。
しかし、努力の方向を間違えると、疲労とストレスだけが積み重なり、
肝心の成果や評価にはつながらないという矛盾が生まれます。



“残業=頑張ってる証拠”って思い込みが一番怖い。
本当は“時間をかけない工夫”こそが評価される時代なんです。
「おばさん社員に多い」と言われる理由と誤解
ネット上では「生活残業はおばさんに多い」と言われることがありますが、
これは誤解や偏見が混ざった表現です。
実際には、性別や年齢に関係なく、“職場環境とマネジメントの問題”が根本原因です。
たとえば、家庭と仕事を両立している人ほど、
「残業代がないと家計が厳しい」「自分の存在価値を示したい」という心理が働きやすくなります。
一方で、男性社員でも「上司に評価されたい」「チームを裏切りたくない」といった思いから、
結果的に生活残業を繰り返すケースも多いのです。
むしろ問題なのは、“生活残業を是正できない職場構造”です。
上司がマネジメントせず、「長くいる人が頑張っているように見える」という古い価値観を放置している限り、
誰でも“生活残業予備軍”になり得ます。



“おばさんが残業するから悪い”じゃなくて、“残業を評価する会社”が問題。
世代や性別じゃなく、“仕組みのアップデート”が必要なんですよね。
生活残業する人にイライラ・むかつくときの対処法
「自分のせい」と思わない|怒りの感情を整理する
生活残業する人を見て「なんで早く帰らないの?」「そのせいで空気が重い」と、
イライラやむかつきを感じるのは自然なことです。
特に、「自分だけが効率的に動いているのに報われない」と感じると、
怒りが積もってしまうのも無理はありません。
ただし、その感情を「自分が心の狭い人間だから」と責める必要はありません。
むしろ、原因はあなたではなく、
「残業する人が得をするような職場の構造」にあります。
心理学的にも、“不公平感”はストレスの最大要因とされています。
この怒りは“嫉妬”ではなく、「正当に評価されたい」という健全な感情なのです。



僕も“だらだら残業組”を見てモヤモヤしてた時期がありました。
でも、よく考えると怒りの原因は“その仕組みを放置する会社”にあったんですよね。
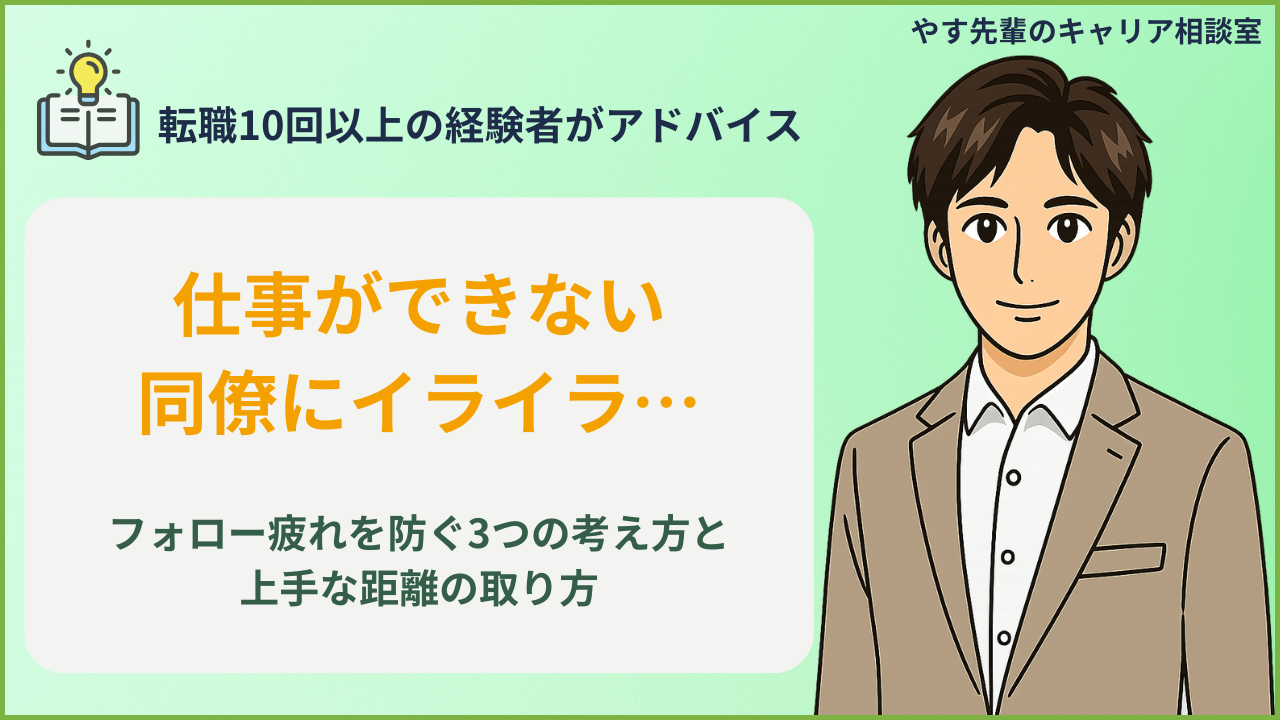
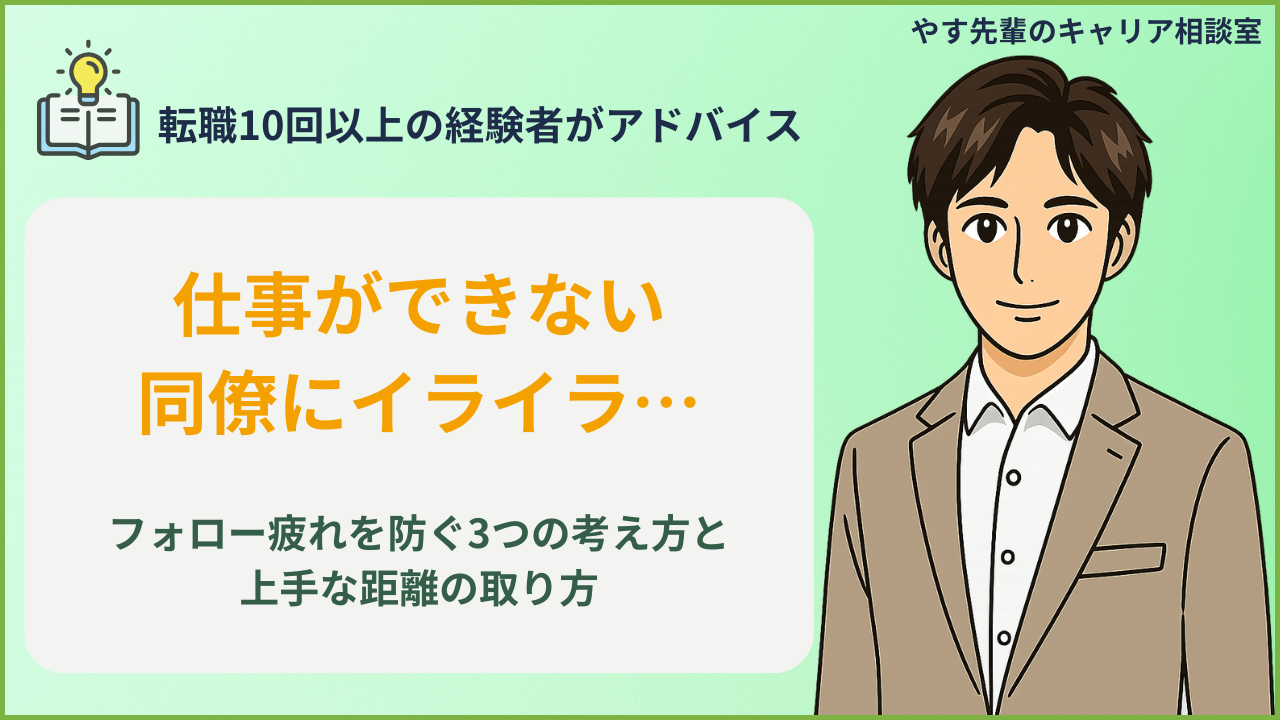
上司や人事に“業務効率の観点”で相談する
感情的に注意すると、関係が悪化したり、逆にあなたが“冷たい人”と誤解されることがあります。
そこで有効なのが、“業務効率”という客観的な切り口で相談する方法です。
たとえば、こんな伝え方が効果的です。
「一部の人の残業が続いていて、全体の業務効率に影響が出ている気がします」
「残業を前提にしたスケジュールが常態化していませんか?」
こうした言い方なら、個人攻撃ではなく“職場改善の提案”として受け取られやすいです。
また、人事部や管理職に相談する際は、
・残業時間の傾向
・作業分担の不均衡
・業務指示のタイミング
といった具体的な情報を添えることで、改善の動きが現実的になります。



“〇〇さんが残ってるのが嫌です”じゃなくて、“職場の効率が落ちてます”と伝える。
これだけで、相談の通り方が全然変わります。
直接注意するより“仕組みで変える”のが効果的
生活残業する人に「早く帰ってください」と言っても、
相手の生活スタイルや価値観に踏み込むため、ほとんどの場合は逆効果になります。
むしろ、職場全体の“仕組み”を見直す方向にシフトするのが現実的です。
たとえば
- 業務の見える化ツール(タスク管理シート・チャット連絡)を導入
- 残業理由を必ず上長承認制にする
- 定時退社デーや「ノー残業キャンペーン」を社内提案する
こうした取り組みで、「残業が当たり前」から「定時で帰るのが普通」という空気をつくることができます。
ポイントは、“人を変える”より“環境を変える”こと。



注意しても人は変わらない。でも、ルールを変えたら空気は変わる。
結局、“仕組みで守る”のが一番賢い方法なんですよね。
生活残業をやめさせる方法【上司・同僚・人事別】
上司の場合:業務の“見える化”で残業の必要性を明確に
上司が生活残業をしている場合、
「仕事量が多いから」「部下の前で頑張って見せたいから」など、
本人の意図と実態がズレているケースが多いものです。
まずは、“見える化”を通じて残業の必要性を客観的に示すことが大切です。
具体的には
- 毎日のタスクを「時間別・優先度別」に共有する
- 進行状況を週報やミーティングでオープン化する
- 残業が発生している理由を「業務構造」として整理する
これにより、上司自身も「どこで無駄が出ているのか」を把握でき、
“やらなくてもいい残業”を減らす意識が芽生えます。
もし上司から「残業減らせ」と指導されているのに、
実際は管理職が生活残業しているようなら、それは会社の構造問題。
「上司が残ってるから帰りにくい」という空気を放置すると、
“生活残業が文化化する”危険信号です。



上司が遅くまで残ってる職場ほど、部下は帰れません。
“率先して定時で帰る上司”こそ、本当のマネジメントができる人です。


同僚の場合:波風を立てずに“空気を変える”会話術
同僚が毎日生活残業している場合、
直接「もう帰ったら?」と言っても、反発を招くだけです。
大事なのは、“指摘”ではなく“空気を変える”アプローチです。
たとえば
「このタスク、明日まとめて一緒にやろうか?」
「もう今日は区切りつけよう、続きは明日で十分じゃない?」
「〇〇さんの進め方、すごく効率的ですよね」
こうした前向きな声かけで、“残業しないのが自然”な流れを作るのがポイント。
人は指摘よりも、「安心して帰ってもいい空気」があると行動を変えやすくなります。
また、チーム全体で「定時退社チャレンジ」などの
軽い制度やキャンペーンを提案するのも効果的です。
「残業=悪」ではなく、「残業しない=成果を出してる」と
評価軸を変える空気づくりが、最も確実な“やめさせ方”です。



“注意するより空気を変える”。これが一番効きます。
残業しない人が“浮かない”環境を作るのが、いちばんのマネジメントです。
人事の場合:勤怠データと評価制度の見直しが鍵
人事や管理職の立場から生活残業をなくすには、
“仕組み”と“数字”で是正することが不可欠です。
まず取り組むべきは、以下の2点です。
① 勤怠データの分析
- 残業時間が多い部署や個人の傾向を把握
- 定時以降の「メール・チャット送信ログ」もチェック
- 残業申請と実際の労働時間に乖離がないか確認
数字で可視化すると、“どこで生活残業が発生しているか”が明確になります。
② 評価制度の見直し
「残業している=頑張っている」と見なす風土を改め、
“成果と効率”を評価する制度に切り替えることが重要です。
たとえば
- 残業時間ではなくアウトプット量で評価
- 業務改善提案を評価項目に追加
- 定時退社を推奨するインセンティブ制度を導入
これにより、生活残業が“損な働き方”になる構造を作り出せます。



制度を変えれば、行動は自然と変わります。
“残業で稼ぐ人”が損をする仕組みに変える。
それが本当の“やめさせる方法”なんですよね。
生活残業が続く職場の末路とコンプライアンスリスク
残業代の水増し・不正請求が発覚するリスク
生活残業が常態化している職場では、「実際には働いていない時間まで残業代を請求している」という構造的な問題が起きやすくなります。
これは本人の悪意がなくても、“不正請求”や“労務管理違反”と見なされるリスクがあります。
たとえば、
- 定時後に何となく事務所に残っているだけ
- 上司が「残業しておけ」と黙認し、実質的に不要な時間を残業扱いにしている
- 残業申請に具体的な作業根拠がなく、形式だけになっている
こうした状態が続くと、労働基準監督署の監査や内部通報で発覚することがあります。
最悪の場合、「虚偽の勤務報告」「会社への損害」として懲戒や減給の対象になることも。
実際、厚生労働省の監督指導事例では、
「労働時間の適正把握義務違反」や「不適正な残業申請」が是正勧告の対象になるケースが年々増加しています。
これは、厚労省が公表している以下の資料にも明記されています:
これらの資料でも、「勤怠データの不一致」「不正な残業申請」「管理職の黙認」が労基法違反として是正指導の対象になっていることが確認できます。



“ちょっとくらい”のつもりでも、それが積み重なると“虚偽申告”に変わる。本人に悪気がなくても、会社も自分も守れなくなるんです。
「働かないのに残る人」が評価を歪める構造
生活残業が放置される職場では、“残っている人が頑張っているように見える”という評価の歪みが生まれます。
その結果、本来成果を上げている人よりも、「長く残っている人」が高く評価されるという不公平が起こります。
この構造が続くと
- 「どうせ帰れない」と皆が効率を落とす
- 生産性の低下が常態化
- 優秀な人材が離職し、会社の競争力が低下
つまり、生活残業は個人の問題ではなく、組織を腐らせる構造的リスクです。
企業が成果主義やリモートワーク制度を導入しても、
上司が「長く残る=頑張っている」と誤解していれば、
“昭和型マネジメント”が再び顔を出すだけです。



“遅くまで残ってる人が偉い”っていう空気は、若手のやる気を確実に潰します。
結果を出すより“帰れないほうが正義”なんて、誰も得しませんよね。
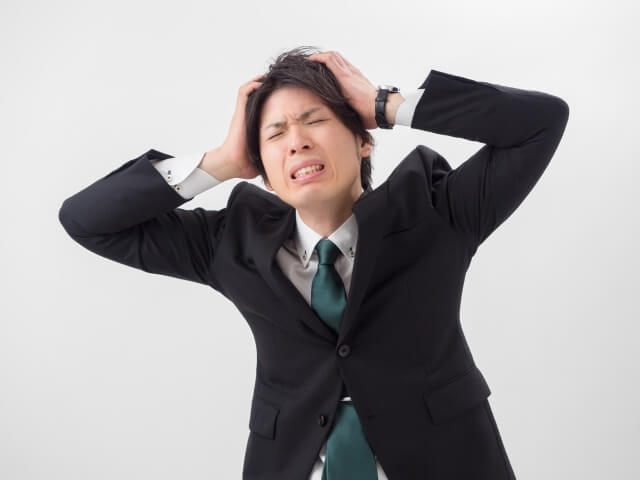
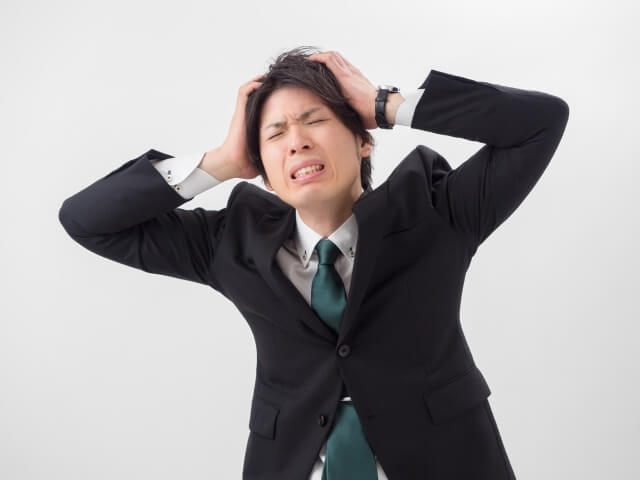
企業が監督署に指摘されるケースも
生活残業を黙認し続けると、会社そのものが労働基準監督署から是正指導を受ける可能性があります。
特に、次のようなケースは要注意です。
- 打刻時間と実際の労働内容に乖離がある
- 管理職が残業を黙認している
- 労働時間管理システムが形骸化している
これらは、労働基準法第108条「労働時間の記録・管理義務」に違反する可能性があり、
企業としても「管理体制の不備」として改善命令を受けるリスクが高まります。
また、社内で生活残業を是正しないことが原因で、
社員からの内部通報やSNSでの暴露につながるケースもあります。
現代では、たった一件の告発でも企業イメージが大きく損なわれる時代です。



“生活残業くらい”で会社が指摘されるなんて、と思うかもしれませんが、
今は“コンプライアンス意識の低さ”自体がブランドリスクです。
働く人の意識が変わってるんですよね。
やす先輩の体験談|生活残業が当たり前の会社を辞めた理由
当時の状況:毎日誰かが“帰れない空気”を作る職場
当時勤めていた会社は、「誰かが残っていると帰りづらい」という典型的な“生活残業文化”の職場でした。
定時を過ぎてもオフィスの照明は消えず、特にベテラン社員(いわゆる“おばさん社員”)が「まだ帰らないの?」と声をかけてくる空気。
本来であれば業務効率を重視すべき時間に、“残ることが仕事”という価値観が染みついていたんです。
上司もそれを黙認していたため、誰も指摘できない。まさに「暗黙の生活残業」が常態化していました。



“頑張ってるように見える人”が評価される職場は、実は一番危険です。
努力じゃなく、“残業時間”で競うようになったら、もう末期ですね。
感じたこと:成果より「残業時間」が評価される不条理
一番つらかったのは、成果を出しても“早く帰る人”が評価されにくいこと。
逆に、遅くまで残って“忙しそうにしている人”ほど頑張っているように見える。
特に上司は、「あいつはよく頑張ってる」と“残業時間=努力”で判断していました。
私は「本来の成果とは何か?」という疑問を感じながら、毎日定時退社できない自分にモヤモヤしていました。



評価されたい気持ちが“無駄な残業”につながる。
でもそれ、会社の成長にも自分の成長にもならないんですよね。
行動:勤怠を定時退社に切り替え、周囲の意識変化を観察
ある日を境に、「自分が変わらなければ何も変わらない」と思い、あえて定時で退社する習慣をつけました。
最初は周囲の視線が痛かったものの、帰っても仕事が回ることを実績で示すように意識。
- 作業の優先順位を明確化
- 無駄な会議や雑務を削減
- チャットでの確認をルール化
すると、数週間後には同僚も少しずつ早く帰り始め、「残業しなくても成果を出せる」空気が広がっていきました。



“帰る勇気”って、実はチームの文化を変える第一歩なんですよ。
結果:上司から「無駄が減った」と評価され転職にも有利に
結果的に、上司から「やす先輩が帰り始めてから、残業減ったよね」と声をかけられるほどに変化。
職場全体の業務効率が上がり、私自身の評価も改善しました。
さらにこの経験を“労働生産性の改善事例”として転職面接で話すと、
採用担当者から「仕組みで動けるタイプですね」と高く評価され、転職にも有利に働きました。



“残業を減らした経験”は、どんな会社でも評価されます。
生産性を上げられる人は、どの環境でも強いです。
学び:「長く残るより、成果で残す」ことが本当の評価軸
生活残業文化にどっぷり浸かっていた頃は、“時間で働く”ことが努力の証だと思っていました。
でも今ならはっきり言えます。
「残る時間」ではなく、「残せる成果」こそが評価軸です。
もし今、「帰りづらい」「周りが残ってるから帰れない」と感じている人がいたら、
一度“時間ではなく価値”で働く姿勢に切り替えてみてください。
それが、自分のキャリアを守る最初の一歩です。



“長く残るより、成果で残す”。
この一言に尽きます。あなたの努力は、残業時間ではなく“結果”で証明していいんです。
生活残業文化に限界を感じたら“環境を変える勇気”を
コンプラ違反の温床になる前に距離を取る
「生活残業」は、一見“頑張ってる”ように見えて、実は企業コンプライアンスを揺るがすリスク要因です。
前述の通り、厚生労働省のガイドラインでは「労働時間の適正把握義務」が明確に定められており、
上司の黙認や不正な残業申請は是正勧告の対象になります。
それでも、「残業ありき」でしか評価されない文化が変わらないなら、
個人の努力ではどうにもならない職場かもしれません。



“空気を読む残業”が当たり前の会社は、いつか“働く人の心”を壊します。
自分を守るために、離れる勇気も必要です。
ミイダスで“市場価値”を把握して動き出す
まずは焦らず、「自分の市場価値」を客観的に知ることから始めましょう。
ミイダスなら、経歴とスキルを入力するだけで、
- 自分と同じキャリアの平均年収
- オファーをもらえる企業傾向
- 自分に合った働き方(リモート・残業少なめ企業など)
をすぐに確認できます。
「今の職場を我慢して続けるべきか」「転職で環境を変えるべきか」――その判断材料になります。



“辞めたい”と思った瞬間に動くより、“今の自分を知る”ところから始める。
それだけで転職の成功率はぐっと上がります。
ビズリーチ/マイナビジョブ20’s/トリケシで新しい環境を探す
もし今、生活残業に限界を感じているなら、転職という選択肢を前向きに考えてみましょう。
- ビズリーチ:年収アップ・管理職・ハイクラス転職向け。残業の少ない企業も検索可能
- マイナビジョブ20’s:20代のキャリアチェンジ・未経験職種に強いサポート型サービス
- 退職代行サービス「トリケシ」:即日退職代行で“今すぐ抜け出したい”人をサポート
「今の職場にしがみつく」より、「もっと健全に働ける環境を選ぶ」方が、ずっと建設的です。



生活残業の職場は、抜け出した人しか“異常さ”に気づけません。
環境を変えた瞬間、“働くってこんなに楽だったのか”と実感できます。
まとめ|生活残業を“普通”にしない勇気を持とう
生活残業は、“努力”でも“真面目さ”でもありません。
それは、「残ることが評価される」悪循環を黙認しているだけの悪習です。
たとえ上司や同僚が黙認していても、
その文化が続けば、評価の基準が歪み、やがて自分自身の成長を止めてしまう。
そして何より、コンプライアンスの観点から見ても、
「不要な残業を続ける=勤怠不正や是正勧告のリスク」を抱える危険な状態です。
最悪の場合、「生活残業でクビ」や「査定マイナス」に繋がるケースも実際に存在します。
だからこそ、
「仕方ない」「みんなやってる」と諦めるのではなく、
“普通にしない勇気”を持つことが、あなたのキャリアを守る第一歩です。
今すぐできる3つのアクション
👉 ミイダス市場価値診断
自分のスキルと年収相場を知ることで、「転職すべきか」「今の会社で頑張るべきか」を冷静に判断できます。
👉 ビズリーチ
管理職・ハイクラス求人の中から、「成果主義×ワークライフバランス重視」の企業を見つけやすいです。
👉 退職代行サービス「トリケシ」
「もう限界」「今すぐ抜け出したい」と思ったら、法的に安全な手段で即退職が可能です。
よくある質問
- 生活残業って違法ではないの?
-
生活残業そのものが即「違法」になるわけではありません。
ただし、実態として「業務がないのに残業している」「上司が黙認している」場合は、
労働基準法32条(労働時間の上限)や36協定違反、勤怠不正に該当するおそれがあります。
厚生労働省も「使用者は労働時間を適正に把握する義務がある」と明記しており、
企業が放置すると是正勧告や行政指導の対象になるケースもあります。
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置」 - 生活残業を注意されたらどうすればいい?
-
まずは素直に受け止めて“改善のチャンス”と考えるのが正解です。
「残業しないと仕事が終わらない」場合は、業務量やフローの改善を上司に相談しましょう。
一方、「ただ帰りづらくて残っている」なら、自分の行動を見直す絶好の機会です。 - 残業で稼がないと生活できないのはおかしい?
-
生活費のために残業せざるを得ない人も多いですが、
“残業で補う構造”自体が長期的にはリスクです。
物価上昇や税負担を考えると、“稼ぐ時間を増やす”より“収入源を変える”発想が重要。たとえば、
- 残業なしでも稼げる企業に転職する
- 副業・スキルアップで収入源を増やす
など、“時間で稼ぐ”から“価値で稼ぐ”への転換を目指しましょう。
- 同僚がだらだら残業していてイライラする…どう対応?
-
「自分は早く帰りたいのに、周りが残っていて帰りづらい…」
そんなときは、相手を変えようとせず、仕組みで距離を取るのがベスト。- 仕事の進捗をチャットやタスクツールで共有
- 定時で業務を終える流れを“習慣化”
- 必要があれば上司に業務効率の改善提案をする
直接注意すると人間関係が悪化する可能性があるため、
“働き方を可視化する工夫”で空気を変えるのが賢明です。 - 生活残業文化の職場を変えるには?
-
職場単位で変えるには、個人よりも仕組みから変える発想が必要です。
勤怠システムの導入や業務フローの見直しなど、
“残らないのが当たり前”という風土を作らなければ、
生活残業は永遠に続く構造問題になります。もし社内改善が難しいなら、
- ミイダスで市場価値を把握する
- ビズリーチで「残業少なめ」企業を探す
- 退職代行サービス「トリケシ」で即日退職の相談をする
といった“環境を変える選択”も現実的な手段です。